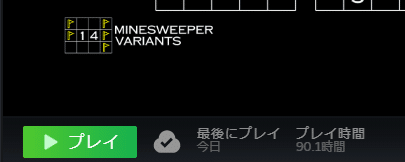「14 Minesweeper variants」攻略メモ
各ルールの自分用攻略メモです
Q.2×2に必ず地雷

[2]の周囲は縦に地雷2個か、横に地雷2個のどちらか確定。
緑は安全マスです。

2×2の範囲に残り1マスなら確定地雷。
分かっていても見落としがち。

安全マスが2つ並んだ隣は必ず1つ以上地雷。
よくあるパターン。
C.8方向地雷隣接
安全マスで挟まれた1~2マスの隙間を地雷が通るかどうかを考える(画像なし)
T.必ず3連地雷でない

壁際に[4]があった場合、必ず黄色のライン2つ以上に地雷があるので安全マス2つと地雷2つが確定する。
これの応用で「壁際[3]+安全マス1つ」「中央[4]の一方向(3マス)が判明済み」などがある。
下図は応用例。
赤枠と青枠、それぞれ3個づつ地雷があるため、「壁際[3]+安全マス1つ」と同じ理屈で安全マスが確定する。
忘れてたので覚えておくこと。(戒め)

O.4方向安全/地雷〼隣接
地雷が安全マスに囲まれてないか(もしくは逆)に着目する。

ルールからだと分かりづらいが、「斜めのみ」の隣接は絶対にない。
赤マスのどちらか一方は必ず安全マス。
[1]の周囲に地雷を置いた時、安全マスに囲まれるパターンはありえない。(画像なし)
D.長方形

壁際から垂直に[1][1]が伸びてその先のT字に[4]が絡む頻出パターン。
緑で塗った4マスが確定。
更に壁に挟まれた1マスも安全だと確定する。

突き出す形で[1][3][1]が並んでいるパターン。
この場合、緑マスが安全となる。
S.ヘビ
端を確定させたらとにかくラインを引く

緑マスが端、赤マスが端候補。残り地雷数が「9個」だったので赤マスにピッタリたどり着けない黄色のラインはNGだと分かった。
要するに片方の端を確定させたら偶奇性を利用してもう片方の端を絞る。
慣れればライン引かなくても分かるかも?
偶奇性に関しては全部数える必要はなく、スタート地点とゴール地点の最短距離を数えればよい。最短が偶数なら到達可能(総地雷数は偶数のはずなので)、奇数なら矛盾する。
B.行列に同じ数地雷

図のようなブロック分けを示すメモ書きが有効。
3列で範囲を絞り込み、絞り込めなかった残ったマスが全て地雷といったことが多い。
盤面が大きくなるとこのブロック思考で考えることが多くなる。
M.色付き2、色なし1

[4]に着目すると、黄色ラインの2マスのうち片方は地雷。
よって[2]の上の黒マスは安全マス。
あたりまえだね。
L.虚言

図の安全マスは[1][1]。
このように壁から伸びる安全マスの根本の数が大きく、先の数が小さければ2マスの数が確定する。
W.グループの長さ
[1,1,2]で1マスだけ確定してる場合が結構ある気がする。(画像なし)
N.相殺
1.2マスのセットを作って考える。
2.色で分けて考える

[0]を見た時、黄色の2マスは必ず相殺する。
よって[2]は黒2マスしかありえないので黒2マスが地雷、間の白マスは安全になる。
つまり相殺セットを作ってから黒or白しかありえないパターンを見つける。
[0]の隣に[2]以上のヒントがあるマスを探すのがいいかも?
色確定したら[黒2],[白1]みたいな「色+数字」が分かるようなメモをするのが良さそう。(自分は[b2],[w1]とメモしている)

相殺でよくあるパターン。
隣り合った2マスが[0](または0相当の相殺)で未確定4マスが並んでいる場合、4マスの両端が安全マスで、間の2マスが相殺となる。
X.十字地雷

[4]と[1]を見た時、赤枠はどちらか片方が地雷。
青枠は確定する。
P.グループ数
1番大きなグループの線を描いて、そこから分割されるか検証していく?
E.視野

最初に、調べる安全マスに目星を付ける。(図の場合[9]に着目している)
目星をつけたらそのマスを縦に伸ばした時の最小マス数と最大マス数を調べ、マス数のパターンを書き出す。
図の場合、5~7マスまで縦に伸ばせる。
あとはこのパターンについて総当たりを試し、矛盾したパターンを消していくと1パターンに絞れる。
1つ縦マス数が確定すればそれに繋がる全ての安全マスの縦・横マス数が芋づる式に確定するので、クリアまで一気に進めます。
ちなみに図の場合次に着目するマスは赤枠のマス。
[5],[7]の両方に影響するため、調べると縦5マスのパターンが矛盾することがわかります。
あとがき
steamのリモートプレイで寝る前にスマホでプレイすると、寝落ちでプレイ時間爆上がりするのでおすすめです。