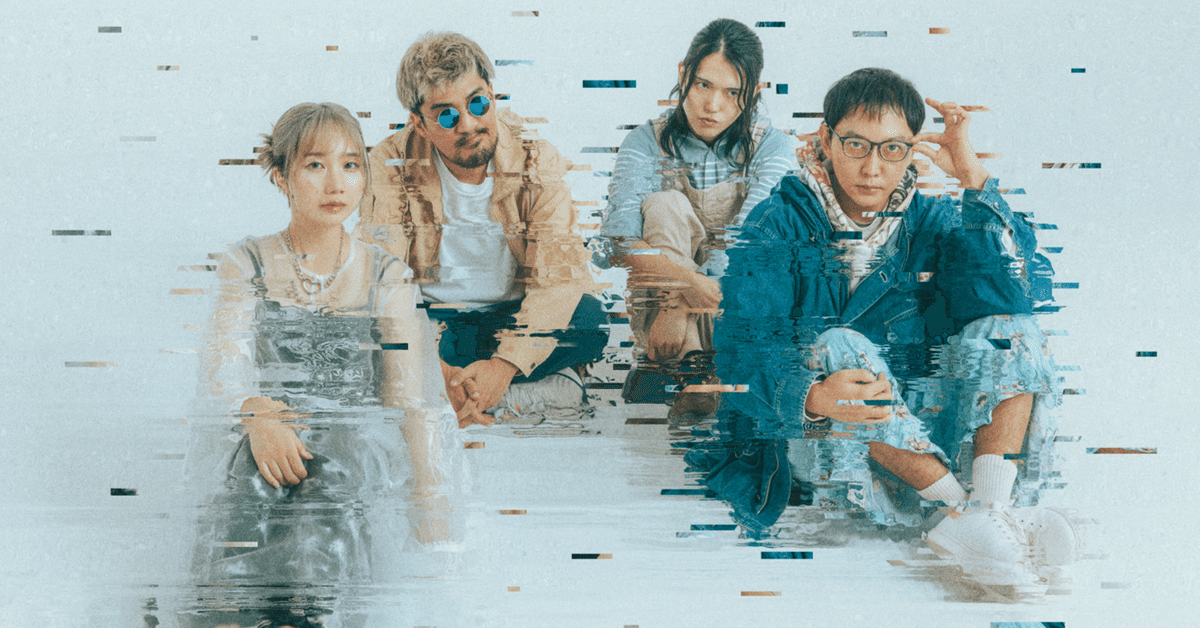
神聖かまってちゃん "団地テーゼ"

千葉出身のロックバンドによる、オリジナルフルレンスとしては5年ぶり10作目。
うかつにも朝っぱらにこの新作を聴き始めて、一気に胃が重たくなってしまった。さすがにタイミングを間違えた。なにせ1曲目から "墓" 、しかも歌い出しが「遺書を書く/今日の始まり」である。煮えくり返ったはらわたを思いきりぶちまけている。これがの子本人の感情なのか他者のイメージを描いたのかはわからない。仮に本人のものだったとして、そういった感情を直視して作品として形にする際の苦しさとはどれほどのものだろうかと思いを馳せてしまう。インタビューを読むと、の子は神聖かまってちゃんを短命で終わらせる気は最初からなく、常に長く継続したいという意志をもって活動してきたと述べている。つまりの子は創作を続ける限り、こういった負の感情からは決して逃れられないことになる。日々の鬱屈をブーストし、過去の記憶をあえて蘇らせ、自分自身を焚きつける。年齢も40代に差し掛かり、かつて受けた心の傷も時間の経過とともに和らいで、衝動を表現することが困難になってくるのでは…と思うが、冒頭の "墓" 、そして続けざまの "死にたいひまわり" を聴くだけでも、今のの子がそんな生易しいステージにいないことをはっきりと突き付けられ、むしろ聴き手であるこちらの体調が悪くなってくる。さすが5年のインターバルは伊達ではない。
音楽的にはこれまでの神聖かまってちゃんらしさを踏襲し、濃密さをさらに高めている。ギターのラウドさよりも、高音域がキンキンに出たシンセ類が前面に広がり、ハイピッチに加工したボーカル、ファンタジー系 RPG を思わせる聖歌隊を模したコーラス、それらが混ざりあってキッチュで混沌とした音像を作り上げる。聴けば一発で彼らだとわかる音。神聖かまってちゃんはデビューした当初から、の子が宅録で作り上げた原曲をバンドサウンドでブラッシュアップする際にアクの強さをどう保つか…という課題が常にあったが、良い意味でのチープでノイジーな音作りに由来する毒っぽさと明瞭なポップさのバランス感覚は、もしかしたら今作がこれまでで最も研ぎ澄まされているかもしれない。聴いているのが電車の中であっても、音が鳴り響いている間は外界と自分が強引にシャットアウトされる感覚に陥る。それくらい音に主張が漲っているのだ。
曲に遠慮がなければ歌詞にも遠慮がない。の子自身が「ゲロ」だと明言するように、身も蓋もないほど陰惨な、痛々しい傷跡をわざと見せびらかすかのような表現ばかりが並んでいる。上記の "墓" や "死にたいひまわり" もそうだし、"卒業式" には門出を祝う華々しさや切なさ、"カエルのうた" や "雨あめぴっちゃんの歌" には童謡のノスタルジックな可愛らしさ、そんなものは微塵も存在しない。あるのは他人と自分を傷つける言葉の刃ばかりだ。の子の過去の体験を切り売りしたようなものもあるだろうし、架空の主人公を設定してある曲にしても、それはきっとの子の抱える鬱屈を具現化させた姿だろう。清らかな美しさを放つ曲調も歌詞によって全くの反語と化し、アップテンポで騒がしい演奏はおちゃらけた軽さを印象付けるが、それも歌詞のせいで正気と狂気の狭間を駆け巡る際どい精神状態のように感じる。こういった音と言葉の対比効果もかまってちゃんがかねてからずっと実践してきたことだが、ポップさとダークさのコントラストがより一層ドギツくなっているため、一見さんはもちろん古参のファンの神経もしっかり逆撫でて、最後まで強烈に惹き付ける。ひとつの集大成というか、ベテランの貫禄と評してしまってもいいかもしれない。
そう、神聖かまってちゃんはすっかりベテランなのだ。デビュー当初はとてもそうなるとは思えなかったが、長く続けたいという意志を彼らは確かに現実のものとしている。そして彼らの表現はあちこちに種を飛ばして芽吹き、ずっと真夜中でいいのに。や ano といった異色の才能を筆頭に、多方面からのリスペクトを勝ち得た。J-POP 史上に神聖かまってちゃんを起点とするひとつの文脈が生まれたのだ。その上での最新の成果が今作。ベテランと呼ぶことに何の躊躇もいらない、聴き応え抜群の新譜だ。今後も彼らはこうして波長の合わない人を徹底的に遠ざけ、波長の合う人を徹底的に魅了するのだろう。自分が今までに愛したミュージシャンは皆、そんな風にいびつで極端な個性を持つ人ばかりだった。そういう人こそ、自分はあえてポップスターと呼びたい。
