
概念の歴史は、僕らの歴史 | ハイデル日記 『グローバル概念史学』
もし宇宙人が地球にやってきて、あなたにいま「この”社会”という概念とはなにか、説明してくれ」と頼んできたら、あなたは説明できるだろうか?
もちろん、彼らは地球に降り立ったばかりでなにもわからない。
人によっては、学校や仕事、メディアを通じて学んだことを自分なりに表現しようとする人もいれば、「社会」を構成する要素(人間の集団、経済活動の場、政治の役割など)を分解していくアプローチをとる人、あるいは「社会」という単語自体がもつ意味を説明しようとする人もいるかもしれない。
おそらくどのアプローチをとっても、完全な理解はえられないだろう。それはこの概念がきわめて複雑だから。
こうした「概念」をより正確に理解すべく、歴史的な視点からひもとこうというのが、ドイツ発祥の学問コンセプチュアル・ヒストリー(Begriffsgeschichte、概念史学)である。歴史学の中のインテレクチュアル・ヒストリー(日本語でいうと思想史などが近い)に分類される学問で、上のような概念がいかにして社会の中で構築され、利用されて、あるいは変容していくかを探究する。
そのコンセプチュアル・ヒストリーに「越境文化的(transcultural)」な視点を加えたのが、僕が昨年の冬学期に履修した「Toward a Global History of Concepts: Translation, Appropriation, Transformation(グローバルな概念史へ:翻訳/変換、私物化、変容)」というコースだった。
本記事では、このかなりマニアックな学問を通じて僕が学んだことを、いくつかの例とともに紹介していきたい。
グローバル時代の概念史学
まず、上でふれた「インテレクチュアル・ヒストリー」というものがなんなのか、簡単に説明したい。
Wikipediaの日本語ページによると、
インテレクチュアル・ヒストリー (英: intellectual history) は、人文学の用語で、「知の営み」についての歴史学のこと。専門家の間でも明確な定義が無く、日本語では「精神史」や「知性史」とも訳され、思想史・観念史・心性史と並列されることもあるが、必ずしも対応しない。特定の分野にとらわれず多角的な歴史を扱う分野とも言える。
旧来の「歴史学」と「思想史」のあいだに横わたる広大なフロンティアを開拓しているのが、21世紀現在の潮流と言える。
そもそも歴史学には多数の視点やアプローチがある。それをたとえばテーマ性によって「経済史」「美術史」「科学史」などと区別した場合、たとえ同じ時期に同じ場所で起きたことを分析していても、まったく違う風景がみえてくる。それぞれが「経済のメガネ」「美術のメガネ」などをかけた状態で歴史を観、独自の縦糸を編んで、それらが多数絡みあった結果、いわゆる「歴史学」が形成されていくからだ(歴史書などを読むときは、著者がどのような縦糸を編もうとしているのか注目してみるとおもしろい)。
インテレクチュアル・ヒストリーは、経済でも美術でもなく、「人間の知的な営み」に焦点を当てるメガネをかけた一本の縦糸といえるだろう。つまり、観念(idea)や思想(thought/philosophy)を主人公とし、それらが織りなしてきたさまざまな人間の物語を多角的に分析する歴史学、という感じだろうか。

インテレクチュアル・ヒストリー、とりわけコンセプチュアル・ヒストリーの草分けとして知られるドイツの歴史学者ラインハルト・コゼレック(出典:Aeon)
そしてその方法論の一つとして提唱されるようになったのが、コンセプチュアル・ヒストリー(conceptual history、概念史学)だ。その名のとおり、概念(concept)という一つの単位に注目した歴史学である。
しかし20世紀初頭まで、歴史学の視野は主に国や言語の範囲に限られていた。Methodological nationalism(方法論的ナショナリズム)とも呼ばれるこの傾向は、あたかも歴史や社会過程が国や国家の単位でしか生成されないかのような幻覚を生み出し、その過程でたとえば政治的な目的のために歪曲した歴史像を構築するなどの危険をはらんでいる。
そこでグローバル時代に適したインテレクチュアル・ヒストリーやコンセプチュアル・ヒストリーを切り拓いているのが、Samuel MoynやMargrit Pernau、Andrew Sartoriといった歴史学者たちだ。
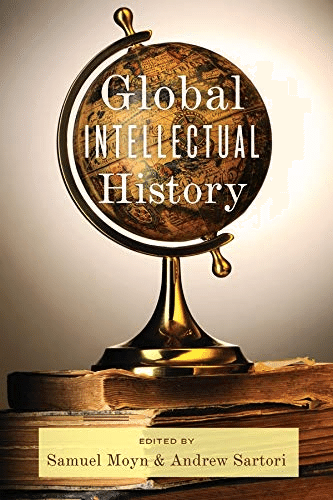
MoynとSartoriが編集した著書(2015年、出典:Columbia University Press)
彼らはまず、これまで固定的と思われてきた文化的、社会的、言語的、地理的な境界を、さまざまな接続関係や足跡を残していく仲介者(mediator)や橋渡し役が往来する空間と捉えることで、いかなる「閉鎖」も実はひらかれていることを強調する。
次に、概念などの移動や運動を追跡する際、欧州発祥の概念でも、「欧州という中心から波紋のように広がり、流布していく」という一方向的なベクトル構図で説明しようとする従来の視点ではなく、
- そもそも欧州で生まれたとされる概念も、実は欧州外からの影響のもとで生まれた可能性が十分にあること
- 新概念を受け取る側の言語がもとからもっていた諸概念や語彙、そしてその社会が置かれていた社会的・歴史的文脈が関係してくること
- 新概念の翻訳や変換(translation)に携わった行為者たちの創造的な変換作業に目を向ける必要があること
これらの点に注目し、越境文化的なコンセプチュアル・ヒストリーの土壌を耕している。
そこで特に中心的なトピックとなるのが、このtranslationという行為だろう。僕は「翻訳や変換」と訳したが、translationには、一つの言語から別の言語へ単純に内容を移転させるだけでなく、その過程でホスト側の言語そのものを変容させる力があるという意味合いが込められている。
それだけでなく、言語的なtranslationは、たとえば「近代性」という概念が日本語という言語に新たな語彙を追加しただけでなく社会的な変革をも可能にしたように、人間の社会的なリアリティと密接に結びついているということを前提にしているのだ。
抽象的な話が続いているので、ここでコースで扱った歴史的事例をいくつか紹介したい。
「society」から「社会」へ
一つ目の例は、冒頭でもあげた「社会」という概念について。
明治初期の日本では、数百年間つづいた封建制が崩壊し、その混乱のなか多くの知識人や政治家が西洋諸国と対等に渡り合える新たな政治形態を模索していた。
そこで1860年代から80年代にかけて一気に注目されるようになったのが、英国の社会学者ハーバート・スペンサーだった。従来の士農工商という身分階級制度に取って代わる視点として、スペンサーの自由主義的な自然権(身分にかかわらず、人間は誰だって人権を保有しているという考え方)の観点が支持を得ていったが、その根幹にあったのがsocietyという概念だった。

19世紀終盤の明治日本で最も愛読された海外の思想家の一人、ハーバート・スペンサー(出典:Wikipedia)
日本や中国の歴史に詳しい歴史学者ダグラス・ハウランドによると、
これらの主張における進歩というものの確実性には、その基盤となったある斬新な新概念があった。それが1880年代に広がっていた政治的実践や科学的思弁と密接に結びつき、物象化され有機的に理解されるようになった「社会」という”もの”である。1880年代以前は、「society」の標準的な訳語が存在しなかった。それはつまり、日本語においてそのような概念が存在しなかったといえるであろう(2000年、78頁)。
日本にはそれまで「世間」といった言葉はあったが、当時福沢諭吉や中村正直が読んでいたスペンサーやミルのいう「society」はどうやらニュアンスが少し違うらしい。「交際」と訳す者もいたが、それだと意味の幅が狭い。「政体」だと政治的すぎて、個々人間のインタラクションという意味合いが除外されてしまう。そこで80年代ごろに流行っていた「社」という言葉(明六社といった使い方)と「会」を組み合わせた「社会」がsocietyの訳語として使用されるようになっていった。
この新単語/新概念は、人々に大きな影響をもたらすことになる。
まず、それまで明確に区別されていた「政府」と「人民」の関係性は、この社会という概念でもって相互補完的かつ流動的なものとして説明できるようになった。すなわち人間の集合体の歴史において、一種の必然的な「進歩」の形態として、人々と政府が共構築するこの「社会」というものが顕現するとしたのである(これはスペンサーの社会進化論に基づいている)。
そしてその進歩の内容として、平権(平等な権利)や民主主義、工業化や科学の発展が必要とされた。これはさまざまな政治的・軍事的・経済的変容の引き金となっただけでなく、人間の関係性や人生の意義を考えるうえで(たとえば19世紀の終わりに使われるようになった「社会問題」という表現)、人々の新たな想像を可能にした。
スペンサーの「society」とそれを「社会」と変換した翻訳者、そしてその概念を各々の目的のために利用・拡張していった行為者のはたらきによって、極東の島国で近代化の真っ只中を生きる人々のリアリティが新たな色と解像度と疑問とともに広がっていったのである。
「近代性」や「自由」と結びつく「自然」の概念
もう一つ、セミナーで扱った日本の例に「自然」の概念がある。
米国の歴史学者ジュリア・アデニー・トーマスは、20世紀の思想史家丸山眞男をフランクフルト学派のアドルノやホルクハイマーと比較し、前者にとって近代性が「人間が自然を超克したとき」に訪れるものであると同時に、日本という国では未だに人間が自然の檻から抜け出すことができていないがゆえに、近代性を達成できていないとする、という考察を打ち出した。
トーマスが言及しているのは丸山が戦時中・戦争直後に書いた諸論考であるが、このころ(1930〜40年代)は、京都学派の西田幾多郎や和辻哲郎の哲学、また和辻が編纂に携わった『国体の本義』などにおいて、西洋中心ではないより日本らしい近代性を想像すべきだといういわば「日本ってすばらしい論」が、ナショナリズムの旋風を巻き起こしていた。
そこでは「自然」を支配し物質的な産業化を推し進めることで富と力を得た西洋諸国を批判し、逆に日本人は「自然」との美しい調和を保持しているからこそ凄いのだ、という主張がなされるのだが、丸山はこれを批判し、こういった日本すごいぞ論やそこに必然的に発生する他のライバル存在(西洋や中国)への敵対視は、戦争中のファシズムや超国民主義(ultranationalism)の惨劇を引き起こしただけでなく、日本の近代性は一方で西洋から独立しようと必死にもがいているにも関わらず、他方では西洋から学び、西洋を模範とするしか道がなく、その運命(という言葉を丸山は使わないが)において「自然」を脱却できていない日本は悲劇的である、というのだ。
ここで重要なのは、京都学派のような保守派が正しいのか、丸山のようなリベラル派が正しいのかではない。そのどちらも「自然」という概念を動員し、そこに人間や社会のあり方を投影することで、みずからの政治思想を構築し、補強しているという現実が興味深いのである。

20世紀を代表する日本の思想史家、丸山眞男(出典:国体文化)
もう少し現代的な例でいえば、トロント大学の人類学者佐塚志保の著書『Nature in Translation: Japanese Tourism Encounters the Canadian Rockies』(2015年)などが面白い。
佐塚は、カナディアン・ロッキー山脈の観光地バンフで働く日本人のツアーガイドに着目し、彼らが日々の活動のなかでいかに「自然」という概念を翻訳・変換しているかを分析する。
そこではカナダの「大自然」の素晴らしさを日本人観光客に理解してもらうために、さまざまな工夫がなされる。たとえば、保護区内をバスで走行中、車窓から見えるカナダの”手つかずの森林”を説明する際には、日本のスギ林とその産業的な林業史を引き合いに出し、いかにカナダの木々は真っ直ぐ生えるのにもかかわらず、人の手で植えられたのではなく「天然」であるかを強調する。
彼らは、この北米のカナダといういかにも開放的でゆとりのある世界において、人の意思とは関係のないところで天然的に育つ大自然を前に日本人が抱く圧倒的な自由や解放の感覚をみずからも経験していて、それをはるばる訪れてきた旅行客にも味わってもらうべく、北米の大自然だけでなく、それを支える北米的な精神文化までも翻訳・変換しているのだろう。

バンフ国立公園(出典:National Geographic)
多くの「当たり前」の「当たり前じゃなさ」に気づいていく
なんだかわかりづらい事例を選んでしまったのだけど、なんとなくこの超マニアックなコンセプチュアル・ヒストリーという学問がどういったことを探究しているのか、という像の輪郭がみえたかと思う。
概念の歴史に注目すると、単に学問的なことだけではなくて、普段理解していると思い込んでいるさまざまな「当たり前」に気づかされる(今さら聞きづらいようなやつ)。
自由、感情、科学、西洋、障害、ジェンダー、国民。
さらに無数に存在する概念たちのほとんどがトランスカルチュラルな歴史をもっていて、その結節点で起こることを追っていくと、いかに普段当たり前のように使っている概念が、実はさまざまなアクターが起こした偶然の積み重なりで形成されてきたのかに驚く。
なぜならそこには、宇宙人が一朝一夕には理解できないような、複雑で豊かな人間の歴史があるから。
さて、次はどの概念を掘り下げてみようかな。
主な参考文献
Moyn, Samuel, and Andrew Sartori, eds. Global Intellectual History. New York, NY: Columbia University Press, 2015.
Pernau, Margrit, and Dominic Sachsenmaier, eds. Global Conceptual History: A Reader. London, England: Bloomsbury Academic, 2016.
Howland, Douglas. “Society Reified: Herbert Spencer and Political Theory in Early Meiji Japan.” Comparative Studies in Society and History 42, no. 1 (2000): 67–86.
Thomas, Julia Adeney. “The Cage of Nature: Modernity’s History in Japan.” History and Theory 40, no. 1 (2001): 16–36.
Satsuka, Shiho. Nature in Translation: Japanese Tourism Encounters the Canadian Rockies. Durham, NC: Duke University Press, 2015.
おすすめ文献リスト
上記のMoynとSartori & PernauとSachsenmaierによる各書籍
ラインハルト・コゼレック(Reinhart Koselleck)ーー コンセプチュアル・ヒストリーの草分けとして知られ、『Geschichtliche Grundbegriffe』では歴史学におけるbasic concepts(代替がなく、それなしでは歴史を語れないような概念)を辞書的にまとめた。そのほか著書『The Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing Concepts』(2002年)など。
クェンティン・スキナー(Quentin Skinner)ーー ドイツではなくイギリスのケンブリッジ学派のインテレクチュアル・ヒストリアン。方法論などを探究。論文『Skinner, Quentin. “Meaning and Understanding in the History of Ideas.” History and Theory 8, no. 1 (1969): 57-89.』など
McMahon, Darrin M., and Samuel Moyn, eds. Rethinking Modern European Intellectual History. New York, NY: Oxford University Press, 2014.
日本関連でいえば、上記テクスト内で挙げた三人のほかに、Richard Reitanや栗山茂久など。
論文
期末論文では、明治時代の粘菌学者・民俗学者である南方熊楠における「森」の概念について論考を書きました。「奇人」や「知の巨人」と称される南方は、その「南方曼荼羅」や神社合祀反対運動、そして粘菌研究においていかに「森」なるものを概念化したのか。そしてその概念は、いかにトランスカルチュラルな諸過程の産物と捉えられるのか。興味のある方がいればどうぞ。
