
【ランチェスター戦略2】負けてもいい戦いはない。「僕が僕であるために」By尾崎豊(超ざっくり覚えるランチェスター)
対ヤンキー百戦錬磨のJoが語る「ランチェスター」(喧嘩の話ではありません)
最近は「頑張らなくていいんだよ」自分らしく、という風潮が日本に浸透していますが、今回の話はあくまで「勝負」という局面にフォーカスしています。

ランチェスター戦略(法則)イギリス人の航空工学の研究者F.W.ランチェスター(1868〜1946)が第一次世界大戦のとき提唱した「戦闘の法則」。
兵隊や戦闘機や戦車などの兵力数と武器の性能が戦闘力を決定づけるというものであることを話しました。
今回は中級編で少しビジネスに近づけて説明していきます。
≪1.あなたは弱者≫

基本的にこの記事を読んでいる人は「弱者」の戦略を選択、意識しなければなりません。(失礼な!!!)
後述しますが「強者」とは1位のみです。ではGoogleのラリーペイジが私の記事を読みますか?読まないですよね(笑)。

≪2.サラッとランチェスターVr.1と2≫
ランチェスターVr.1 とVr.2があります。
(Vr.1原始的な戦い)
戦闘力=武器効率×兵士数
・一騎打ち ・局地戦 ・接近戦
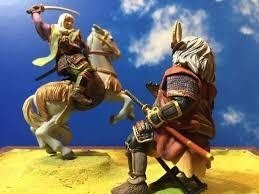
(Vr.2近代的な戦い)
戦闘力=武器効率×兵力数(2乗)
・確率戦 ・広域戦 ・遠隔戦
なんとなくVr.2になったら勝てない気がする・・・・( ゚Д゚)

≪3.このまま俺は負けてしまうのか・・・≫
結局、でかい奴が勝つんじゃん。そうなんです。数字だけで見ればでかい(数が多い)やつが勝つんです。
「負けたー気持ちいいくらいに負けたー!!!」
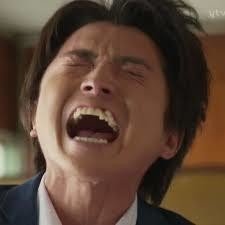
(ドラマチックを見たい場合はぜひ「カイジ」シリーズの映画を見てください
ん?でも信長は今川義元に勝ったよな?(前回の記事)Joはヤンキーに負けなかったよな。
そうなんです。Vr.1は「原始的な戦い」と表現されていますが現在もこの戦いは有効に動いていて意識しなければならないのです。
≪4.小が大に勝つ3原則≫
小が大に勝つにはVr.1に持ち込むしかないんです。つまりは局地戦やゲリラ戦などです。ベトナムもこの局地戦やゲリラ戦を得意としてましたよね。
自動車の世界販売台数1位がTOYOTAでも全世界で常にトップではありませんよね。

Vr.2 第二法則の戦い・・・戦闘力=武器効率×兵力数(2乗)に持ち込まれれば「勝てない」と思ってください。
なので何とか Vr.1の第一法則の戦いに持ち込むべきなのです。
第一法則適用下であれば、武器効率を兵力の比以上に高めれば勝てます。
例えば・・・「田舎で企業する」・・・四国に2013前までセブンイレブンがなかったのは有名な話でセブンイレブンが流通の効率を考え不採算と考え進出をしなかったのです。以下はコンビニにおける日本のシェアです。

ん?北海道のセイコーマートってなんだ?凄くない?

福岡出身の私はこの存在を知りませんでしたが、東洋経済では「セブンの上を行く最強コンビに」とまで言われています。
まさに局地戦で圧倒的勝っています。
≪5.ビジネスならこれを覚えておこう≫
武器・・・情報力、技術開発力、品質や性能、ブランドなどの製品の付加価値、顧客対応力、営業パーソンのスキルなどの質的経営資源
兵力・・・社員数、営業パーソン数、販売代理店の当社担当者数、製造現場の設備機器数、売り場面積、席数など、量的経営資源
≪6.大が小に勝つ必勝法≫
まぁ正直、「中身」が重要なんでこれがわかったからって・・・とは言わずに知っているだけでも少しは役にたつと思いますので。
STEP①局地戦、ゲリラ戦に持ち込む (ここで勝負する)
STEP②武器を磨く・・・大手と同じ「情報」「技術」では意味がありません。どう鋭利な刃物を作るのか、差別化していくのか。
戦闘力=武器効率×兵士数
で局地でいくらでも大に勝てるのです。
ただ、近年プラットフォームやインフラ事業など小が勝てない戦いも増えてきています。しかし、GoogleもSoftbankも歴史は浅く、最初から「大」ではなかったのです。
≪7.負けてもいいと思ってない?≫
価値癖、負け癖ってあるけど周りを見渡せば「負けてもいい」って思っている奴が多すぎる。「この数字達成できなくてもいいや」「練習試合だから負けてもいいや」「コンペで負けたけど給料変わんない」
もう、もう、もう腹が立つ!!・・・という個人的な苛立ちで締めたいと思います。
次回は少し数字を入れて中~上級編をサラッとやりたいかなぁと思います。
いいなと思ったら応援しよう!

