
「プログレッシヴ・ロック」愛憎。
俺は人間嫌い。
冗談抜きで、俺ほどの人間嫌いって、あまりいないと思う。
長いこと友だちも彼女もいない。
だけど、そもそも欲しくない。
昔は(遊び相手の女の子が欲しい…)とか、バカげたことを考えたりしたけど、生来の「メンドクセー」病の人なので、連絡とかとるのが「メンドクセー」ってなって、結局、ひとりのまま。
そのくせ若い頃の俺は(寂しい)って気持ちになりやすかった(メンドクセー奴だなァ)。
だけど、その寂しさを紛らわすための努力をするのが面倒くさい…。
それで、結局一人でいることが多いけど、最近は(寂しい)って、あまり思わなくなってきている。
理由は分からない。
一人でいるのが当たり前だから、だろうか。
それとも感受性が鈍ってきたのか…。
今回取り上げる「プログレッシヴ・ロック(以下プログレ)」は、そんな気難しい俺の精神安定剤だった。
だった、と過去形なのは、今はあまり必要としなくなっているからだ。
昔と違って、他の音楽でも代用できているんだ。
それにしても、この「プログレ」というジャンルほど、他人と話していると、イライラさせられるものもない…と、個人的に思っている。
「変拍子=プログレ」とか、その手のことを言われるだけで萎える。
また、この手の話しをするとすぐに「DREAM THEATER」の名前が出てくるのもイラつく(ちなみに誤解なきよう、俺はDREAM THEATERのファンだ。ライヴも行ったぜ!笑)。
つまり、何が書きたいかというと、俺の中の「プログレ像」と、周りの人たちの「プログレ感」に乖離があるのだ。
偏見だろ、と言われるのを覚悟で書くと、俺がプログレだ、と納得するものは圧倒的に昔のバンドに多く、主に60年代後半〜70年代まで、と思っている。
もちろん、これ以降も素晴らしいバンドは多く輩出されたが、何事にも「旬」「ピーク」というものがある。
俺はこの時期に「プログレ」の地盤が固められ、後の様々な音楽に影響を与えた…と、思っている。
今回取り上げるこの書籍は、そんな俺の価値観に合っている。
読んでいると突っ込みどころもあるが、ここでは割愛する。

こと、日本では「プログレ」というジャンルはあまり語られない傾向がある(当社比ならぬ、俺比 笑)。
だが、90年代にJ-POP界を席巻した「小室哲哉」はKIETH EMARSONの古くからのファンであり、影響を公言しているし、名プロデューサーの「佐久間正英」は「四人囃子」の元メンバーである。
日本を代表するドラマー「村石雅之」は「KENSO」の元メンバー…だったりと、実は普段慣れ親しんでいる音楽の中に「プログレ成分」は入っていることがある。
だいぶ前だけど、大河ドラマ「平清盛」は「TARKUS」を劇中曲として取り上げていた。
だが、定義付けが難しいのがこのジャンルの特徴だ。
正直俺も「プログレの定義を明確に言いなさい」と問われても、少し黙ってしまうかもしれない。
だが、この書籍に載っているバンドを紹介するのなら、分かりやすい。
この書籍から俺は、多数のプログレ・バンドを新宿とかで発掘した。
この書籍はまず「最重要10アルバムからのプログレ入門」と称したアルバムを10枚紹介している。
その次の章で「代表的名盤100選」と、100枚紹介している。
んで、まさか全部紹介する訳にはいかないので、ここでは「最重要10アルバム」の10枚を載せる。
①KING CRIMSON
1969年発売
「IN THE COURT OF THE CRIMSON KING(邦題 クリムゾン・キングの宮殿)」

②PINK FLOYD
1970年発売
「ATOM HEART MOTHER(邦題 原子心母)」

③YES
1972年発売
「CLOSE TO THE EDGE(邦題 危機)」
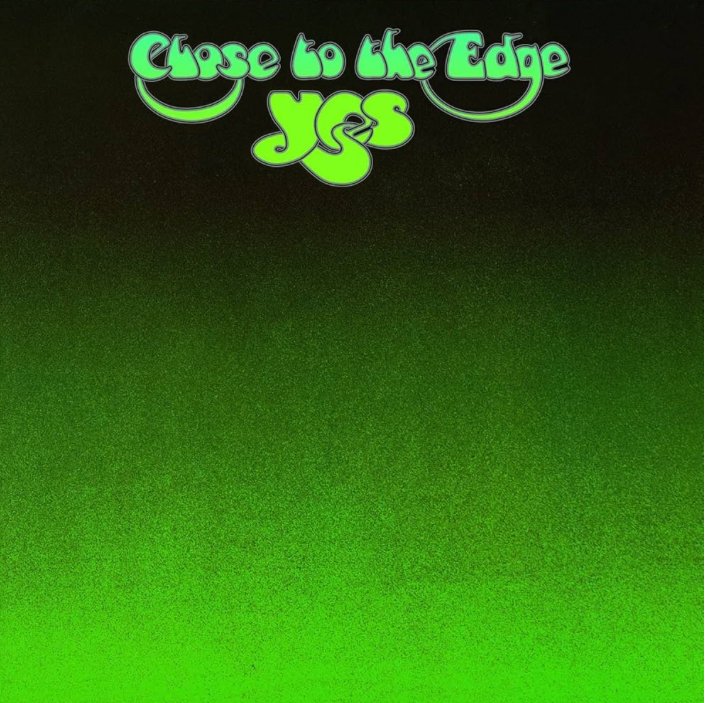
④EMERSON,LAKE&PALMER
1971年発売
「TARKUS(邦題 タルカス)」

⑤GENESIS
1974年発売
「THE LAMB LIES DOWN ON BROADWAY(邦題 幻惑のブロードウェイ)」

⑥PINK FLOYD
1973年発売
「THE DARK SIDE OF THE MOON(邦題 狂気)」

⑦SOFT MACHINE
1970年発売
「THIRD(邦題 3RD)」
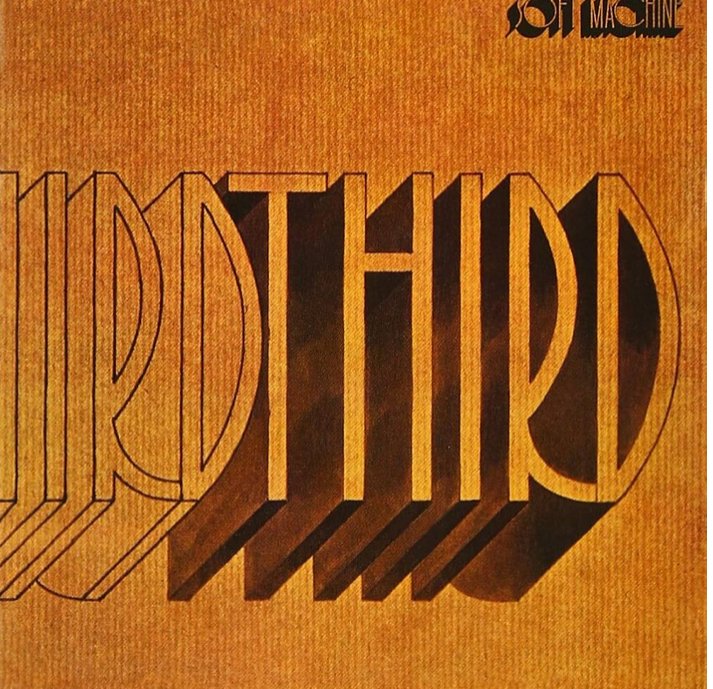
⑧GONG
1974年発売
「YOU(邦題ユー)」

⑨CAN
1973年発売
「FUTURE DAYS(邦題 フューチャー・デイズ)」

こっちはCANね。このアルバム、持っているけど内容覚えてない…(´・ω・`)
確か、ドイツのバンドだったかと。
⑩AREA
1978年発売「1978 gli dei se ne vanno,gli arrabbiati rsetano!(邦題 1978)」

…うん、これ、後半に行くにつれて、アヤシイ感じになっていくけど、皆さんはどれだけ知ってましたか?
こんなの、この書籍のライターたちの独断で選んだものなので、異論ある人もいるだろうけど、個人的には①〜⑥を聴いていれば良いんじゃないかな、と思う。
俺が思い入れあるのが⑤のGENESISの「幻惑のブロードウェイ」。
このアルバムは凄いよ。
なんつったって、この当時でコンセプトアルバム(アルバムを通して一つの物語になっているアルバムのこと)で、音楽と歌詞だけでは説明しきれないから、ヴォーカリストのPETER GABRIEL執筆の小説が付いている。
「ヒプノシス」というアート集団のジャケットも、アーティスティック。
視覚的にも、音楽的にも「プログレ」している。
しかし、この作品の「具体的な意味」は未だに分からない……誰にも分かることはないだろう。
「レエル」という、ニューヨークに住んでいる不良少年が、不可思議な世界に迷い込んで、ユニークなキャラクターとの出会いの中で、終わりの見えない旅を続ける…というストーリーなのだが、読んでいてあまりにも「不可解」である。
メインの作者のGABRIEL自身「意味は誰にも分からないだろう」と述懐していた(GESESIS SONG BOOKというドキュメンタリーでの発言)。
俺の10代はGENESISと共にあった、と言ってもいいほどGENESISは聴いていた。
しかし、このGENESISは、元メンバー含め、来日公演が少ない。
唯一、頻繁に来るのがギタリストのSTEVE HACKETT。

俺はHACKETTのライヴは計4回行った(六本木STB、川崎クラブチッタ2回、なんばハッチ)。
いずれも良かったが、とりわけ印象に残ったのが、川崎クラブチッタ(上の写真の更に前。何年かは失念しました)。
早めに「ラ・チッタ・デッラ」に来ていた俺は、噴水広場のラジオブースでHACKETTがゲストでトークをしているのを発見した。
(マジか…!)
まさかの本人がトークしているのを見て、軽くコーフンした俺。
ラジオが終わると「Get 'em by Friday(初期GENESISの曲)」がかかり、HACKETTがラジオブースから出てきたではないか!
どうやら、ファンと記念撮影するらしい。
そこで俺も一緒に撮った。
すぐ目の前にHACKETTがいるのだが、彼の黒いTシャツの肩に、フケが落ちていたことを覚えている 笑
(HACKETTも人間なんだなぁ…)と、思ったものだ。
その後、HACKETTは階段をのぼり、レストランなどがある施設に向かった。
俺は後を追い、
右手を差し出して
「NICE TO MEET YOU」
と、死ぬほど下手くそな英語で、HACKETTと握手を交わした。
これ以降、彼のコンサートに行っても、このような機会はなかったことを考えると、貴重な体験だったことは間違いない。
HACKETTはGENESISの元メンバーで、最も精力的に音楽活動をしている人だ。
そのバイタリティーは驚嘆に値する。
もし、また来日するようなら、行くと思う。
GENESISだけは本当に特別だから。
上記のバンドだとYES,KING CRIMSONもコンサートに行った。
KING CRIMSONに至っては、渋谷のオーチャードホール公演で不覚にも泣いてしまった…😞。
KING CRIMSONも本当に思い入れがあったので…。
なんだかんだで計3回KING CRIMSONは観れた。
プログレが俺に与えた影響は甚大なものがあり、ほとんど縋るように聴いていた時期もある。
今はあまり聴かないけれど、それでも曲をコピーしたりして、自分のできる範囲で接している。
これを読んでいる皆さんも、良かったら上の10枚のどれか、気になるものあったら、聴いてみてください。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
了
