
はじめに
初めまして。株式会社ドットコムの坂井です。
こちらのnoteでは、少数株式に関しての情報を発信していきます。
具体的な事例を交えながら、少数株式の基本やポイントを丁寧にご説明させていただきます。
早速ですが、まず、弊社について少し紹介させてください。
代表のいしだは、東証一部上場企業の創業者一族の家に嫁ぎ、「同族会社」はどのようなものか実体験として理解しており、少数株主のお気持ちはよく分かります。
代表の周りも、非上場企業の「少数株主」「同族会社」であるが故の苦い経験をしています。祖父の代まではとても仲のよい兄弟だったのが、子から孫へと相続を繰り返す中で株式が分散し、会社との関係も希薄になってきたそうです。
そうして少数株主となった者は相手にされず、会社は分散した株式をとにかく安く買い集めようとします。場合によっては、第三者やメインバンクを使ってまで強引に自社株を増やしていくところもあります。

ニュースソースとして扱われることも少ないため、世間一般ではあまり知られていませんが、「少数株主」は、適正価格で換金したいのに、会社の言いなりに二束三文で売るしか方法はないのか? と悩んでいる人が全国に数知れずいます。実際のところ私たちの会社では、社会問題として捉えています。
FAS(フィナンシャルアドバイザリーサービス)を中心に、生前相続対策支援、不動産投資等を行っておりますが、その中で、友人やお客様からの要望により、少数株主の非上場株式売却・現金化支援のノウハウを確立してまいりました。
今回のnoteで一番にお伝えしたいことはこの3つです。
◯非上場株式は、困難であっても売却できる
◯譲渡制限付き株式でも売却できる
◯非上場株式の売却には、税金の知識が欠かせない

今まで八方塞がりだと絶望していた方々には、このような非上場株式現金化の方法があることをぜひ知っていただきたく、このnoteがみなさまのお悩みの解決にお役に立てれば幸いです。
非上場株式には売買するマーケット(株式市場)がない

非上場株式には上場会社のような株式を売買するマーケット(株式市場)がありません。
そのため、非上場株式を所有していてもなかなか売却することはできないのです。それはたとえ業績を大きく伸ばしているような優良企業の株式であっても同様です。
上場企業の場合は、好業績を上げれば株式市場での株価が上がり、配当金も上がります。ところが非上場企業は、株価が上がるわけではありません。また、業績に関係なく配当のない会社も多いです。非上場企業の場合は、株価も配当も経営者の考えひとつで決まります。言ってみれば、経営者の好き勝手に決められるのです。

会社法で規定されているにもかかわらず、株主総会をやらない、取締役会をやらない、配当金は出さない、従業員の給与は安いまま上げない、それなのに経営者は高い報酬を取り、家族の生活費も遊興費も会社の経費として計上し、公私混同は珍しくありません。
そして、株式を公正な価格で買い取らない、このような非上場会社はごまんとあるのです。
非上場株式を売却するには、その株式を発行している会社に買い取ってもらうか、第三者の買い手を探してきて買ってもらうしかないのですが、会社が買い取らないと言えば、それ以上なす術はありません。発行会社に株式の買取義務はないからで す。
また、仮に発行会社が買い取ってくれても額面等、資産や業績から見ても、とても妥当とは思えない価格でしか買い取ってくれないケースは驚くほど多いのです。さらに、上場会社のように株式市場で株価が決まっているわけではないため、個人で買い手を探すのは容易ではありません。
※発行会社に株式の買取義務はありませんが、極めて限られた条件のもとで「株式買取請求権」を行使し、株 式の売却が可能なケースがあります。行使できるのは、株主総会で特別な決議が行われたとき(定款変更・譲渡制限等(116条)、吸収合併(785条)、吸収分割(797条)、新設合併等(806条)、株式交換(797条)に関する議決)です。
相続税問題

現金化できないのに、多額の納税義務が……
このように、非上場株式には「買い手が見つからない」「見つかっても買い叩かれる」といったことのほかにも、相続税の問題も挙げられます。
以下は、大正時代からの老舗製造業V社の株式を保有していたA氏の事例です。
お父様が社長を退任した後、A氏が代表取締役、弟が専務取締役となってV社を切り盛りしてきました。大手得意顧客からの信頼が厚く、業績は安定していましたが、兄弟で力を合わせて新規顧客も開拓し、この 年、少しずつ業績を伸ばしてきました。
しかし、3年前、A氏は突然解任され、弟が代表取締役となったのです。弟は、A氏が知らないところで親族株主に根回しし、議決権の3分の2を確保した上で、株主総会でA氏を解任決議したのです。

なぜ、こんなことになったのでしょう。A氏が社長時代、弟の反対を押し切って、 思い切った改革を断行したことも奏功し業績を伸ばしていたのですが、業績と反比例のように兄弟の関係は冷えていきました。弟は、経営方針が合わないことや、兄への嫉妬からの行動だったのでしょう。
会社への貢献の大きかったA氏は、保有株式( 20%)の買取り交渉をしましたが、なかなか折り合いがつかないまま時間だけが経過していき、「このままでは相続税が心配だ」と弊社に相談があったのです。
A氏が依頼した税理士が算出した相続税評価額は約7億円でした。このまま会社が買い取ってくれなければ現金化できないのに、相続税は最高税率の 55%、概算で3億円以上の現金を用意しなければならないのです。
A氏は突然解雇されたため、先行きの不安もあります。そのうえ相続となった場合に、子どもが負担する相続税の心配もA氏に大きくのしかかったのです。
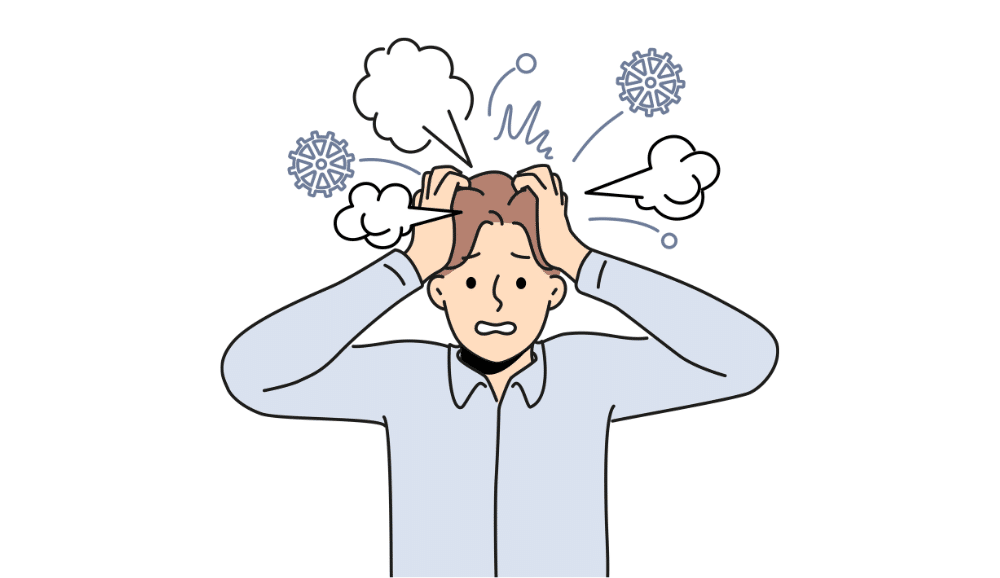
同族会社における株式相続税は、相続する株式の相続税評価額というものを元に計算されることが多いのですが、これは、国税庁が作成している「財産評価基本通達」の「取引相場のない株式等の評価」に基づいて評価することになります。
取引相場のある上場株式であれば、取引所の株価という客観的な数字で株価を評価することができますが、中小企業のような非上場会社の株価を評価する場合、客観的な数値がないためです。相続税評価額は、相続する株式や会社規模、業種により異なります。

非上場株式とは、上場株式以外の株式の総称であり、非上場株式の中でも上場株式に近い規模の大会社から、個人事業並みの小規模会社まで、その内訳は千差万別です。
よって、非上場株式の評価方法を定める財産評価基本通達では、取引相場のない非上場株式を、規模に応じて大会社・中会社・小会社に区分し、その区分に応じてそれぞれに即した評価方式を定めています。
また、非上場株式を贈与や相続で取得した株主が、同族株主かそれ以外の株主かによっても評価方法が変わってきます(後述しますが、「同族株主」は株式保有比率が高いためです)。同族株主か否かで会社経営への影響度が変わるため、株式保有目的も変わってくると考えられるからです。
支配権を有する同族株主が保有する株式の評価は、会社の業績や資産内容等を反映した原則的評価方式(類似業種比準方式、純資産価額方式およびこれらの併用方式)により評価し、同族株主以外の少数株主が保有する株式は特例的評価方式(配当還元方式)により評価することになります。
一般的に特例的評価方式(配当還元方式)による評価の方が株価は低くなる傾向にあります。
評価対象会社が保有している資産の大半が株式・土地等といったような、資産内容が特異な会社、開業間もない会社・休眠会社等の営業状態が特異な会社(特定会社)は、通常の事業活動を前提としている原則的な評価方法は馴染まないため、特定会社として個別にその評価方法が定められています。
事例のように、現金化できない非上場株式にもかかわらず、多額の納税義務が発生するという最悪の事態が起きることもあるのです。特に、事例のV社のように長い歴史があり、安定した業績を続けてきた非上場会社の中には、自社株の相続税評価額が高くなることがよくあります。内部留保として利益の蓄積が大きくなるからです。相続税の税率は、累進課税制度(課税額が高いほど適用される税率が上がる課税方式)によって10%から最大55%にもなります。

実際に相続が発生した場合は、事業を引き継がない少数株主であっても、持ち株比率に応じて相続税を計算する方式が異なります。
「自分は会社を継ぐわけではないから関係ない」のではなく、会社を継がないからこそ不可避で、かつ大きな影響が生じます。
事業承継をする大株主には税制の優遇措置がありますが、少数株主に対しての措置はありません。
だからこそ、あなたは自分自身で考え、備え、心の準備をしておく必要があるのです。
なお、このnoteでは、相続税評価ではなく、非上場株式を売買する際の売買価格の考え方を中心に述べたいと思います。
非上場企業の多くは「同族会社」

非上場企業の多くが「同族会社」です。分かりやすく言うと、特定の支配株主によって経営権が握られている会社のことです。
具体的には、3人以下の会社の株主等、およびその株主等と「特殊の関係」にある個人および法人(これを「同族関係者」といいます)が、発行済株式総数又は出資総額の 50%超を保有している場合、その会社は同族会社となります。
なお、同族関係者の範囲について、ここでは個人の場合を説明します。
①株主等の親族(配偶者、六親等以内の血族、三親等以内の姻族)、②株主等と事実上婚姻関係と同様の事情にある者、③個人株主等の使用人、④上記3項目以外の者で、株主等から受ける金銭やその他の資産により生計を維持している者、⑤上記②から④に該当する者と生計を一にする、これらの者の親族となっています。
創業者から子に、子から孫に、と株式が相続され、孫や曾孫以降になると、会社の役員でもなく従業員でもなく、経営に全く関与していない、配当もなく、経営している親族と疎遠である、あるいは関係が悪く、株式売却の交渉もしづらい、といったケースも多く見受けられます。
親族だからこそ、なおさら株式売却の交渉が困難という事例が多いのです。その点、私たちのような、株式発行会社とは何のしがらみもない第三者の方がむしろ話が進むケースも多いのです。
これからこのnoteでは、株式について知識のない人でも分かりやすく、株式にはどのような種類があり、
・その中でも自分が保有している非上場株式はどのような性質を持つのか?
・非上場株式を保有する上での株主の権利にはどのようなものがあるのか? ・ 非上場株式を保有する上で起きうる問題にはどのようなものがあるのか?
・問題を回避する方法はあるのか?
・非上場株式の株価評価はどのような算定方法があるのか?
・非上場株式を換金化する方法はあるのか?
・またそのメリットはなんなのか?
事例を示しながら、みなさまにお伝えしていきたいと思います。
=============================
\ 非上場株式を正当な価格で一括買取、現金化します /
あなたもこんなお悩みありませんか?
✔️ 相続税が高いから現金化したいが、買い取ってもらえない
✔️ 不当に安い価格、もしくは額面で提示されている
✔️ 売却交渉ができないぐらいと株式発行会社と関係が悪い
そんなお悩みは少数株ドットコムにお任せください!
👇まずは気軽に無料ご相談
=============================
