
答えのない数学#5 【津田塾大学 学芸学部 数学科 原隆先生 ロングインタビュー】
いろいろな同期の存在
編集者:高校のときにガロア理論の存在を知って,大学で本格的にやってみようと思われたとのことですが,その中で例えば書籍ですとか,直接面識があるかどうかは別として数学者の先生ですとか,たぶんその当時は論文はまだ手に取られることはなかったかもしれないですけど,なにかそういうものとの出会いやきっかけのようなものはありましたか.
原先生:あんまり1~2年生に関しては,そんなに.うーん,どうだろうな.
編集者:これは私の勝手なイメージなんですけれど,原先生はすごく――こんな言い方をしていいかどうかはあれなんですけど――,本を読むのがすごく速そうですし,吸収の速度が速そうという感じがします.
原先生:いえいえいえ(笑)
編集者:数学科の中には,私の同級生にもいたんですけれど,すごい勢いで本を買って,すごい勢いで読破して,というタイプの友達もいて.授業には出てるけど,内職で数学書をひたすら読んでる――みたいな同級生もいてですね.
原先生:僕はそういうタイプではないですね.むしろ,僕の同期の,IPMUの阿部知行君(東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構教授)とか――.
編集者:阿部先生とは同期なのですね.
原先生:実はそうなんです.あと同期といえば,今回の『手を動かしてまなぶ 群論』を献本させていただいた北山貴裕君(東京大学大学院数理科学研究科准教授)とか,見村万佐人君(東北大学大学院理学研究科数学専攻准教授)とかも同期生で.
編集者:そうだったんですね.
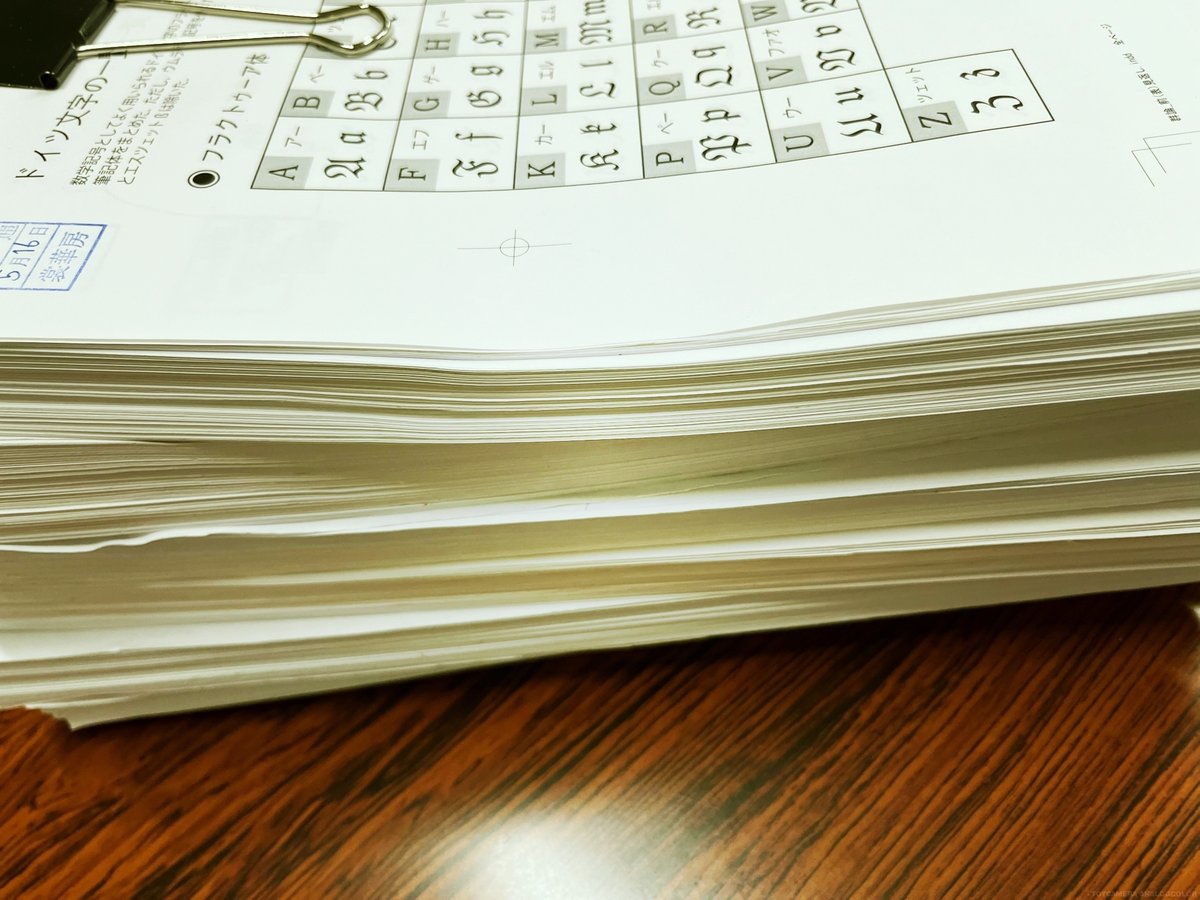
赤字の入った校正刷がうず高く積み上がる.
原先生:去年,見村君と三石史人さん(福岡大学理学部応用数学科助教)そして高津飛鳥さん(東京都立大学大学院理学研究科数理科学専攻准教授)が,同期の数学関係者が40歳になることを祝う研究集会「多分野交流会」を企画してくださって.今月の『数学セミナー』にも巻頭言で高津さんが書いていらしたような.
編集者:あ,はい.書いておられましたね.あの会に参加していらしたのですね.

「例えば,学生のときにあんなことあったねという同窓会的な雰囲気があり,
たまにはこうして肩を並べてほんの少しだけ立ち止まる良さを感じた」
という文章に強く共感した.
原先生:同期で久しぶりに会って,という感じでしたね.初めてお会いする人もたくさんいて,とても楽しい会でした.そういえば『数学セミナー』編集長の飯野さんも同期になりますね.大学2年の後半から専門に分かれるので,その辺から一緒という感じですかね.ただ,在籍時によく話したりとか,そこまではしていなかったとは思うんですけど.
編集者:いろいろな方との繋がりがあるのですね.
原先生:あと,見村君とは麻布中学校のときからの繋がりで.見村君という人は本当に頭がいいというか,すごいというか.学年の中でも有名で,しかも,数学はすごくて.将来は数学をやるに違いないとずっと言われていたりしたんですよ.
編集者:見村万佐人先生,そうだったのですね!
原先生:私なんかは,当時は数学をやりたいなんてことはおくびにも出していなかったんで,数学科に進学したとき,見村君に「え!?数学科,来たの??」みたいな感じで(笑).
編集者:ええー,そうだったんですか.
原先生:そんな感じだったんですよ(笑).見村君としては超意外だったみたいで.
編集者:数学科に進学して改めて再会したという感じですね.驚きの再会とという感じだったんでしょうね.
原先生:そうそうそう(笑).私はさっきもお話した通り,中高は国語少年とみんなにも思われていたので「まさかお前が来るとは思わなかった」と(笑).高校時代はそんなに喋ってなかったんですけど,やっぱり意外だったみたいで.
編集者:高校から今までご親交があって,長いご縁ですね.
原先生:そうですね.見村君とはすごく長くお付き合いさせていただいてます.で,私は彼や阿部君のようなタイプとは違って,自分のペースでやればいいやじゃないですけど,高校時代から大学の線形代数をやっていたとか,そういうタイプでは全然なかったです.数学は大学に進学してからやり始めて,東大のカリキュラムですからかなり進度は早いですけれど,それに則ってやっていたという感じで.それこそ阿部知行君なんて数論幾何の教典の EGA Elements de Geometrie Algebrique,1960-67 とか SGA Seminaire de Geometrie Algebrique を一人で読んで――みたいな感じだったんですけど,僕は全然真逆のタイプでひいひい言いながら授業の内容を復習していました.

アレクサンドル・グロタンディーク(1928年3月28日-2014年11月13日)と
ジャン・デュドネ(1906年7月1日-1992年11月29日)が著した
『代数幾何原論』 "Elements de Geometrie Algebrique", 通称 EGA.
整数論のセンス
原先生:むしろそういうところでいろんな先生と巡り会えたのが良かったのかなぁと.今にして思えば,有名な先生がたくさんいらっしゃって.
編集者:原先生はいろいろな有名な教科書を書かれている先生方のTA(※ ティーチング・アシスタント,略してTA)をたくさんされている印象です.TA経験が豊富といいますか(笑).すごい数学者の方々のTAを担当されていたのだなと改めて感じました.
原先生:そうなんですよね(笑).東大はすごい先生が山ほどいらっしゃるところなので.
編集者:あと,私,てっきり原先生は「天才型」だと思っていたので,先程のお話はちょっと意外でした.
原先生:そんなことないです(笑).でも,やっぱり当時の代数の授業は,私にとってはすごくいい年で,群論とか環の初歩とかの授業を斎藤秀司先生(東京大学大学院数理科学研究科名誉教授)が担当されていたんですね.斎藤先生がちょうど東大数理に赴任された直後だったんですけど.
編集者:確か,原先生の学部のときの指導教員も斎藤秀司先生?
原先生:はい,学部4年のゼミも斎藤先生にお願いしました.それで,当時の学部の演習の授業のときかな,環準同型定理のところで「ガウスの整数環ではこれがこう分解して・・・」とか,いかにも数論っぽいお話をしてくれたりとか,「このクンマーの理想数がイデアルの元となっているんだ」とか,そういうお話を,たっぷりと演習の時間に.おそらく斎藤秀司先生はノリで話してくださっていただけかもしれないんですけど,それに感銘を受けて.
編集者:ええ.
原先生:3年の後期かな,学生の自主ゼミみたいなものがあって.最後に口頭試問だけあるんですけど.高木貞治の『初等整数論講義』(共立出版)っていう有名な本で,後ろの方に二次体のイデアル論の問題があるっていうので,それを自主ゼミでやったっていうのが本格的に整数論を始めた経験になりますね.

この本の内容 代数学講義の姉妹編で,初等整数論・連分数・二元二次不定方程式・二次体の整数・二次体の整数論および付録として二次体論の高等な部分にも論及し,かつ二次体のイデアルの類数の計算やディリクレの定理の函数論的証明法を平易に概説した名著.
https://www.kyoritsu-pub.co.jp/book/b10011316.html
原先生:で,その後,環論――加群と環論の後半とかネーター環のところ――は桂利行先生(東京大学名誉教授)に,ガロア理論は志甫淳先生(東京大学大学院数理科学研究科教授)に習ったりしたんですけど,代数学の先生,特に整数論の先生方にはお世話になりました.あと,それこそ2年生の解析とかかなぁ.グリーンの定理とか出てくるでしょう.あれは斎藤毅先生(東京大学大学院数理科学研究科教授)に習ってたりするんですよ,実は.
編集者:えっ,斎藤先生ですか?少し意外な感じですね.
原先生:当時はそういう教養科目も担当されていらしたんですよ.
編集者:今でこそ,ご執筆されている教科書の『集合と位相』(東京大学出版会)の授業を持たれているイメージが強いですけれど,そのような科目も担当されていたのですね.

写真は編集者が学生のときに買ったもの(若干カバーが古びてしまっているがお赦しを).
多くの数学科生にとって愛着があり,人気のテキストである.
原先生:ええ.当時はそんな感じで.そんなこんなで整数論のセンスに関しては,いろんな先生方から自然と身についていった感じです.
やっぱり整数論
編集者:ちなみに,高校のときにガロア理論に興味を持たれて,数学科で過ごされる際も代数に照準を絞って過ごされていたと思うんですけれど,途中で代数ではなく,幾何や解析に進もうかなと迷うことはなかったのですか.
原先生:解析はなかったですね(笑).解析はどうしてもちょっと苦手意識があったんですよね.誤差評価とかが特に私はあまり好きではなくて.なんだかんだで解析も整数論では使いますけどね.
編集者:幾何はいかがですか.
原先生:幾何はちょっと面白いなとは思いました.でも,結局,私はやっぱり整数論かなぁと.まぁ,だからそのときは東大が数論幾何のメッカになっているなんてこともあまり知らなくて.その後どうするかもあんまり考えてなかったんですけど,修士を受けるときですね.結構,大変だったんですけども,整数論をやりたいということで進んでいった感じですかね.
編集者:なるほど.修士課程は辻雄先生のところに進まれて.
原先生:はい.辻雄先生は授業を受けた経験がなかったんですけど――辻先生は$${\bm{p}}$$進ホッジ理論の先生で――,栗原将人先生(慶應義塾大学理工学部数理科学科教授)とのご共著や共同研究とか,結構,$${\bm{L}}$$関数絡みのことも実は研究されていて,私はそのときは岩澤理論をやるとかは全然考えてなかったんですけど,最終的には一番いい先生のところでお世話になったなぁと.私の後,岩澤理論をやりたい人は辻先生のところに行くみたいな流れができたみたいなので.

写真は東大新聞オンラインより.
編集者:東大ですと,研究テーマは完全に自分で選ぶといいますか,見つけるという感じですよね.
原先生:大体そんな感じですね.辻先生の研究室の卒業生には社会に出て活躍されている方など多彩な方がおられるんですが,個人的にちょっと興味深いのは,卒業後に数学者の道に進まれたお弟子さんの中で$${p}$$進ホッジ理論を専門にされている方ってあまりいらっしゃらないんですよね.
編集者:そうなんですか(驚).
原先生:そう.日本で$${p}$$進ホッジ理論を研究されている方だと,例えばRIMSの越川皓永さん(京都大学数理解析研究所助教)とか,他にもいらっしゃるんですけど,辻先生の研究室ではゼロみたいな感じです.私のときもそうだったんですけど,辻先生は「別のテーマをやってくれると私も勉強になって助かるんで,どんどんやって下さい」という感じのところがあって(笑).それもあって,結構,みんなバラバラなテーマをやってるんですよね,辻先生のところって.やっぱり東大数理の中でも,斎藤毅先生のゼミでは分岐理論をやってるとか,志甫淳先生のところだとクリスタリン・コホモロジーとか$${\bm{p}}$$進コホモロジーをやっている人が多いとか,そういう傾向はもちろん指導教員の先生の影響っていう感じであって.あとは,斎藤秀司先生のところだとモチーフ理論とか代数的サイクルとか.先生のご専門に応じてかなりカラーが出るんですけど,辻先生のところは結構異彩を放っている研究室だなと.私はそういうところがすごくいいなと思ってますけど(笑).
編集者:いろいろ面白いですね.やっぱり指導教員の先生の選択というのは,将来において少なからず影響を受けるといいますか.
原先生:いやぁ,私の場合は本当にご縁があった,良かったとしか思えません.
【津田塾大学 学芸学部 数学科 原隆先生 ロングインタビュー】
← 答えのない数学#4 → 答えのない数学#6
(文責: 裳華房 企画・編集部 久米大郎)
