
古代技術:炭とナトロンで花崗岩の中の石英を融解〜その2 遺跡は人工の石?
強烈だった前回の続きから見ていきます。今回も驚嘆の事実がw
エジプトの有名な製造中のオベリスク

岩盤から切り出される直前のオベリスクの色が日光の加減でちがく見える時がある。オベリスクは周りの黄色っぽい岩よりも灰色が強い。
これはマルセルさんがいうように炭とナトロンをかぶせて、酸素を送り込み高温にして石英を溶かすことで表面の組成が変化したせいではないか?(もしくは天然の石を人工の石でコーティングしてある。後述)

ペリッとハゲそうな部分があり
揺すると柔らかい感触がある。
(人工の石の材料の混ぜ方が均等じゃなかったかも?後述)

実際にインタビューしているほうの兄ちゃんがオベリスクを訪れたときにこのような柔らかい部分が周辺にあることに気がついた。
それに対し、単に1000度以上に加熱するだけでもこういう感じにハゲることはあるとマルセルさんの体験から証言。同じ工程ではないかも。
荒い粒子のナトロン
現代の工業製品としてのナトロンは細かい粉末タイプであるので、これを岩に炭と一緒に乗せて酸素を吹き付けると粉末が飛び去ってしまいうまく行かないらしい。空き缶にいれて加熱したときはうまくいくし、炭で岩を1100度までなにも囲わずに熱することも可能なので、天然の水が乾いてできたような荒い粒子のナトロンが入手できればうまく行くんじゃないかとマルセルさん。
エッチング
エッチング(英: Etching)または食刻(しょっこく)とは、化学薬品などの腐食作用を利用した塑形ないし表面加工の技法。使用する素材表面の必要部分にのみ(防錆)レジスト処理を施し、腐食剤によって不要部分を溶解侵食・食刻することで目的形状のものを得る。
つまりナトロンで表面をエッチング(腐食)させて柔らかくし、石のハンマーで砕いて剥がして加工したんじゃないの?そうやってできた跡が有名なスクープマーク(スプーンの裏を押し付けたみたいな、アイスクリームをすくい取った跡みたいなやつ)。これがナトロン理論である。

滑らかさが異常。やはり柔らかくしてから研磨してそう。


流し込むためのもの。そうしてグラナイトを腐食し剥がすのが次の工程。
そうして得られるのが水ガラスだ。

水ガラス

ケイ酸ナトリウムの水溶液、もしくは乾燥させたシリカゲル。これがマルセルさんがいっているWaterglassであろう。
水ガラスが凝固した物を加熱乾燥させると、シリカゲルと呼ばれる二酸化ケイ素のキセロゲルとなり、多孔質で表面積が大きいため、乾燥剤や触媒などとして利用されている
加熱して作っているのでシリカゲルとなっていると思われる。
エジプトの壁画はナトロンを使ったガラス作りの様子を描いている?
ナトロン理論ではこのスクープマークはモルテン状のナトロンをためておくための構造だという。
しかし、モルテンとなったナトロンを流し込んでもあっという間に冷めてしまい、有効に石英を引き出すことは不可能である。
古代エジプト人はどうやってこの温度管理を行ったのっだろうか?
そのヒントがこのレクミラの墓の壁画にある。

右上にはナトロンの採掘場と思われる絵
左下の絵にはかまどがあり何かを熱している
そして二人の作業員が地面?を何かで押し付けている
エジプト学の専門家によるとこの工程は金属を抽出しているもので、作業員が踏みつけているのは金属らしい。まだ鉄は使われていない時代。銅か?
以下、これは金属を抽出する工程だと仮定したときの問題点。

金属を描くのに水色で描く?
溶けた金属が平らな地面から逃げ出しそう。

バネの代わりに紐でもって持ち上げていたに違いない。
この太陽みたいに描かれたものがかまどみたいに水色のものを覆って熱が逃げないようになっており、燃焼を継続するために空気を送り込んでいる感じに見えるのは金属精製説でも同様。
地面で何かを熱しているのだという点から、マルセルさんとしてはこれはモルテンナトロンでグラナイトをエッチングしている工程じゃろうと。
そうやって見てみると

均質じゃない。黒いのは炭で白はナトロンか?
混ぜて熱したらモルテンのナトロンになりそう。
ちゃんと混ぜたら水色のやつになる?
そして右へ工程が進むと加熱されたモルテンは白い部分が多くなっている。

周りに炭が不十分で熱せられずに表面に浮き出てくるナトロンを
こすり取ってると実験からリアルな想像するマルセルさんw
マルセルさんの想像では、これはナトロンと炭を混ぜたものを熱してガラスを作っている作業じゃないかと。岩にナトロンと炭の混合物を押し付けて加熱すると、溶けたナトロン溶液が花崗岩の中からシリコン(ケイ素)を奪ってガラスになるのだ。マルセルさんの実験でポロポロと岩の表面から出てくる小石みたいなやつがそれだ。色が黄色いときがあってそれはWater glassが混ざった小石なのだ。

この岩から剥がれたものを砕いて水につけておくためにあるのが後ろにある壺だろうと。数日後には透明なガラス(Water glassつまりSodium Silicate溶液)が出来るはずだと。
後は色素を混ぜて酸と一緒にすればガラスになり、ステンレスも作れるだろう。

金属精製工程ならなぜこれが一緒に描かれてる?

ストーンヘンジなどにもあるこの滑らかな削り出しのあと。
ペルー、メキシコ、イギリス、エジプトなど世界各国で
みんなこれやってたわけだ。
現代の科学で人工の石を判定する手順

現代でも水ガラスは人工の石を作るのに使われているらしい。ガラスも石もケイ素だらけだし、そうかもね。

計測不可能

既存の石にキャリブレーションをする必要がある
蛍光X線分析(XRF)

物質にX線を照射すると、物質を構成する元素固有のエネルギー(波長)を持つ蛍光X線(特性X線)が発生します。この蛍光X線のエネルギーを測定すると含有されている元素が分かり(定性分析)、各元素の蛍光X線の強さから濃度を計算する(定量分析)ことができます。このように未知の物質にX線を照射し、そこから発生する蛍光X線を測定することで、物質の定性あるいは定量分析を行なう方法を蛍光X線分析法といいます。
XRFでもマススペクトル質量分析と同じで、水素、酸素、炭素、ケイ素といった石を構成している重要な元素については測定ができないとマルセルさん。
その他の大きめで蛍光をだして来やがる元素や分子について、組成とその比率については分かるわけですが、その比率だけをもって「これは人工の石です!」「これは天然の石です!」とは言えないわけだ。
これがキャリブレーションの罠。キャッチ22な状況になっており、人工の石を判定するにはまずは既知の人工の石のサンプルをもってきて、それに対してキャリブレーションを行い、それを用いて未知の石が同じ組成をもつか判定して人工の石の判定が可能になる。
そういう状況なので、古代の人々がつくった人工の石であると既に判明したものを一つは見つけないと話が始まらんのだ。
現代の地質学者はXRFやマススペクトル質量分析を使わない

吸水性を図る
石の特性を特徴づけるには割と原始的な手法が好まれるようだ。つまりXRFなどはあまり有用な情報を地質学者に与えない。
3Dプリント用ジオポリマーとしての水ガラス
ポルトランドセメント(Portland cement)は、モルタルやコンクリートの原料として使用されるセメントの種類の一つ。最も一般的なセメントである。
普通のセメントはPortland cementと呼ばれライムストーンが主要な原料。古代共和制ローマから使われているローマンコンクリートとかもこれ。
これはもともとは貝殻など海洋生物からできているので海と生物活動が前提であり、地球上にはありふれているが惑星探査を始める人類には新しいセメントが必要だ。そこで注目されているのがジオポリマーだ。

それとも人間やめますか?
Na2CO3 + SiO2 = Na2SiO3 + CO2
のび太さんのエッチングの過程では炭酸から二酸化炭素を放出しつつ、ケイ素を引っ張り出す。そうやってできるのがケイ酸ナトリウムだ。これが水ガラス。そして水ガラスにはジオポリマーとしての活用法がある。
ジオポリマーで家が3Dプリンティングされ、コンクリートより硬い壁ができる


3Dプリントに使えるくらいなので固くなる前は柔らかくてチューブから押し出せるわけだ。

粘土細工のようなお手軽さを感じる入れ物が左上。
柔らかい内に手のひらを当てた感じの右上。
柔らかい内にちょうこく彫刻した感じの右下。
どでかいスケールで石が加工されている左下。
上の図で見た山盛りの白黒のあれに戻る。

他の絵からこれは布袋から注ぎだされている。黒いのはやはり炭だろう。しかし、マルセルさんによるとこれは薪をしたあとの灰とできた炭の混合物だろうと。つまりナトロンを温めている過程でできる副産物かもしれない。合理的。
その灰がもしアルミニウムを含む植物だった場合、これが面白いことになる。
マツ網の植物
マルセルさんは3Dプリントの原理からして、水ガラスとアルミニウム(酸化アルミニウム)を混ぜると石になることを知っているので、エジプトにもたくさんある植物でアルミニウムが含まれるものを探しはじめ、友人の学者たちに相談。
木を燃やした灰というのは色々な酸化金属を含んでおり、その種類は植物によって違う。そして地球に沢山存在しているアルミニウムは生き物に毒性が高いので植物は必死に排除するのでアルミニウムは灰には存在しないと生物学者がいう。
しかし木材を切り出す時に、松の木がノコギリの歯を腐食するので大変だという話があり、その原因はアルミニウムだと言われていることにマルセルさんは気がつく。
生物学者と木材加工業者、どっちが正しいのか?
実験してみりゃいいのだ。身近にある松の木を燃やして、購入した水ガラスと混ぜ混ぜする実験をしたマルセルさん。
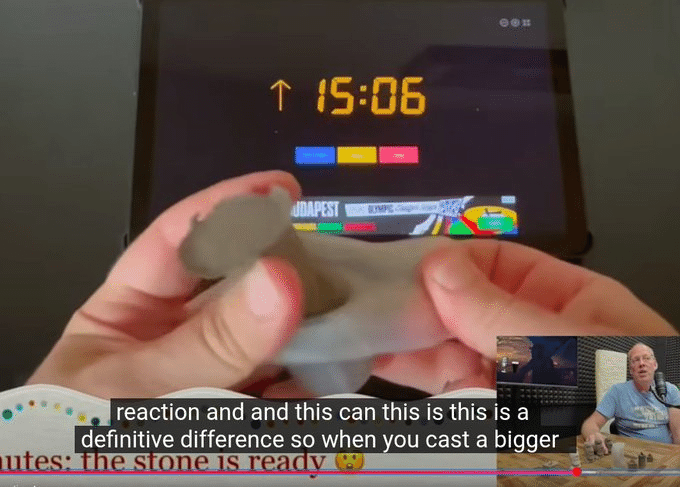
使う木材により固化する速度が違うそうだ。
一日かかるものから数分のものまで。

左からニオイヒバ、セコイア、不明、オウシュウトウヒ
ニオイヒバ(匂檜葉[9]、学名: Thuja occidentalis)は、裸子植物マツ綱のヒノキ科クロベ属(ネズコ属[10])に分類される常緑針葉樹の1種である。
セコイア(英: sequoia [sɨˈkwɔɪ.ə]、学名: Sequoia sempervirens)は、裸子植物マツ綱のヒノキ科[注 2]セコイア属に属する巨大な常緑針葉樹の1種である(図1a)。
オウシュウトウヒ(欧州唐檜[4]、学名: Picea abies)は、マツ科トウヒ属の針葉樹。ヨーロッパ原産で、標準和名はドイツトウヒ[2](独逸唐檜)[5]、別名でヨーロッパトウヒ[6]、ドイツマツ、欧州トウヒなどとも呼ばれる。
つまり、世界各国で現地にある松の木を燃やせば、後は水ガラスを石からナトロンと炭で抽出して人工の石を作れる。そうやって天然の石に柔らかい石を木の枠とかで押し付けてある程度固まったら枠を剥がして彫刻すれば古代遺跡にあるような石細工が可能に。

つまり、これは石の表面に人工の石を塗りつけていた証拠にもなる。上のエジプトのオベリスク採掘場での剥げてくる石版ももしかしたら天然石の周りに塗った人工の石の層が剥げて来ているだけかもしれない。
ここまで1時間14分まで。
衝撃の事実wwww
すごいですなー、マルセルさん。
続きはその3で。
