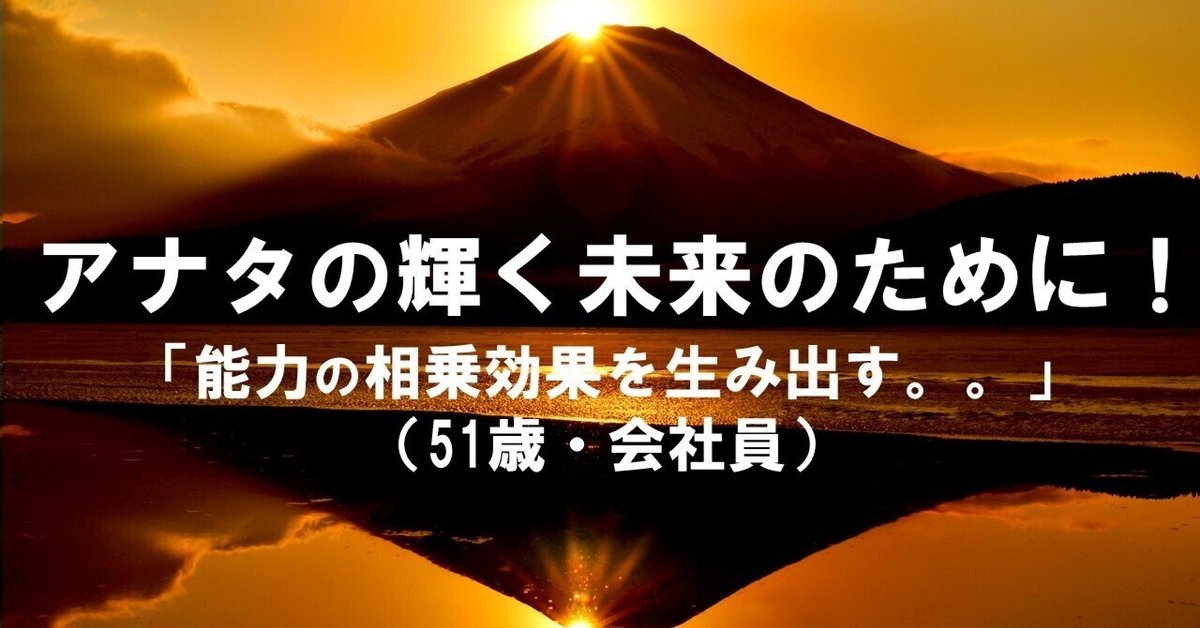
【お題拝借】能力の相乗効果を生み出す(51歳・会社員)
大田区にお住まいの51歳の男性会社員Nさんから頂いたお題を紹介します。

ポークソテーをツマミに赤ワインで乾杯

当時のトップは合併で3銀行の相乗効果を生み出し、1+1+1 が 3 ではなく、4 にも 5 にもなると言っていたけど、3 どころか未だにベクトル合わせが出来ていない。
そこで今回は、Nさんから頂いたお題「相乗効果を生み出す」を拝借して、「能力の相乗効果を生み出す」を「未来を輝かせるツール」に変えたいと思います。
【私ならこう考える】
中世イタリアでは豪商メディチ家が、互いに異なる教養(カルチャー)を持った者をフィレンツェに集め、化学反応(相乗効果)を起こさせてルネッサンスを生み出しました。
ちなみにイタリアでは教養のことをクルトゥーラと言いますが、この言葉の語源には「耕す」という意味があるそうです。
このフィレンツェで花開いたルネッサンスは、
「自分の専門分野」だけでなく「他の専門分野」にも好奇心を働かせてそこを「耕す」と化学反応(相乗効果)が発生する。
その結果「自分の専門分野」だけでは達成できなかったことを達成できる可能性が高まる。
ことを後世の人間に教えてくれました。
「相乗効果」を生み出す「他の専門分野」
では
・「自分の専門分野」に相乗効果を生み出す「他の専門分野」は何か?
・その「他の専門分野」を今更どうやって身に付けるのか?
この問いに対する私の考えは以下の通りです。
① まず、いま一度「自分のやりたい事」「自分に必要な事」「自分に足りない事」を整理したうえで、自分が楽しめそうで、ワクワクを感じる「他の専門分野」を絞り出す。
② 次に、選んだ「他の専門分野」の中で「良書といわれている書籍10冊」を読み込み、エッセンスを抜き出し、自分の教科書を作成する。
③ そして、「他の専門分野」の経験を積むために、
会社に留まり「仕事の中で見つける」「社外で見つけて副業する」「師匠を探して休みの日に無償で師匠を手伝う」、それらが叶わないのであれば「転職を検討する」。
下記の書籍分類をご覧ください。
これは大型書店(「ブックファースト新宿店」「紀伊国屋新宿本店」の2店舗)に行って調べてきたビジネス関連本の書棚分類です。
言い換えれば「良書といわれている書籍が10冊」以上ある分野です。
【「他の専門分野」(職能系)を見つける】
ヒューマンスキル、コーチング、NLP、ファシリテーション、心理学、リーダーシップ、組織マネージメント、キャリア管理、人材開発、グローバル人事、グローバル人材調達、リストラ、人事制度、グローバル経営、ナレッジマネージメント、イノベーション、経営者採用、IR、情報経営、生産管理、在庫管理、物流管理、労務管理、品質管理、プロジェクト責任者、経営戦略、経営分析、企業価値評価、バランスト・スコアカード、株式上場、リスクマネージメント、情報セキュリティ、ISMS、CSR、コンプライアンス、コーポレート・ガバナンス、M&A、MBO、事業再編・再建、事業承継、流通・マーケティング(国内)、流通・マーケティング(海外)、コンシューマー営業、法人営業、ブランド戦略、CS、広告・宣伝、企業法務、知的財産法、財務管理、企業会計・決算、資金繰り・倒産処理、企業税務、TQC、5S、ISO9001、ISO14001、トヨタ式、安全管理、セキュリティ管理、商品・製品開発、企画・プレゼンテーション、工学、理学、AI、IT、データサイエンス、プログラミング、エンベデットシステム、システム監査、ネットワークシステム、データーベースシステム、CISSP、語学、思考法
【「他の専門分野」(FA系)を見つける】
研修講師、ファイナンシャルプランナー、アクチュアリー、公認会計士、税理士、弁護士、弁理士、司法書士、社会保険労務士、不動産鑑定士、建築士、医師、看護師(看護士)、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、薬剤師、社会福祉士、介護支援専門員、保育士、獣医師、動物看護師、トリマー、管理栄養士、美容師、デザイナー、グラフィックデザイナー、経営コンサルタント、臨床心理士
「相乗効果」を生み出す「習慣」
私が自分自身の経験を踏まえておススメしているのは、
故スティーブン・R・コヴィー氏の「7つの習慣」です。
ご存知の方も多いと思いますが、彼が提唱した「7つの習慣」のエッセンスを以下に紹介します。
【第一の習慣】主体性を発揮する
人間は、刺激に対して、自分の反応を選択する能力と選択する自由を持っている。重要なことはその刺激にどう反応するかだ。
【第二の習慣】目的を持って始める
自分のミッション・ステートメントを書く。
その中で自分はどうなりたいのか、何をしたいのか、を明らかにする。
【第三の習慣】重要事項を優先する
私生活の質、仕事の業績、結果を著しく向上させる活動、そうした
インパクトを持つ活動は、緊急ではないが、重要な領域の活動である。
【第四の習慣】Win-Winを考える
強いか弱いか、厳しいか甘いか、勝つか負けるかといった「二分法」ではなく、当初それぞれの当事者が持っていた案に限定されない、全く新しい
第三案の存在を考える。
【第五の習慣】理解してから理解される
話をしているとき、ほとんどの人は、相手を理解しようとして聞いているのではなく、答えようとして聞いている。「理解してから理解される」ことには、大きなパラダイム転換が必要である。
【第六の習慣】相乗効果を発揮する
ほんとうに効果的に人生を営む人というのは、自分のものの見方の限界を認め、豊かな資源を活用する謙虚さを持っている人である。相乗効果の本質は相違点を尊ぶことである。
【第七の習慣】刃を研ぐ
上向きのらせん状の循環を歩むためには、私たちは学び、決意し、実行し、さらに学び、決意し、実行し続けていかなければならない。
以上です。
この機会に一度
・ご自分にとっての「他の専門分野」をチェックして
・ご自分の「習慣」をチェックして
・ご自分の「能力の相乗効果」について考えてみませんか?
アナタの輝く未来のために!
