
【論文紹介】7テスラMRIが捉えた脳の深部:うつ病理解への新たな一歩
現代社会において、心の健康は重要な課題となっています。特に「うつ病」は、誰にでも起こりうる、身近な心の病気です。しかし、その詳しい原因やメカニズムは、未だ謎に包まれています。
そんな中、最新の脳画像技術である「7テスラMRI」を用いた研究が、学術雑誌「Journal of Affective Disorders」に掲載されました。この研究は、うつ病患者さんの脳の深部にある「視床」という領域に注目し、その微細な構造の変化を明らかにしました。
視床とは
視床とは、脳の奥深くに位置する、卵のような形をした神経細胞の集まりです。その役割は、まるで「脳の司令塔」。五感(視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚)から得られた情報を、大脳皮質の適切な場所に中継する、重要な役割を担っています。さらに、感情、意欲、睡眠など、心の働きにも深く関わっていることが知られています。

従来のMRIでは見えなかった視床の「亜核」
視床は、実は一つの塊ではなく、さらに細かな領域(亜核)に分かれています。それぞれの亜核は、異なる役割を担い、異なる脳領域と繋がっています。しかし、従来のMRI装置では、これらの亜核を詳細に観察することは困難でした。
7テスラMRIが可能にした視床亜核レベルの解析
本研究では、従来のMRI装置よりも強力な磁場を持つ「7テスラMRI」を用いることで、視床を構成する25個の亜核を、一つ一つ詳細に観察することに成功しました。さらに、拡散MRIという特殊な撮影法を用いることで、神経線維の走行や、白質の微細な構造を評価できる拡散テンソル指標(FA, AD, MD, RD, SLCなど)を測定しました。これにより、視床の各亜核と、他の脳領域との間の神経線維の繋がり具合(構造的接続性)を、これまでにない高い精度で調べることが可能になったのです。
うつ病患者と健常者の視床を比較
研究チームは、53名のうつ病患者さんと、12名の健康な方々の脳を、7テスラMRIを用いて撮影し、視床の構造的接続性を比較しました。その結果、うつ病患者さんでは、健康な方々と比べて、すべての視床亜核において、白質の微細構造に変化が生じていることが明らかになりました。特に、以下の領域で顕著な変化が観察されました。
視床枕 (PuM):左側の視床枕で、神経線維の数が減少(低いSLC値)
外側核 (LTR):右側の外側核で、神経線維の配列の均一性が低下(低いFA値)
腹側核 (VA):両側の腹側核で、神経線維の配列の均一性が低下(低いFA値)
前核 (AV):右側の前核で、神経線維の配列の均一性が低下(低いFA値)
髄板内核 (ITL):右側の髄板内核で、神経線維の配列の均一性が低下(低いFA値)
視床枕下部 (PuI):両側の視床枕下部で、神経線維周囲の水分量が増加、細胞密度が低下(高いRD, MD値)
腹外側核 (VPL):左側の腹外側核で、神経線維の配列の均一性が低下(低いFA値)
内側膝状体 (MGN):左側の内側膝状体で、神経線維の配列の均一性が低下(低いFA値)
これらの領域は、感覚情報の処理、情動の制御、意欲や動機づけなど、心の働きに深く関わる脳領域と繋がっています。つまり、うつ病患者さんでは、これらの脳領域との情報伝達に、何らかの異常が生じている可能性が示唆されたのです。

臨床的特徴との関連:発症年齢や再発との関係
さらに、本研究では、視床亜核の構造的接続性の変化が、うつ病の発症年齢や再発の有無といった、臨床的な特徴とも関連していることが明らかになりました。具体的には、
発症年齢が遅いほど、両側の外側膝状体(LGN)、両側の髄板内核(ITL)、両側の内側膝状体(MGN)、右側の外側膝状体(LGN)、左側の腹外側核(VPL)、左側の腹側核(VLa)、左側の髄板内核(ITL)、左側の視床枕(PuM)、左側のL-SG、左側の内側核(MED)における神経線維周囲の水分量が少なく、神経線維の配列の均一性が高く、神経線維の数が多い傾向にある。
再発を繰り返している患者さんでは、初めてうつ病を発症した患者さんと比べて、視床亜核(外側核(LTR)を除く)のほとんどにおいて、神経線維周囲の水分量が少なく、神経線維の配列の均一性が高く、神経線維の数が多い傾向にある。
これらの結果は、うつ病の発症や再発に、視床亜核の構造的接続性の変化が、深く関わっていることを示唆しています。
個別化医療への第一歩
本研究は、7テスラMRIという最先端の脳画像技術を用いることで、うつ病患者さんの脳深部で生じている、微細な構造変化を捉えることに成功しました。これらの知見は、うつ病の新たな診断マーカーや、治療効果の予測因子として、将来的には、患者さん一人ひとりに最適な治療を提供する「個別化医療」の実現に繋がる、重要な一歩となることが期待されます。
参考文献
Liu W, Heij J, Liu S, et al. Structural connectivity of thalamic subnuclei in major depressive disorder: An ultra-high resolution diffusion MRI study at 7-Tesla. J Affect Disord. 2025 Feb 1;370:412-426. doi:10.1016/j.jad.2024.11.009.
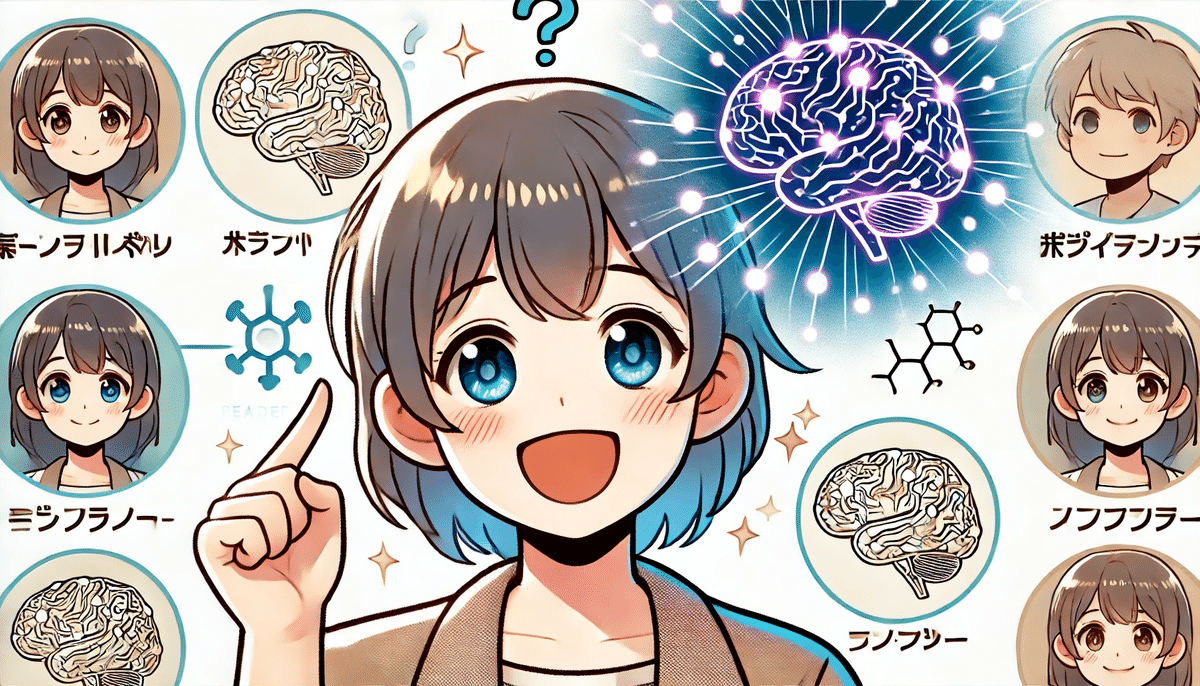
専門家向け解説
already known(既知の知見)
大うつ病性障害(MDD)は、心理社会的機能の著しい障害、生活の質の低下、そして社会に大きな疾病負担をもたらす一般的な疾患である。
MDDの病態生理学に関する完全な理解は未だ得られていないが、視床がその発症に関与していることが先行研究で支持されている。
視床は、皮質ネットワーク内の中枢ハブとして機能し、皮質領域の活動を同時に調節し、大脳皮質に出入りする感覚情報の中継点として機能する。
視床は、皮質下領域との豊富な接続を介して、情動処理にも重要な役割を果たしている。
MDD患者は、健康な対照群と比較して、左視床全体の体積と左側のいくつかの視床核の体積が有意に減少している。
MDD患者は、様々な皮質および皮質下領域への視床からの上行性入力の増強と、これらの領域から視床への下行性接続の減少を特徴とする機能的接続の変化を示し、過剰な感覚情報処理と不十分な負の情動の抑制との間の不均衡を示唆している。
拡散MRI(dMRI)研究により、MDD患者では、右視床前放射におけるFA値の有意な低下、および両側視床前放射におけるAD値の低下が示されている。
視床放射におけるMD値の低下は、抑うつ症状の重症度の増加と関連している。
視床に関連する構造的接続性は、MDD患者において異常である。
unknown(未解明の点)
従来のMRIスキャナーと取得技術の使用により、視床とその核下接続プロファイルの徹底的な調査が妨げられてきた。
視床は多くの亜核で構成されており、異なる亜核は異なる線維接続を有し、それぞれが異なるMDDの病態生理学的メカニズムに関与している可能性がある。
視床白質接続性に関する先行研究では、標準的な磁場強度MRI(1.5/3.0テスラ)が用いられ、視床全体を対象としており、その核下構成が見落とされていた。
current issue(現在の問題)
従来のMRI装置および撮像技術の限界により、視床およびその亜核レベルでの結合プロファイルを詳細に調査することが困難であった。
視床の亜核レベルにおける白質構造結合の異常に関する知見が不足している。
purpose of the study(本研究の目的)
7.0テスラの超高磁場拡散MRIを用いて、MDDにおける視床亜核の白質接続性をマッピングする。
FA、AD、MD、RD、およびSLCを指標として、MDDとHC参加者における視床亜核の白質接続性の異常を調査する。
視床亜核の接続特性と、いくつかの臨床変数との関連を調査する。
Novel findings(新規な発見)
7.0テスラの超高磁場拡散MRIを用いることで、MDD患者における視床亜核の構造的接続性の異常を初めて明らかにした。
MDD患者では、HC群と比較して、すべての視床亜核における白質接続性が低下していた。
MDDおよび臨床的特徴(投薬状況、発症年齢、再発)は、感覚処理、情動機能、目標指向行動を制御する皮質および皮質下回路との視床亜核接続の変化と関連していた。
MDD患者では、右外側核(LTR)におけるFA値の低下が認められ、右LTRのFAは発症年齢と正の相関があった。
再発性MDD患者では、初発エピソードのMDD患者と比較して、視床亜核(LTRを除く)のほとんどで白質測定値が高いという軽度の証拠が示された。
MDD患者において、左視床枕(PuM)の構造的結合性(SLC)が低下していた。
Agreements with existing studies(既存研究との一致点)
視床枕は、セロトニン作動性およびノルアドレナリン作動性活動の部位である。
MDDの既往歴のある個人を対象とした死後研究では、セロトニントランスポーターシステムと、ニューロン数で測定された視床枕の体積に異常が報告されている。
視床枕におけるベースライン活動の亢進が、負の情報に対する顕著性ネットワークの増幅された反応の一因となっていることが、安静時PETおよびSPECT所見のメタアナリシスで示唆されている。
視床枕の白質接続の変化は、神経伝達物質レベルと重要なネットワーク機能を変化させ、不適応行動や抑うつ行動を促進する可能性がある。
外側膝状体(LGN)に関連する機能的回路は、光療法の抗うつ効果に関与している可能性がある。
視床-一次聴覚野回路は、MDD治療の潜在的なターゲットである。
腹側視床核は、うつ病における重要な脳領域である。
前視床核は情動調節と密接に関連している。
視床内層核(ITL)は、非特異的覚醒システムに不可欠な中継点と考えられている。
ITLの損傷は、非海馬依存性作業記憶課題を障害する可能性がある。
Disagreements with existing studies(既存研究との相違点)
視床亜核レベルの構造的接続性を詳細に検討した先行研究がほとんどないため、直接的な比較は困難

