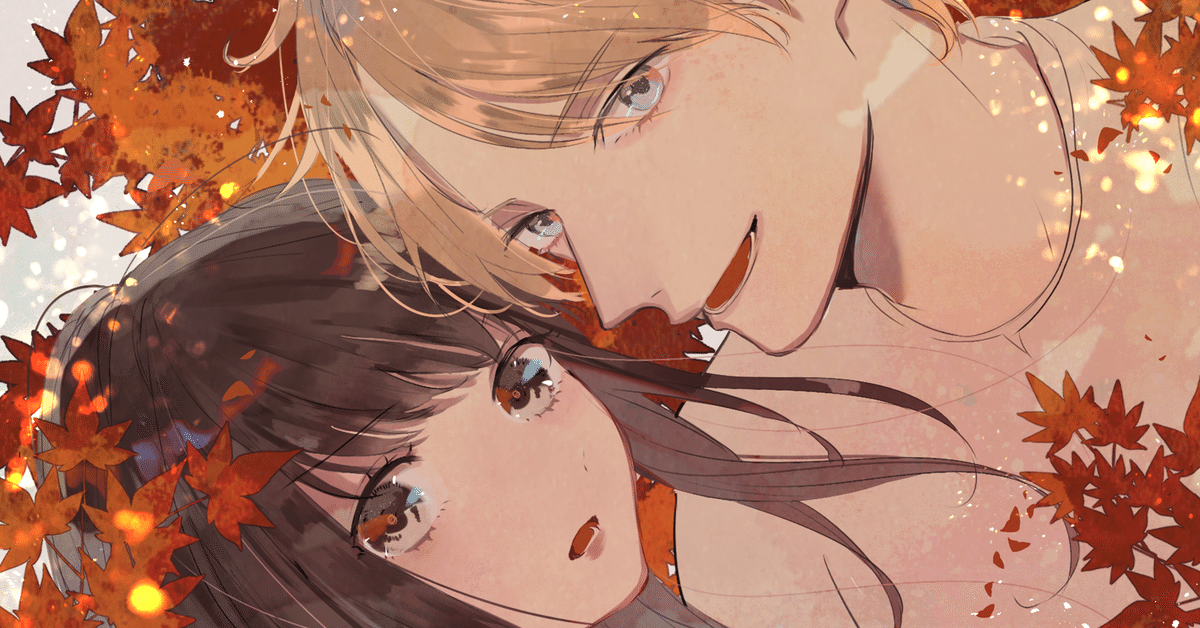
ヒーローじゃない17
それから暫くして、起きてきた力也が大きな欠伸をしながらリビングへと入ってくる。完全に寝巻きのままだが、アマネとしてはもう見慣れているので特に気にしない。オンオフをきちんと切り替えていると言えば聞こえは良いが、要は仕事以外はずぼらなだけなのだ。
「なんだ、お前一人か?」
「チアキなら巡回中だけど」
「はっはあ、お前も上手く顎で使えるようになったじゃねえか」
人聞きの悪いことを言いつつ、力也は隣にあった一人掛けのソファにどっかりと座る。ついでにとばかりにリモコンのスイッチを入れたようで、目の前にあったテレビが点いた。
丁度朝のニュース番組が折り返しを迎えている頃合いだ。画面の向こうではキャスターやアナウンサーが特集と称した話題を取り上げている。
「あっチアキくん!」
跳ねるような声を上げて、ひめのは一目散にテレビの前を陣取る。どうやら特集は今活躍中のヒーロー達のようで、その中にはチアキの姿も映っていた。
現在進行形でこの町にいる彼がカメラの前に立てる筈がない。映像はただの録画だろう。
ぼんやりとテレビを眺めていたが、ふと力也の視線を感じて思わずテレビから彼に顔を向ける。
「何?」
「いや、お前も変わったなあと思ってよ」
「どこが」
「この手のモン見ても平然としてるなんざ、前はありえなかっただろうが」
言われて、確かにそうかも、と思ってしまった。その理由もなんとなく分かっているだけに、次いで見せた力也のにやついた顔はシンプルに苛つく。
「アイツに絆されたか? お前も案外単純だな」
「違うから。私はただ……」
ただ、なんだというのだろう。すぐに言葉が出てこないアマネを力也は気怠そうな表情はそのままで見ている。ひめのは相変わらず目の前のテレビに釘付けだった。
一度口を閉じて、それからまた話を続けた。
「……一種って、皆ああなるの」
「ああなる?」
「常に危険と……死と、隣り合わせなの」
アマネの問いに、力也は答えない。ただじっと、まるで探るように、アマネを見つめているだけだった。聞いてはいけないことを聞いてしまったような、いたたまれない気持ちになって俯くと、力也はひめのに顔を向けた。
「ひめのー、テレビ占領するんなら自分の部屋行け。そっちの方が沢山見れるだろ」
「えーっ! せっかくアマネちゃんが来てくれたのに!」
「アマネはパパと仕事だ仕事。邪魔するような娘に育てた覚えはねえぞー」
そんなことを言われてはこれ以上我が儘は言えないのだろう。ぷっくりと頬を膨らませながらもひめのは渋々リビングを出ていった。仕事というのはただの口実で、本当はこの話を幼い娘に聞かせたくなかったのだろう。話を持ち出すなら、もっと気を配るべきだったとアマネは今更反省する。
「ごめん……」
「いや、お前は気にしなくて良い」
首を横に振って、力也はテレビを切ってからまたアマネに視線を向けた。
表情からは、特に何も読み取れない。怒っているわけでも、ましてや悲しんでいるわけでもない。いつも通りの宮前力也がそこにはいた。
「同情したか」
昨夜のチアキと同じことを聞かれて、アマネは息を呑む。すぐに答えられずに口を噤むが、力也の方も何も言わない。今度はアマネが何か言うまで動く気はなさそうだった。
「……分からない」
たっぷりの沈黙の後、返すことが出来たのはその一言だけだった。
本当に、分からなかったのだ。彼があんなに追い詰められていることも、それがヒーローであるが故だということも、今まで知らなかったことが多過ぎて脳みそが上手く処理をしてくれない。
否、本当はとっくに気が付いていたのかもしれない。二種であってもヒーローの端くれ、ほんの少し想像を巡らせれば容易に思いつく話だ。つまらないプライドと嫉妬心が、その目を曇らせていただけである。
はっきりとしない返事をしてしまったが、力也は特に窘めることはしなかった。ただ腕を組んで「そうか」とだけ返す彼の表情はやはりいつもと変わらなかった。その様子は、丁度今朝に見たチアキと重なる。
「どうして、平気でいられるの。それとも、一種にはそういう素養が求められるの?」
「国に雇われりゃ嫌でもそうなる。所詮、兵隊稼業だからな」
「だからって……あんな傷跡、異常でしかない」
目を閉じれば、今でも鮮明に思い出せる。身体中に走る、痛々しい傷跡の数々。アマネは医療に精通しているわけではない。それでも、その数が尋常ではないことは分かるし──いくつかは、致命傷に近かった。今なお元気なのが信じられないくらいだ。
「身体の傷は消しきれてねえのか。残酷だな」
「どういうこと?」
「おキレイな顔は傷一つ付いちゃいなかっただろ、アイツ。国の最先端医療ってヤツで[商売道具]だけは元通りにしてんだな……いや、させられてるって言った方が正しいか」
「チアキは顔だけでヒーローになったわけじゃない。分かってたから、力也さんだってここにいること許可したんでしょ、本当は」
思わず睨み付けると、それを躱すように力也はひらりと手を振った。
「ったり前だろ、こっちは人手不足に悩む小さな町のヒーローだぞ? 余計な荷物背負う余裕はねえよ」
「私のことは雇ったのに?」
満足に仕事の自由が与えられていない二種など、お荷物以外の何物でもない気がする。実態としては力也の目を離れて仕事をしてしまう面も多々あったが、それでも監査が入る時は口裏を合わせるなど色々準備をしなければならなかったので、それも彼にしてみれば手間だっただろう。
自虐的な答えに力也は呆れたような顔で「お前なあ……」と呟いた。
「俺が言ったことまるで理解してねえだろ。余計な荷物背負うのはご免だが、お前はそうじゃなかった。だから三年経った今も切らずに置いてる。単純な話だろうが」
「使えない、とは思ってないけど。でも面倒でしょ、色々」
「……俺が募集かけた時、なんで条件に一種限定とか入れなかったか分かるか?」
この町でヒーローの求人は何回かしているが、力也が指しているのはアマネがこの町に来るきっかけになった時期のものだろう。確かに、条件にはヒーローの種別は問わないと書いてあった。だからこそ数少ない貴重な就職先候補だと真っ先に飛びついたのだ。
大抵、種別を問わない理由はお世辞にも良いものとは言えない。仕事内容が極端にきつかったり、あまりにも僻地で人が寄りつかなかったり、税金対策だったり。そういう裏事情を知った上で、それでも二種ヒーローの道を選ぶ者は少なからずいるし、脱落していく者もまた存在していた。
「田舎で一種は寄りつかないと思ったからでしょ? 実際、一種限定で募集した時は空振りだったし」
「否定はしねえが……二種は、一種に比べて自由だからな。その自由さが、結果的に俺達を守ることに繋がる」
「……え?」
予想もしなかった返答に目を瞬かせる。その表情が余程間抜けに映ったのか、力也はやれやれといった風に笑った。
「気付いてる一種は多くねえ、裏技みたいなモンだ。ま、二種で優秀な人間ってのもそういねえから、俺はラッキーだったんだろう」
「な、なんの話?」
「ちったあ自信持てって話だよ。それよりチアキだ、お前が拾ってきたんだから責任持って最後まで面倒見ろよ」
「だから犬猫拾ってきたみたいに言わないでよ!」
眉を寄せるアマネにからりと笑って、力也はそれ以上話すことはしなかった。
結局、知りたいことは何も分からなかった。それでも、なんとなく知りたいことの一端を掴めたような。そんな気がした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

