
グローバル企業で働く上で、英語学習より重要だった4つの工夫
UIデザイナー/PdMとして外国籍のメンバーと英語で開発する上で得た「英語そのものより優先して習得すべき、4つの工夫」まとめです!
日本にいながらも、グローバルなチームで業務する機会に度々恵まれています。
語学力にはそれなりに自信があったのですが、「英語がある程度話せること」と、「英語話者と開発を滞りなく進めること」にはスキルとして大きなギャップがあることを実感しました。

経験を通じてはっきりしたのは、もしグローバルチームで働くのであれば、英語力を闇雲に上げるよりも先に、「コミュニケーションをなめらかにする努力」をしたほうがいいということです。
なぜなら、雑なコミュニケーションでも通じるくらいの英語力をつけるほうがよっぽど大変だからです。
このnoteでは、わたしが英語で仕事する上で行っている、コミュニケーションのずれを防ぐ工夫を4つ紹介します☕️
この工夫を先に習得することで、流暢に話せなくても英語話者がいる環境でもスムーズに仕事できるかもしれません。
英語学習のショートカットにもなると思うので、参考になればうれしいです!
英語を話すときの4つの工夫
①構造を意識して話す
自分が話者となる場合、聞き手が話を聞きやすくするTipsとしてまず挙げたいのが、構造を意識しながら話すことです。
構造がわかりやすい話し方の最高のお手本として、WWDC23の動画をとりあげます。
冒頭【00:21~00:42】を確認すると、以下のように話しています。
In this talk, I'll give you an overview of some of the accesibility features available in this platform.Next, I have been to the some of the specific what you can do your apps to support people who are blind and low vision.
Then, I hand off it to Drew, to discuss mortor, cognitive and hearing accecibility in spacial computing.
このトークでは、このプラットフォームで利用可能なアクセシビリティ機能の概要を説明します。
次に、目の不自由な方や弱視の方々をサポートするためにアプリで出来ることを解説します。
そして、空間コンピューティングにおける運動機能、認知機能、聴覚機能のアクセシビリティについてDrewがお話します。
このトーク全体のテーマ、これから話しうることを順番に要約して紹介し、聞き手のわたしたちはこの冒頭を聴くだけで、話の全体像を把握することができます。
そして02:07以降、各トピックに移ってもこの構造は保たれています。
Let's start talking about the way you can support who are blind and low vision in your apps. There are few things to consider when discussing.
では、みなさんのアプリで視覚障がい者の方々をサポートする方法についてお話していきます。
視覚アクセシビリティについて話す際に考慮すべき点がいくつかあります。
「〜についてお話ししていきます」「考慮すべき点がいくつかあります」など、詳細な話に移る前に、何をこれから話すのか「現在地と全体像」を常に提示しながら進んでいます。
全体-部分の構造が明確なことは、プレゼンテーションとしては王道な話し方かもしれません。でも、改めてこの話法のメリットを整理すると、聞き手が「聞く準備」をできることにあると思います。
つまり、「なんの話をするのか」「今何の話をしているのか」を構造的に話すことは、聞き手にとっては話を整理するためのファイルが用意され、そこに具体的な内容を格納していくように話を聞くことに繋がります。
先の例であれば、「考慮すべき点がいくつかあります。」と言われたことで、いくつかある具体例を聞く準備をすることができます。

もしこの構造がない場合、「この人は何について話しているのか」「先ほどの話題との連関は何か」「全体で伝えたいことは何か」を聞き手が聞きながら整理する必要があります。この場合、話の中心と枝葉もわからない状態で瞬時に整理していくので、たとえば話の中心にない事例に気をとられてしまうことも。

自分はまず日本語でこの話し方を癖づけたことで、英語でも同様に話すことができるようになりました。聞き手/話し手両方が会話が楽になるのでおすすめです!
②いつもの半分のスピードで話す
いくら英語が話せても、ネイティブではありません。 言い方の癖や、言い間違いによって起こった誤解が、会話の中でなんとなく見過ごされることも少なくありません。
これを防ぐためにオススメしたいシンプルですが強力な方法は「ゆっくり話す」ことです。
わたしはだいたい日本語で話すときの半分くらいのスピードを心掛けています。(元々がとても早口なのもありますし、冒頭はゆっくりでも後からどんどん早くなってしまうこともありますが)
ゆっくり話すことで、話し手・聞き手の双方に以下のようなメリットがあります。
話し手:次に話す内容や言い方を整理できる
聞き手:シンプルに聞きやすく、内容の確認も入れやすい
③図を準備して見せながら話す

図を準備するだけで、関係性や時系列など、英語で説明しきるにはちょっと難しい話題も一気に理解しやすくできます。特に自分は数字を英語で言うのがとても苦手で、瞬時に「何倍」「何円」などを正しく翻訳できる自信がないので、データを見たり、過去の経緯を説明するときなどに重宝しています。
また、開発業務でしばしば発生する「ここからグラデーションをかけて…」といった細かい指示も図があればすぐに伝えることができるます。
また、事前に準備するだけでなく、話しながら図を作るのもおすすめです。
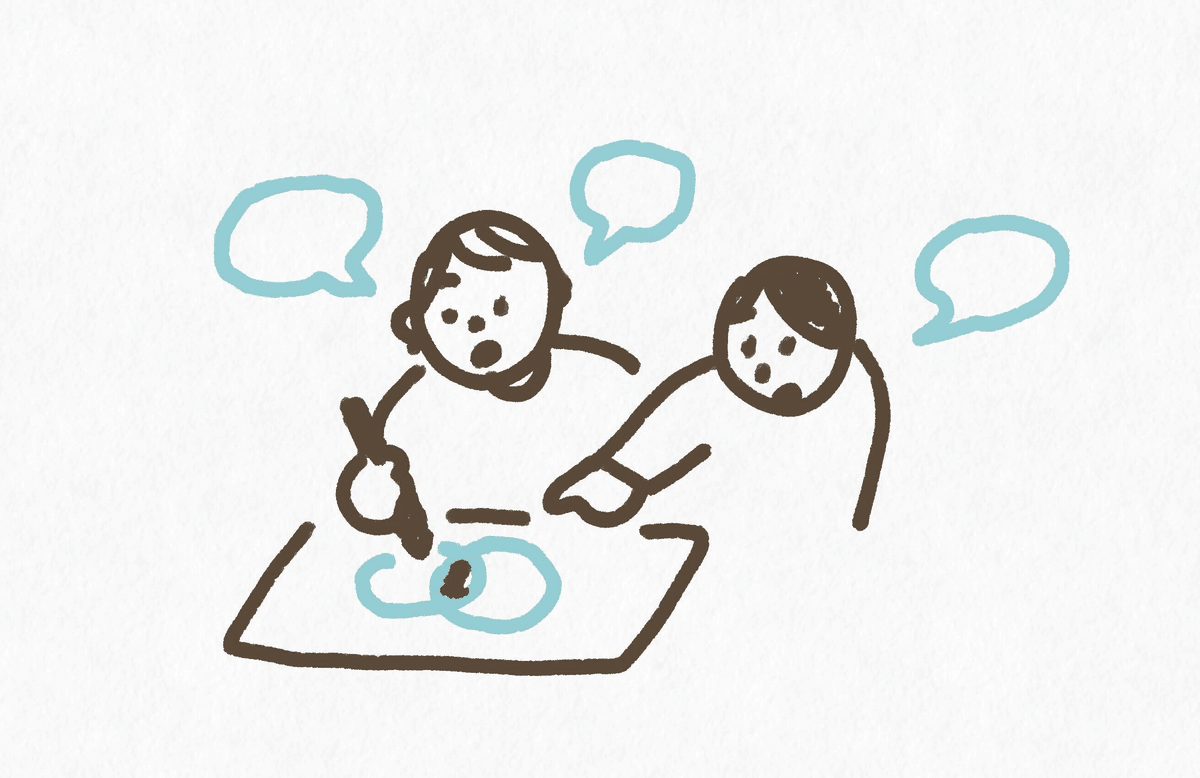
自分が話したことの更なる補足として、更にはメンバーからのリアクションを自分が正しく理解できているのかの確認のツールとして、私はよく使っています。
それは、同じ単語を使っていても、前提情報の量によって解釈が異なったり、そもそも不慣れな言語を話す場合は解釈そのものが間違っている可能性もあるからです。
④話したことは「テキストで」簡単にサマリし、会話の直後に送る
英語でワーッと自分が話しているとうっかり言い間違えていることもありますし、聞く側もその場その場の理解にエネルギーを使っています。
そのため、話が終わってから「アレ?さっき聞いたけどなんだっけ?」「聞き取れなかったことがあったけど忘れた」ということは頻繁に起こります。
会話の直後に補足としてテキストで話した内容を送信することで、事前のドキュメントにはなかったその場の議論の記録や、正確性に不安がある自分の理解に関して、話し手/聞き手双方が確認を取れる場所をつくることができます。
「今日はうまく話せなかったな・・・」というときこそ、「もし付け加え忘れたことがあったら言ってね!」と末尾につけることで補填しています。
まとめ
①構造を意識して話す
・聞き手に話の現在地を伝え、内容に集中できる状態を作れる
②いつもの半分くらいのスピードで話す
・自分が話しながら次に話す内容や言い方を整理できる
・聞き手に確認の余裕を作る
③ 図を準備して、見せながら話す
・言葉で伝えきれない部分を補完できる
・議論の内容を可視化し、理解度を確認できる
④ 話したことは「テキストで」簡単にサマリし、会話の直後に送る
・正確に話せていたか/聞き取れていたか不安な箇所の確認
今回紹介したことは、日本語同士でのコミュニケーションでも発生しうる課題と、その解決策とも言えます。
どの言語を話す場合でも、小さなディスコミュニケーションをなあなあにせず、仕組みと工夫で曖昧さをなくしていくことで、開発はもっとスムーズになるはず🚀
参考になれば幸いです!
