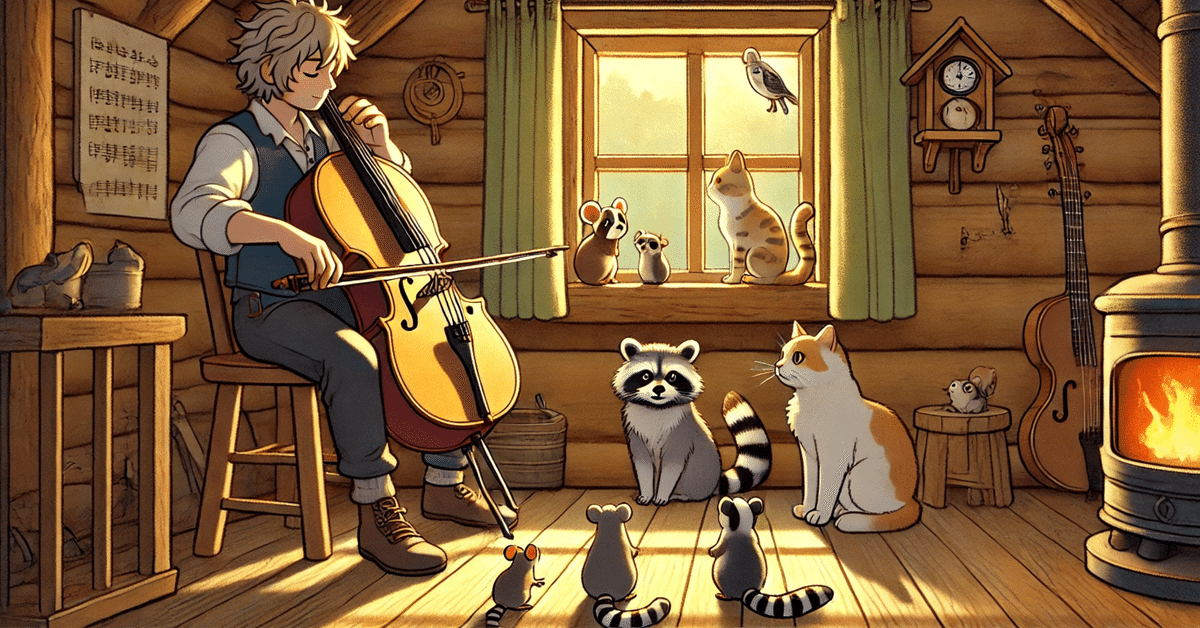
「セロ弾きのゴーシュ」考
前書き
「セロ弾きのゴーシュ」は、チェロを愛した宮澤賢治が、チェロを始めたころに執筆を始め、7~8年後の死の直前まで筆を入れていたという作品で、賢治の思いが深く、また、彼の宗教観も垣間見ることができる完成度の高い作品ゆえに、多くの人を惹きつけてきたのだと思います。この作品には、アマチュアのチェロ弾きとしての賢治が、自分自身をゴーシュに重ねて、下手なチェロ弾きとして彼自信が味わっていたふがいなさや苛立ち、そして、彼が夢見た自身がチェロを弾く姿が見えているように思います。
クラハの仲間とともに、南木千絵(みなきちえ)さんが作曲された「セロ弾きのゴーシュ」の公演を行っています。そのようないきさつから、この作品をなんども読み返し、また、宮澤賢治の他の作品、及び賢治についての書き物もいくつか読んでみました。すると「賢治ワールド」の広がりの大きさを改めて感じるところです。
このノートでは、「セロ弾きのゴーシュ」を読んでいて気づいたことを記し、それらに考察を加えたものです。加筆、修正させていただくかもしれません。
このノートの一部、または全部の無断転載はお断りします。引用されたい場合などは、コメントにてご連絡下さい。また、内容についてにご意見、ご批判は歓迎いたします。よろしくお願いします。
ここがポイント
この物語を読んでいて気付くことがいくつかあります。それらを指摘しながら考察を加えたいと思います。
ゴーシュという名は?
この物語の主人公の名前はゴーシュ。フランス語のGausche(ゴーシュと発音)には、「不器用な」、「下手な」という意味合いがあるので、フランス語を知っている人なら、すぐに、この言葉から来た名前であろうと考えることと思います。そして、そうである可能性が高いと思います。
しかしながら、宮澤賢治が得意としていたのはドイツ語でした。親友であった音楽教師藤原加藤治との関係は、賢治がドイツ語を教える代わりに加藤治が音楽を賢治に教えるというものです。賢治は、フランス語も少しはかじっていたかもしれません。でも、ドイツ語に詳しかった賢治がなにゆえこのフランス語の言葉を主人公の名として選んだでしょう?
そもそも、Gauscheが姓なのか名なのかもわかりません。ChatGPTに、1990年ころ、ドイツで男の子の人気の名前は以下のようなものだとか。
マイケル (Michael)
トーマス (Thomas)
アレクサンダー (Alexander)
ダニエル (Daniel)
クリスチャン (Christian)
マティアス (Matthias)
ヤン (Jan)
フィリップ (Philipp)
ルーカス (Lukas)
フランク (Frank)
他方で、ドイツ人の姓で多いのは、
ミュラー (Müller) - 「ミルク製造者」や「製粉業者」を意味する姓で、非常に一般的です。
シュミット (Schmidt) - 「鍛冶屋」を意味する姓で、広く使われています。
シュナイダー (Schneider) - 「仕立て屋」や「裁縫師」を意味する姓です。
フェルダー (Fischer) - 「漁師」を意味する姓で、多くの人がこの姓を持っています。
ウェーバー (Weber) - 「織り手」や「織物業者」を意味する姓です。
ホフマン (Hoffmann) - 「農場主」や「家主」を意味する姓です。
ケラー (Keller) - 「地下室の管理者」や「ワインの貯蔵者」を意味する姓です。
バウアー (Bauer) - 「農夫」を意味する姓で、広く見られます。
シュルツ (Schulz) - 「村の長」や「監督者」を意味する姓です。
メイヤー (Meyer) - 「地主」や「管理者」を意味する姓です。
とのことです。賢治が、これらの名前や姓では表せないものをイメージしていたということなのでしょう。ちなみに、フランスでは、1990年代の人気の男の名前は
ニコラ (Nicolas)
アレクサンドル (Alexandre)
マキシム (Maxime)
ジュリアン (Julien)
トマ (Thomas)
エマニュエル (Emmanuel)
ロマン (Roman)
アントワネット (Antoine)
セバスチャン (Sébastien)
クレマン (Clément)
だそうです。また、フランス人に多い姓は、
マルタン (Martin) - フランスで非常に一般的な姓です。
ベルナール (Bernard) - 古くからのフランス姓で、多く見られます。
デュポン (Dupont) - 「橋の下」という意味の姓で、広く使用されています。
ドゥニ (Dumont) - 「山の下」という意味の姓です。
ルフェーブル (Lefebvre) - 「鍛冶屋」を意味する姓です。
ルビエ (Roux) - 「赤毛の」という意味の姓で、多くのフランス人がこの姓を持っています。
ルブラン (Leblanc) - 「白い」という意味の姓で、一般的です。
ルメートル (Lemaître) - 「師匠」や「教師」という意味の姓です。
ラフォレ (Lafont) - 「泉の近くの」という意味の姓です。
モロー (Moreau) - 「暗い」や「赤褐色の」という意味の姓です。
とのことです。これらのイメージでもなかったということでしょう。ちなみに、Gauscheは名としても姓としても相当に希のようです。となると、やはり、Gauscheには賢治の特別の思いがあるのでしょう。チェロ弾きとしての賢治自身の思いを乗せたのだとしたらば、仏語の「不器用な」、「下手な」のイメージが合いそうです。ちなみに、ドイツ語で「不器用」というと、
ungeschickt - 直訳すると「不器用な」「不器用な」という意味です。
tollpatschig - より口語的で、少しおどけた感じの「不器用な」「ぶきっちょな」という意味で使われます。
だそうです。また、「下手な」は、
schlecht - 「悪い」「下手な」という意味で、一般的に使われます。
例: „Er spielt schlecht Tennis.“(彼はテニスが下手です。)
unfähig - 「無能な」「下手な」という意味で、能力が不足していることを示す場合に使われます。
例: „Er ist für diese Aufgabe unfähig.“(彼はこの仕事に不適格です。)
ungeschickt - 「不器用な」「下手な」という意味で、特に手先が不器用なことを示す場合に使われます。
例: „Sie ist ungeschickt beim Umgang mit Werkzeugen.“(彼女は工具の扱いが下手です。)
klumpig - 「下手な」「不器用な」という意味で、動作がぎこちない場合に使われます。
とのことですが、名前として使えそうなのはSchelecht, Klumpigくらいでしょうか。
実は、セロ弾きのゴーシュを書き始めた当初は、名前はなく「セロ弾き」だけだったそうです。それが、原稿を作成している過程で、テイシウ→ゴーバー→ゴーシュと書き直されたのだそうです。テイシウが何を意味するのかは分かりませんが、ゴーバーはGoverだったのではないかと思われます。
Goverには、支配する、管理する、規程する、(怒りを)抑制するというような意味があります。この名を使おうとしたときは、あるいは、このセロ弾きにそのような性格付けを試みたのかもしれません。しかし、Gauscheというフランス語の「下手」、「ぎこちない」という性格付けがこの主人公に、そして、それに重ねたチェロ弾きとしての自分自信に嵌ったのではないでしょうか(賢治自身は、几帳面なところがあり、「管理する」、「規定する」も一つの賢治の側面ではあっただろうと思います)。ゴーシュは、名前としての響きがよくて、しかも、ゴーゴー、ガーガーとチェロを弾いたという音の感じにもフィットしているように思えますがいかがでしょうか。
第六交響曲とは?

ゴーシュが所属していた金星音楽団がリハーサルを行っていたのは、「第六交響曲」でした。映画や書籍他では、第六交響曲は、ベートーベンの「田園」に間違いないとほぼ決めつけたものとなっています。確かに、ベートーベンの「田園」は物語全体にあるほのぼのした雰囲気には合ってますし、賢治自身、ベートーベンは大好きな作曲家でした。話にでてくるカッコーも、二楽章の終わりに登場します。では、なぜ、「田園」と書かずにあえて「第六交響曲」と書いたのか?
ベートーベン好きな賢治でしたが、もっとも好きな曲は「運命」だったそうです。この第六交響曲を「田園」と決めてかかると、原作の記述とは、いくつか疑問や齟齬が出てきます。
第一に、物語の冒頭で、
トランペットは一生けん命歌っています。
ヴァイオリンも二いろ風のように鳴っています。
クラリネットもボーボーとそれに手伝っています。
と書かれていますが、そのような場面は、「田園」では浮かびません。チャイコフスキーの第六交響曲「悲愴」なら、随所にみつかります。
第二に、終わりの方で、演奏会のあとに、アンコールを求められた際に、楽長は、「いけませんな。こういう大物のあとへ何を出したってこっちの気の済むようには行くもんでないんです。」と述べていますが、「田園」は、アンコールをかけることができないほどの大物でしょうか?もちろん、そのように受け止める人はいるかもしれませんが、同じベートーベンの「合唱」のように、まさに、アンコールが蛇足となってしまうような大曲ではないのではないでしょうか。実際、「田園」なら、いくらでもアンコールのかけようがあるのではないでしょうか。他方、音楽としてのダイナミックス、表情の幅が大きく、最後が消え入る様に終わって深い余韻が残る「悲愴」であったなら、アンコールをかけにくいというのは「田園」よりもはるかに説得性があります。
第三に、アマチュアのオーケストラが「田園」を演じることの難しさがあります。「田園」は、「古典曲」としての演奏の難しさがあり、観客受けする演奏はしにくく、その意味で、失敗しやすい曲です。技術的にはより難易度が高くとも、チャイコフスキーの第六交響曲「悲愴」の方が聴き映えし、成功しやすい曲です。
第四に、美しい旋律が好きだったと思われる賢治として、どちらかと言えば地味で、特段、チェロの旋律が目立つわけでもない「田園」に、チェロ弾きとしての立場ではどれほど惹かれたでしょう?「悲愴」には美しい旋律がたくさんあり、チェロのメロディーも多く、チェリストにとっては「田園」より魅力的な曲であっておかしくありません。
第五に、ゴーシュは、リハーサルのときに、リズムがあわず、他の楽器と合わないところを指摘されます。もちろん、「田園」を始め、どの曲でもそのような情況はありえます。が、「悲愴」には特徴的なリズムがあり、リズムが合わないと言われればあそこかと思い浮かぶとのころがいろいろあります。
このように、「田園」よりは「悲愴」の方がフィットすると考えられる部分が多々出てきます。では、なぜ、「第六交響曲」として、「田園」とも「悲愴」ともしなかったのか?
これは、賢治が、「田園」のイメージを抱きつつも「悲愴」にある美しさと曲想の大きな、ダイナミクスも意識し、いずれの曲とも決め打ちをすることを避けたからではないでしょうか。いろいろな解釈があってももちろん良いのですけれども、決めつけてしまうと、物語のディーテイルとの齟齬に気づくことさえできなくなってしまいます。なぜ「第六交響曲」と記したのか?を考えながら読み解いていくとより物語のふくらみが増すのではないかと思います。
猫とトロイメライ


物語りには、最初に大きな三毛猫、次いで、カッコー、子どもの狸、そして、ネズミの母子が登場します。カッコーはドレミを教わりたいと言い、ゴーシュが苦しんでいた「音程」を学ぶきっかけとなりました。子どもの狸は、ジャズの曲(愉快な馬車屋)を弾きながら「リズム」学ぶことになります。そして、ネズミの母子への演奏(なんとかラプソディー)を弾くなかで、曲想を学びます。それらは、すべて、楽長さんに手厳しく指摘されていたものでした。
では、最初に登場した「三毛猫」の役割は何だったのか?
宮澤賢治の童話は102あるそうですが、そのうち20作品に「猫」という言葉が出てくるそうです。主要なものは、「セロ弾きのゴーシュ」の他、「注文の多い料理店」、「ドングリと山猫」、「猫の事務所」、「鳥箱先生とフウねずみ」、「クンねずみ」、「ポラーノの広場」があり、このほかに、謎めいた「猫」という小品があります。いずれにおいても、猫は愛玩の対象ではけっしてなく、どこか憎たらしいような、いやみをもった、しかしどこか間抜けなキャラクターであり、擬人化された役回りとなっているようです。
「セロ弾きのゴーシュ」においては、「先生、そうお怒りになっちゃ、おからだにさわります。それよりシューマンのトロ(イ)メライをひいてごらんなさい。きいてあげますから。」と言って、ゴーシュを怒らせます。
でも、ゴーシュは、これを聞いてどうしてそんなに怒ったのでしょう?それは、アマチュアのチェリストにとっての「トロイメライ」の意味を考えると浮かび上がります。
「トロイメライ」は、優しく美しい小品であり、チェロ他、多くの楽器での演奏用に編曲されています。多くの楽器奏者が演奏してみたいと一度は挑戦する曲であろうと思います。
しかしながら、演じるには意外に難曲です。なかなか思う通りの美しい曲にはならないものです。もしもゴーシュが、この曲を弾こうと思って弾くことができずにいたのなら、「シューマンのトロ(イ)メライをひいてごらんなさい。きいてあげますから。」は、かなりカツンとくる言葉だったのではないでしょうか?
ゴーシュは、後に出てくるカッコーには最後に謝りますが、カッコーに対してよりはるかにひどい仕打ちをした三毛猫には謝っていません。
そうすると、この「三毛猫」はいったい誰だったのでしょう??朗読演奏会にて語らせていただきます(笑)
ところで、この「トロイメライ」は、当初の原稿では「アヴェ・マリア」であったということです。「アヴェ・マリア」も「トロイメライ」同様、様々な楽器で演奏され、また、チェロ奏者にとってもお馴染みの曲の一つです。演奏にあたっての難しさは「トロイメライ」と共通するものがあります。旋律が美しい曲が好きで、また、ミサ曲など宗教曲も聴いていた賢治には当然のように思い浮かんだ曲だったのでしょうが、この物語の中ではあえて宗教的な意味合いを持たせることを避けたのかもしれません。また、猫が「トロメライ、ロマチックシューマン作曲。」と言ったように、「ロマンチックな曲」であることが強調されていることから、そのような曲が弾きたくても弾けなかった気持ちをより強く表したかったのではないでしょうか?
ところで、花巻にある宮澤賢治の記念館では、このトロイメライが館内に流れているそうです。
カッコーとドレミファ
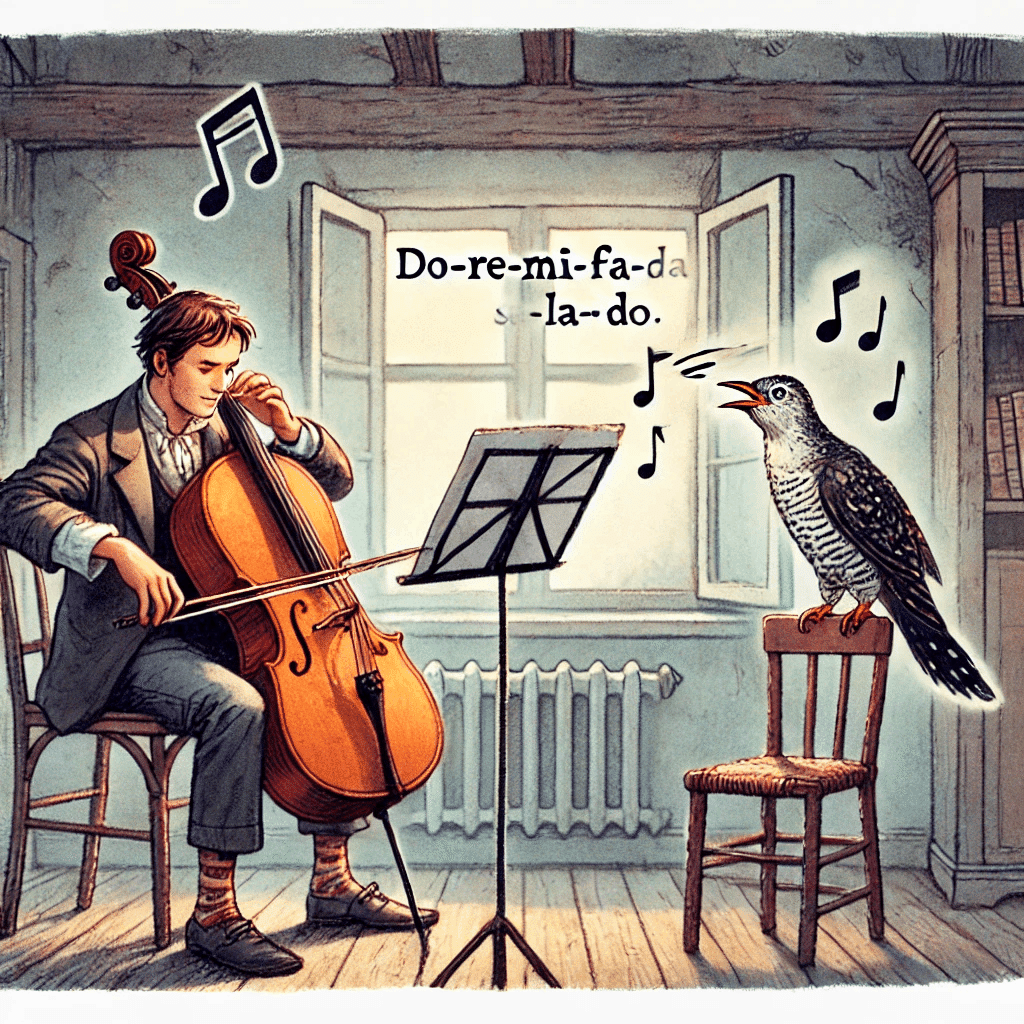
カッコーは、音楽にはよく登場する鳥です。ソッミー、とかレッシーなどの短三度の下降音形を聞くと反射的にカッコーと思ってしまうくらいでしょう。逆に、カッコーというとその音形が浮かんでしまうがゆえに、カッコーがドレミファソラシドを歌いたいと言うなら大きな意外性があります。
ゴーシュが、「音楽だと。おまえの歌は、かっこう、かっこうというだけじゃあないか。」と言うと、カッコーは「わたしらのなかまならかっこうと一万云えば一万みんなちがうんです。」と言い、それで、このカッコーは「ドレミファを正確にやりたい」の言うのです。100年前の話でありながら、現在、その重要性が強く認識され始めた「多様性」のなかの「個性」の尊重が訴えられているように思えます。
初めはカッコーを馬鹿にしていたゴーシュは、次第に、カッコーの方が本当のドレミファに嵌っていることに気が付くこととなります。最後は、「このばか鳥め。出て行かんとむしって朝飯に食ってしまうぞ。」と言って、なんどもドレミファを練習しようとしたカッコーを追い出してしまいます。これは、音程がしっかりととれていない自分自信へのいら立ちの表れでしょう。そして、それを気づかせてくれたカッコーに、最後に詫びを言うこととなったのだと思います。
子たぬきとジャズ

カッコーの次に登場したのは子たぬきでした。子たぬきは、「愉快な馬車屋」というジャズの楽譜を持って現れます。なぜ、たぬき? やはり、「証城寺の狸囃子(しょうじょうじのたぬきばやし)」のイメージが重なっていると思われる方が多いでしょうし、筆者もそうだろうと思います。
さて、それではなにゆえ「ジャズ」か?
ジャズの特徴は後打ち。そして後打ちに慣れると音楽に乗れるようになります。ゴーシュは、楽長から「遅れている」と叱られましたが、アマチュアにありがちなのは遅れるだけでなく走ることも。練習では、きちんと数えながらリズムを音を刻むことで長さをしっかりと合わせるものですが、実は、より根本的な問題は、音楽にちゃんと乗れていないために変なところでゆるんだり、小説の末尾が短くなったりすることが多いのだろうと思います。音楽にちゃんと乗っていればそのような問題はそもそも生じにくくなるものです。なので、「ジャズ」が出てきたのは音楽に乗るための練習ということなのでしょう。
その上で、「ゴーシュさんはこの二番目の糸をひくときはきたいに遅おくれるねえ。なんだかぼくがつまずくようになるよ。」と子たぬきは言います。これは、ゴーシュの問題がゴーシュの腕だけではないことを暗示しています。それが、次の「チェロの穴」の布石となっているようです。
ネズミの母子とチェロの穴

ネズミの母は、「先生、この児があんばいがわるくて死にそうでございますが先生お慈悲じひになおしてやってくださいまし。」とゴーシュに頼みます。ゴーシュは「先生」となっています。
さて、何故、ここで「ネズミ」が登場するのか?このネズミは、「猫」や「カッコー」や「たぬき」とは性格付けが異なるようです。というよりも、「小さい」ことが大事なポイントとなっています。なぜなら、子ネズミをチェロの穴から楽器の中に入れることとなるからです。
チェロにもヴァイオリンにも、穴は開いています。fの形をしているのでf字孔(えふじこう)と呼ばれます。その両端は円形です。
しかし、チェロのf字孔の両端の円は、大きい方で17mm、小さい方で13mm(私の楽器で測りました)しかありません。一円玉の直径が20mmですので、例え小さなネズミであったとしても、大きい方の穴をくぐりぬけることが果たしてできたでしょうか?

また、金星音楽団が首尾よく演奏を終え、楽長に言われてゴーシュがアンコールの舞台に出るときに「ゴーシュがその孔のあいたセロをもってじつに困ってしまって舞台へ出る」という記述があります。果たして、どの弦楽器にもあるf字孔を以てしてわざわざ「孔のあいた」と言うのでしょうか?
このことについては、朗読演奏会で続きを語りたいと思います。
ともあれ、ネズミの母子に対して、ゴーシュは「なんとかラプソディー」という曲を弾きます。「ラプソディー」は狂騒曲とも訳されますが、即興性の高い自由で感情の豊かな曲を指します。賢治の腕前でどこまでの曲が弾けたかはわかりませんが、彼が、聴き手に感動をあたえるような、こんな曲を弾きたかったというイメージだったのではないでしょうか。それにより、団長から「君には困るんだがなあ。表情ということがまるでできてない。怒おこるも喜ぶも感情というものがさっぱり出ないんだ」と厳しく指摘されていた課題を克服した(夢を見た?)のでしょう。
ネズミの母子の話を聴き、ゴーシュは、拙い自分の演奏がほかの者たちの役に立っていたことを知ります。そして、ネズミの母子に対しては、病気の子供のために心を込めて演奏をすることとなります。利他の心で徳を積むことにより、崇高な境地に到達するという心は、法華経の熱心な信者であった賢治の宗教心の根源的なものを反映したのではないかと思います。
インドの虎狩りとは?

さて、三毛猫が「トロ(イ)メライ」を聴きたいと言ったときに、そして、演奏会でアンコールをさせられたときに弾いた「インドの虎狩り」とはどういう曲だったのか?
この名前でWeb検索しても、この「セロ弾きのゴーシュ」の物語が出てくるだけで、具体的な曲は出てきません。つまり、この曲は、この作品の中で賢治が想像した曲だったのだろうと考えられます。
それでは、なぜ「インドの虎狩り」というタイトルをつけたのか?
ネコ科のトラを狩るということで、三毛猫を懲らしめようとした、というような解釈がありうるとの指摘があったりします。いろいろと説が立てられそうですが、どのような曲であったのかを想像してみたいと思います。
賢治は、Suzuki Violinが製作していた量産品の中では最上級のチェロを買い求めていました。しかりながら、チェリストとしての彼の腕はあまり上達することはなかったようです。それでも、チェロの音は気に入っていたようで、ガーガーゴーゴーかき鳴らしていたとのことです。開放弦のまま、あるいは適当なところを左手で抑えて弓に圧をかけてごしごしと弾いていたのかもしれません。その弾いている様子は他の人が聴くには堪えないものだった可能性は高く、そのことは賢治も自覚していたのではないでしょうか。そして、このイメージが「インドの虎狩り」となっているのではないでしょうか?
三毛猫に対しては、まさに、この聴くに堪えないガーガーゴーゴーをやったのでしょう。しかし、アンコールでは、楽長は、「ゴーシュ君、よかったぞお。あんな曲だけれどもここではみんなかなり本気になって聞いてたぞ。一週間か十日の間にずいぶん仕上げたなあ。十日前とくらべたらまるで赤ん坊と兵隊だ。やろうと思えばいつでもやれたんじゃないか、君。」と褒めています。となると、三毛猫に対して弾いたのときは「赤ん坊」の演奏だったのが、アンコールでは「兵隊」の演奏へと大きな進歩を遂げたということになります。
賢治は、チェロを購入した年の年末に、東京の新交響楽団でチェロを弾いていた大津三郎を訪ねて、三日間でチェロのレッスンをしてほしいと願いました。大津は驚きながらも、彼がリハーサルに出るまでの早朝6:30-8:30までの2時間、3日続けてレッスンをつけています。賢治は、一生懸命頑張ることで、短期間でも大きな進展ができることをいつも期待していたのでしょう。なので、アンコールで弾いた「インドの虎狩り」は、そのように夢見た演奏であったということだったのではないでしょうか。
「セロ弾きのゴーシュ」本文
「セロ弾きのゴーシュ」は、青空文庫に掲載されています。そのリンクは以下にあります。
文献
(順不同)
梅津時比古著「《セロ弾きゴーシュ》の音楽論-音楽の近代主義を超えて」、東京書籍(2003)
梅津時比古著「《ゴーシュ》という名前ーセロ弾きのゴーシュ編」、東京書籍(2005)
横田庄一郎著「チェロと宮沢賢治ーゴーシュ余聞」、音楽之友社(1998)
多田幸正著「宮澤賢治とベートーヴェンー病と恋」、洋々社(2008)
岡屋昭雄著「宮澤賢治論ー賢治作品をどう読むかー」、桜楓社(1995)
福島章著「不思議の国の宮沢賢治ー天才の見た世界」、日本教文社(1996)
福島章著「心の軌跡ー宮沢賢治」、講談社学術文庫(1985)
丹治昭義著「宗教詩人宮澤賢治ー大乗仏教にもとづく世界観」、中公新書(1996)
中村稔著「宮沢賢治論」、青土社(2020)
板谷栄城著「素顔の宮澤賢治」、平凡社(1992)
