
女人高野の面影残り 奈良県宇陀市 真言宗室生寺派大本山室生寺 私の百寺巡礼282
真言宗室生寺派大本山室生寺は、女人高野と如に呼ばれている。
かつては、お寺は女人禁制であり参詣も出来ないものであったが、その中でも女性が参詣出来る寺としての立ち位置があった。
平安時代を通じて興福寺別院としての性格が強く、俗世を離れた山林修行の場、また、諸宗の学問道場としての性格も持っていた。中世以降の室生寺は密教色を強めるものの、なお興福寺の末寺であった。興福寺の傘下を離れ、真言宗寺院となるのは江戸時代のことである。真言宗の拠点である高野山がかつては女人禁制であったことから、女性の参詣が許されていた室生寺には「女人高野」の別名があるが、この別名は江戸時代以降のものである。
中世を通じ興福寺末寺であったが、江戸時代の元禄7年(1694年)に護持院隆光の拝領するところとなり、護国寺末の真言寺院となった。翌年、徳川綱吉生母の桂昌院は室生寺に2千両を寄進し、これをもとに堂塔の修理が行われた。元禄11年(1698年)、室生寺は真言宗豊山派の一本寺となって護国寺から独立し、現代に至る。
1964年(昭和39年)には真言宗豊山派から独立し、真言宗室生寺派の大本山となった。







近鉄・室生口大野駅から奈良交通バスにて室生寺に向かう。写真家・土門拳氏の愛した有名な旅館が寺の前にあり、その旅館からこの橋を渡ると室生寺である。
バス停からは参道が続き、焼いたヨモギ餅を売る店が並ぶ。

この仁王門を抜けると、山の中。4日分の荷物いっぱいのリュックを背負って石段を登るのだ。





実際に訪れての感想は、コンパクトで可愛らしいお寺だな、であった。
五重塔、茅葺屋根のお堂。昔ながらの建物。
更には、本数の少ない路線バスを「待ってー!」と走り、飛び乗り山の中へ。
ああ、古都に来たのだなと思うのであった。
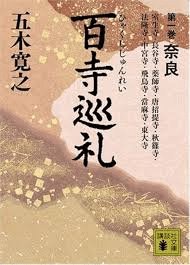
ここで、五木寛之先生の本を一部紹介したい。
室生寺は山中の寺である。
境内の急な石段を一歩ずつのぼってゆくと、突然、空中に浮かぶように五重塔が現れる。その瞬間、思いがけないほどの小ささゆえの優美な姿に目を奪われる。
実際に目にすると、聞きしにまさる「小さな塔」だということに驚く。
他k差は約16メートル。屋外にある五重塔では、この塔が「小ささ」において日本一だといわれている。
写真集などで目にする室生寺の五重塔は、なぜかもっとずっと大きく見える。しかし、こうして実際に来て眺めると、本当にミニチュアのようで、なんとも言えず可愛らしい。私はしばらくのあいだ、その前で言葉もなくたたずんでいた。
この小さな塔の周囲には、それを圧するように杉の巨木がそびえている。その杉木立のなかから、輝く金色の帯のような光が射し込む。すると、一瞬、ひどく妖艶な風情を感じてどきりとした。
「女人高野」として知られる室生寺を象徴するのが、この五重塔だろう。
寺院でも女性を不浄なものとして、参詣や修行を禁じているところが多かったのだ。
そんな時代に、悩み多き女性たちを受け入れた真言宗寺院がわずかにあったらしい。その一つが、都から遠く離れた奥山の麓にあったこの室生寺だという。そのため、この寺はいつの頃からか「女人高野」と呼ばれるようになった。
室生寺が「女人高野」の寺、女性を受け入れる寺として存在したことが、どれほど多くの女性たちのこころの支えになったことだろうか。

表門のすぐ前を室生川が流れ、その上には朱色の欄干の太鼓橋がかかっている。
見上げれば、深い杉木立の山がそびえている。
女性たちはどんな気持ちでこの橋を渡ったのだろうか。
川は結界である。この橋を渡った女性たちは。俗世を離れ、聖なる空間へと迎えられるのだ。おそらく、この橋のところへたどり着くまでには、一人ひとりに様々なドラマがあり、葛藤があったのではあるまいか。室生川の清流はそれを清めるイメージがある。川は濁った水も汚れた水も、すべてを差別なく受け入れて流れていくのだ。
今でこそ、私たちは鉄道やバスや車を利用することが出来る。しかし、かつて人々が室生寺へ詣でるのは大変なことだったに違いない。
ここは当時、大和の中心部からは遠く離れている山里である。
「女人高野」という言葉は、優美で女性的な寺を感じさせる。ところが、そうではない。
室生寺の仁王門をくぐると、目の前に次から次へと石段が現れ、一番上の奥の院へ行くまでには、全部で700段くらいの石段があるらしい。
明治以前、この奥の院に参詣するのは大変なことだった。当時は石段もなく、険しい崖のような所を女性たちは杖をつき、草鞋を踏みしめながら登っていったはずだ。また、登るだけではなく、おりてくるのも危険だったらしい。
それほどの難行苦行をしてまで奥の院まで登り、御影堂の弘法大師像に参拝した女性たち。いったいどれほど切実な思いに駆られて、女性たちはここを訪ねたのだろうか。
私たちが見る国宝級の建築物、或いは古寺、名刹というものは、創建された時の姿ではなく、何度か兵火に遭っていることが多い。
織田信長による比叡山の焼き討ちは有名だ。
けれども、室生寺は創建以来およそ1300年にもわたる長い年月を経ながら、兵火に遭わなかった。この室生寺の五重塔も、日本の平安初期の山寺では、当時の姿が残っている唯一のものだという。
私はその話を聞いて非常に感動した。
室生寺はおそらく、僧兵がたむろするような強い自衛力を持った寺ではなかったのだろう。室生の里の村人たちに支えられ、全国の女性たちの想いに支えられて、小さな五重塔や仏様が宇陀郡の山中にひっそりとたたずんでいる寺だ。
小ささゆえの強さ。或いは、強くないが為の強さ。
この寺の持つその「力」は、やはりある種の女性的なものであり、女性の真の強さ、或いは女性の粘り強さではなかろうか、とふと考えた。
寺というものは、寺だけで成り立っているのではない。その地域の村とか町の人々の思いや信仰心によって続いてきているものだ。
国宝級の伽藍や仏像を保ってきた寺にも、大変な苦労があっただろう。しかし、私はむしろ、その寺を支えている人々の思いこそが国宝級ではないか、という気がする。
そして、小ささゆえに強く、強くないがために強いという「女人高野」と呼ばれる室生寺の不思議さ。山中にこの小さな寺が作られ。1300年もの間しなやかに生き続けてきたこと。それは、女性が永遠の謎であるのと同じように永遠の謎かもしれない。
室生寺の急な石段を上り下りしながら、そのことを肌で感じた一日だった。


山寺や 紅葉便り 古都の香よ
真言宗室生寺派総本山室生寺
奈良県宇陀市室生78
近鉄・室生口大野駅より奈良交通バス奈良龍穴神社行きにて、室生寺バス停で下車。バス乗車時間は15分。
