
マーケター井上 大輔氏から見たセプテーニグループの新規事業開発 ~「The Entrepreneur」スピンオフ企画~
こんにちは。セプテーニグループnote編集部です。
セプテーニグループはミッションに「ひとりひとりのアントレプレナーシップで世界を元気に」を掲げています。
いま社会で活躍する様々なアントレプレナーをお招きし、セプテーニグループに所属するひとりひとりに、それぞれの「アントレプレナーシップ」について考えてもらう場「The Entrepreneur」が先日開催されました。
第6回目のゲストはニュージーランド航空、ユニリーバ、アウディ、ヤフー、そしてソフトバンクと、多数の企業でマーケターとして活躍し、先日発売された新著「マーケターのように生きろ」でも広く知られている井上大輔さんでした。井上さんからは書籍の内容を踏まえてグループ向けにお話しいただきました。マーケティングの考え方をプロセス単位でも認識し、自分が生み出せる価値を定めていくことの大切さなどを学び、参加メンバーにとってとても貴重な時間となりました。
▼井上さんの書籍「マーケターのように生きろ」
後日、お礼のご連絡をした際、ふと井上さんから「セプテーニグループのアントレプレナーや新規事業開発の取り組みについて少し覗いてみたい」との一言が。
そこで今回「The Entrepreneur」のスピンオフ企画として、マーケターである井上さんと、セプテーニグループでアントレプレナーや新規事業の育成を行っているグループ会社のセプテーニ・インキュベート斉藤さんとの対談が実現。
対談ではセプテーニ・インキュベートは何をしている会社なのか、マーケター視点から考える新規事業の創出についてなどをお話しいただきました。
ぜひご覧ください!
ーーーーーーーーーーー

井上 大輔
ソフトバンク株式会社 コミュニケーション本部 メディア統括部長
ミュージシャンを志すも挫折。小さな広告会社でプランナーの仕事を始める。当初はまったく仕事のできないお荷物社員だったが、マーケティングの英知から学んだ「仕事とは人の役に立つこと」という思想に目覚めて以降、仕事にかぎらずあらゆる場面で「必要とされる」ようになる。以降ニュージーランド航空、ユニリーバ、アウディジャパンなどでマネージャーを歴任。ヤフー株式会社マーケティングソリューションズ統括本部マーケティング本部長を経て現職。
雑誌・Web媒体への寄稿や講演会・セミナーへの登壇多数。NewsPicksアカデミアプロフェッサー。著書に『マーケターのように生きろ』(東洋経済新報社)『デジタルマーケティングの実務ガイド』(宣伝会議)など。

斉藤 彼野人
株式会社セプテーニ・インキュベート 取締役
セプテーニグループにおける新規事業の推進&イントレプレナーの育成担当。2013年 同グループに入社後、デジタル広告事業に配属。その後、新規事業コンテスト「gen-ten」での優勝をきっかけに新規事業畑のキャリアを築く。新規事業の責任者、システムディレクター、子会社代表に従事する過程で10以上のサービス立ち上げに関わる。現在はメディアコンテンツ、D2C・EC領域を主要分野としながら、直近はブロックチェーン・NFT関連のビジネス促進に注力中。
斉藤さん)
まずは、僕が所属しているセプテーニ・インキュベートについて簡単に紹介させてください。セプテーニ・インキュベートは、セプテーニグループにおいて新規事業の開発やイントレプレナーの育成を手掛けている会社です。社内の新規事業プランコンテスト「gen-ten」で上位に入賞したメンバーをはじめ、自ら手をあげてボトムアップで新規事業に挑戦したいと希望する社員が事業化に向けて取り組んでおり、会社としてその成長ステージにあわせた立ち上げ支援を行っています。
これまでに、デザイナー向けの就職・採用プラットフォーム事業を手掛けるビビビットや、社会貢献プラットフォーム事業を展開するgooddo、育児プラットフォーム事業を行うTowaStela、マッチングアプリ向けのプロフィール撮影サービスやメンズコスメの企画・販売などを手掛けるアルファブルをはじめ数社が、この仕組みのもとグループ会社として法人化しています。
今回は、新規事業の創出に関して、マーケターの視点・ご意見などをお伺いすることで、今後の活動に活かしていければと思っています。
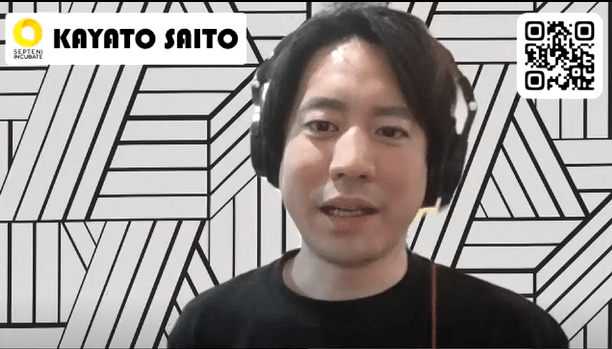
マーケターもアントレプレナーも顧客のニーズを満たすプロセスは同じ
斉藤さん)
サービスや事業を考える上で、すでに顕在化している市場に取り組むマーケットイン(※)のアプローチと、まだ認識されていない潜在的な市場に取り組むプロダクトアウト(※)の考え方がありますが、マーケターの活動ではマーケットインのアプローチが多い印象です。
一方でマーケティングにおいても顧客へのインタビューなどの過程を通して、より潜在的な課題を発見し、プロダクトアウトに近いアプローチをされることもあるのでしょうか?
※マーケットイン:顧客の声を聴き、顧客の要求や困りごとを突き止め、それらを解決する製品を市場に投入しようとする考え方 /プロダクトアウト:製品を提供する企業側が良いと判断した製品を市場に投入しようとする考え方
井上さん)
私は顕在化しているニーズを見つけるのがマーケットインだとは思っていません。お客様のなかに潜在しているものも含めニーズを見つけて、それを提供していくというプロセスはマーケターもアントレプレナーも変わらないのかなと思っています。
顕在化されていないし、ときに顧客自身認識すらしていない欲求を満たす商品やサービスが、しばし「イノベーション」と呼ばれます。それをセンスでつくりだすジョブズやフォードのような人もいますが、「液体洗剤」や「ジェルボール」のようなイノベーションは、技術のシーズ開発と同時に顧客の声を聞きながらそこに辿り着いたのではないでしょうか。「聴き方」次第では、顧客の内なる声を聞いて起こるイノベーションもあると思います。
ただ、直感でそれができるなら、一番強いなとは思います。
以前務めていた職場で、私ともう一人がある企画を手掛けることになりました。3か月ほどかけて顧客サーベイなども行ってデータドリブンで作っていったんです。
それを上司に見せようとしたところ、見せる前から「あーこれね~僕はこうだと思うんだよね~」と言ってホワイトボードにさらさらっとコンセプトを書いたんですが、それは私たちが出した結論と一緒だったんですよね(笑)。
データで導くのに3か月かかった答えをその人はその場で出せてしまう。結局出そうと思っていた結果は一緒なので、その人の感性や勘が本当に優れているのであれば、それに頼るのが一番いいなとは思います。
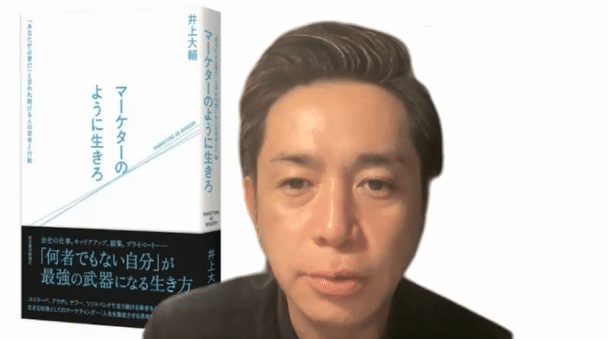
市場性か情熱か
井上さん)
僕が新規事業を創っていくことについて気になったのは、市場性とやり手の情熱のバランスです。
もし私が新規事業を企画するなら、大きめの市場がすでにあって、まだ供給も十分ではなく自分たちが満たせるニーズがたくさんあるような領域に参入すると思います。例えば、アイスクリームとか。この市場は規模が大きく、成長市場で、プレイヤーも少ないんです。
これだと結構確度は高いと思うんですが、ただこれの弱点だと思っているのは、やる人が情熱を持てないということ。
たとえこの領域は供給が不十分だし市場がたっぷりあるから参入しよう、といわれても、アントレプレナー魂が騒がないと思うんですよ。
起業するには大変なことがいっぱいあって、その大変なことを乗り越えていこうと思ったときに、なにがなんでもやってやる、という情熱がないと、乗り越えられないんじゃないかというのが私の想像です。
よくVCが人やその人の真剣度を見るとかっていうのは、そういった市場性は重要なんだけれども、仮に市場性やチャンスがあっても、アントレプレナー側の覚悟がないとどっちみち上手くいかないから人を見ているんじゃないかなと思っていて。
この点のバランスはどう取るのでしょうか。

斉藤さん)
当社では大きく二つの取り組みを行っています。
ひとつは、マーケットが顕在化していて、この領域に対しては人材や資本を大きく張っていくぞという領域に対する取り組みです。この領域では、ボトムアップというよりはトップダウンで戦略子会社を創ります。
ただアサインするプレーヤーはシニア以上を選びます。会社の中である程度ビジネス経験が豊富な人材を選ぶことで、成功確度をあげていきます。
この場合、市場の成長の波が見えているので、情熱というよりその波にうまく乗れるかという点が重要なので、ビジネススキルが安定的に高い人材を配置することが大事かなと。
一方で、どれがあたるかわからない潜在的な市場かつ新規性の高い領域については、本人の意志やここを変えたいぞという情熱がとても必要になってくるので、ボトムアップでやりたい人材に任せます。
やっぱりどれだけ上から言われたとしても本人がその領域に興味がなかったらやらされている感が強くなってしまうので、全然推進できないんですよね。
当社グループも今ではデジタル広告事業のイメージが先行すると思うのですが、創業当時は人材サービスやダイレクトマーケティング事業がメインでした。しかし現グループ代表の佐藤が新卒3年目の時に、「何か新しいことやらせてください」と手を挙げて、インターネット事業を始めました。
それは別に既存事業とのシナジーがあるとかトップダウンだったとかではなくて、本人の意志でゼロイチで新しいことを始めていったわけですが、その結果今の主軸事業にまで成長しています。
なので、戦略的に今までの事業とシナジーを生むという文脈ではなく、将来的に第3の柱になるような事業をつくるためには、ボトムアップで数を張ることも大事なことで、僕がやっているのはその小粒な事業の種を育てる事なんです。

当社では外部から見ていると一言では表現できないくらい様々な分野に着手しているのですが、ここにおいてはパイオニア精神を求められてくるので、どちらかというと本人がやりたいかどうか、情熱を傾けられるかどうか、が大事だと思っています。
ただ、やはりボトムアップの新規事業においても領域が分散しすぎると経験値が貯まらないという側面もあるので、メディアコンテンツやD2Cなどある程度広いテーマを提示しながら新規事業をボトムアップで出してもらうようなアプローチも大事だなと感じています。
井上さん)
なるほど。
市場性があると判断した領域にはトップダウンでビジネス経験が豊富な人材に、不確実性の高い領域では意欲と情熱を持っているボトムアップのアントレプレナー人材に任せる、というのがいいんですね。

そもそも新規事業に野心は必要?
井上さん)
あと、お聞きしてみたいのが、インキュベーターというのは「保育器」って意味ですよね。
なので保育器の中に入っているベンチャーに比べ、野生の中でワイルドに育っているベンチャーのほうが強そうに見えるのかなと思ってしまうのですが、その違いはいかがでしょう。
斉藤さん)
そうですね、グループの様々な資産を活用できるメリットがある反面、スピードとトレードオフになる要素は多少なりともあるのかなとは思います。
それから当社で面白い取り組みをしているところでいうと、サラリーマン経営者を増やしたくない、という思いがあります。
ボトムアップ型の新規事業でも成長に対し継続して動機付けができるようするため、当社ではある程度の基準を超えるとその成果に応じてより大きいリターンが得られるといったミドルリスクミドルリターンのような制度設計をしています。
このように、純粋なベンチャー企業に対し野心負けしてしまわないように、どのようにしたら企業内であってもハングリーさを持ち続けられるかということはテーマとしてありますね。
井上さん)
実際問題として、野心やハングリーさって絶対必要な条件なのでしょうか?
企業の経営者の方々の中でもぱっと見では野心をもっているようには見えない方もいらっしゃるのかなと思っていて。
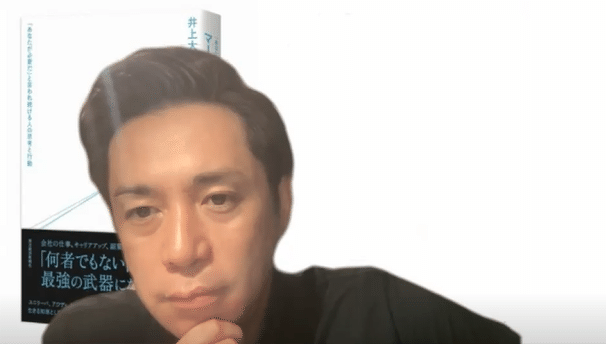
斉藤さん)
野心の方向性なのかなと思います。いわゆる名誉やお金といったものは分かりやすい野心かと思うんですが、それ以外の文脈でいうと社会貢献とかより大きい枠組みで世の中に貢献したいという思いは、見えづらいかもしれないと思うんですね。
そういう静かな野心や志みたいなところは、事業を推進していく上である程度大きなウエイトを締めているんじゃないかと。
あとは、継続して成長性を求めるスタートアップなのか、ある程度の事業規模で満足してしまうのかで大きな違いがあると思っていて、当社で創りたいと思っているのは前者です。
この点では当社では企業の中にあっても常に増収増益を課せられるので、現状に満足することなく成長を目指し続けられるような構造にはなっているかと思います。
井上さん)
歴史上、コーポレートインキュベーターみたいなところから生まれた一番の成功事例ってどこなのでしょうね。世界的に見て事例はいっぱいあると思うのですが、その成功している企業における共通項として、担当者の情熱や野心がどの程度あるものなのかが気になります。
社内の新規事業が成長して親会社の規模を超えた例で思いつくものを考えてみると、仕組み以上に事業を牽引する個人に依存しているように感じていて。それはそうとして、その個人の何が決め手だったのか、野心なのか能力なのか、能力だったらどんな能力なのか。そこも面白い論点かなと思いました。
斉藤さん)
予想も含めてですが、個人に依存するというのは色々分析すると共通点としてあるかもしれないですよね。
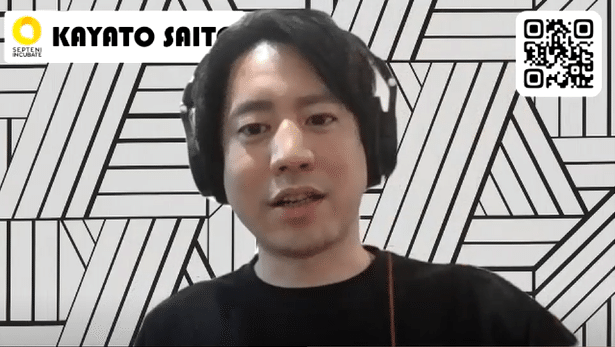
マーケター視点でのアドバイスとこれから
井上さん)
その意味では、人の話と仕組みの話は切り離して考えたほうがいいのかもしれません。仕組みの話で、かつ再現性という観点からいえば、企業内で新しい事業をインキュベートする場合も、どっちかというとマーケター的な発想でお客さんやマーケットを理解する仕組みをつくっていったほうが有利な気がします。一方で、ドライブする人をどう目利きするか、どう育成するか、というのはそれとは全く別で考えないといけない課題だと思いました。
斉藤さん)
僕は今までのお話を聞いていて、いきつくところはタレントマネジメントなんじゃないかと思いました。いかに新規事業のポテンシャルの高い人材を発掘し、その才能や能力を伸ばしていけるかという。
そこに対して魅力的な制度設計とか、続けていきたいと思える動機づけをしっかりすることが大事なのかなと思いました。
その点、井上さんがおっしゃる通り、当社で足りない部分としては、マーケター的な視点で理解する仕組み化かなと思います。これまではどちらかというと人のタレント自体を見て、後は好きにやりなさいというかたちを取っており、外で起業するのと大差ない体制だったので。
最近ではその点のフォローや支援ができる体制を整えています。まだ道半ばではありますが、そうした2軸で当社の取り組みをより一層推進していきたいと思いました。
本日はありがとうございました。
**編集後記**
ふとしたことから実現したスピンオフ企画でしたが、トップマーケターである井上さんの視点や対話を通じて、セプテーニグループの新規事業創出への取り組みについて振り返り、今後の活動へ向けた良い機会となったようでした。
今後も様々な取り組みについてご紹介していきたいと思います!
▼セプテーニグループの新規事業創出への取り組みに関する記事についてはこちらもぜひご覧ください!
#セプテーニグループ #新規事業開発 #The Entrepreneur #アントレプレナー #セプテーニ・インキュベート
