
歴史のことばNo.21 伊藤敏『歴史の本質をつかむ「世界史」の読み方』の読み方
各所で話題になっている伊藤敏先生の『歴史の本質をつかむ「世界史」の読み方』をご恵贈賜りました。
具体的なところに目がいってしまう質なので、特に読みでがあったのは、「より深い理解へ導く見方」とうたう第Ⅲ部である。

ラシードゥッディーンの『集史』における騎馬兵との違いをビジュアルで紹介(258-259頁)
さらに読み進めていくと、なんと「モヒの戦い」が!
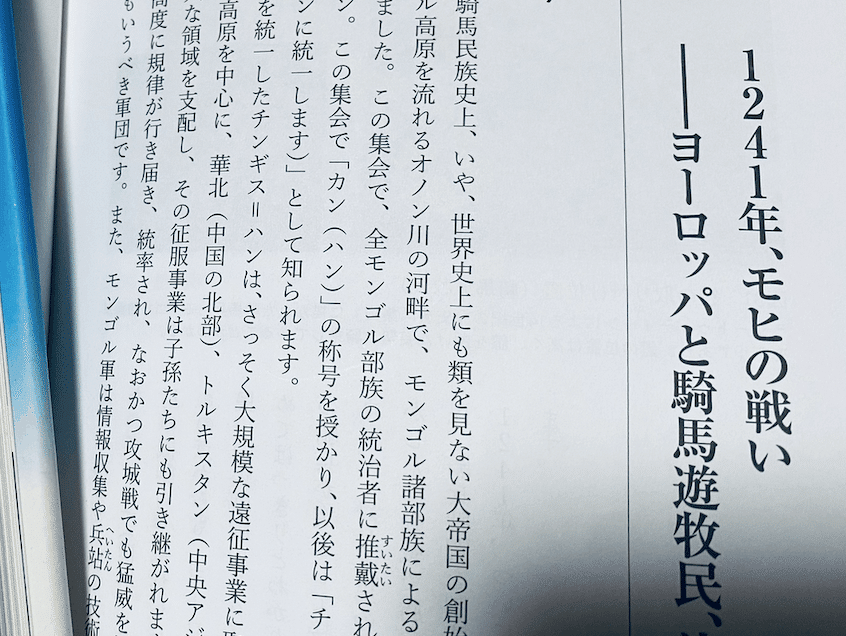
モヒの戦いなんて、高校世界史の教科書には載っていない。
じゃあモヒの戦いなんて必要ないんじゃないのか?
単にマニアックなのではないのか?
さらにその後には、イギリスでもフランスでもなく、なんとスイス(盟約者団)がとりあげられる(参考文献にスイス史の瀬原義生先生の著書も)。
入門とうたっているのに、これは細かいのではないか?
そんな反応があるとすれば、著者なら次のように釘を刺すだろう。
こうした過去と向かい合うときにメルクマール(指標)となるのが、世界に登場する用語です。教科書などで強調されていたり、受験で頻繁に問われたりする用語だけが、必ずしも重要とは限りません。すべての用語(=メルクマール)には必ず意義があり、この意義を介して過去を有機的に捉え直すことができるのです。ですから、究極的には世界史に無駄な用語や些末な用語というものは存在しえないのです。
網羅から、概念へ
ようするに、教科書に載っていない言葉は重要ではない、わけではないという話である。
ふつう世界史入門をうたう書籍であれば、「入門」的な言葉が精選され、いっしょうけんめい網羅していくのが常だろう。本書にそのようなことを期待していると、みごと肩透かしを食う。
むしろ、多くの人は網羅しようと思って世界史に入門しようとするからこそ、世界史学習に挫折する。同様に、教える人間にとっても、いたずらな網羅こそが苦役への道(小川幸司)を舗装することになる。
しかるに、「概念」をおさえた上で歴史的な事象をながめると、些末に思えるようなどのような知識も、たとえ目立たない辺境であっても、かけがえのない意義を帯びてくる。そのメッセージをなげかけたところに、本書の創見がある。
たとえば教科書的には、モンゴル軍がヨーロッパをやぶった「ワールシュタットの戦い(リーグニッツの戦い)」が「重要だ」と覚える。そこから、ワールシュタットの戦いという言葉そのものが重要ということになると、それ以外の言葉、たとえばモヒの戦いは二軍三軍扱いになる。もちろん事細かにすべてを記憶せよということではない。歴史とは本質的に、あまたの事象から「選びとられたものである」との認識が欠かせない。その選択の根っこにあるのが、「概念」をもちいて考える力だ。
世界史を「考える」手ほどき
もちろん「概念」を先行させれば、そこからはみ出るものはつかまえにくい。だが、入門であるからにはバッサリと見取り図を描くことも必要だ。本書は第Ⅱ部で、「概念」を理解すること、各時代の特徴(キャラクターあるいはシステム)に即した時代区分をベースに、歴史的な出来事を「考える」ことが、世界史の本質をつかむ学びであると提起する。
その上で先ほどあげた第Ⅲ部では、各時代の特徴に即して「宗教」「戦術」「思想」をもとに歴史的な出来事を「考える」方法が実演されるのだ。けっして好事家的なエピソード紹介にとどまるものではない。
第Ⅰ部は通史をコンパクトにまとめたパートだが、おそらく第Ⅱ部の理解に基づいて、もう一度再読してもらいたいとの立て付けになっているのだろう。
「見えないなにか」と世界史
というわけで、本書にはあまり人物のエピソードや物語的な要素は登場しない。
人間を中心にとらえるか、それとも人間の社会を背後でうごかす「なにか」を中心にとらえるかは、たとえば昭和史論争をあげるまでもなく、歴史叙述をめぐる永遠のテーマだ。
「なにか」中心の歴史観といえば、かつてはマルクス主義的な歴史観が主流を占めていた。しかし現在関心が高まっているのは、そうしたものとは別次元にある、経済や地理、進化や気候といった、人間をこえる「しくみ」への関心だ。『銃・病原菌・鉄』や『サピエンス全史』に触発されてのこともあるだろう。私のnote(ゼロからはじめる世界史のまとめ)もそういった欲望が根本にあるように思う。
では、どうしてそのような趨勢になっているか。
端的にいえば、われわれの時代が「これからどうなるかわからない歴史的転換点にある」「特定の文明の普遍性が崩れ、文明の本来的な多元性が露出しつつある」との漠然とした意識が強まっているからというのもあるし、人間社会の背後にある何かよくわからないドロドロしたものがせり出してくることに対する不安感もあるのだろう。AIや感染症、気候変動はそういった意味でおなじ位相にあるのかもしれないし、ロシア侵攻以降の「地政学」的な歴史理解の盛り上がりも、「見えない何か」が人間社会をうごかしているとの不安がベースにある。
われわれの世界をうごかす「見えない何か」は一体何なのか。「現代とは、今とは何か」(本書のラスト・クエスチョン)。これをとらえる力は、歴史を動かす「しくみ」について「考える」ことで養われる。歴史が不確実な時代に求められるのは、いつの世も変わらない。
ただ、「しくみ」に対するとらえかた自体、時代に大きく規定されるものだ。どのような「概念」を用いて、どのように歴史を読み解くのかによっても、大きく左右される。
著者も述べているように、本書の掲げる概念=しくみをベースにした時代区分もまた、多くの見立ての一つにすぎない。たとえば世界システム論についてはヨーロッパを中心に組み立てているが、そうではない理解もあるし、国家のない地域をどう見るかという問題もある。たとえば中国史については、やや違ったアプローチも必要になるだろう。
とはいえ、とにかく知識を詰め込まれることに苦しんだ経験をもつ(おそらく)大多数の人にとって、「概念」に着目して世界史を学び直していくプロセスには、新鮮な面白さがともなうはずだ。「この一冊で」ではなく、「この一冊から」世界史の学び直しがはじまる。むしろ入門書にありがちな「この一冊で」とうたわないところが誠実である(内容は帯通り)。どちらかというと一度世界史を網羅的に学んだことのある人が、ベストフィットなのだと思う。もちろん資史料を通して世界史を解釈していくことを重視する新科目「世界史探究」とも相性がよい。
こういった視点を大事にしながら、軍事史やスイス史への造詣も含め、限られた紙幅で「守破離」の展開をコンパクトに実現させたところに、本書の芸当がある。
このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊
