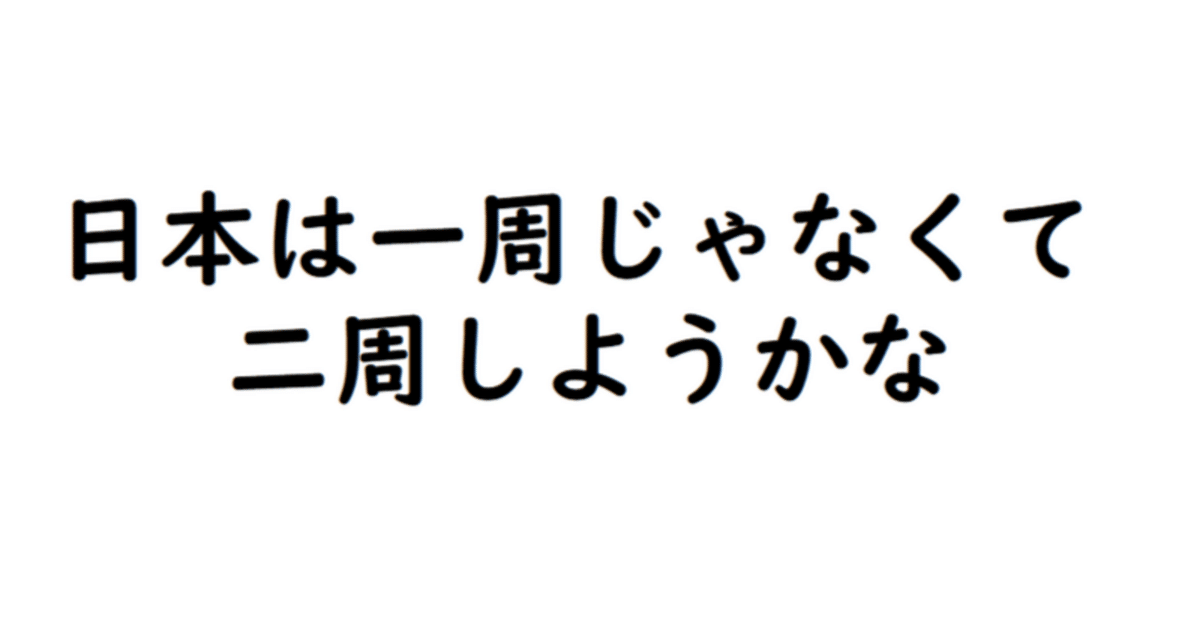
第143話 兄貴は医学の常識を破り、薬なしで癲癇の発作をなくした【夢夢日本二周歌ヒッチ旅 回顧小説】
兄は退院した。
でも退院後1年程は30分会話するだけでも異常に疲れ、疲れると声が出しにくくなる。
見た目は普通だからまわりには理解されにくい。
余計に疲れる。
疲れがピークに達すると癲癇(てんかん)の発作が起きる・・・。
そんな状態で兄は就職活動を始めた。
就職活動は会話を駆使する活動だから、きっとこれも過酷だっただろう。
それでもなんと九州の大手企業に就職。
そして同期では営業トップとなる。
兄は「いかにして楽して仕事するか」をテーマに働いていた。
昼間はなるべくどこかで昼寝する。
営業は午後遅くにたたみかけていくととれるらしい。
決して怠け者だからではない。
いや、もともと無駄なことは省きたいという性格だからというのもないことはないが、そうでもしないと体がもたないからだ。
営業だからしゃべらないといけない。話を聞かないといけない。
少しでも無理すると声が出なくなる。
癇癪でも起きたらきっとクビになる。
よくそんな状態で営業をしていたものだ。
でもだからこそ究極につきつめたやり方を編み出したのだともいえる。
結局3年間勤めたところでドクターストップがかかった。
発作が起きたのだ。
ただ、兄としてはそもそも独立する前段階のサラリーマンという設定だったらしく、何年かしたら辞めるつもりだったので、3年勤められたし、ちょうど次のステップに移るタイミングだと受け止めていた。
実は兄は大学に行きながらダブルスクールで柔道整復師と鍼灸の専門学校に行って免許を持っていた。
運動が好きだったからスポーツをする人のサポートをしたいという思いがあったのだという。
しかし、自分が後遺症を持つ身となってからは、「自分を治す」ことが大きなテーマになっていった。
サラリーマンを辞め、誰かのペースで働いてオーバーワークしないですむ環境を自ら作るため、兄はまずは何カ所かの治療院やリハビリセンターで経験を積みながら、ついに府中に自分の治療院を立ちあげた。
実は癲癇の発作を防ぐため、兄は病院から薬を処方されていた。
薬は確かに癲癇を起きにくくするのだが、その弊害もある。
薬を続けることで肝臓をはじめ内臓にダメージが貯まる。
意識もぼーっとしがちになる。
それはつまり通常の生活が送りにくいというだし、ちがう病気を併発する可能性が高いということだ。
医者には「生きても40歳ころまで」と母は言われていたらしい。
兄はそれが許せなかった。
なんとしても生きたい。
薬漬けの人生なんて送りたくない。
医者は間違っているんじゃないか。薬を飲まなくて済む方法があるんじゃないか。
そして兄は「自分で自分を治す」ために研究に研究を重ね、ついに薬を飲まずに生活することに成功した。
成功したというのは、体を自分で治し、癲癇の発作が起きなくなったということだ。
癲癇と聞くと脳の中がどうにかなっているというイメージが真っ先に浮かぶ。しかしそれが全てではなかった。
癲癇が起きる時の前兆というのも分かって来て、薬ではなく、もちろん休むことが一番だが、鍼や手技によって予防することができることが分かって来た。
癲癇が起きる前は身体が極度に固くなっている。
もちろん呂律もまわりにくくなっているが、なぜまわりにくいかというと、筋肉が硬直してきているからという面もある。
簡単に言えば筋肉の硬直をほぐすことで、癲癇を予防できるのだ。
完全に癲癇が起きなくなるまでにはやはり何度か発作を起こしている。
治療院は兄とスタッフ2人での運営だから、どうしても大変なときは無理して働かざるを得ない。
でも発作が起きてしまったときは、体に何が起きているのか、どうすればいいのか、それが研究材料となる。
そうやって兄は克服していった。
「薬でしか解決できない」という西洋医学の限界に挑戦し、成功した。
だから兄の治療法は説得力がある。
自分が実験台で、結果は自分がよく分かっているから、まやかしの治療法は用いない。
自分を治したいのだからあぐらをかく理由などないのだ。
いろいろな治療法を本で学んだり、セミナーに行って覚えてきたり、治療器具を導入したりと、貪欲に吸収していた。
自分が治るかどうかだから使えない治療法はやめるし、時間がかかる治療法は自分に負担がかかるのでやめる。気づくともう前のやり方は変っている。
兄は本当に貪欲な人だ。
自分の「やりたい」という思いにまっすぐで、かなえたいと思う人だ。
やりたいことがかなえられないとき、なんでやらせてくれないんだと怒るような人だ。
それがぼくが昔から兄をすごいと思っていたところだ。
ぼくはどちらかというと何をやりたいかはっきりしない方で、やりたいことがあったとしても、やれないからといってそれほどくやしくないと思ってしまう。
自分の道が絶たれて悔しくて悔しくて泣いた。
なんてことはぼくの人生になかった。
兄は小学校の時、読売サッカークラブのAチームでプレーしていた。
サッカーがうまくて大好きで、でもヘディングをするたびに頭痛がするようになった。
透明中隔腔嚢胞という病気で、「これ以上サッカーを続けると嚢胞が破裂する」と医者に言われサッカーを断念した。
兄は泣いて悔しがっていたと思う。
「なんでサッカーがやれないんだよ!」と。
中高ではバレーボール部に入ったが、同期のメンバーと考えの方向性の違いで決裂し、退部。
兄は自分自身がうまくなりたいという思いも人一倍強かったし、チームを強くしたいという思いも人一倍強かった。
ある時、女子部のバレー部と練習試合をしたいというメンバーに対し、
「絶対女子の方が圧倒的に強いから、士気が下がるからやめた方がいい。」
と兄は反論したそうだ。
女子とやりたがっていた風潮も嫌だったのだろう。意見がぶつかってしまった。
それに顧問の監督が練習にあまり現れてくれなかったことにもどかしさを感じていて、
「おれたちにもっとバレーボールを教えてください!」
と監督のもとに土下座をしに行ったこともあるそうだ。
それでも監督が来てくれなかったことにも腹を立てていた。
最終的には、
「こんなクソみてえな部活やってられっか!!」
と言い捨てて体育館を出ていき、二度とバレー部には戻らなかったそうだ。
ちなみに後にぼくもそのクソバレー部に入ったのだが、兄のその時の去り方は伝説として語り継がれていた。
ぼくにはそんな風に熱くなれるものがない。
ぼくもそんなふうに熱くなりたい。
そう思ってきた。
きっと兄からみたらぼくはもどかしく見えることが多かったに違いない。
「やるならもっとやれよ!」と。
だから、音楽を始め、日本二周の旅に出たことは初めてぼくが見せられた勇気ある姿だったと思う。
兄はきっと喜んでいたことだろう。そう思うとぼくはうれしく思えた。
大学でサーフィンを始め、兄は自分の生きがいをようやくまた見つけたようだった。
サーフィンをしにアメリカに行ったこともある。
海に行くと自分をリセットできるというほど、海が大きな存在になっていた。
でもそのサーフィンの最中に倒れた。
前の様にサーフィンに没頭できる体力も時間もなくなった。
いったいいつまで運命は兄から兄の宝物を奪っていくのか。
なぜ?なぜ求める人から奪い、なぜあやふやなぼくからは奪っていかない?
きっと兄が一番運命を呪っただろう。
でも兄はそういうことをつゆほども表に出さなかった。
しんどいときも、「寝れば大丈夫だから。」とか「手抜いて仕事してるから。」とか言って適当に流していた。
そんな兄の苦労とはよそに、ぼくは旅を続けていた。
当時のぼくは実際には兄に対して何もできていない。
自分のことで精いっぱいで、人の事なんてかまう余裕もない。
兄がぼくに海に連れていってと言ったのは、そんなぼくに対してだった。
特に何もしてあげられていないぼくとしては、
(運転手役で役立てるなんてうれしいな。)
というのが正直な気持ち。
その後もぼくは時々兄を海に連れていっている。
そして兄は無理だと言われた40歳をとうに超え、50代を元気に生きている。
限界や常識をつきやぶって生きている。
