
切磋琢磨する環境だとパフォーマンス(成果)が上がる!?『ピア効果』

『ピア効果』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!
お申込みは上の画像をクリック!
仲間や同僚の仕事振りやパフォーマンス(成果)が、他の人に生産性などの影響を与える『ピア効果』。立証された実験や注目されている理由、メリットや注意しておきたいポイントなどについて解説しています。
■『ピア効果』とは?

『ピア効果』とは、仲間や同僚の仕事振りやパフォーマンス(成果)が、他の人に生産性などの影響を与える心理事象のことです。
ピア(Peer)は、年齢や地位、能力などが同等の者、同僚や仲間を意味する英語であることから『同僚効果』とも呼ばれています。

一般的に、集団を構成する個人個人が、お互いに切磋琢磨し合うことで、その集団のレベルアップや個々人の成長に相乗効果をもたらす心理効果を『正のピア効果』と呼んでいます。
一方、集団の構成によって、逆にお互いに悪い影響を与え合うことで、集団・個々人の行動や生産性が低下してしまうことを『負のピア効果』と呼んでいます。
元々は、教育分野で注目された心理作用でしたが、それが限られた人材を有効に活用することが求められる企業の人材育成や生産性の向上などへ活用されるようになっています。
■ピア効果の実証実験

◆①スーパーのレジ打ちの場合

2009年にアメリカのスーパーマーケットで行われた実験です。
一列に同じ方向に向いて並んでいるレジの場合、レジスタッフAの視線の先には、同僚のスタッフBの背中が見えています。
同僚のスタッフBは仕事が早く、スタッフAからは客の商品をどんどんと処理している状況がわかります。
この場合、スタッフAは同僚のスタッフBの仕事振りに感化されて仕事が早くなるのでしょうか?

結果は、スタッフAのパフォーマンスはそれほど向上しませんでした。
むしろ、スタッフAの仕事振りに影響を与えたのは、視線の「先」ではなく「背後」に配置された優秀な同僚Cの方でした。
これは、「優秀な人に見られている」というプレッシャーが仕事のスピードを引き上げたと考えられます。
この効果を得るための前提条件として、自身の背後に優秀なスタッフCがいることを予め知っている必要があります。知らなければ効果が出なかったと実験では明らかになっています。

そして実験結果によると、同僚が10%多く仕事をこなすと、他のスタッフは1.5%ほど仕事のスピードがアップすると推定しています。
人間が、同じ集団に所属する他人のパフォーマンスにどんな影響を受けるかを示す好例と言えます。
◆②スポーツ(水泳のクロールと背泳ぎ)の場合

次に、2015年に日本の小学生~高校生までの水泳のデータをもとに検証した実験を見てみます。

クロール(自由形)の場合、隣のレーンの泳者が自分よりも遅い場合、両隣に誰もいない場合と比較して速く泳ぐことができた。が、隣のレーンの泳者が自分よりも速い場合は、遅くなってしまった。
このケースでは、スタート前に隣の泳者の情報が確認できることから、『ピア効果』が働くことによって「自分よりも遅い泳者には負けられない」と考えたと思われます。
ちなみにこの実験では、隣のレーンの様子が泳いでいる際に確認できない背泳ぎの場合は、ピア効果は見られませんでした。
スーパーのレジ打ちの実験では、優秀な同僚の影響を受けたにも関わらず、この水泳のケースではそれが起こらず、しかも自分よりもパフォーマンスが劣った泳者に影響を受ける結果となりました。
まだ『ピア効果』については明らかになっていないことがありますが、「プレッシャー」の与え方や感じる状況が影響していると考えられます。
◆③実業団スポーツの場合

上述のレジ打ちや水泳の実験では、影響を与える人と受ける人の物理的距離が近いケースでした。
では、企業に所属し一般の従業員と同じように通常業務を行い、その後トレーニングに専念する実業団のスポーツ選手が職場に与える影響についての実験を見てみます。
そもそも、企業が実業団スポーツに期待することとしては、広告効果やCSR(企業の社会的責任)、社員の帰属意識(企業という特定の集団の一員であるという意識)の向上といったことが挙げられます。
「帰属意識の向上」の観点から見てみると、同じ会社に所属する従業員でもある選手やチームが活躍すると、その他の従業員含め一体感が生まれ、労働意欲が高まるのでしょうか。
企業スポーツに力を入れている、ある自動車メーカーへのアンケート調査を行った研究結果では、この企業が取り組んでいる野球・ラグビー・駅伝の試合結果が、一般従業員の労働意欲にどういった変化をもたらすかを5段階評価で質問しました。

チームの勝敗の観点から見てみると、勝った時には従業員は喜び、労働意欲が向上し、逆に負けた時は怒ることはなく労働意欲も低下しませんでした。
従業員の年齢の観点から見てみると、従業員の年齢が上がると、勝つことが労働意欲の向上につながる確率が0.7%高まることがわかりました。
これは、年齢を重ねればその分、長年勤務している可能性があるため、会社に対する帰属意識が高まったと考えられます。
選手と同じ部署に所属する従業員に限定して見てみると、同僚の選手が試合に勝った場合、労働意欲が向上すると答える確率が10%以上高まる結果となりました(野球:約17%、ラグビー:約14%、駅伝:約11%)。
そして負けても同僚の従業員の労働意欲に低下は見られませんでした。
負けても寛容的な態度であることから、勝ち負けよりも「頑張っている姿」に共感していると調査結果では考えられています。
■ピア効果が注目されている理由

◆コロナ禍で広まった『テレワーク』

この『ピア効果』が注目されている理由の一つとして、コロナ禍で広まった『テレワーク』が影響しています。
コロナ禍でテレワークが普及し、リモートワーク・在宅勤務といった、職場の仲間・同僚と離れた場所で仕事を行う機会が増えることになりました(今では出社傾向となっていますが)。
従来のオフィスワークでは常に上司や同僚が周りにいるため、一人で作業をしていても孤独感を持つことはあまり無かったと考えられます。
ですが、テレワークの場合、チャットやオンライン会議などでコミュニケーションをとることができますが、オフィスワークのようにお互いの存在を近くに感じながら状況を共有したり、その場の空気感を共有したり感情を読み取ることは難しいため、孤独を感じる人も一定数いると思われます。

つまり、オフィスワークをしている時には気づかなかった仲間や同僚の存在が、テレワークの普及によって再認識されることになったのです。
こういったテレワーク環境下でも『ピア効果』を高めていくためには、チームの一体感を物理的に感じられるよう、定期的にオフィスに出社して顔を合わせる機会を意識的に設けることが必要になってきます。
◆日本で進む高齢社会

日本の高齢社会が進んでいることも、注目されている要因の一つと言えます。
同じ集団の中の人々のパフォーマンスや活動が、他の人に影響を与える心理事象である『ピア効果』ですが、例えば介護施設といった高齢者施設では「集団」でのレクリエーションなどが取り入れられています。

(状況は個々人によっても変わりますが)加齢によって知能低下や運動能力の低下が引き起こされやすくなり、思考機会がない・身体を動かす機会の減少によって、物事への関心や集中力、運動能力の低下のほかにも、周囲への関心や役割認知、仲間意識や帰属意識、生活意欲の低下といった悪影響を及ぼすことにつながってしまいます。
そのため、個々人の体力や機能に応じて「集団」でのレクリエーションなどによって、施設利用者の集団参加を促し、各能力の活性化以外にも、役割意識や自信を高める、他者への理解や人間関係の構築機会の創出につながることから、集団で行うレクリエーションなどが注目され、多くの施設で取り入れられるようになっています。
↓
この続きでは、『ピア効果』が発生することにより生じるメリット、
活用時に注意しておきたい2つのポイントについて解説しています。

『ピア効果』を解説したPDFデータを無料でプレゼント!
お申込みは上の画像をクリック!
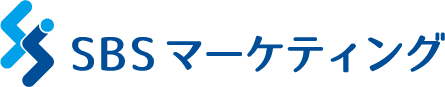
株式会社SBSマーケティングでは、中小規模企業様、個人事業主・フリーランス様向けに集客や販売促進、マーケティングに関連したコンサルティングサービスをご提供しております。


『心理テクニック』を販売中!
■中堅・小規模企業様向けサービスはこちら
■個人事業主様・フリーランス様向けサービスはこちら
ご興味ありましたら、まずはお問い合わせください。

株式会社SBSマーケティング コンテンツマーケターより。
