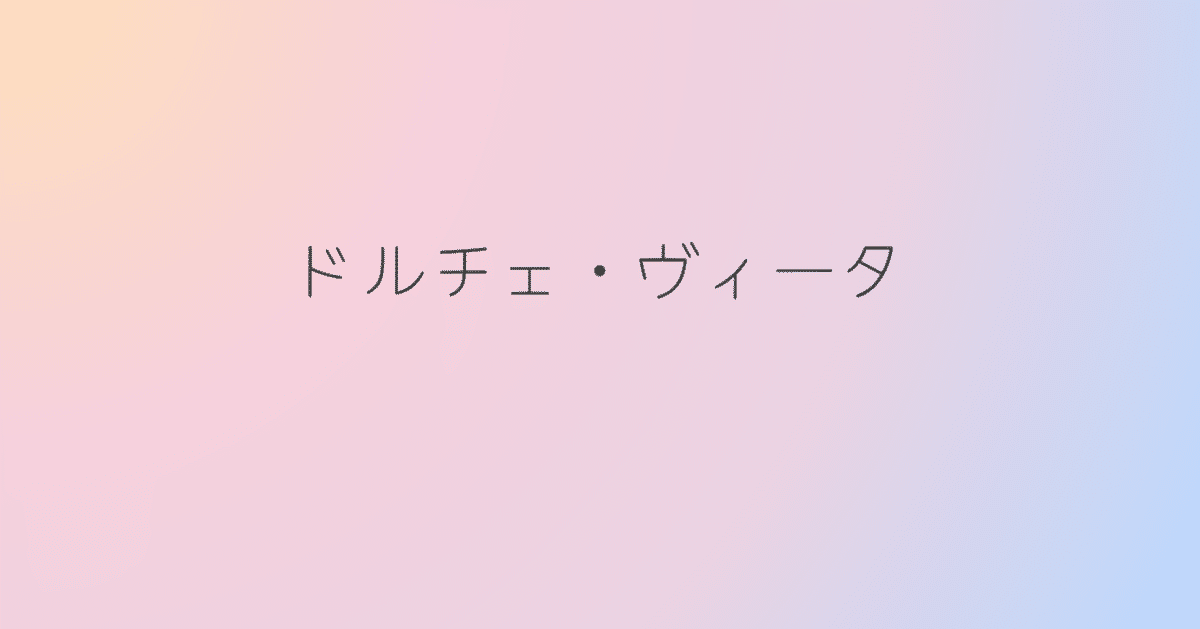
小説「ドルチェ・ヴィータ」第2話(全11話)
これまでのお話
・第1話はこちら
*
第2話
*
その日の帰りはすっかり遅くなってしまった。私は平泉さんに留守電を吹き込んだ。
「祥穂です、遅くなってごめんなさい。結局長引いちゃいました。ハラペコなので、駅前でラーメン食べて帰ります」
平泉さんは電話の応対はしないのだが、こうして声でメッセージを残しておくことで安心してくれる。なんだかんだで心配しながら待っていてくれるので、遅くなった時は、いつからともなくこうして留守電を残すようになった。
地元の駅に辿り着いて、いつものラーメン屋に向かう。こってり豚骨醤油系の太麺で、ほうれん草と味玉が載っている濃厚なラーメンを出す店。この時間に食べるのはよくないとわかっていながらも、扉の前に立つと背徳的な喜びでぞくぞくしてしまう。
「いらっしゃい」
「醤油、麺かため、ほうれん草多めで」
「はい」
「あ、あとビールもお願いします」
「グラスですか? ジョッキですか?」
「ジョッキで」
注文を通してから、流れているテレビをぼんやりと眺める。グレートバリアリーフに潜る芸能人が、澄み切った海の中で小魚の群れに囲まれながらはしゃいでいた。
そういえば、いつか別れた彼がオーストラリア土産にチョコレートを持ってきてくれたことがあったっけ……と思い出した。年に一度、家族サービスと称して海外旅行をしていた彼は、オーストラリアに行っても、ハワイに行っても、イタリアに行っても、チョコレートしか買ってこなかったのを思い出して、私はくさくさした。
「はい、ジョッキ生」
「ども」
私は店長に向かってジョッキをちょっと上げ、ビールを飲んだ。どうにもならないことなんて、忘れてしまえ、流してしまえ。ビールの泡といっしょに、きれいさっぱり流してしまえ。
「いらっしゃい」
扉が開いて、新しい客が入って来た。背が高い髭の青年で、大きな機材を抱えている。
「特盛、にんにく多めで」
「はい」
「あと餃子も」
店長は青年の前に水を置いた。青年はどこか楽しげな様子で、テレビを眺める。芸能人は海から上がって、メルボルンの夕景を楽しんでいる。
「今日はうまくいきましたか」
店長が青年に話しかける。
「ああ、ちょうどいい画が撮れたんでね、よかったですよ。やっぱり自然相手はいいですね、気持ちがひろびろする」
聞くともなしに、会話に耳が傾く。
「たまに都内をこうして離れると、すっきりしますね。最近どうしても、人相手の仕事が多くなってきちゃったから」
「いいなあ、俺もたまには自然の中でリフレッシュしたいっすよ」
専門職の若者どうし、ふたりの会話に、頬が緩む。私はビールをちびりと飲んだ。
「いやね、それが今日、こーんな大きなヤマメが跳ねて」
髭の青年がヤマメの大きさを手で示そうとした時、勢い余ってコップの水を倒した。私のズボンやジャケットに、水がかかった。
「わ! す、すみません!!」
髭の青年が慌てて立ち上がる。店長が厨房の奥に走る。私は手元のおしぼりでかかった水を拭いた。
「ごめんなさい、僕の不注意で……本当に申し訳ないです」
「だいじょうぶです、ただの水だし」
「いや、でも……」
「お客さん、こちらもお使いください」
「どうも」
店長から熱いおしぼりを受け取り、私はジャケットを押し叩く。うん、これなら全然問題ない。
「や、ほんとに問題ないんで、大丈夫ですよ」
「そしたら……せめて、餃子おごらせてください」
「へ?」
「店長、餃子もう一枚」
「はい」
私が目を丸くしていると、青年は人懐っこい笑顔になった。
「ここの餃子、ほんとにうまいんですよ」
「……そんじゃ、遠慮なく」
「もちろん」
青年は人懐っこい笑顔のまま、答えた。その笑顔に心ほぐされ、気が付いたら私達はお互いのことを語り合っていた。渋沢というその青年は、フリーランスのカメラマンで、今日は秩父の渓谷まで撮影に出向いていたらしい。
「秩父ねえ、いいですね」
「そう、だからね、こんなに大きなヤマメが……って」
ヤマメの話がループしていたのに気付いて、私達は笑い合った。
「でもね、普段は都内での仕事が中心ですよ」
「都内ではどんな撮影を?」
「結婚式の撮影です。新郎新婦の型物撮影や、ご家族写真とかですね」
「ブライダル業界ですか!」
私は思わず声が大きくなった。
「どうかしましたか」
「いや、実は私もブライダルやってるもんで、つい」
「そうでしたか!」
そう、私はウェディング・プランナーという肩書きで仕事をしている。土日は現場に出ることが多いが、普段はこれから式を迎えるおふたりの相談に乗りながら、結婚式から披露宴のプランの提案をしている。教育学部で音楽を専攻していて、学生時代から結婚式のオルガニストなどで現場に入ることが多かったもので、この仕事に対する憧れも膨らんだのだ。
実際やってみると、憧れだけではつとまらないことも多いが、それはどんな仕事でも同じことだ。なんだかんだで、式の後のおふたりの笑顔や、ご家族、ご友人の皆様の笑顔にエネルギーをもらいながら、今日まで続けてこられている。
ただ、こんな仕事をやっているもんだから、前の彼との恋愛はとりわけつらかった。結婚という人生の大きな節目を迎えるふたりを毎週末のように送り出しているのに、自分の人生ではそれを諦めざるをえなかった期間の疲れというのが、澱のように私の心に積もっていたことを、離れた今となっては明晰に自覚する。
「山奈さん? 山奈さん……?」
気が付くと、髭の青年、渋沢氏が心配そうに私の顔を覗き込んでいた。
「あは、ごめんなさい、ぼーっとしちゃって」
私は薄く笑って、ビールをひと口飲む。そして餃子に箸をのばす。
「それにしても、ほんと美味しいですね、ここの餃子。じつは初めてです」
「そうでしたか、それはよかった! ここのはキャベツの代わりに白菜使っているんですよ、それに大葉がきいててうまいんですよ」
この髭の青年は、本当に楽しそうに話すんだなあ、そんなことに感心しながら、私は彼に相槌を打っていた。意気投合した私達は、どちらからともなくLINEのIDを交換し、またの再会を約束した。店長は鍋の火加減を見ながら、横目で微笑んでいた。
(つづく)
*
つづきのお話
・第3話はこちら
・第4話はこちら
・第5話はこちら
・第6話はこちら
・第7話はこちら
・第8話はこちら
・第9話はこちら
・第10話はこちら
・第11話(最終話)はこちら
