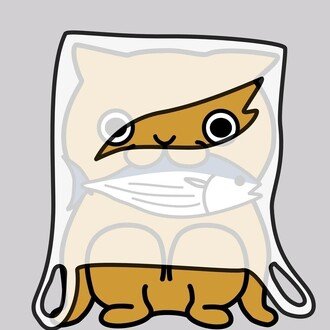(PR)AI時代の主導権を取り戻す思考法とは:答え方より問い方「安藤昭子」Audible版
なぜ「問い」が未来を変えるのか
今、私たちはAIが身近にある世界に生きています。
質問を投げかければ、瞬時に答えが返ってくる便利な時代です。しかし、そんな時代だからこそ、多くの人が抱える共通の悩みがあります。
それは、自分の頭で本質的な「問い」を生み出す力が弱まっているのではないかということです。
かつて幼い頃は、物事に疑問を抱き、
「なぜ?」
「どうして?」
と考えることが自然でした。しかし、成長するにつれて、その感覚は薄れがちです。日常生活や仕事の中で、効率を重視し、既存の答えに頼る場面が増えたからかもしれません。
特にAIが普及する今、アルゴリズムや定型化された思考に流されてしまい、自ら「問う力」を失っていると感じる人が増えています。
問いは、未来を切り拓く鍵です。例えば、ビジネスにおける課題発見力は、単に問題を解決する力以上に求められています。また、個人の成長や創造力を高めるためにも、「問い」を持つことが原動力となります。
本書では、その問いを生み出す具体的なプロセスが編集工学の観点から丁寧に解き明かされます。読者は自分の思考を深く掘り下げ、新たなアイデアや視点を見つけ出す手助けを得ることができるでしょう。
「問い」が生まれない理由とは
人が「問い」を失う背景には、社会や教育の影響があります。
学校教育では答えを求めることが重視され、正解を導き出す能力が評価されてきました。結果として、「問いを立てる」というスキルを学ぶ機会がほとんどないまま、多くの人が成長してしまいます。
さらに、仕事の場でも答えをすぐに求められる風潮が強まっています。
明確な目標や数字で成果を示す必要があるため、問いをじっくり考える余裕が奪われがちです。その結果、自分で考え抜く力が鈍り、疑問を抱くことさえ難しくなります。
本書では、「問い」が生まれない要因を丁寧に解説しながら、その障壁を取り除く方法を提案しています。
例えば、問いを生むには、まず思考の「土壌」を耕す必要があります。
これは、既存の固定観念や思い込みをほぐし、柔軟な発想を促すための第一歩です。そして、問いの「タネ」を集め、多角的な視点を取り入れることで、新しい問いを発芽させるプロセスを詳しく解説しています。
問いを生み出すプロセスの魅力
本書で提案される「問い」の生み出し方は、編集工学を基盤に構成されています。
この手法は単なるテクニックではなく、思考の深みを増すための哲学とも言えるものです。以下の4つのフェーズに分かれたプロセスが、その核心を成しています。
Loosening(問いの土壌をほぐす)
まず、思考を柔軟にするために、意識的に自分の先入観や固定観念を見直します。これは新しい視点を取り入れる準備段階です。Remixing(問いのタネを集める)
多様な情報やアイデアを組み合わせることで、問いの元となる材料を増やしていきます。情報の「編集力」が鍵になります。Emerging(問いを発芽させる)
集めたタネが次第に形を成し、具体的な問いへと発展していきます。この段階では、意識的な試行錯誤が必要です。Discovering(問いが結像する)
最後に、問いが具体化し、他者との共有や実践が可能な形に結実します。このフェーズは、新たな知見や価値を生む瞬間でもあります。
これらのフェーズを通じて、問いを生み出す力を養うことで、単に「答え」を求めるだけでは到達できない新たな発見や成長が得られるでしょう。
「問いの編集力: 思考の『はじまり』を探究する」書籍紹介
本書の概要
『問いの編集力: 思考の「はじまり」を探究する』は、編集工学に基づいて「問い」の発生を解明し、そのプロセスを具体的に解説した一冊です。
AI時代において自分の思考を深め、主体性を取り戻すための指南書とも言える内容が詰まっています。
著者の背景
著者は編集工学の専門家として活躍し、これまで多くの人々の思考を支援してきた実績があります。その豊富な経験を基に、「問い」を生み出す力を一人ひとりが引き出せるよう、独自の視点でアプローチしています。
目次から読み解く本書の魅力
本書は5つの章で構成されており、それぞれが問いを生む過程を体系的に解説しています。特に、柔軟な思考を養う第1章や、多様な視点を取り入れる第2章は、読者の固定観念を打破するためのヒントに満ちています。
AI時代に必要なスキルを養う
「問い」を生む力は、これからの時代を生き抜くための基盤です。
本書を手に取ることで、自分自身の思考を磨き、新たな視点や価値観を得られるでしょう。
【PR】オーディオブックを何冊でも聞き放題
★Amazonオーディブル
【PR】問いの編集力: 思考の「はじまり」を探究する
【マガジン】情報書籍
【マガジン】レベル60から稼ぐためのヒント
【stand.fm】NECO mimi TikTok BGMチャンネル
【Spotify】SATOSHI
いいなと思ったら応援しよう!