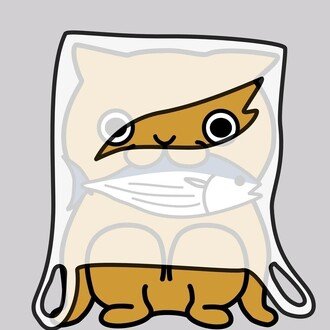【PR】問いの力で未来を切り開く方法:AIが答えを出す時代の考え方「安藤昭子」
「問い」が消えてしまった現代の背景
私たちの社会では、子どもの頃に自然に口にしていた
「なんで?」
「どうして?」
という問いかけが、大人になるにつれて減少していきます。
その背景には、学校教育や社会の枠組みが「正しい答え」を求めることに集中し、「問い」を探究する重要性を見過ごしてきた歴史があります。
さらに、AIやアルゴリズムが進化した現代では、私たちは簡単に「答え」を得られる環境にいますが、肝心の「問い」を自ら生み出す力が衰えてしまう危険性も抱えています。
こうした状況において、編集工学の観点から問いの発生プロセスを解き明かす本書は、「答え」に埋もれた現代人に新たな思考の道を提示します。
この本が示す「問い」を編集する力は、未知の可能性を探り、世界の見方を刷新するための強力なツールです。
「問い」の重要性を再認識する
多くの人が「課題解決力」を重視してきた中で、近年「課題発見力」や「問いを立てる力」の重要性が増しています。
たとえば、企業が求める人材像も、自発的に課題を見つけ出し、他者と協力しながら新しい価値を創出できる人物が重視されるようになっています。
本書は、「問い」を生成する過程を4つの段階に分けて考察しています。
このプロセスは、単なる知識の習得を超え、自分自身の思考や価値観を見つめ直す機会を与えてくれます。また、この力は日常生活においても活用できます。
仕事や家庭での問題解決、人間関係の改善、さらには人生の方向性を見直すときに、「問い」を生む力が役立つのです。
誰でも「問い」を生み出せる理由
「問いを生む力は、特別な才能が必要なのではないか?」と思う人もいるかもしれません。しかし、本書が強調するのは、「問い」はすべての人が持つ編集力を基盤にして生まれるということです。
第1章では、「私」という枠組みから解放されるための準備が語られています。たとえば、「私」と「世界」が接する境界を柔らかくする方法や、「間」を意識した思考法が紹介されています。
このような基盤を整えることで、私たちの中に眠る「問い」を呼び覚ますことが可能になります。
さらに、第2章では「問いのタネ」をどのように集めるかが具体的に解説されています。
異なる視点を持つこと、偶然の出会いを楽しむこと、そして多面的な情報の受け取り方を学ぶことが大切です。これらの方法を取り入れることで、問いを生み出す力を着実に養うことができます。
「問いの編集力 思考の「はじまり」を探究する」書籍紹介
本書『問いの編集力 思考の「はじまり」を探究する』は、編集工学の理論をもとに「問い」を生成するプロセスを4つの段階で明らかにしています。
落合陽一氏や佐渡島庸平氏が推薦しているように、この書籍は「問い」の重要性を改めて考えさせられる一冊です。
具体的には、
Loosening(問いの土壌をほぐす)
Remixing(問いのタネを集める)
Emerging(問いを発芽させる)
Discovering(問いが結像する)
の4つのフェーズを通じて、「問い」がどのように生まれ、成長し、世界を変える力を持つかが詳述されています。
著者は、「問い」を生むための具体的な方法だけでなく、思考の枠組みそのものを柔軟にし、未知なる世界に向き合う姿勢を養う術を教えてくれます。
この本を手に取れば、単なる知識の詰め込みを超え、あなた自身の思考を深めるきっかけとなるでしょう。
【PR】問いの編集力 思考の「はじまり」を探究する
******************
Kindle Unlimited(アマゾンアンリミテッド)
でサブスクに加入していただくと200万冊以上の書籍を
読み放題でご購読いただけます
※30日間の無料体験でお試しいただけます
******************
【マガジン】情報書籍
【マガジン】レベル60から稼ぐためのヒント
【㏚】無料体験!聴くだけ読書でタイパ・コスパ・カンタン
【Spotify】SATOSHI
いいなと思ったら応援しよう!