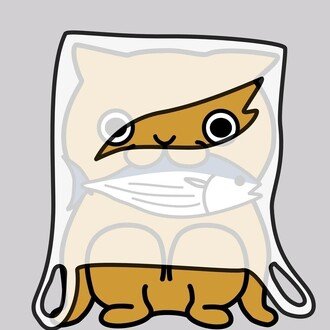【PR】働く理由、共にする人、続ける期間を見直す20の心得:人生は一度きり「有山徹」
仕事への違和感とモヤモヤ、その正体とは?
「日々の仕事に不満があるわけではないけれど、どこか満たされない」
そんな漠然とした違和感を抱えていませんか?
社会人として積み重ねてきたキャリアの中で、職場や仕事内容に慣れるにつれ、次第に自分が
「何を目指しているのか」
「本当に満足しているのか」
と自問する場面が増えている方も多いでしょう。
しかし、いざ考えてみても、「やりたいこと」がはっきりしなかったり、「強みを活かせる職場」を探しているのにピンとこなかったりと、結局はモヤモヤを抱えたままの日々が続いている方もいるかもしれません。
本書は、そんな現代のビジネスパーソンが抱える「働く目的」への疑問に対し、自己を見つめ直すための視点とヒントを提供します。
大切なのは「何を」やるかや「どこで」働くかではなく、「何のために」「誰と」「いつまで」働くのか。後悔しないためのキャリア選択を促す「プロティアン・キャリア理論」に基づき、著者はあなたにとっての正解を探る20の心得を提案してくれます。
職場での人間関係と幸福感の深い関係
職場での人間関係が、実はあなたの「仕事満足度」に大きな影響を及ぼしているのをご存じでしょうか?
一日の多くの時間を過ごす職場で、誰と一緒に働くかは、働く環境やモチベーションに直結します。
近年では、単に成果を追うだけでなく、信頼できる仲間と共に働き、互いを尊重し合う環境が求められています。
本書では、そんな「人間関係」についての洞察も深く掘り下げています。
本書の著者が提案するのは、自分がどんな人たちと働きたいのかを再確認することです。
それは単に職場で仲良くなること以上に、人生を豊かにするための大切なポイント。
約30万人ものビジネスパーソンや200以上の企業が注目するキャリア理論を基にした著者のアドバイスは、今の人間関係に違和感を感じている方に、どうすればより良い環境が築けるのか、考え直すヒントを与えてくれます。
定年まで働くことが本当に正解ですか?
働き方が多様化している今、必ずしも定年まで同じ会社で働き続けることが最適とは限りません。
むしろ「いつまで働くか」を自分で決めることで、キャリアと人生の質を高めることができるとも言われています。
今後の人生に向けた「働く時間」や「退職時期」について、具体的な目標やプランを立てることで、新たな道が開ける可能性があります。
本書では、「プロティアン・キャリア理論」を用いて「いつまで働くか」という視点からキャリアの見直しを提案しています。これにより、単に年齢や慣習に縛られず、自由に自分自身のキャリアをデザインする方法がわかります。
働き続ける期間や働くペースを自分で決められる時代において、自らの意思で選ぶキャリアは、あなたの人生をより充実させてくれるでしょう。
「なぜ働く?誰と働く?いつまで働く? 限られた人生で後悔ない仕事をするための20の心得」書籍紹介
著者は、日本国内外でキャリア支援や企業コンサルティングを行い、プロティアン・キャリア理論を広めてきた第一人者です。
この理論は、変化が激しい時代において、キャリアを「流動的」かつ「柔軟」に捉える考え方です。
著者は、30万人のビジネスパーソンや200社以上の企業に対して、この理論を基にしたキャリアアドバイスを提供してきた実績を持ち、特に「働きがい」を求める現代人に対し、明確な指針を示しています。
本書の中で提案されている20の心得は、働く意味を再考するきっかけとなるでしょう。
やりたいこと探しや強み探しで迷っている方に、具体的で実用的なアドバイスを提供しており、それぞれの心得が実生活に応用できるように構成されています。
自身のキャリアに対して主体的に取り組む意識を養い、どんな変化が訪れても柔軟に対応できる考え方が学べる一冊です。
この書籍を通じて、これからのキャリア選択に自信を持ち、後悔のない人生を築くための「あなた自身の正解」を見つけてください。
【PR】なぜ働く?誰と働く?いつまで働く? 限られた人生で後悔ない仕事をするための20の心得
******************
Kindle Unlimited(アマゾンアンリミテッド)
でサブスクに加入していただくと200万冊以上の書籍を
読み放題でご購読いただけます
※30日間の無料体験でお試しいただけます
******************
【マガジン】情報書籍
【マガジン】レベル60から稼ぐためのヒント
【㏚】無料体験!聴くだけ読書でタイパ・コスパ・カンタン
【Spotify】SATOSHI
いいなと思ったら応援しよう!