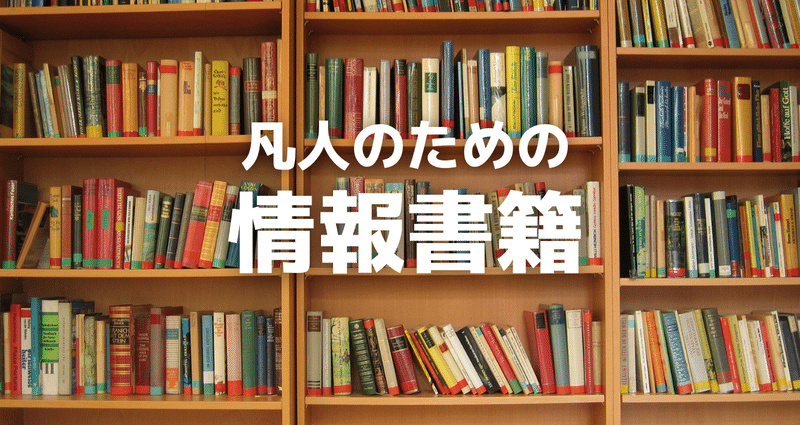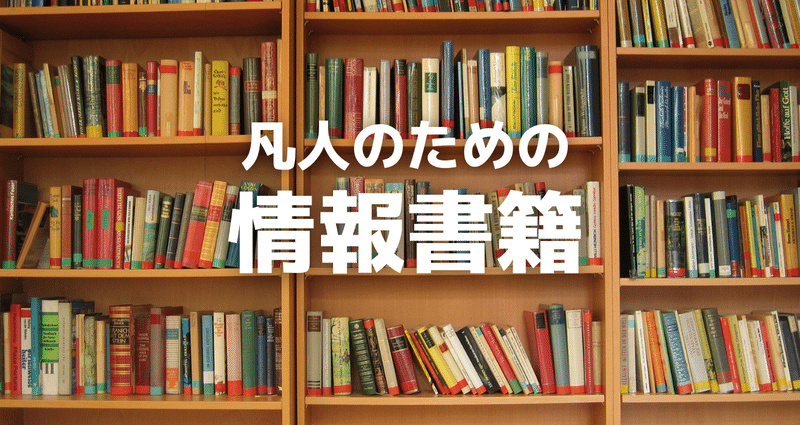【PR】言葉で心が軽くなる!悩み解消の新習慣:究極の悩み解消法「樺沢紫苑」Audible版
自分の悩みが解消できない理由とは?悩みが消えない理由の一つに、「解決方法がわからない」ことがあります。
例えば、仕事でのストレスや人間関係の悩み、未来に対する不安など。悩んでいるとき、私たちはどうしてもその問題を複雑に考えてしまい、つい深みにはまっていくものです。
しかし、問題の根本的な解決には、まず「自分の思考を整理すること」が不可欠だと、精神科医の著者は提案します。
自己認識を深めるための第一歩は、「言葉にすること」です。
多くの人は悩みを内面的に抱え込み、心の中でぐ