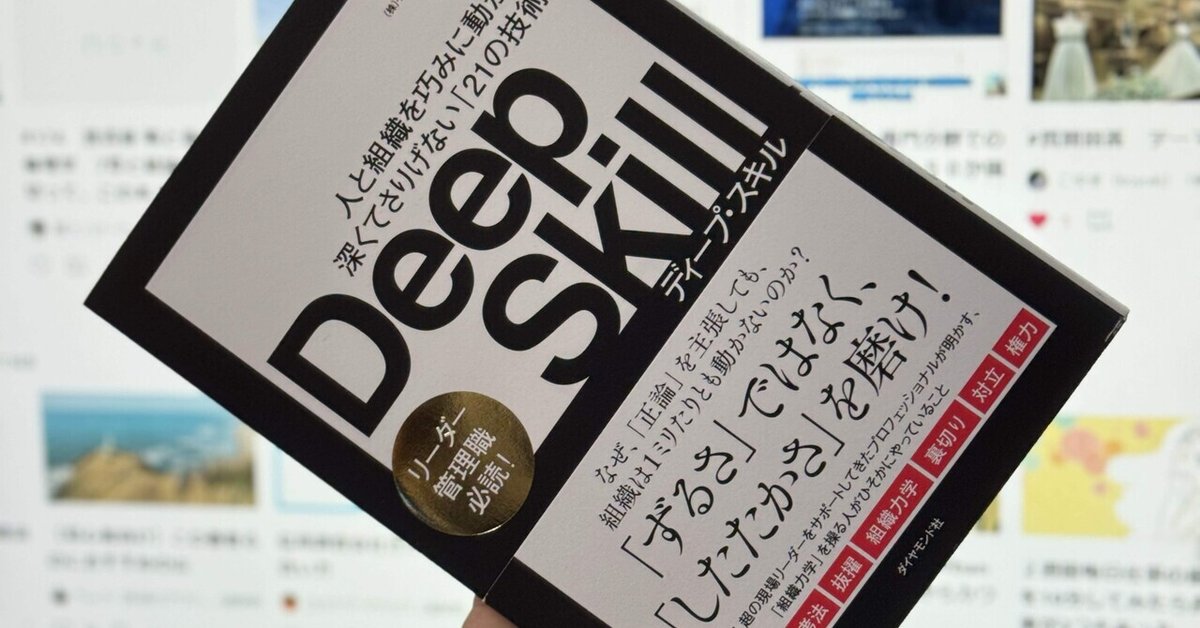
#175 読書録 DeepSkillを読んで、生き抜くためには、したたかさだよねってうなずいた話
こんにちは!けーたです。
本日は「DeepSkill」を読みましたので、読書メモを投稿したいと思います。
この本との出会いは、自分が利用させてもらっている「Tomogaku」というサービスから読書会のお誘いが届いたからです。
「Tomogaku」ってなに?って思った方はリンクを覗いてみてください。自分が感じているこのサービスの嬉しさは2つ。
1、読書会の日程が設定されるので、それまでに読み切るという半自動的なゴール設定でお尻に火が付く読書体験ができる
2、読書会で初めまして!という人と出会い、同じ本を読んだという共通点から、スムーズに新たな読書仲間が増えること
本の中身とは少し話がそれましたが、ここからは「DeepSkill」の中身や気づきに触れていきます。
この本を読み終わった読後感
どこから読んでも、組織というモノに所属をしている人にとっては、新しい視点や組織構造のとらえ方ができるようになる具体例が本当にたくさん載っているので、学びが深いです。
そして、読みやすい。たぶん、「スキルセット」ごとにカテゴライズされている事で読み始める前に、読者に内容を受け取る前準備を促している事。
そして、具体例が今まで見た事ない切り口なのに、あるあるだから。と自分は読みやすさの要因を分析してみました。
この本のイメージとしては、影響力の武器をより身近なビジネスの日常に引き寄せつつ、なぜ、組織に所属する人はそのような動きをしてしまうのか?
組織における原理原則が示されており、どう自分の想いを実現させるかにフォーカスされている感じです。
どんな人におススメ?
組織の壁などを超えて、新しい何かを実行しようと思った時に、壁を感じた事がある人は、是非読まれることをおススメします。
すぐに明日から仕事場で使える、組織の中でしたたかに立ち振る舞う為の行動のヒントをたくさん学ぶことができます。
完全フラットな組織以外の企業に属している方で、まだこの本を読まれていない方がいらしたら、激オススメです。
刻みこみたい、フレーズ達
すぐに9回裏2アウトだと思うからおかしくなる
このフレーズのあとに、「まだ4回の表ぐらいだから慌てるな!」が続きます。例えが本当にわかりやすいです!!なおかつ、人に話をしたくなります
話をしたくなる。と書くと未来系の様に感じますが、実際はこのフレーズを読後にすぐに会社のメンバーにこのフレーズ&考え方をシェアしています。
未来の話ではなく、過去の実績ですね笑
ついつい組織に属していると、決済などを取る際に、考えられる最大のリスクなどを想定し、モノゴトを悲観的に見る思考の癖がついている事に、気づかされました。
ビジネス上のトラブル解決不能なものはそうそうあり得る事ではない、だからことさら「深刻になる必要はない」こうも書かれています。
この二つのフレーズから、ココロの在り様は自分でコントロールするモノ、と学びましたので、さっそく明日から日常に取り入れてきます。
機嫌の良さという「ディープスキル」
なぜ、これを頭に刻みこみたいと思ったか?
それは、基本的に自分は機嫌が悪いことがないからです。逆に悪くはないけど、良い状態に保ち、積極的に話しかけやすい状況をつくるまでには、ココロをいたせていないという反省からです。
機嫌が悪いは話にならない。機嫌が悪くないでも普通。機嫌がいつも良いこれが重要と気づかされました。
特に、自分のやりたいことに時間を使い、夜更かしをして次の日眠気を我慢している顔は周りに不機嫌に映っている可能性が高いので気を付けます。
誰かと話すことが、最高の「考える技術」である
自分の考えを生煮えの状態で人と話をすることにより、壁打ち効果で思考が整っていく。
この経験を自分もしており、積極的に活用しています。ただし、この本では、誰かと話すことのメリットがもっとあると書かれておりなるほど!と
気づかされました。
1、社内のさまざまな人たちと壁打ちをすれば、社内に神経回路を張り巡らせることと同義
2、壁打ちが根回しと同様の意味をもち、いざ起案などをするときに一緒に考えたか仲間として味方につけられる
3、一人で考えるプライドを捨てることができる
ここまで、壁打ちの意味というか組織で行うメリットを考えた事がありませんでした。もう、これを知ったからには生煮えの壁打ちを使わない手はないですね。
まとめ
今回は、代表的な自分の学びのフレーズと理由について、頭に刻みこむ為に書いていますが、まったくもって書ききれませんでした。
それぐらい、日常のビジネスに起きる課題に対して、したたかに振る舞い周りを動かす。そんなヒントが沢山あります。
どの章も読みやすく、最近読んだビジネス書のなかではタイパが最高ランクではないかと思いました。
1600円とコスパも良しです。本当にそう思います。この本の回し者ではありません笑
ということで、自分の読書メモが誰か選書の参考になると幸いです。
ではでは
いいなと思ったら応援しよう!

