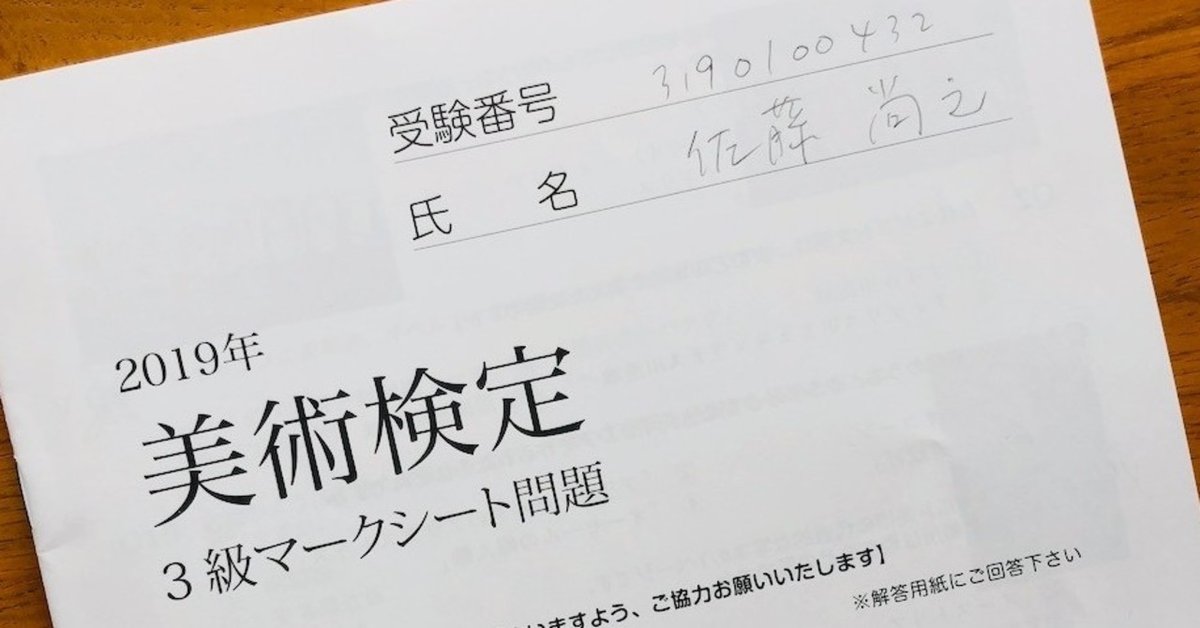
1000日チャレンジ 〜『美術検定3級』になんとか合格したっぽいので、偉そうに傾向と対策を書いてみる
先週の日曜(11/10)に受けた美術検定3級テストであるが、昨日、解答が美術検定サイトで発表になり、自己採点してみたところ、なんとか合格していたっぽいので、とりあえずご報告します。
90問中18問間違えたので、正答率80%。
サイトによると「合格の目安は、正答率約60%です(受験者全体の解答率によって左右します)」とのことなので、マークシートへの記入間違いがなければ、たぶん合格!
まだ始めてたった4ヶ月弱とはいえ、毎朝コツコツ勉強してきたので、ちょっとうれしいな(嬉)。
前日に受けた4級はまぁまぁ楽勝だった。
でも、3級はかなり手強く感じた。
だから、受験後、このnoteでこう書いた。
4級は楽勝だった。
公式問題集をきっちりやっとけば絶対受かる内容だった。
だから3級もそうだと思い、3級公式問題集は4周くらいやったし、公式テキストもわりとちゃんと読んで、いろいろ暗記して行ったんだけどなぁ。
・・・いや、まいった。
えらく難しかったw
まぁまぁ勉強していったつもりだったので、もうちょい出来るかと思っていたんだよね・・・高得点どころか、受かるか受からないかギリギリだと思う。わりとショックである。
問題集をさらっとやっただけでは答えられない問題がいくつも出た。
うーん、出直しか・・・。
まぁ受かっている可能性もあるんだけど、どうだろうなぁ・・・。
まぁ前日に受けた4級が、50問中で1問間違えただけだったので、急に自信をもったわけですw
で、3級の受験後、自信がない問題が20問以上あったので、つまり「前日の20倍以上間違えている実感」があったので、こりゃダメだ・・・と、悲観したわけ。
でも、自己採点で18問の間違いで済み、正答率的にはそれで充分だった、ということですね。
あ〜良かった。ホッ。
さて。
正式な合格発表は12月になるらしいのでまだわからないけど、でも「たぶん受かっているのではないか」ということを前提に、来年3級を受ける人のために「傾向と対策」を書いてみたいと思います。
いったいどのくらい勉強しておけばいいのか、ということですね。
ボクの主観ですけど。
サイトによると、各級の出題範囲はこういう感じ。
なお、4級はCBTテストで一年中受けられるし、たとえば3級・2級の併願も可能だ。
4級-西洋美術・日本美術の名作を知る
西洋美術・日本美術史の中から、代表的な作品や作家などについて問われる。
3級-西洋美術・日本美術の基礎的な歴史的な流れを理解する
西洋美術・日本美術史に登場する作品や作家だけでなく、美術の動向や形式、時代背景など、歴史的な流れについても問われる。
2級-幅広い美術に関する知識や情報、美術鑑賞の場の社会的役割や歴史などを理解する
西洋美術・日本美術史の基本的な知識や情報を始め、建築工芸や技法、写真映像、現代美術、美術館など幅広い美術史の知識と、美術鑑賞の場の役割や機能、現状に関する実践的な知識が、それぞれマークシート問題で問われる。
1級-美術や美術鑑賞の現場に関する知識、情報を基に自分で解釈・思考し、明確に伝達できる
美術鑑賞の場の役割や機能、現状に関する知識をはじめ、鑑賞をする視点からの作品描写や、より楽しい鑑賞のためのアイデアなど、実践的な現場で求められる能力が記述式問題で問われる。
つまり、3級は美術史だ。
公式テキストはこれ。
ただ、この公式テキスト、1級も2級も対象なので、3級を狙う人にとってはちょっと難しい。
そこで役に立つのが3級問題集。
これをやると、3級がどのくらいなレベルかがわかる。
これ、大事。
どのくらいなラインを目指せばいいかがわかると、ずいぶん気持ちが楽になる。
それと、もし4級を受けてない人がいたら、4級のテキストと問題集もやっておく必要が(絶対に)ある。
※4級合格をもっていなくても3級は受けられるけど。
ん?
かったるいから4級を受けるのは飛ばしたい?
その場合は、(アート初心者であれば)たぶん、上の4級テキスト『この絵、誰の絵?』をざっと答えられるようになるのに2週間。
そして、4級問題集をざっと出来るようになるのに2週間。
つまり1ヶ月くらいは4級の問題をやり、それから3級にステップアップするのがいいと思う。
いずれにしても4級でやる「西洋と日本の名画を知る」のは必要だ。
あと、副読本的にいいのは、山田五郎さんが出している「知識ゼロからの」シリーズ。
このシリーズは素晴らしいなぁ。
これを読んでそこそこ覚えるとずいぶん理解が進みます。
この3冊、マジでオススメ。
ものすごくわかりやすいし、アタマにも入りやすい。前後の文脈もよくわかるし、絵画の変遷の必然性もよくわかる。
で、この辺を本を読んで理解しだすと、一気に美術脳になるので、そのあたりから3級問題集をやるのがいいと思う。
上記「公式テキスト」が難しいので、ボクは3級問題集をくり返しやる方法を選んだ。
毎朝、数問ずつやり、試験直前に一気に4周やった。
ただ、4級は4級問題集をくり返しやれば絶対に受かると思うけど、3級はそうはいかない、という印象。3級問題集をやり込む(極端に言ったら暗記する)だけだと、たぶん3割くらいしか正答できないと思う。
なので、問題の解説を読み込んで、その部分を「公式テキスト」でより深く読む、という方法でやる必要があるかと思う。
それで、なんとか80%くらい答えられるようになるのではないか、と。
それでも20%間違えたからなぁ・・・間違えたというか、知識として知らないのもあった。
「うへー、公式テキストをよくよく読むと書いてあるような、こんな細かい問題もでたー」って後で思ったから、まぁそういうのは捨てるとしても、それなりに公式テキストは読んだ方がいいかな、って思う。
ちなみに、西洋史を、公式テキストと問題集と山田五郎の3冊で理解したあとにこの本を読むと、ものすごくアタマが整理されるのでオススメ。
そして、絵の見方として、これ(↓)も本当に役に立った。
この本を読まなかったら、名画が名画たる理由に気づかず、美術検定が単なる「暗記系のお勉強」になってしまっていたかもしれない。
ま、テストに合格するために勉強しているわけではなく、「アートをよりよく知って人生を豊かにするために」勉強しているので、上記の本はすべてなにかしら役に立つし、知ってることが増えるのは本当に楽しいこと。
だから、美術を楽しむのが前提ですけどね。
それと、勉強するとほんと「アートを見る目」が変わり、「世界を見る目」も変わります。
3級受験程度でそう思うから、きっと1級とかなると「世界が変わって超楽しい!」ってなるのだと思う。
知識って大事だわ。
「別に勉強なんかしなくても、感性でアートを楽しめりゃいいじゃん」って言う人の気持ちもわかるんだけど、でも、知識があるとアートの見方が変わるので、ある程度集中して知識をつけるのは重要だな、って、勉強し始めてみて思う。
いままで見えなかったことが、どんどん見えるようになってきた(その途上がまた楽しい)。
なんか、そういうビフォーアフターを味わうために、3級終わるまでは美術館行きを封印していたのだけど、復活させようと思う。
勉強し始めた自分が美術館をどう味わうか、いままでとどう違うか、とても楽しみだ。
ということで、今日からは1年後の「美術検定2級テスト」を目指します。
※
ちなみに、3級テストは、出題数は90問。
配点は、Q1〜Q85=1点、Q86〜Q90=3点。
Q86〜Q90はいわゆる「活用問題」と言って、知識を試す四択とは違い、文章題で思考能力を試してきます。
とはいえ、わりと常識的な思考問題なので、大学受験で現国が得意だった人は類推で解けると思う。そうでない人も、3級問題集をちゃんとやっていれば、たぶん消去法で解ける。
※※
これまでの美術検定試験合格率は以下の通り。
2018年度実績
4級 - 96.5%
3級 - 78.0%
2級 - 41.9%
1級 - 15.1%
2級はなかなか難関だな。がんばろう。
いいなと思ったら応援しよう!

