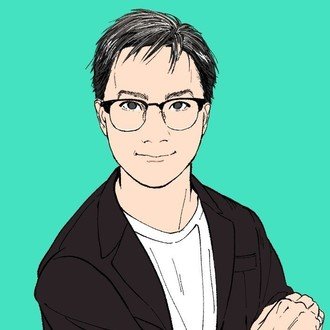【Vol.672】「部下のわからないこと」に答える環境を整える!
【本のタイトル】
GAFA部長が教える自分の強みを引き出す4分割ノート
【著者】
寺澤伸洋
【インプット(引用文章)】
僕は、後輩との間で「わからないことがあったら、いつ聞いてもいいし、何回聞いてもいい。逆にわからない状態で先に進もうとしないこと」というルールを作って、質問しやすい環境の構築に努めています。
自分が何をすれば良いのかわからない場合は、きちんと理解するまでしつこいくらいに質問する方が、最終的にみんなが幸せになれます。上司や先輩もそれをわかっていれば、質問したぐらいで怒ることなどないはずです。ですから「怒られるのではないか」という不安で萎縮する必要はありません。逆に、質問をしないでわからないまま仕事を進めようと、それこそ本当に怒られるでしょう。
また、話を聞いて全てを理解できなかった場合、重要になるのが質問の仕方です。
もし「わかった」、「わからない」という0か100かで返してしまうと、相手は「もう一度、1から話さなくてはいけないのか?」と困惑することになります。ですから、2回目以降の質問は「ここまではわかった」、「ここからがわからない」という境目をはっきりさせることが重要です。
この境目をはっきりさせようとすると、教える側がまず内容を項目別に分けておく必要があります。プロセス型の図を使い、まずは大きなプロセスの全体像を見せた上で、各プロセスついて話をしていくと、教えてもらう側がわからないときに、どこがわからないのかを明確に指摘できます。
教える側も、教わる側も「今全体の中のどこの部分の話をしているのか」を意識・理解しながら話すことで、より理解を深められるはずです。
こんなことを書きながらも、僕も20代の頃、当時新入社員だった後輩に「同じことは3回聞くなよ」と偉そうに言っていたことがありました。
当時の僕は「自分の説明は完璧で、わからないのは相手が悪い」、「何回も教えるなんて、後輩を甘やかしてはいけない」と本気で思い込んでいました。
説明が伝わらないのは、往往にして情報の受け手の問題ではなく、情報の伝え方が悪いことがほとんど。それなのに、自分のことを棚に上げて「何回も聞くな」だなんて、何を勘違いしていたんだという話です。このような指導する側の勘違いは僕の話にとどまらず、多くの会社で起きている光景です。
本当に目指すべきチームのゴールは、後輩に早く仕事を理解してもらい、力を合わせて売り上げを増やしたり、プロジェクトを完遂したりすることです。その本質をとらえず、後輩に過剰に厳しくすることで「時間がかかっても後輩が自ら成長するのを期待する」、「ついてこれなかった場合は彼らの努力不足として叱責する」という手法をとるのは、全くゴールに近づかないアクションであり、時代遅れも甚だしいと言えます。
僕の社会人人生を振り返ってみても、怒ったり、叱責することでうまくいったことは、ただの一度もありません。このやり方は絶対に間違っていると言えますし、もし部下や後輩にそうした接し方をしているのであれば、今すぐに見直すべきです。
「自分が何度も同じことを聞いている」というのは、教えてもらう側が一番よくわかっています。それでも、仕事をきちんと遂行するために勇気を振り絞って上司や先輩に聞いてきているのです。ですから彼らのその勇気をきちんと理解してあげた上で、怒る代わりに、わかるまでしっかりと教えてあげてください。
【アウトプット(具体的アクションプラン)】
組織力を向上させるために、「部下のわからないこと」に答える環境を整える!
いいなと思ったら応援しよう!