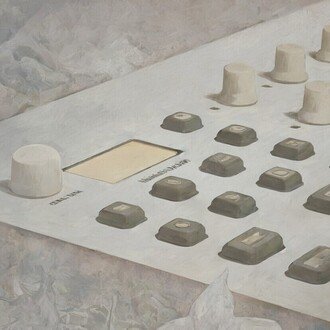映画風なDeep Houseを制作したよ ▶︎ Model:Cycles
前作アンビエントなDeep Houseに続き、Elektron Model:Cycles(以下、m:c表記)を使って
シネマティックなDeep Houseを制作
しました。
BPM129のそこまで速くないテンポで、
シンセ・ストリングスを重ね、
ときおり効果音をいれつつ、
前半は緩やかなビートで、
中盤以降は激しさを増して
盛り上がるセクションに、
最後は余韻を感じるエンディングまで
全体的にドラマチックに展開
させました。
アイデアがたくさん浮かんだので、試行錯誤しながらできるだけ多く盛り込みました。
ライブレコーディングでは、
何度も録ってはやり直しを繰り返し、
途中で行き詰まりそうになることもありました
が、ようやく納得のいくテイクを録音することができました。
Elektron Model:CyclesでCinematic Deep Houseを制作📽️動画は中盤後ですがシンセストリングスを重ねた冒頭から時折SEを入れつつ映像的でドラマチックになるように展開させました🙂👍チェーン機能を思い出したのは時すでに遅し。。。改めてm:cのシーケンサーはアイデアを反映させやすいなあとしみじみ https://t.co/AwlQVu6Vtk pic.twitter.com/ziRC7UufPA
— NicaFelt (@NicaFelt) September 26, 2024
ぜひ聴いてみてください。
今回の楽曲では、たくさんの要素を取り入れているので、すべてを詳しく解説するのは難しいかもしれません。ですが、
応用できるポイントを絞って
別途Tips記事を書く予定です。
今日は楽曲の制作過程に焦点を当てた内容です。
【 コンセプト】
Deep Houseの心地よさをベースに、
映画のような場面展開を取り入れた楽曲
を作ろうと思いました。
曲の中で、静かな部分と盛り上がる部分のコントラストをつけて、全体をダイナミックでドラマチックな印象にしています。
具体的には、以下の要素を取り入れました。
・シンセストリングスを重ねて、感情が揺れ動くような叙情感をつくる
・SE(効果音)を加えて、ミックスに立体感をもたせ、映画風な雰囲気を演出する
・ストリングスの叙情感にあわせてビートを作り、グルーヴを生み出す
・中盤までは抑えの効いたリズムトラックをベースにし、後半は盛大に盛り上げる構成
・リフに少しずつ変化を加え、飽きさせない工夫をする

【 制作する上でのポイント 】
映画的な雰囲気を出すために、撮影時の照明や動画編集時のカラーグレーディングにもこだわりました。
一方で、音楽的には
ダイナミックな展開
をめざし、m:cのパラメーターロックなどの機能を活用しながら、細かくパターンを作り込みました。
パターンをいくつも作り、それぞれが自然につながるよう試行錯誤しましたが、
m:cだけでは効率が悪く、
思うようにいかない
こともありました。しかし、いろいろ試した結果、良い方法を見つけました。
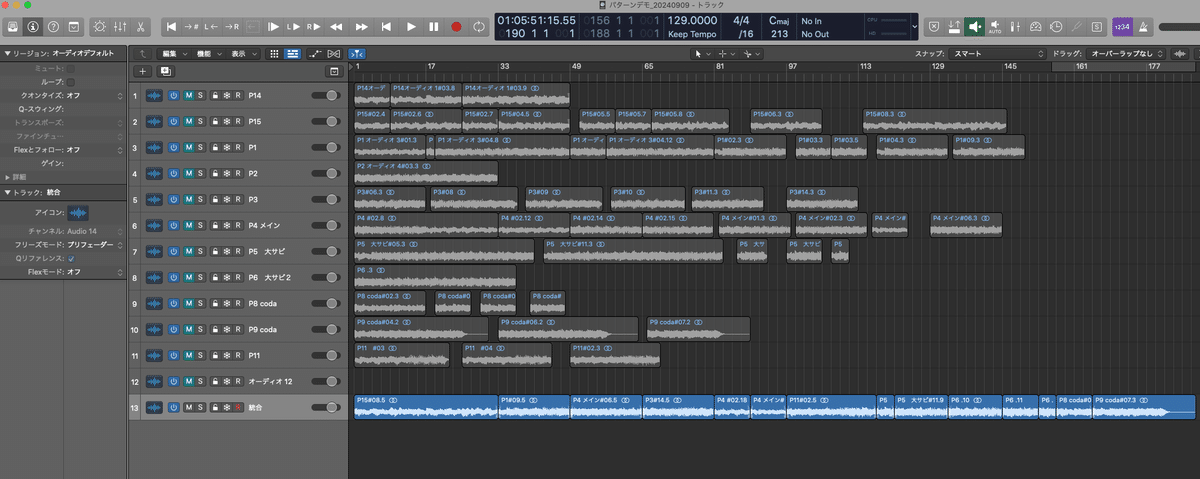
【 DAWを使って全体の流れを俯瞰する 】
邪道かもしれませんが(笑)、すべてのパターン(つまみを動かして作るフィルイン含む)をLogicに録音し、イメージ通りの展開になるようにパターンを並べ替えました。(上画像)
並べ替えの途中で「ここにこんな効果音が欲しい」や「別のパターンを追加したい」と思ったときは、m:cに戻って新たにパターンを作り、それをまたLogicに録音する、という流れを繰り返しました。
この方法の最大のメリットは
楽曲全体の流れを俯瞰して見ることができる
点です。
m:cだけでは、
パターンのつながりを
俯瞰するのが難しく、
また、短い小節の範囲内で繰り返し確認するのも効率的ではありません。
これまでm:cで制作した曲は、パターンの数がそれほど多くなかったのですが、今回はパターンを多く作り込み、展開を多くしたかったため、m:cだけでは頭の中のイメージを形にするのが難しいと感じました。
そこで、基本的にはm:cで作りつつ、
楽曲の構成を
整理する段階でのみ
DAWを使うことにしました。
DAWがあるからこそ、今の時代に可能な曲作りの方法です。もしm:cや他のグルーヴボックスで複雑な展開を作りたいときは、
楽曲のクオリティを
ぐっと上げることができる
ので、この方法をおすすめします。
「シネマティックなDeep Houseの作り方のコツ」については、また改めて書こうと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
いいなと思ったら応援しよう!