
あなたは何問わかる? 葬儀豆知識クイズ
こんにちは、燦ホールディングスnote編集部の祖父江です。
去る2024/11/5(火・友引)に、厚生労働省認定「葬祭ディレクター技能審査」試験が行われました。受験された皆様におきましては、ぜひ良い結果が届きますことを、私共もお祈り申し上げます。
さて、葬祭ディレクター技能審査試験において、いわゆる”教科書”となるものが、こちらの「葬儀概論」という書籍です。
本書籍の内容は、葬儀に携わる人間が身につけておくべき"実務知識"はもちろん、葬儀の意味を知ることからはじまり、葬儀の歴史や、主な宗教の概要および宗教儀礼、葬儀にまつわる関連法令…など、葬儀業を営むにあたっての必要な知識が詰まった手引書ともいえる内容です。
(当社でも「知識に困ったときは、まず葬儀概論を引くように」と教えられています)
今回は、この葬儀概論に書かれている内容を参考に、葬儀の世界と縁遠い方々にも楽しめるような「葬儀の豆知識」クイズを、私の方で10問考えてみました。
さて、皆さんは何問正解できるでしょうか? ぜひ挑戦してみて下さい。
(※出題の後に、少し空白行を置いてから正解を記しますので、ゆっくりと縦スクロールをしながら挑戦してみて下さい。)
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
早速問題をスタート!
【Q1】この幕の名前は、何と呼ばれているでしょう?
(難易度★☆☆)
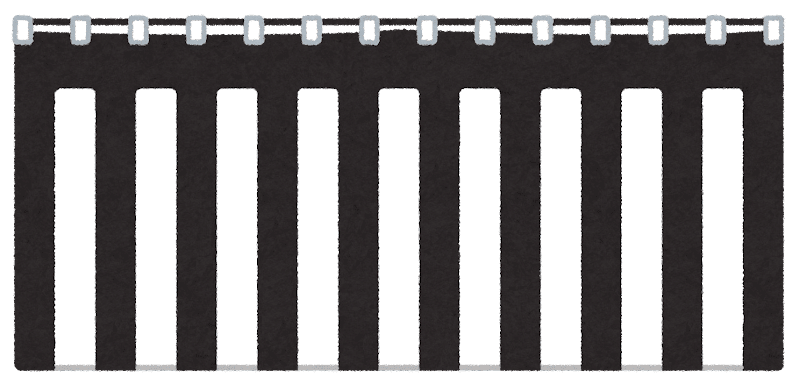
鯨幕(くじらまく)
鮪幕(まぐろまく)
鮃幕(ひらめまく)
※回答が決まったら、ゆっくりと下にスクロールしてください。
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
【A1】鯨幕(くじらまく)
黒と白の縞模様から連想される動物として、くじらの名が付けられたようです。なぜ"シマウマ幕"ではないのでしょうかね?
(※碑文谷創『葬儀概論・増補三訂(表現文化社)』 P127 より)
【Q2】墓地、埋葬等に関する法律において、一部の例外を除き、死亡後に「一定の期間」が経過しないと、埋葬や火葬を行ってはいけないよう定められています。その「一定の期間」とは、どのくらいでしょうか?
(難易度★☆☆)
12時間
24時間
48時間
※回答が決まったら、ゆっくりと下にスクロールしてください。
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
【A2】24時間
この内容は「墓地、埋葬等に関する法律」第3条に定められています。
ただし「妊娠7ヶ月に満たない死産」や「感染症による死亡」の場合は24時間以内でも火葬・埋葬することが許可されています。
(※碑文谷創『葬儀概論・増補三訂(表現文化社)』 P101 より)
24時間の間隔を設けるのは「蘇生の可能性がある」という理由のようですが、この法律が制定されたのは70年以上も前のことであり、現在の医学から考えると、もしかしたら少々時代遅れなのかもしれませんね。
【Q3】:葬儀後や法要後の会食の席で、代表者(喪主)が杯を捧げるときに発する掛け声は、何というでしょう?
(難易度★☆☆)
かんぱい
きんぱい
けんぱい
※回答が決まったら、ゆっくりと下にスクロールしてください。
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
【A3】けんぱい(献杯)
なお「乾杯」と違う点として…
献杯の唱和は、落ち着いた発声で行う。
互いのグラスは、打ち合わせない。
献杯の発声の後に、拍手は行わない。
などのマナーがあります。
【Q4】以下に挙げる宗派の中で、通常「3回」の焼香を行うのは、どれでしょうか?
(難易度★★☆)
臨済宗
真言宗
曹洞宗
※回答が決まったら、ゆっくりと下にスクロールしてください。
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
【A4】真言宗
ちなみに、臨済宗は通常「1回」、曹洞宗は通常「2回」となります。
(※碑文谷創『葬儀概論・増補三訂(表現文化社)』 P167 より)
なお、参列者が多く焼香時間が長引く可能性がある場合には「お心込めた一回でお願いします」とアナウンスするなど、状況に応じて上記とは異なるご案内をする場合もございます。
【Q5】日本において、火葬が禁じられていた時期がある?
(難易度★★☆)
はい
いいえ
※回答が決まったら、ゆっくりと下にスクロールしてください。
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
【A5】はい
明治政府は、1873(明治6)年に火葬禁止の布告を出したのですが、2年後の1875(明治8)年には、早くも撤回されてしまいました。
この時代の政府は、神道の国教化を目指しており、神仏分離政策の一環として定められたようなのですが、土地不足や衛生面の課題もあり、現実的ではないとして早々になくなってしまったようです。
(※碑文谷創『葬儀概論・増補三訂(表現文化社)』 P58 より)
【Q6】全国の葬祭会館の数は、次のどの数に一番近いでしょうか?
(難易度★★☆)
全国の「中学校」の数
全国の「喫茶店」の数
全国の「EV充電スポット」の数
※回答が決まったら、ゆっくりと下にスクロールしてください。
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
【A6】全国の「中学校」の数
総合ユニコム社が発刊する「全国葬祭会館データリスト総覧」によると、2022年現在の葬祭会館の数は、10,389か所とのことでした。
ちなみに、
全国の中学校の数は、およそ9,900(日本私学教育研究所のデータより)
全国の喫茶店の数は、およそ58,000(日本コーヒー協会のデータより)
全国のEV充電スポットの数は、およそ21,200(次世代自動車振興センターのデータより)
とのことです。
(※本記事執筆時点での数値です)
【Q7】葬儀の会葬者(参列者)の人数が一番多かった時期は”バブル期”とのことでした。さて、その時期の会葬者の平均人数は、どのくらいだったでしょうか?
(難易度★★☆)
70人
140人
210人
280人
※回答が決まったら、ゆっくりと下にスクロールしてください。
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
【A7】280人
この結果を見ると、葬儀の規模というのは世相や経済を色濃く反映するものですね。
(※碑文谷創『葬儀概論・増補三訂(表現文化社)』 P19,33 より)
【Q8】「告別式」という儀式が初めて行われたのは、1901(明治34)年。ある思想家の葬儀であるといわれています。その人物とは誰でしょう?
(難易度★★★)
内村鑑三
中江兆民
新渡戸稲造
※回答が決まったら、ゆっくりと下にスクロールしてください。
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
【A8】中江兆民
ときは明治時代。お葬式を行う際、会葬者が故人のところに集まり、葬列を組んで、皆でお寺まで向かうという風習がありました。明治中期に差し掛かると、この葬列がだんだんと”豪勢”かつ”多人数”となる傾向がみられ、喪家側の懐を圧迫するという問題が顕在化していきました。
また都市部では、葬列が公共交通の妨げになることが問題視され、そのアンチテーゼとして、葬列の代わりに「告別式」という儀式を中江兆民がはじめて行ったことから、一般の世に広まっていった…と言われています。
(※碑文谷創『葬儀概論・増補三訂(表現文化社)』P63 より)
【Q9】建物内に火葬炉が設けられた「近代的な火葬場」がはじめてできたのは、1878(明治11)年である、とのことでした。さて、どの都道府県に建てられたのでしょうか?
(難易度★★★)
東京都
京都府
奈良県
長崎県
※回答が決まったら、ゆっくりと下にスクロールしてください。
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
【A9】京都府
明治11年に西本願寺・東本願寺が建設した「両本願寺火葬場」が、近代的な火葬場のはじまりと言われています。
こちらの火葬場は、昭和初期に京都市に受け継がれ、その後の撤去や改築を経て「京都市中央斎場」として現在も運営されつづけています。
(※碑文谷創『葬儀概論・増補三訂(表現文化社)』P60 より)
【Q10】国内の火葬場は公営が圧倒的に多いですが、東京都や神奈川県など、一部の都道府県では民営の火葬場も存在します。次の中で、民営の火葬場が存在する県はどこでしょうか?
(難易度★★★)
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
※回答が決まったら、ゆっくりと下にスクロールしてください。
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
【A10】愛媛県
愛媛県松山市の「光輪閣北山」が、四国唯一の民営火葬場です。
(※厚生労働省:全国火葬場データベース調べ)
最後に…
お疲れ様でした。あなたはどれくらい正解できたでしょうか?
特に、難易度★★★の問題は、択一式でないと、正解できる方は相当絞られるのではないか?と思います。
今回の記事をきっかけに、葬儀の世界に少しでも興味を持っていただけたのであれば幸いです。
