
英語学習にOttercastをオススメする3つの理由
こんにちは、Choimirai School のサンミンです。
【主要なアップデート】
(2020.11.21)ポットキャストをOtter.ai にインポートする方法を追加
0 はじめに
ポットキャストは、2004年に「iPod」と「Broadcast」をあわせて作られた造語。技術の発展で情報発信・消費の手段が変わった良い例です。
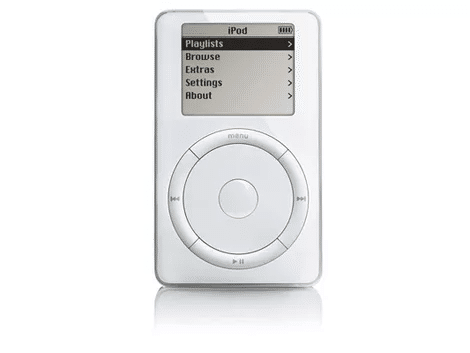
ポットキャストを発信する方法は年々進化していますが、ポットキャストを聴く方法はアプリの数が増えるだけでそれほど変わってないのが事実。
しかし、2020年、ポットキャストを聴く側にも大きな革命の到来です。
Ottercastを始めませんか?
Ottercast = ポットキャストをOtter.aiで「文字起こし+読む+聴く」こと
英語学習者には特に Ottercast* をぜひ試して欲しい。効果を最大限に引き出すための進め方は、
— Sangmin @ChoimiraiSchool (@gijigae) August 12, 2020
①興味のあるポットキャストを準備
②Otterで文字起こし
③話者ごとにボイスラベルをつける
④聞きながらテキストを修正
⑤もう一度聞く
※ Ottercast : ポットキャストを @otter_ai で聞く・読むこと https://t.co/XNTHCXsaVE
今回の note では英語学習で Ottercast を勧める理由を3つシェアします。
①能動的に聴く習慣が身につく
②感動を受けた箇所だけを集められる
③検索しやすい
【追記:2020.11.21】ポットキャストをOtter.aiに追加する方法は下記のnoteを参考にしてください。
1 能動的に聴く習慣が身につく
英語のリスニングになりますと聞き流すような聞き方をされている人も多い。英語の読みと一緒で、リスニングもご興味のある素材を今のレベルにあわせて聴くことが肝要。
Ottercastの note を書いている。Ottercastを勧めるのは学習者を「能動的にさせる」から。ポットキャストだとボーッとして聞いてる人も多い。ところが、Ottercast は話を聞きながらテキストを修正するので聞き取れてないところが歴然とわかる。修正を繰り返す中で、英語が英語のまま聴けるようになる。 pic.twitter.com/e6TiN17j3H
— Sangmin @ChoimiraiSchool (@gijigae) August 12, 2020
▼なぜ能動的な学習ができるのか?
Otter.ai の文字起こしの精度は約95%。100%ではないのが能動的な学習につながります。

例えば、上記のポットキャストではゴルファーがショートパットを逃す原因となる「yips(運動選手を失敗させる神経不安)」についての話です。しかし、Otter.ai の文字起こしでは、「hips」となっていて意味が通じない。
Otter.ai の文字起こしでは、「hips」となっていて意味が通じない
テキストを選択すると選択された箇所から再生されますので、複数回聴くと、hips ではなく、yips のように聴こえることに気づきます。

そこで、「golf yi」とグーグルに入力しますと、候補に「yips」が出てくるので、ここでは、hips ではなく yips が正しいことに気づきます。そして、ついでに yips に関して調べるとポットキャストの文脈ともあっている。
こうして、検索をして、文字起こしを修正することで能動的なリスニングができます。また、ご自分で修正したスクリプトですと後から復習する際も、格段と見やすいと思います。
検索をして、文字起こしを修正することで能動的に聴くことができる
▼話者の特徴に気づく
Otter.ai ではまた、音紋を利用してボイスラベルが付けられるのも能動的な学習の手助けとなります。誰が話をしているのかが明示的にわかりますので、その人のアクセントや話し方により早く慣れます。
. @otter_ai ではそれぞれの人々の声が持つ「音紋」を活用して話者を見分けている。音紋を認識することで会話を誰と誰がやっているか、区別できる。あとからその人が誰かを教えてあげれば、音紋をベースに残りの会話についても、自動的に誰がしゃべったか、名前がボイスラベルとして反映される仕組み。 pic.twitter.com/VWeUWOjpZB
— Sangmin @ChoimiraiSchool (@gijigae) July 29, 2020
2 感動を受けた箇所だけを集められる
梅棹先生は「知的生産の技術」で発見についてこう説いてます。
今日も「知的生産の技術(👉https://t.co/rVFNBr9ilR)」を読みながら@RoamResearchで新しく学んだ事実と感動を一緒に書く✍️。
— Sangmin @ChoimiraiSchool (@gijigae) May 23, 2020
"「発見」には、いつでも多少とも感動が伴っているものだ。その感動が冷めやらぬうちに、文章にしてしまわなければ、永久に書けなくなってしまうものである。" ー梅棹忠夫 pic.twitter.com/vUhfyPOusm
ポットキャストも一緒で、聴いた時に受けた感動を、文章として残さないとすぐ忘れてしまいます。
聴いた時に受けた感動を、文章として残さないとすぐ忘れてしまう
Otter.ai では文字起こしが終わった後、感銘を受けた箇所だけを切り取ってシェアすることができます。このリンクを Roam や Notion、Evernote などに埋め込んで感想を綴りますと記憶にも定着しやすいです。
. @otter_aiのデータを@RoamResearchに埋め込む方法です。とても簡単で、
— Sangmin @ChoimiraiSchool (@gijigae) July 10, 2020
① 必要な箇所を選択し、シェア用のリンクを生成
② Roamの iframe 機能を使って、埋め込む
③ 感想を書く
書いておけば、前の発見が次の発見のための栄養素になって、次第に巨大な木へと育てることが出来ます🌳。#Roam部 pic.twitter.com/nr192YHizI
3 検索しやすい
英語圏の場合、オーディオブックやポットキャストなどオーディオコンテンツ市場は急速に拡大しています。同時に、これらの消費量も圧倒的に増えるはず。
オーディオコンテンツは他の作業をしながらも聴けるというメリットが大きいです。しかし、これは「この間の話、どこで聞いたけ?」と思った時、検索できないという短所にもなります。
英語が聴けるメリットは想像以上に大きい。英語圏でのオーディオ・コンテンツ市場は急速に拡大していて選択肢も豊富。あと、リスニングに慣れるとオンライン授業などを1.5倍速でもついて行けるので生産性向上にも直結。最近は @otter_ai などの文字起こしサービスも多く、後から検索するのも簡単🎧。 https://t.co/KrQuAeozd5
— Sangmin @ChoimiraiSchool (@gijigae) July 27, 2020
そういう時に便利なのが、Otter.ai による文字起こしです。

例えば、僕が文字起こしをしたポットキャストで「obama」と検索しますと全部で9個のコンテンツがマッチングしていることがわかります。
Otter.ai では検索の範囲をいくつかに絞ることができます。「Home」画面での検索は文字起こしをした全てのコンテンツが検索対象となります。
検索結果のページを見ますと「obama」が出ている箇所が詳しく確認できます。

探していた箇所が見つかりましたら、①そのセンテンスをクリック→②元のコンテンツが表示→③ピンポイントで再生、することができます。

4 まとめ
英語学習においてポットキャストを Otter.ai で「文字起こし+読む+聴く」メリットは実に大きいです。Ottercast、始めてみませんか?
Otter.ai の詳細は下記の note を参考にしてください。
