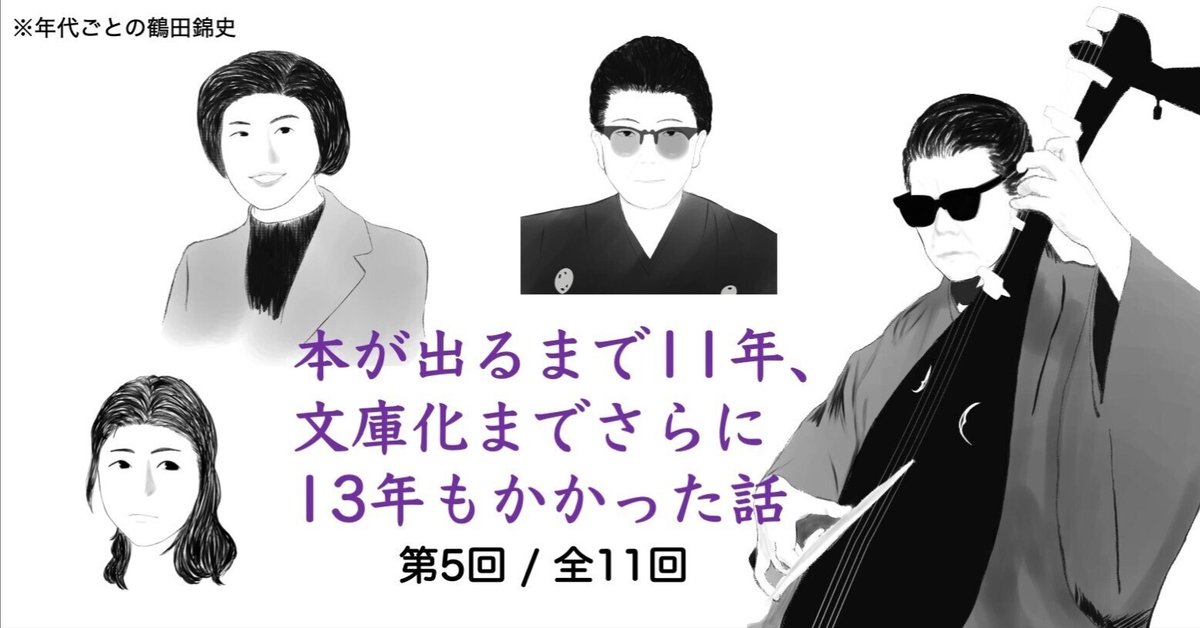
第5回 謎を残したまま
何度かの呼び出し音のあと、電話がつながりました。
「はい、水藤でございます」
私はまた頭が真っ白になりました。
その言葉と話し方から察するに、声の主は、夫を亡くしたばかりの水藤桜子さんに違いありませんでした。
息子さんが出るものとばかり思っていた私は、しどろもどろになりながら、
「先ほど、ご子息にお話しいただきました者です」
水藤桜子さんは、
「あぁ、いつか水藤が話していた方ですね」
胸が詰まって「はい」とすぐにはお返事できませんでした。
あの勉強会のあと、水藤五朗さんは桜子さんに私のことを話してくださっていたのです。
なのに私は、1か月も水藤五朗さんをお待たせしてしまったのです。
私はとっさに「自分は水藤五朗さんに取材を許された人間であること」をなんとか水藤桜子さんにお伝えしなければと思い、錦琵琶と水藤錦穣について語れる人間は水藤五朗さんのほかにいないこと、水藤五朗さんから「取材に協力するので、琵琶界の正しい歴史と事実を本に書いて、後世に伝えてほしい」と託されたことなどを熱っぽく語りました。
すると、水藤桜子さんは小さな沈黙のあと、ひとり言でもつぶやくように、
「でも、あのひと、ぜぇんぶ、持ってっちゃったわね」
失意で強張っていた顔が、とたんに羞恥で火照りました。
私は貴重なお話の聞けるチャンスを失ったことばかりに気がいって、もっと大切なものを失っていたことに気づきませんでした。
あの日、私は水藤五朗さんから話を聞いて、「封印された水藤錦穣と鶴田錦史の師弟関係」と「ほとんど資料に残されていない錦琵琶の歴史と水藤錦穣の人生」を後世に正しく伝えると約束しました。
なのに、その約束を果たす機会は永遠に失われました。
琵琶の魅力を若い人たちにも伝えたいという私の想いに共感して、「よろこんでお話ししますよ」とおっしゃった水藤五朗さんの期待と信頼を裏切ってしまったのです。
どれほど後悔しても、水藤五朗さんのお話を聞くという約束は、もう果たせませんでした。
私の失態で、水藤錦穣さんの人生と鶴田櫻玉の師弟関係の詳細を知る絶好の機会を逸しました。
私にできる唯一の罪滅ぼしは、なんとか少しでも事実を突き止め、後世に書き残すことだけでした。
錦琵琶宗家の水藤五朗さんが虚血性心不全で急逝されてから数か月後、幸運にも、私は水藤錦穣さんに関する貴重な資料を入手します。
昭和47年に開催された演奏会で配布された「藤の実」と題される水藤錦穣自身の手になる回顧録です。
そこには19ページの紙面を割いて、水藤錦穣の自分語りで三十代半ばまでの半生が綴られていました。
ちなみに「鶴田櫻玉(錦史)」の名前は一切出てきません。
この回顧録の最後には、次のような文章が添えられています。
《幼い頃より終戦第一回の会までの思い出を綴ってみました。いかがでございましたでしようか。なおこの後の二十七年のよしあしごとを又綴つてみたいと思つて居ります。私は如何なる場合でもこの錦の琵琶を後生に残したい、弾き継ぐ人をつくりたいの気持が一杯でございまして雨の日も風の日も教室へ通つて居ります。幸い私の伜も邦楽好きで琵琶三弦を習得中でございます》
文末の「幸い私の伜も邦楽好きで」の「伜(せがれ)」が水藤五朗(本名 水藤五郎)さんです。
ここで書かれた水藤錦穣の「この後の二十七年のよしあしごとを又綴つてみたいと思つて居ります。」という思いは、結局、果たされませんでした。
半年後の昭和48年4月25日、水藤錦穣は享年62歳で亡くなります。そして、奇しくも彼女の三十三回忌の法要を終えた直後、水藤五朗さんも享年61歳で母の待つ天へと召されました。
「藤の実」は非常に貴重な資料です。しかし、国会図書館で集めた昔の新聞記事を合わせても、大正時代の邦楽界を代表するスーパースー「水藤錦穣」の人生を描くには情報が不十分でした。
水藤錦穣の人生と鶴田櫻玉の活動について、きちんと書けるようになるのは、この時から6年後、取材を始めてから10年半後のこと。
それが「本が出るまで11年もかかった主な理由」の4つ目と大きく関わっています。
謎は残りましたが、打てる手は全て打ち尽くして、もうこれ以上、新たな取材の可能性は残っていません。
私は忸怩たる想いを抱えながらも、原稿の執筆に取り掛かかりました。
資料は膨大にありました。20人以上の取材対象者へのインタビューの録音テープはのべ50時間近く。それらを原稿に起こし、整理し、資料と照合して信憑性の担保できるものを取捨選択するだけでも、相当な時間がかかります。
かかったのは時間だけではありません。資料購入費、交通費、取材対象者にお持ちする高級和菓子代に至るまで、経費は全て自腹。本が出て印税が入るまで収益はゼロなのに、相当な出費を強いられ、しかも、本の仕事をしている時間は、生活費を稼ぐための記事の仕事ができません。
精神的にも肉体的にも金銭的にも追い詰められながら、私は原稿を書き続けました。
取材開始から5年半が経った2006年春、ついに私は鶴田錦史の伝記を書き上げます。
しかし、実際に出版されるまでには、さらに5年半もかかることになるのです。
第6回につづく
