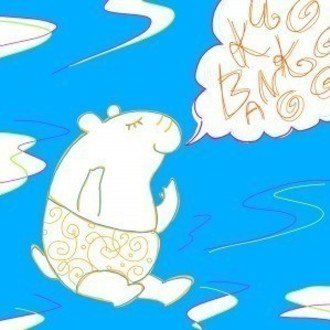ジル・チャン「静かな人の戦略書」を読んだ感想~自分は自分以外にはなれない〜
読んですぐにハッとしたページ
私はこの作者と同じ内向的人間です。
MBTIの結果は6:4で内向型優位で、この本の中に内向型か外向型かわかる簡単なテストもあったのですが、それでは15対3で内向的との結果。
内向的な人間ならだれでも、外向的な人になりたいなあ…と一度は思ったことがあるのではないでしょうか?
みんなから「私、あの人と仲がいいんだ」と自慢されるような人になりたかった。
いつでも気の利いたことを言える、スピーチの達人になりたかった。一緒にいて楽しい人だと思われたかった。
私はかっこつけるために鎧で身を守るためにしそれこそ多大な努力を払って、「活発」「ほがらか」「楽しい」「ポジティブ」「元気いっぱい」などなど、誰もが好感をもつ理想のイメージを片っ端から体現しようとした。
鎧はずしりと重くなるいっぽうだったが、護身のためだし、こうすればみんなに好かれる、期待に応えられると思っていたから、どんなにしんどくても、私は鎧を脱ごうとしなかった。
私は外向型の人間になりたかった。
心の中では考えていることも言いたいこともたくさんあるのに、考えすぎて一瞬出遅れがちになるし、結局話すのは一言二言になる。
考えすぎる性格のせいで、自分が損をしたり苦しめているような気がしていた。
世界は外向的な人たちを基準にできている…外向的な人に圧されている…うらやましいし、そうなれない自分が悔しい…そう考えてしまうこともありました。
なのでこの本の序盤で書かれているこの文が凄く良くわかった。
自分以外の誰かを演じた反動は大きかった
私は社会人になってからは特に、無理をして自分を外向型人間として演じていました。外向的な人の方が上司や先輩に気に入られるし、そうでないと仕事の割り振りや普段の仕事で損をすることばかりでとてもやっていけなかった。(最初に配属された部署が特に社内でも厳しいと有名で、人が半年ごとに消えてゆくような場所だった)
当時、無理をして外向的な人を演じた反動は凄まじく、無理を続けたことと、体育会系風味な社風が合わなかったことなども重なって一度体調を崩してしまった。しばらく謎の体調不良(原因のわからない身体症状:不定愁訴ともいう)に襲われていました。
そしてそれからしばらくして悟ったのは「自分に合わないキャラを演じ続けることは不可がかかりすぎて無理だ」ということでした。
私はこの本の序盤に書かれている「外向型になる必要はない」という言葉にハッとしてしまった。
ありのままで外向型の性格なのであれば外向的でいることは負担は少ないと思う(ありのままなので当たり前)。内向型でも仕事で人格が変わる人もいるし、それを無理なく続けている人もいることはわかっている。
だけどやっぱり、この本に書かれている通り合わない外向型な振る舞いをするよりも、持ち合わせている内向的な人の良さ(後述)を活かす方がよほど得策だと思うのでした。
「自分を感情から切り離してしまうと、やがて身体にも問題が生じてくる」
エックハルト・トールの言葉
これ、全くその通りですね。
そして下の引用も。
就活生たちは、私のように勇敢で優しく、それでいて意志の強い人になりたいと語った。
けれども、私の望みはそれとはちがう。私が彼女たちに望むのは、本当の自分を見失わずに、自分らしくあることだ。
私のように膨大な時間と労力を無駄にしたあげく、本来歩むべきだった道に戻るなんてことは、してほしくないから。
内向的な人間が外向的になる努力をするよりも、内向的な人間の持つ能力を伸ばし活かしていく方が建設的だということだった。
著者は外向的なふるまいを続けること=膨大な時間と労力を無駄にしたことだと言い、内向的な能力を活かすことを「本来歩むべきだった道」だというのだ。すんなり納得はできかねたけど、その通りだと思う。
自分は自分以外になれないので、内向的人間の強みを活かすべき
近年は、内向的な人の良さが評価されてきているらしい。
著書は主にアメリカでのキャリアを積んだ台湾人である著者の経験から書いているのだが、それは日本でも同じだと思う。
この本の中には、内向的な人がするべき戦略が何個も書かれている。
その中で自分が特に気になったもの↓
・脳がそもそも即座の反応には向いていないので、前もって準備をすること・練習しておくことが重要
→内向的な自分の気に入らないところだったけど、納得。心の準備も含めた準備が重要
・内向型がエネルギーをチャージするには、一人になる必要がある
・ただし「内向的だから~できない」「自分が~なのは内向的だから」などの考えは危険
→自分の成長の可能性をつぶしてしまうので注意
・重要なのは、自分がもっとも価値を生みだせる仕事に就くことで、自分にとっての理想の仕事というのは外向的にも内向的にも存在しない
・新しい場になじむには「仲間を見つけること」「仕事の能力を示すこと」「明確な成果を出すこと」の3つが重要
→親切そうな人から仲良くなる・仕事で質問をする・傾聴することも重要
・グループより個別に話す方が得意なので「歩き回って個別に話す」
・相手が感情をぶつけてきたら、一歩引いて冷静に対応するがいうべきことは言う
→反論や慌てるのは得策ではない
・社交イベントは無理せず要所のみ出る
→その際は小さな目標を立てる(誰か一人に話しかける等)
・休むことも計画に入れておく
やっぱり内向的な自分が難儀だなあ…とは思う。好きかといわれると、そうは言えない気がする。でも付き合っていくしかないんだよねーと今では納得しています。
この本にはその他いろいろな例とともに、内向的な人がどうすれば物事に対応できるのかが書かれていました。
まとめ、外向的な人が苦手だと思っていた昔とそうでない今
昔は外向的な人が苦手だった。
クラスで目立っていて、他人の迷惑なんて考えずになれなれしくて無神経なのに、目立つ分自由にふるまえて評価をされている気がしていたから。
今は違うけど、学生の時は俗にいう「陽キャ」とか「外向的な人」ってすごく嫌だったんですよ。
自分が細かいことを気にして進めないところを、さっと先にいって失敗する。それで他人を巻き込んできて迷惑なのに総合的にはうまくいっている。煩くてこっちの迷惑も考えずすごく迷惑。煩い音も苦手で関わりたくなかった。(ボロクソ)
でも外向的な人全員がそうでないことや、そういった特性によって苦労もしていることが大学以降だんだんわかってきて、外向的なさまざまな人と関わったりできるようになって、理解できるようになった。
今思うと、今まで苦手だった「外向的な人」は「無神経な人」だった。何もしていなくても相手から嫌な風に関わってくる…だから反感も持ったし、できる限り関わりたくなかった。
だけど、外向的な人は決して無神経じゃない。今まで外向性について勘違いをしていたと気が付いた。
そして、外向的な人がどういう考え方をしているのか・どういう人なのかももっと知りたくなった。
そう思った今は、昔よりももっと内向的人間として動いていけると思った。
やっぱり内向的な自分が良いかといわれると、難儀な特性だなあと思うし手放しに自分が内向的であることには喜べない。でも著書にある通り「内向的だから~できない」「自分が~なのは内向的だから」などの考えは自分の成長の可能性をつぶしてしまう。
だから、外向内向に関わらず、結局ありのままの「自分」でどう戦略をとって生きていくのか…って話なのかなあと思う。
おしまい。
※外向的な人への批判の意図はありません。
いいなと思ったら応援しよう!