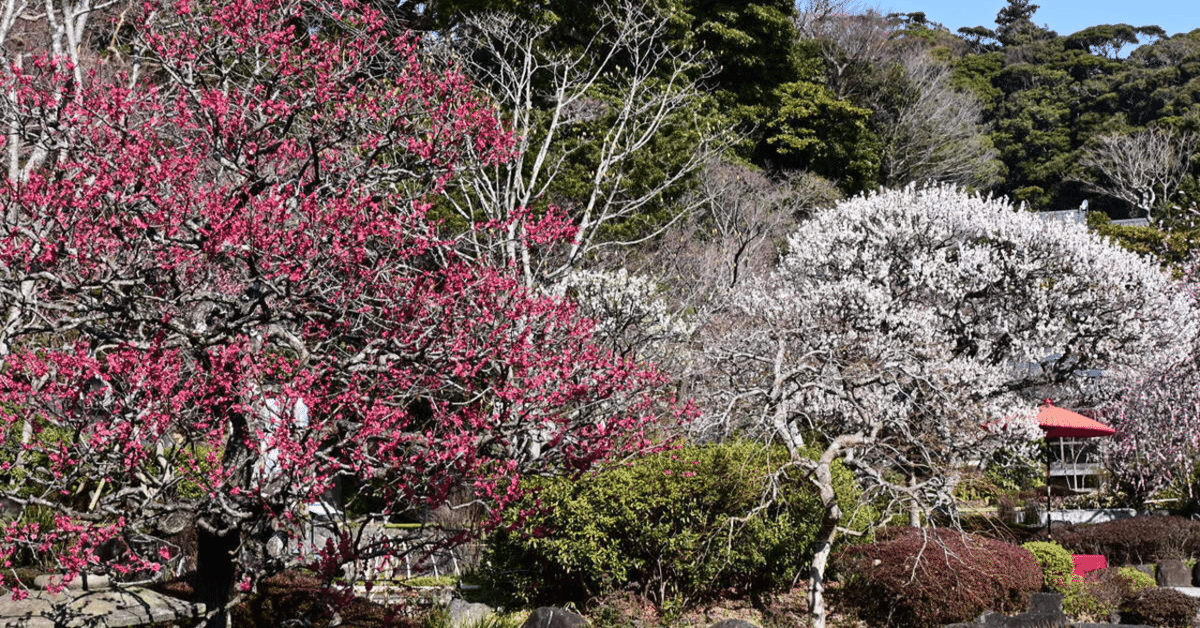
悲しみの中で
※ 最新の小説です
霜月(十一月)下旬。
「お師匠様、遅いな。」
「そうね。」
囲炉裏に薪を焚べていた、お師匠様の末娘で、オレの幼馴染のさくらが手を止めて不安げに答えた。
オレは、数年前から、信州戸隠山に暮らす甲賀流忍術の師匠、戸澤白雲斎先生に弟子入りしている。
若い頃から「甲賀にその人有り」と迄言われたお師匠様は、最近は以前に比べると、やや足腰が弱ってきていると感じてはいたけど、まだまだ健在だ。
そのお師匠様が、未の刻(午後二時)頃、山へ山菜を採りに出かけたまま。酉の刻(午後六時)を過ぎてもまだ戻らない。
一抹の不安を覚えたオレは、自分も探しに行く、と言って聞かないさくらを「お師匠様と行き違いになるかもしれないから。」と言い聞かせ、山中迄、松明を持ち探しに行った。
そして、山中で俯せで倒れているお師匠様を見つけたんだ。
*****
「お師匠様っ‼︎」
オレは慌てて駆け寄りお師匠様を抱き起こした。
「佐助か。」
お師匠様の声は弱々しかった。
見ると左足の太腿辺りから出血している。
動脈をやられている。
一刻も早く手当をしないと取り返しのつかない事になる。
だが、此処では暗い。
家へ戻らねば。
オレは焦った。
とりあえず、応急処置だけでも急がないと。
オレは自分の着物の端を引きちぎり、傷口を縛り止血をした。
そして、お師匠様を背負おうとした。
「佐助、それには及ばぬ。」と、お師匠様。
「お師匠様を背負う事位出来ますよ。 さ、遠慮せずにオレに掴まって下さい。」
「下ろすのじゃ。」
お師匠様の言葉には、有無を言わせぬ力があり、オレは背負いかけたお師匠様を下ろした。
「佐助、今迄黙っておったがわしはもう長くはない。
この足の傷も敵に襲われてできた傷じゃ。
以前なら難なく交わせた攻撃もこの様じゃ。」
そう力なく話すお師匠様からはかつての壮健さは微塵も感じられなかった。
「お師匠様。」
オレもそう言った後、暫く二人とも無言になった。
やがて沈黙を破るようにお師匠様は仰った。
「佐助、わしは此処で自害する。。
先程も申したが、わしは、目もろくに見えんようになってきた。
もう長くはない。
済まぬが介錯を頼む。」
オレは、悲しかった。
同時にとても腹がたった。
涙が自然に頬を伝った。
「お断りします。この程度の怪我で、お師匠様らしくない、弱気な事を仰らないで下さい。
目だって多少不自由だって、オレとさくら、さんで‥」
そこまで話してオレはお師匠様の目に涙が浮かんでいるのに気づいた。
お師匠様
厳しくも優しかった。父親代わりだ、と思っていた。
お師匠様の技術だけでなく、その考え方も含めてオレはお師匠様を尊敬していたんだ。
そのお師匠様が命を断とうとしている。
弟子として従うべきなのか、分からなかった。
「「人間を含めて無闇に生き物の命を奪ってはならぬ。
人が刀を奮って良いのは大切な物や人を護る時だけじゃ。」
そう仰ったのは紛れもなくお師匠様じゃないですか。」
オレも、そう言って食い下がった。
いくらお師匠様の頼みだって聞けない。
お師匠様は、ふと遠くを見るような目をした後、真っ直ぐにオレの顔を見た。
そして穏やかな口調で、こう仰った。
「確かにわしはそう言った。
だが人には皆、権利があるのも事実。
生きる権利。死ぬ権利。
わしは充分生きた。
お前も立派に成長した。
佐助、わしの介錯をするのは決して無闇に命を奪う事ではない。
わしの意思を尊重し、手助けする事だ、と思う。
やってくれるな。」
お師匠様の言葉はオレの心の中に錘のように深く深く沈んでいった。
オレは腹を括った。
そこまで話して、お師匠様は自らの腹に短刀を押し当てた。
そして最期にオレの方を振り向き、こう仰った。
「娘を、さくらを頼む‥」と。
オレは俯せになって倒れ込んだお師匠様の盆の窪にノミを打ち込んだ‥
オレは、お師匠様にトドメを刺した。
さくらの唯一の肉親を奪ったんだ。
オレはお師匠様を背負って家まで帰った。
家までの距離は、たかが半里(約二キロ)だったけど、途轍もなく長く、背中に背負ったお師匠様は子どものように軽かった。
*****
「ただいま。」と、オレ。
「お帰りなさい。」
待ちかねたように引き戸を開けたさくらの顔が一瞬で凍りついた。
「お父上‥」
さくらは既にこと尽きたお師匠様に縋り泣き崩れた。
「一体、どうして、こんな事に‥お父上‥」
「誰が、こんな事を。」
「オレだよ。」
「え⁉︎」
「さくら、オレがお師匠様にトドメを刺したんだ。」
それから、オレは事の流れをさくらに説明した。
正直オレもまだ頭が混乱していて、きちんと説明出来たとは到底思えない。
「佐助さん、お父上の体を綺麗にして差し上げたいの。」
「そうだな、オレがやるよ。」
「ううん、やって差し上げたいの。
どんな状態になったって、あたしのお父上だもの。」
「そうだな。じゃ、一緒にな。」
「うん。」
お師匠様の着物は真新しい物になり、体はお湯で洗い綺麗になった。
湯灌が終わり、オレはさくらに向き合った。
「さくら、オレは体を張ってでもお師匠様をお止めしなければいけなかったんだ。
それを、オレは‥」
そこまで話してオレはついに堪え切れなくなって嗚咽した。
さくらは、そんなオレをそっと抱きしめてくれた。
「佐助さん、辛かったよね。泣いてもいいよ。」
さくら自身も涙声になっている。
「さくら‥ごめん‥オレ、さくらの唯一の‥肉親のお師匠様を‥」
「ううん、ううん‥」
オレとさくらは暫く二人で泣きながら抱き合った。
外は、お師匠様の死を悼むように冷たい雨が降り出していた。
終わり
