
【ミステリーレビュー】翼ある闇 メルカトル鮎最後の事件/麻耶雄嵩(1996)
翼ある闇 メルカトル鮎最後の事件/麻耶雄嵩
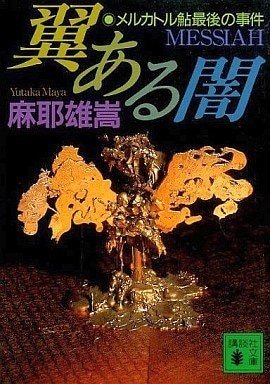
京都大学在学中に執筆された、麻耶雄嵩のデビュー作。
「黒死館殺人事件」をモチーフに、新本格ミステリーのセオリーが全部盛りになっている。
首無し死体に、密室、見立て殺人、双子の登場に生きていた死者…
舞台も、今鏡家の一族が暮らす蒼鴉城という曰くつきの屋敷で、密教儀式が行われていた様子。
そこにふたりの名探偵が颯爽と現れ、推理合戦を繰り広げるのだけれど、それでも連続殺人は止まらない。
情報量が多いので、序盤は頭の整理が大変なのだが、新本格愛好家にはたまらない展開である。
一方で、読み進めるうちに、必ずしも王道を地で行っているわけではないことに気付く。
大きく二部構成に分けられていて、第一部は、事件の発生から、木更津悠也による推理パートまで。
第二部は、メルカトル鮎による推理パートから、どんでん返しに次ぐどんでん返しが展開されるのだが、そのジェットコースターのような加速度が、完全にセオリーをぶち破っているのだ。
これを痛快ととるか、アンチミステリーと受け取るかで賛否は分かれるのだろう。
個人的には、新鮮さを求めていた脳みそにスマッシュヒット。
なんだこれ、頭がおかしいんじゃないか、と読み耽ってしまった。
なお、語り部である香月実朝が木更津のワトソン役だったりするので、どちらかと言えば木更津が主役として描かれている。
当然ながら初登場のはずなのに、警部との関係性が出来上がっていたり、癖の強さをとりわけ強調していなかったり、シリーズものの3作目以降ぐらいの空気を出しているのが面白い。
この辺りは、セオリーを忠実に守っているからこそ可能になるメタの要素と言えるのでは。
【注意】ここから、ネタバレ強め。
本作がアンチミステリーと呼ばれている理由は、大きく3つあるのかと。
ひとつめは、名探偵たちが、結局事件を解決できない。
木更津→メルカトル→木更津の順で推理を披露するのだが、真相は別にあるという仕掛けになっているのだ。
これだけ大掛かりな連続殺人でも、4つの解釈ができるということ。
名探偵が推理をはずしまくるという意外性もアンチと言えばアンチなのだが、"実際はいくらでも可能性があるのだから、推理だけで上手く解決できるはずないでしょ"という皮肉がたっぷり込められているようにも思う。
ふたつめは、"いくらなんでも"なバカミス要素。
切断された首が別の人間の胴体とくっつき、奇跡的な確率で神経が繋がって復活、自ら密室を作り上げる。
表向きには真実とされる木更津の推理が、これなのだもの。
小説としても、最後の最後まで"これが意外な結末であった!現実は小説よりも奇なり!(小説だけど)"と読ませるため、ここで呆れてぶん投げてしまう読者も相応にいたのだろう。
最後は、語り部が秘密を隠していること。
結局、あらかじめ"手品の種"を知っていた香月が真犯人に語りかける形で、読者だけに真相が明かされる。
読者からしてみれば、語り部が見聞きした情報で推理するのがミステリーの醍醐味であるわけで、その語り部が知っている情報を恣意的に隠しているのは「推理小説」としては反則のはずだ。
名探偵たちが3度も騙されたのだ、わからなくて当然ではあるのだけれど、そういう問題ではないでしょ、とついつい突っ込みを入れたくなる。
これらをまとめると、「ミステリー慣れしている読者を手玉にとる」ミステリーと言える。
メタ要素をこれでもかとぶち込んで、絶対に引っかかる、絶対に騙される、絶対に思いつけない推理バトルを、あえて傍観させる。
アクが強すぎるので、肌に合わない人にはとことん合わないのだろうが、常にクライマックスの雰囲気が漂う本作は、新本格のフォーマットは好きだけれど、自分で考えるよりも探偵たちの推理に痺れ、あっと驚く展開に身を委ねていたい、という読者にはこれ以上ない作品ではなかろうか。
