
「生前退位」3つの衝撃と6つの論点──問われているのは「退位」の認否ではない(「月刊住職」平成28年12月号)
宝算82(28年12月23日で83になられた)。昭和天皇、後水尾天皇に次ぐ歴代3位のご長寿となられた今上陛下の「生前退位」問題が、身につまされると感じる本誌(「月刊住職」興山舎刊)読者が少なくないと聞く。
長命は慶事のはずなのに、現実は足腰が弱り、読経も十分に勤まらない。入院が続き、寺務も滞っている。財産目録や収支計算書を毎年、揃えるのは億劫だ。露骨に引退を促す檀家さえいる。宗教法人法上の義務が果たせないなら、行政も黙ってはいない。
税務署は宗教家をサービス業に分類しているが、住職は事業家ではない。寺は事業所ではない。本来、僧侶の務めは何かという本質論が求められている。
陛下もまた同様に、天皇とは何かを、憲法上、主権者とされる国民1人ひとりに問いかけておられるのではないか。
いわゆる「生前退位」問題には、3つの衝撃と6つの論点があるように思われる。
第1の衝撃は、いうまでもなく、今夏(平成28年)のNHKのスクープである。
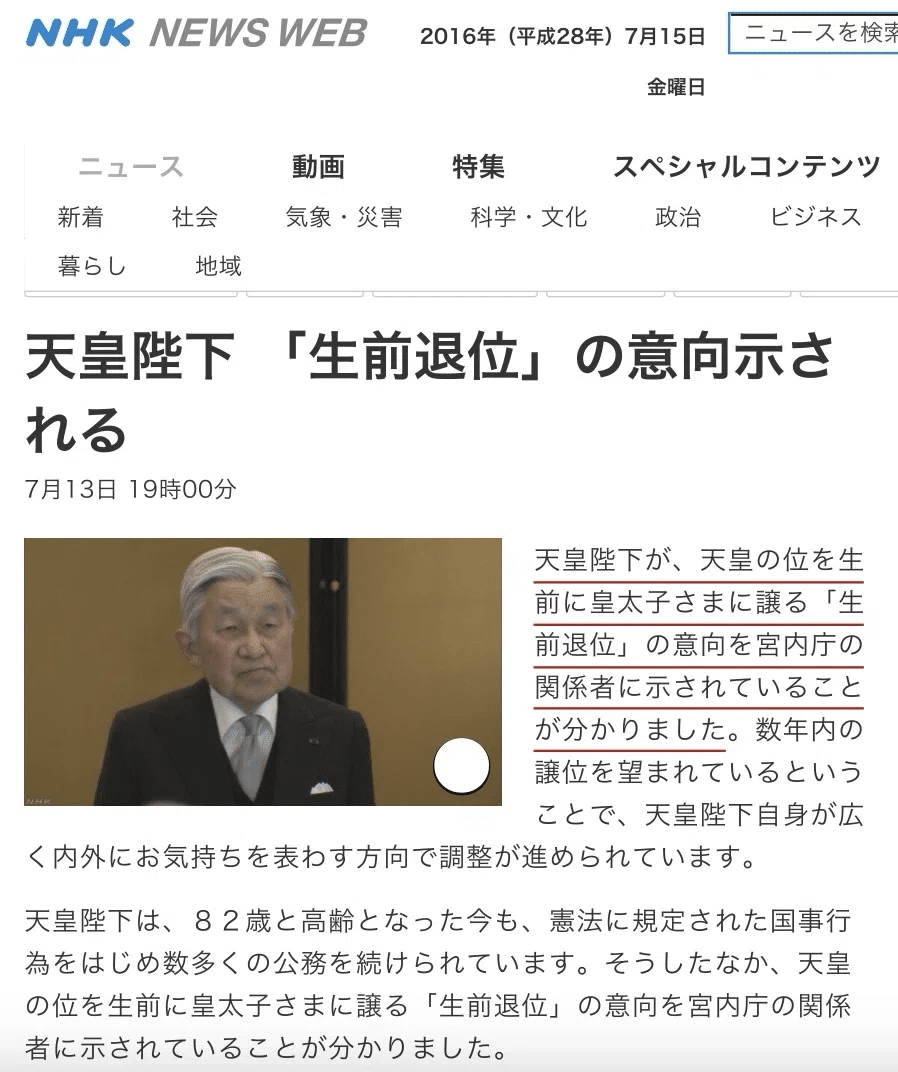
7月13日、夜7時のニュースは「天皇陛下『生前退位』の意向示される」と報道した。数年内の譲位を望まれている。陛下ご自身がお気持ちを表す方向で調整が進められている、とも伝えられ、メディアはそろって後追いした。
2つ目の衝撃は、リークを濃厚に匂わせるNHK報道が今年(28年)の新聞協会賞に選ばれたことである。受賞理由は「国民的議論を提起した。与えた衝撃は大きく、皇室制度の歴史的転換点となり得るスクープ」と説明された。

3番目は、お気持ち表明についての皇后陛下のご感想である。
「新聞の1面に『生前退位』という大きな活字を見た時の衝撃は大きなものでした。それまで私は、歴史の書物の中でもこうした表現に接したことが一度もなかった」と、お誕生日に際しての文書回答で述べられた。
なぜこれらが衝撃なのか、6つの論点をひもとけば、明らかになろう。
▽1 「生前退位」なる皇室用語はない
第1の論点は誰が、なぜ「生前退位」と言い出したのか。第2の論点は、誰が、何のためにNHKに皇室の内部情報を流したのか、である。
もともと「生前退位」なる皇室用語はない。「退位」「譲位」ではなく、もっぱら「生前退位」なる新語が用いられている理由は何だろう。皇后陛下のご感想後、「生前退位」と表現しない報道が増えたが、NHKはなおもこだわっているらしい。
陛下に直接取材することは不可能だから、NHKの特ダネが宮内庁関係者の情報提供に基づいていることは明らかである。陛下が「生前退位」と仰せになったわけではないようだから、情報提供者か、もしくはNHK記者が「生前退位」と表現したことになる。
NHK・WORLDは英語で「abdication」と表現している。朝日新聞の英語版も同様だし、海外メディアは「retire」とも伝えているから、「退位」でもいいはずだ。なのに、である。
国会で天皇の「生前退位」が話題になったのは3回しかない。国会議事録によれば、昭和58年3月の参議院予算委員会が最初らしい。

江田五月議員(社民連)がウォーターゲート事件、ロッキード事件に触れつつ、当時、「生前退位」問題が話題になっていることを取り上げ、皇室典範改正の可能性を内閣法制局にただそうとしたのに対して、法制局を制して答弁した中曽根康弘首相は「不謹慎なデマ」と完全否定している。
翌年4月の参議院内閣委員会では、太田淳夫議員(公明党)が山本悟宮内庁次長(のちの侍従長)に、今日と同様、昭和天皇がご高齢のなか激務をこなされている現実をあぶり出し、「生前退位」の提案が出ていることを指摘して、宮内庁の考え方を問いただした。
これに対して山本次長は、陛下はお元気である。皇室典範は「退位」規定を持たない。皇位安定のためには「退位」否認が望ましい。摂政、国事行為の臨時代行で対処できるから皇室典範再考の考えはない、と否定している。

▽2 「生前退位」を避けてきた宮内庁
今日の議論と真逆なだけでなく、宮内庁が「生前退位」なる表現を避けてきたことは注目される。明治以降、「退位」は認められず、現行皇室典範にも規定はない。政治的権能を持たない天皇の御発意から制度改革の議論が開始されるのは前代未聞だ。違憲の疑いは当然だろう。ましてやなぜ「生前退位」なのか。
「文藝春秋」10月号(28年)によると、今上陛下は平成22年7月22日、御所で開かれた参与会議で、皇后陛下のほか、羽毛田信吾宮内庁長官、川島裕侍従長、3名の宮内庁参与(湯浅利夫元長官、栗山尚一元外務事務次官、三谷太一郎東大名誉教授)を前に、開口一番、「私は譲位すべきだと思っている」と述べられ、はじめて御意思を伝えられたという。

会議では皇后陛下をはじめ全員が反対した。摂政案の提示もあったが、陛下は「摂政ではダメ」と否定された。まれに見る激論となったが、御意思は揺るがなかったという。
少なくとも「譲位」なら理解できる。それがなぜ「生前退位」報道になったのか。NHKは「退位のご意向」とは伝えなかった。歴史用語である「譲位」「退位」ではなく、宮内庁が嫌ってきたはずの「生前退位」を用いた理由は何だろう。
平成の皇室制度改革は、小泉内閣時代の8年、鎌倉節長官の指示で非公式に始まったといわれる。過去の歴史にない女系継承容認=「女性宮家」創設論も、提案者は顔を見せないままだった。媒体を選び、情報を小出しに漏らし、世論の動向を見定めつつ、改革作業は進められた。今回も同じである。
▽3 仕掛け人は風岡長官自身か
第3の論点は、お言葉が発せられるようになった経緯は何か。第4の論点は、本当のお気持ちはどこにあるのか、である。
風岡典之長官は(28年)9月末、退任した。70歳定年とはいえ、年度末まで勤め上げる慣例を破り、有識者会議発足を目前にせき立てられるような退職は異例だ。「お気持ち表明に至る過程で、宮内庁の対応に不満を持った官邸が人事でテコ入れを図った」とも解説されている。
退任会見で、風岡長官は、5、6年前、陛下の意思表示があったこと、昨年(27年)ごろからお気持ちの表明を模索してきたこと、憲法問題もあるので、内閣官房とも調整したことを明らかにした。
これらはメディアが解明してきた事実関係と大差はない。だがNHKのスクープ直後の受け答えとは異なる。
あの夜、次長は「報道されたような事実は一切ない」と全面否定し、長官は「次長が言ったことがすべて」と述べた。長官の退任会見はみずからウソを認めたことになる。

もっとも翌日の会見では、長官は打ってかわって陛下のお気持ちを匂わせた。メディアを利用した一連の仕掛け人はもしや長官自身なのか。
報道によれば、7年前から天皇陛下と皇太子殿下、秋篠宮殿下による三者会談が設けられてきた。24年6月に風岡次長が長官に昇格すると三者会談は定例化し、長官もオブザーバーとして同席し、ご意向を聞き及ぶことになった。
今年(28年)5月、宮内庁当局が大幅なご公務削減策を提示すると、陛下は強い難色を示された。「削減策を出すなら、なぜ退位できないのか」
原案を突き返された官僚たちは遅まきながら仕組み作りに走り出した。
そして編み出されたのが、メディアにスクープ報道させ、宮内庁当局が否定し、「どっちが本当か」と国民の注目を集めさせ、陛下ご自身にお気持ちを表明していただくというシナリオではなかったかというのだ(「週刊新潮」28年7月28日号。「ダイヤモンド・オンライン」同年8月26日など)。

▽4 なぜ今回は「ご意向」なのか
宮内庁は「退位」を思いとどまるよう説得できず、逆に「退位」を認めるような方針転換を図ることになったらしい。
小泉内閣の皇室典範有識者会議は皇族方の意見に耳を傾けず、それどころか女系継承容認への懸念を示された寛仁親王殿下に、羽毛田長官は「皇族の方々は発言を控えて」と口封じに及んだ。だが今回は「ご意向」優先に変わった。
正確にいえば、変更は3年前である。宮内庁は「御陵および御喪儀のあり方」について、非公開で検討を進め、御陵の規模の縮小や御火葬の導入など、改革を決めたが、これは「両陛下の御意向を踏まえ」た結果とされ、内廷のこととされて、議論らしい議論は起きなかった。
そして今回も「ご意向」である。
「個人としての考え」とされる(28年)8月8日のビデオ・メッセージには、もちろん「生前退位」はない。制度上の制約を考えればそのような表明などあるはずもない。陛下は「天皇もまた高齢となった場合、どのようなあり方が望ましいか」を問いかけられたのだ。
身体の衰えから象徴としてのお務めを果たしていくことが難しくなるのではないかと懸念され、一方で、国事行為や公的行為の縮小、摂政を置くことを疑問視され、さらに御大喪関連行事が長期にわたって続くことにも懸念を示されたうえで、象徴天皇の務めが安定的に続くことを念じられた。
これをNHKは「生前退位の意向が強くにじむ」と伝えているが、単純すぎないか。「譲位」のお気持ちは否定できないにしても、ご真意はほかにあるのではないか。
いみじくもお言葉は「象徴としてのお務めについての」と題されている。高齢化社会という現実を踏まえ、「象徴天皇」のあり方について、主権者とされる国民に深く考えてほしいというのがご真意ではないのか。
その意味では、菅義偉官房長官が「ご公務のあり方について、引き続き、考えていくべきものだと思う」と述べているのは正しいと思われる。
戦後の象徴天皇制度は明文法的な規定が十分に整備されていない。戦後70年間、国民もその代表者たちも制度の中身を埋める作業を怠ってきたからだ。
明治憲法下では、憲法と相並ぶ皇室典範があり、宮務法の体系があった。しかし日本国憲法施行とともに、旧皇室令は全廃され、宮務法の体系は失われた。新たな法体系はいまだ創られていない。現行皇室典範は一法律に過ぎない。
▽5 無視された昭和天皇の「退位」表明
伝統主義の立場から天皇第一のお務めとされる宮中祭祀は敗戦後、「宗教を国家から分離すること」を目的とする神道指令により「皇室の私事」に貶められた。祭祀を司る掌典職は内廷機関と位置づけられ、職員は天皇の私的使用人とされた。
当時の政府は、祭祀=「私事」説に不満だったが、占領下では反対のしようもない。「いずれきちんとした法整備を図る」が政府の方針とされたが、結局、70年間、実現への動きはなかった。
それでも祭祀が存続し得たのは、新憲法施行に伴って、宮内府長官官房文書課長の依命通牒、いまでいう審議官通達が発せられたからだ。その第3項には「従前の規定が廃止となり、新しい規定ができていないものは、従前の例に準じて事務を処理する」と記されていた。


皇室祭祀令は廃止されたが、それに代わる規定は作られず、廃止されたはずの祭祀令の附則に準じて、祭式が占領下も、社会党政権下も存続したのである。
皇位継承、服喪、喪儀、陵墓なども同様で、「いずれ」の機会は来なかった。
岸内閣時代の昭和34年、賢所で行われた皇太子殿下(今上天皇)御結婚の儀は、「国の行事」(天皇の国事行為)と政府決定され、ようやく占領下の宮中祭祀=皇室の私事説が打破されたかに見えたが、御成婚の諸行事すべてを国の行事=天皇の国事行為と位置づけるものではなかった。
逆に大きな変化が現れたのは、昭和天皇の晩年である。昭和43年、侍従次長となった入江相政(のちの侍従長)は皇室制度の整備どころか、祭祀の「簡素化」を「工作」し始めた。毎月1日の旬祭の御親拝を年2回に削減し、年末年始の祭儀や皇室第一の重儀とされる新嘗祭を簡略化することに熱中した。目的はご健康への配慮とされたが、疑わしい。
さらに49年、富田朝彦次長(のちの長官)が登場すると、祭祀簡略化は本格化した。50年8月15日の宮内庁長官室会議以後、平安期に始まった天皇の毎朝御拝の歴史を引き継ぐ、侍従による毎朝御代拝の形式が変更された。
その根拠は依命通牒第4項「前項の場合において、従前の例によれないものは、当分の内の案を立てて、伺いをしたうえ、事務を処理する」で、憲法の政教分離原則に配慮した結果だった。公務員である侍従は宗教である天皇の祭祀に携わることはできないとされた。
側近が進める祭祀簡略化に、昭和天皇はご不満で、何度も「退位」を表明されたらしいことが「入江日記」に記録されている。

55年9月、後水尾天皇三百年祭の前日に研究者による御進講が行われると、昭和天皇は退位の事績に高い関心を示され、「資料を集めるように」と侍従らに指示されたという。
昭和天皇最後の側近とされる卜部亮吾侍従の「日記」によると、最晩年には「摂政を置いた方が良いのでは」と繰り返し語られた。しかしご意向は、政府にもメディアにも取り上げられなかった。

▽6 行動主義に基づくご公務
第5番目の論点は、なぜ政府は「天皇の公務の軽減等に関する有識者会議」と称したのか。6番目の論点は、お気持ち実現のために特別法と皇室典範改正のいずれを選択すべきか。目下の議論はこの6番目に集中し過ぎている。
今回の「生前退位」問題は、平成22年7月の参与会議に始まると考えられている。議論の出発点として象徴天皇としてのご公務があり、陛下は「全身全霊をもって象徴の務めを果たして」こられた。「憲法上の象徴としての務めを十分に果たせる者が皇位にあるべきだ」とお考えで、陛下は「退位」を表明されたとされている。
本当にそうだろうか。問われているテーマは、一般に議論されている「退位」を認めるかどうかではなくて、象徴天皇制の暗黙の前提とされているご公務主義、行動主義ではないだろうか。
宮内庁のHPには「ご活動」が列挙され、「国事行為などのご公務」のほか、「行幸啓」「外国御訪問」「伝統文化の継承」などが説明されている。
「ご活動」なさることが天皇の役割だという考えはすぐれて近代的で、けっして125代続いてきた皇室の伝統ではない。
8月(28年)のお言葉で「日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましいあり方を、日々模索しつつ過ごしてきた」と仰せの陛下が、それだけに高齢化によって「譲位すべきだ」と深く悩まれるのは、近代主義にこそ大きな原因があるのではないか。
装束を召され、薄化粧されて御簾のかげに端座されていた古来の祭り主ではなく、洋装し、ときに軍服に身を包むこととなった近代天皇の原理は行動主義である。この原理に立つとき、いずれ否応なしに立ちはだかるのが、ご健康・高齢化問題であることは目に見えている。
高齢化社会の結果であると同時に、日本の皇室が近代主義を受け入れたことが今日の問題を招いたといえる。
▽7 ご負担軽減に失敗した宮内庁
御在位20年が過ぎ、宮内庁はご負担軽減策を推進した。けれどもご公務は逆に増えた。文字通り激減したのは、祭祀のお出ましばかりだった。宮内庁によるご負担軽減策は失敗したのである(「文藝春秋」23年4月号)。
お言葉では、ご公務とは「国事行為」「象徴的行為」のほか、「伝統」とされている。宮中祭祀の意味だろうが、慎重な陛下は「祭祀」とは表現されない。
政府・宮内庁の考えでは、祭祀=「皇室の私事」であり、ご公務として扱われない。しかし陛下は「天皇の務めとして、何よりもまず国民の安寧と幸せを祈ることを大切に考えて来」られた。
まず国事行為があるという憲法第一主義ではなくて、「国平らかに、民安かれ」という古来の祭祀の精神に立ち、祈りの延長上に、憲法上の務めがあるとお考えらしい。行政の理解とは異なり、皇室の伝統と憲法の規定とはけっして対立しない。
陛下は即位以来、伝統と憲法の両方を追求すると繰り返し表明されている。陛下を護憲派と見る向きもあるが、一面的理解といえよう。
皇后陛下とともに地方を訪ね、国民と親しく交わられることを「大切なもの」と仰せなのは、祈り=祭祀が出発点だからだろう。
だが行動主義に立脚する象徴天皇制は、天皇の高齢化という現実に対して、ご公務のご負担軽減どころか、皇室の「伝統」に強烈な圧迫を加えたのである。
それが昭和の悪しき先例を踏襲する平成の祭祀簡略化である。陛下のお悩みと問いかけはこのとき始まったのではないか。
▽8 70年間の不作為のツケ
ご負担軽減で宮内庁がいちばん気にしたのは、「拝謁」の多さだった。
たとえば春秋の勲章受章者の拝謁はほぼのべ1週間にわたって続く。昭和天皇は叙勲者一同に挨拶されるだけだったが、今上天皇は一人ひとりにお声をかけようとされるらしい。受章者は数千人におよぶ。ご負担が増すのは明らかだ。
新聞社やテレビ局主催のイベントにお出ましの要請があれば、公平の原則に基づいて、各社の催し事にお顔を出される。それだけご公務は増える。
今年(28年)6月、ラグビーの国際試合に両陛下がお出ましになった。日本代表チームにとって初の天覧試合だった。キックオフは夜8時を回っていた。ラグビー協会の名誉顧問は森喜朗元首相で、後援は最大手の全国紙だが、これでご負担軽減のまともな国民的議論を期待できるだろうか。
ご公務に関する明確な法的基準は、憲法の国事行為以外には見当たらない。当然、ご負担軽減に関する基準があるはずもない。国民も政治家もメディアも70年間、ご公務のあり方について、本格的な議論を避けてきたのである。
陛下が「これまでのように、全身全霊をもって象徴の務めを果たして」こられたのは、逆に客観的基準がないからであろう。つまり「生前退位」問題とは、国民の不作為のツケだろう。
朝日新聞は、お言葉を受け、翌日の社説で、「政治の側が重ねてきた不作為と怠慢」を指摘し、とくに安倍内閣の消極性を批判したが、論点を矮小化すべきではない。
批判されるべきは、個々の内閣の取り組みではなくて、明文法的基準のない戦後70年の象徴天皇制のあり方そのものだろう。「不作為と怠慢」は、主権者たる国民とその代表者すべてに帰せられるべきだ。メディアも例外ではない。
さて、いよいよ有識者のヒアリングが始まった。外野ではすでに、またぞろ男系維持派と女系継承容認派に分かれて、「生前退位」実現には特別法か典範改正か、と喧しい議論を闘わせている。
しかし政府の聴取項目は、天皇の役割、ご公務のあり方、ご負担軽減の方法など8項目で、「生前退位」という表現はない。設問も今更の感が強い。
伝えられるところでは、平成30年がタイムリミットとされる。とすれば、審議に時間がかかる皇室典範改正ではなくて、特別立法しかないだろう。政府もそのつもりではないか。要するに有識者会議は政治的通過儀礼だろう。
本当なら、皇室典範は国民的議論を離れた「皇家の家法」に戻すべきだろうし、宮務法は国務法とは別の法体系とし、宮内庁も一般の行政機構から独立させるのが筋ではなかろうか。
しかし本格的な提案を行い、国民を説得し、制度化への道筋を示し、これを実現し、実際に維持・運営していくための有能な人材は得られるだろうか。もし人材が容易に得られるのなら、今日の混乱はまったく起きなかったはずである。
(以上は「月刊住職」平成28年12月号に掲載された拙文です。若干の編集を加えています)
