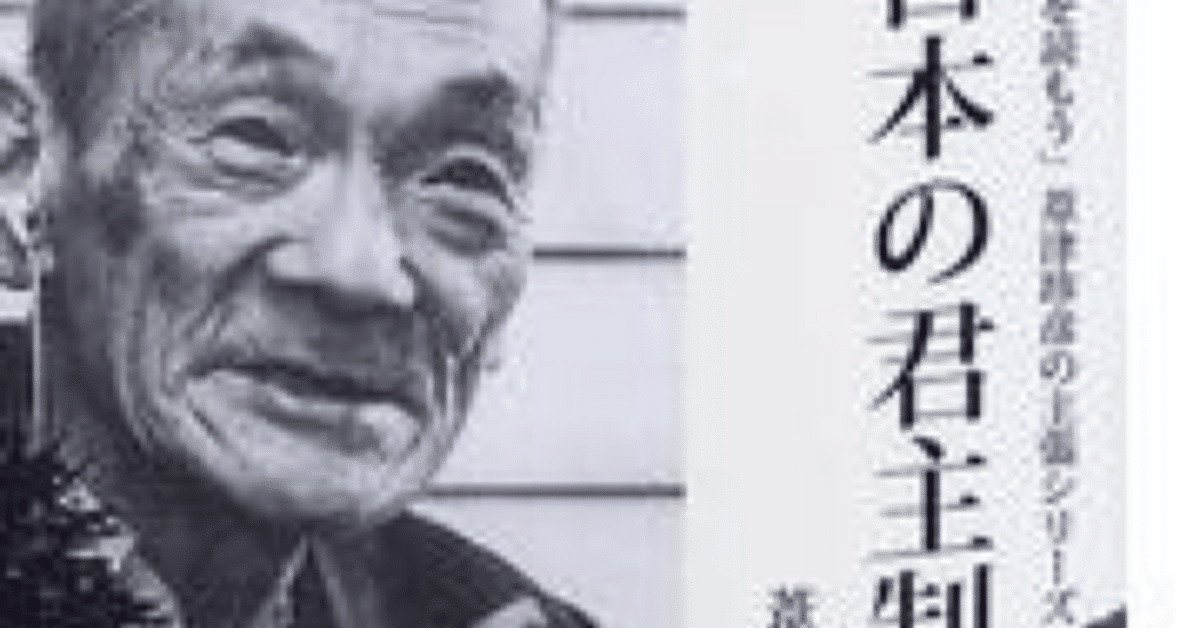
真正面の論争を避けた橋川文三──知られざる「象徴天皇」論争 その2(2009年08月25日)
橋本明『平成皇室論』の批判を続けます。

前号から当メルマガは、約50年前、「思想の科学」誌上で展開された、戦後唯一の神道思想家といわれる葦津珍彦(あしづ・うずひこ)と明治大学教授(政治学、政治思想史)で評論家の橋川文三との天皇論論争について紹介しています。

目的は、一方で政治体制の歴史を世界史的に一様にとらえ、その一方で、国の安定性の要因を君主の倫理性に求める橋本さんの皇室論の誤りを浮き彫りにするためで、前号ではまず、同誌昭和37年4月号に載った葦津論文を取り上げました。
▽1前号のおさらい
軽くおさらいすると、天皇制擁護の立場で書かれた葦津の論文は、
(1)敗戦国の王朝はかならず廃滅し、共和制に移行するというドグマ、
(2)個別性を無視し、世界の君主制をいっしょくたに論ずるドグマ、
(3)国民意識の多面性に目を向けずに、もっぱら倫理的に理解する学者たちの国体論のドグマ、
に対して、痛烈な懐疑を呈し、
(ア)「君主制が少なくなり、やがて日本も共和国になる」という一般的公式を立て、具体的事実を無視し、具体的な国の運命を抽象理論で予見しようとするのは浅はかである
(イ)日本のいまの天皇制ははるかに非政治的で非権力的であるが、無力を意味しないどころか、もっとも強力な社会的影響力を持ち、もっとも根強い国民意識に支えられている
(ウ)日本の国体はすこぶる多面的で、抽象理論で表現するのは至難なほどである。国民の国体意識は、宗教的意識や倫理的意識と割り切れず、さまざまの多彩なものが潜在する。政治、宗教、文学、すべてのなかに複雑な根を持つ根強い国体意識が国および国民統合の象徴としての天皇制を支えている
と指摘するのでした。
▽2 歴史上の2つの問題
同誌編集委員会は「異なった立場を積極的にぶつけ合い、そこからお互いの思想のより着実な成長と実りを求める、という思想の科学研究会の精神に立って、天皇制支持の葦津氏の論文を掲載」(37年4月号)したのですが、今度は、葦津論文批判を書くように、と橋川に要請します。そして、同年8月号に、橋川文三の反論が載りました。

けれども結論からいえば、橋川の論文は反論といえるようなものではありませんでした。橋川は論考の冒頭に「葦津論文は、そのままではとくに反論を必要とする性質の論考でもないように思う」と記しているほどです。まるで真正面からの論争を避けているかのようです。
橋川はその理由を葦津論文においています。すなわち、葦津論文は「国体論そのものとしては、有効な論争の契機を提示していない」。葦津自身、「国体意識の根強く広く大きい事実について、注意を促し、国体研究の必要を力説したに過ぎない」「この論文は討論開始の序曲であり、国体論の本論ではない、と断っている」からだというのです。
橋川は、葦津が書いたほかのミニコミ雑誌の論文にも目を通し、それらが「むしろ論争のためにはより適当な対象だった」と認識しながらも、「ふれる余裕がなかった」として言及しませんでした。
そして、政治史的視角を示さず、非歴史的な比較制度論に傾斜している、と橋川が見る「思想の科学」に掲載された葦津論文の指摘に直接、反論するのではなくて、「やや場違いとも思われる歴史上の問題を序論的に提出する」のでした。
その「歴史上の問題」とは、「明治憲法の天皇制は、民族信仰の伝統の上に成立したものなのか」「かつての日本植民地の人々にとって『国体』とは何だったか」という、2つの命題です。
▽3 作られた「国家の基軸」
橋川は、葦津のように比較制度論や社会心理学の立場から国体=天皇の問題をアプローチするにしても、少なくともこの2つの問題を避けては意味がない、と指摘します。真の保守主義者はこの2つの問題から学ばなければならないというのです。
つまり、橋川は、まず第1に、以下のように指摘します。
1、明治維新は上からの革新であった。それまでの日本人の生き方になかった要素を加えることだった。混沌とアナーキーのなかから1つの秩序を創出するダイナミックな課程であり、「無」からの想像という劇的場面にほかならず、「国体」価値の創造もこの過程で行われた。
2、伊藤博文らが起草した明治憲法は、混沌状態を収束する権力政治上の意味を負わされていただけでなく、国民的統合の創出を最大の任務としていた。それは現代では想像もつかない困難な課題であった。「国家の基軸」とすべきものが欠如していたからである。
3、そこで、伊藤は自然的存在としての国体から憲法を作ろうとしたのではなく、逆に国体の憲法を作ろうとした。学校や鉄道、運河と同じように、「国民」を作り、「貴族」を作り、そして「国家の基軸」を創出した。近代国家となるには、自然的・伝統的天皇と異なる超越的統治権者の創出が必要だった。
4、この国体は、民衆の宮廷崇拝やおかげ参りの意識とは異質のものだった。
要するに、近代天皇制は、悠久の天皇史とは異なる、明治時代にでっち上げられたものだ、というのが橋川の指摘です。
▽4 膨張主義的規範
2つ目の問題は、国体がかつての日本帝国の「新版図」において、どのような意味を持ったか、です。天皇=国体の意識が異民族に対してどのような特質をあらわしたか、確かめる必要がある、と橋川は指摘するのでした。
つまり、
1、明治の領土拡張のあと、国体は普遍的価値として、「八紘一宇(はっこういちう)」の根源的原理として現れている。単に日本の歴史的特殊事情に基づく国柄という域を超え、人類のための当為(とうい)─規範の意味を帯びるに至った。膨張主義的規範であった。
2、国体論は、「帝国主義」権力そのものの神義論という本質をもっていた。宗教と政治の無差別な一体性の空間的拡大ということが日本の帝国主義の顕著な特質であった。日本の「国体論」はこの百年の歴史について責任を負っている。
3、「国体」が「征服・闘争・帝国主義」のシンボルに逆行しないために、我々は「国体」の自然化を戒める必要がある。そのために、葦津氏と同様、私も「国体研究の必要」を力説したい。
要するに、どぎつく表現すれば、天皇制こそが海外侵略の血塗られた元凶(げんきょう)だ、という指摘でしょう。
この反論になっていない橋川論文に対して、葦津は翌38年1月号で、いみじくも「反論ではなく、感想のようである」と指摘したうえで、葦津自身は真正面から反論を加えます。詳しくは次号にゆずりますが、予告的に少しお話しすると、葦津はおおむね次のように橋川論文を批判するのでした。

──日本人の国体論というものは途方もなく複雑で、まったく相反するような多様な思想が錯綜(さくそう)している。橋川氏があげた2つの例のほかにも、大切なものがあるだろう。これを整理し、論理づけるのは容易ではないが、2、3の事例だけで思想史を割り切ってしまっては「思想の科学」は成り立たないだろう。
簡単にいえば、歴史のつまみ食いでは、科学にならない、というのが葦津の反論です。
同じことは、橋本さんにもいえそうです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
