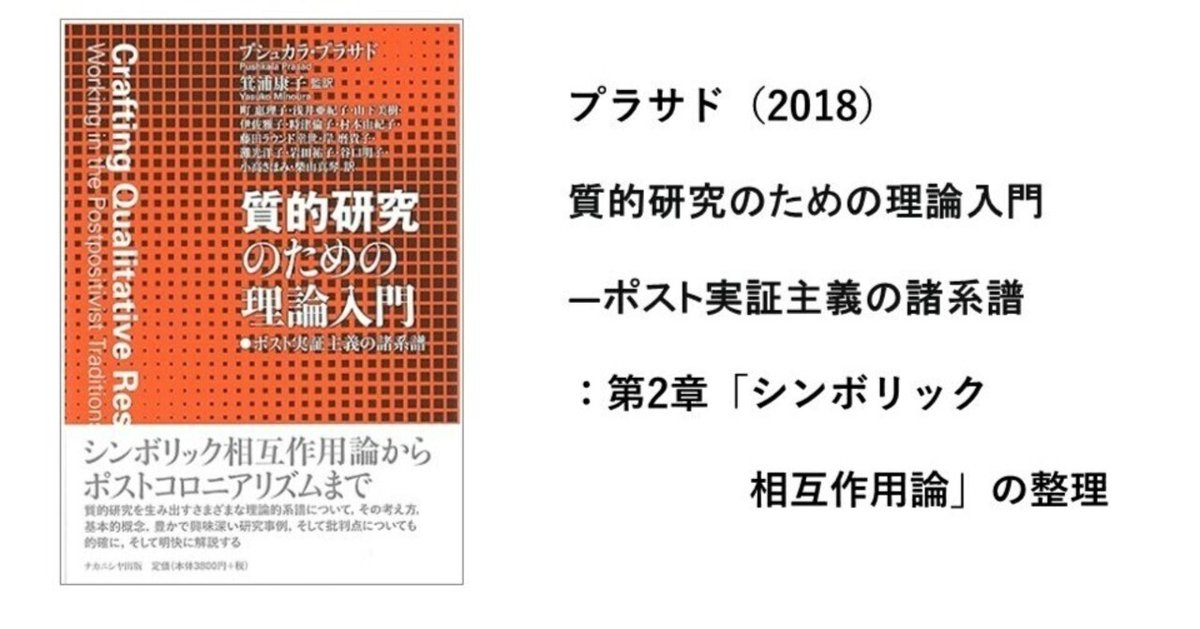
【研究メモ】「シンボリック相互作用論」と言ってみたいお年頃~プシュカラ・プラサド(2018)『質的研究のための理論入門-ポスト実証主義の諸系譜』 第2章「シンボリック相互作用論」からの学び
番匠さん・松井さん・今井さんと一緒に、質的研究を進める上で重要となる理論についての学びを進めています。
今、扱っている書籍は、プシュカラ・プラサド(2018)『質的研究のための理論入門-ポスト実証主義の諸系譜』です。
初回は、番匠さんが、第2章「シンボリック相互作用論 自己と意味を求めて」について発表してくださいました。
シンボリック相互作用論、用語を知っているくらいで、「シンボリック相互作用論ですね!」と口ずさむものなら何かかっこいい!!という浅はかさが過ぎる自分でしたが、読み進めてみるととっても面白かったです!
それもそのはず、シンボリック相互作用論は、プラグマティズムや現象学の影響を受けており、組織開発で大事にされている価値観ともとても繋がるじゃないですか!
中原・中村(2018)にも、組織開発とシンボリック相互作用論/ 質的研究の繋がりを示唆する記述がありました[下記、スライドに転記]。
普段の組織開発の実践中で大事にしていたことを、理論を通して、さらに解像度高く言語化してもらった感覚です。
最近特に感じますが理論や、哲学的なバックグラウンドから学ぶの本当に大事ですね。
「個人によって意味づけされなければ, 本質的な意味は存在しない」という記述なんかも、個人的に好きな量子物理学の世界観(観測者効果)とも繋がり、なんかテンションあがっていました!
番匠さんのわかりやすい発表や補足資料、松井さんの情報共有もあったおかげで、一人で読んでいるときだと理解できていなかった点についても、さらに理解が進みました。
番匠さんの発表の後に、今井さんも加わり、みなさんでの研究に紐づけながらの実践的なディスカッションもあったりで、贅沢な時間でした!
ありがとうございました!
※本ポストは、番匠さんの発表、松井さん・今井さんとのディスカッションを参考にさせていただきました! ありがとうございました!!





#027
#研究メモ
#質的研究
#理論
