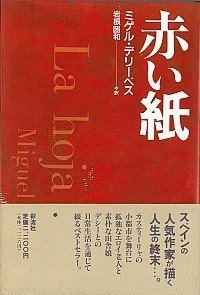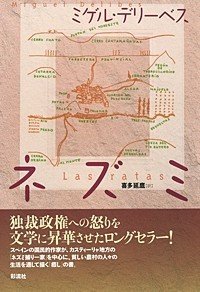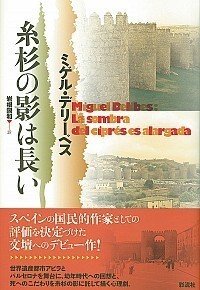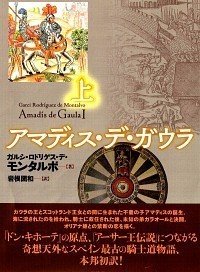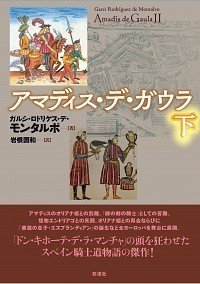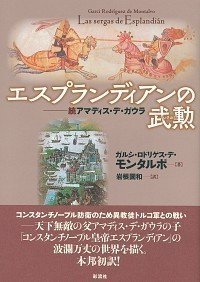スペイン文学を代表する作家 デリーベスの短・中篇集『そよ吹く南風にまどろむ』刊行記念!短編『クルミの木』を全文公開!
『そよ吹く南風にまどろむ Siestas con viento sur』
ミゲル・デリーベス 著, 喜多 延鷹 訳
定価:2,200円 + 税
2020年5月21日ごろ発売予定
5月21日ごろ発売予定の、『そよ吹く南風にまどろむ』。スペインの作家ミゲル・デリーベスは日本ではそれほど知られていませんが、ノーベル文学賞受賞が取り沙汰されるほど、スペインでは有名な作家です。
今回は『そよ吹く南風にまどろむ』の刊行を記念して、本書所収の短編『クルミの木』を全文公開します。
クルミの木──Los nogales
その年、クルミは八月前半に実り始めた。異例の早生現象であった。若ニーロは老木の木陰に横になり、木々の爽やかなざわめきを聞いて楽しんだ。それは、触れ合って喜ぶ木々の声であった。若ニーロは田園が微かに軋む音を聞いて眠気に誘われた。神様のお造りになった自然は完璧であり、人間は神様のお造りになった自然を損なうことしかしない。せっかく、神様の決めた自然の営みを害し、損なってしまう、ということを若ニーロは知っていた。老ニーロは息子のそんなひ弱な姿勢をみると苛々となった。
「ガキ共が入ってきてクルミを盗んで行く前に、クルミの叩き落しをしなくちゃなんねえ」と言いながら、視線を息子から逸らした。息子の空(うつ)ろでひもじそうな目付きを見るのが嫌だった。
若ニーロはそんなことには動じなかった。口を動かすと疲れる、というように、辛そうに話した。兎唇(ミツクチ)だったからである。
「もう、熟してますね。父ザン。ぼく、神ザマより上手に作ることはできっこありません。先生ザマが、そうおっしゃっデダ」
老ニーロは息子の傍に来て、肩を寄せ合った。
「言っておくがね、ネズミトリ鳥は昼も夜もクルミの木の下を飛び回っているぞ。神様は、ニーロ様のクルミがネズミトリ鳥に食われることをお望みではないぞ。分かるか。こんなことでは二十ファネガ〔穀物容量の単位、国によって異なるがスペインでは一ファネガ=五五・五リットル〕も収穫できないぞ」
老ニーロも、神様の造られるものは完璧であり、再生の循環が完璧であることを知らないわけではなかった。また、クルミの仮果は太陽に当たると乾いて割れ、外から力を加えなくとも、木から落ちることも知っていた。また、老ニーロは、世界中のどんなに優れたナイフ作りといえども、太陽に勝る切れ味のナイフ作りはいないことも知っていた。クルミの木を叩いて実を落とし、そのまま放っておけば、村の悪童共、ネズミトリ鳥、クリミガ〔害虫〕、リスなどに横取りされてしまう、そうなると、クルミの木は儲けがなくなってしまうことも老ニーロは知っていた。
八十歳に手が届き、村の外部の人々に対して、老ニーロはこの村人の健康の象徴にも、模範にもされていた。老ニーロは驚くべき精気を漲(みなぎ)らせていた。強靭な歯並み、溌剌とした面構え、完璧な聴力を備えていた。かつて、老ニーロの五感はケモノのように鋭かったが、このところ、めっきり脚が弱り、体を支えるのがやっとだった。五十年前、無性に男の子が欲しいと思った。しかし、どういうわけか、ベルナルダが男の子を産むと、男の子はみんな、すぐ死んでしまい、一人も育たなかった。ベルナルダは言った。
「あんた、名前にこだわってニーロって名前つけ続ければ、あたしたちには男の子はこないよ」
老ニーロは言い張った。しつこく司祭に言った。
「ニーロだ。おれはニーロと言ったぞ」
「ニーロと、あと別名は」〔カトリック国では二つの名前をつけてもらう。長男は通常、父親と同名をつけ、さらに別名をもらう。例=フワン・カルロス(先代のスペイン国王)、ミゲル・アンヘル(イタリア語ではミケランジェロになる)等〕
「ニーロ、それだけだ」
「また、ニーロかい」
「そうだ。おれが男の子が欲しいのは、おれと同じ名前をつけるためだ」
血統の明らかな嫡出性について、老ニーロは少し変わった考えを固持していた。つまり、息子というものは誇らしげに母親の胸に摑まって見せることによってではなく、付与した名前によって明示される、というものであった。息子にフワン、ペドロ、ホセ〔いずれも典型的なスペイン人男性名〕という洗礼名をつけてもらって、そう呼ぶことは父権の放棄を意味していた。この村では姓はどうでもよかった。村の司祭は、
「意地張るんじゃない。この子には別の名前をつけて上げなさい。それとも、この子も死なせたいのかね」
「ニーロだ。ニーロと言ったらニーロだ」
「それで、もし亡くなったらどうなさるかね」
「埋葬するだけの話よ」
こうして若ニーロは生まれた。育ちが悪く、痩せこけていて、医者は、とてももつまいと、部屋の隅に粗麻布を広げ、その上に赤ん坊を放置すると、大量出血した母親の処置に回った。しかし、若ニーロは自力呼吸を始めていた。ベルナルダの手当てを済ますと、医者は赤ん坊を次の間に運ばせ、しきりにあちこちと聴診した後で言った。ダウン症だな。二十四時間も持つまいと思うね、と。
司祭がやってきて、まず、洗礼をいたしましょう、と言った。
「名前はなんとつけますか」
「ニーロだ」
「いいですか。この子は二、三時間も持たないのですよ」
「で、もし生きながらえたら、どうする」
「お前さん、大ばか者の頭領みたいな方だ。この子に、ペドロとかフワンとかの〔洗礼〕名をつけてあげるのが、私の大切な務めだ」
このようにして、ニーロという名前が付けられた。医者は、ベルナルダが奇形の赤ん坊を見てびっくりするといけないから、見せない方がよい、死産だった、と言えばよい、と告げた。
老ニーロは酒場に行った。二、三時間もたないと言われた時間に戻ってきた。
「もう死んだのかい」
ぺチャパイのブラウリアは不安そうに赤ん坊を抱いていた。
「この子、益々逞しく呼吸しているわ」
「まさか」。老ニーロはそう言うと酒場へ戻った。十二時まで飲んでいたが、その後、ブラウリアの元にやってきて言った。
「どうなった」
「あそこにいるわ。あんた、赤ちゃんどうする気。わたし、もう眠んなくっちゃならないわ」
赤ん坊は泣き叫んでいた。
「お腹すかしているよ」。老ニーロは言った。「でもな、母親には、赤ん坊は死んだ、と言ってあるので、母親のところに連れていけないし……」
少しの間、丸腰掛に座り、指を櫛にして髪の中に入れ、くしゃくしゃの髪を整えると、言った。
「ヤギの乳あるか」
「あるわ」
「水で薄めて少しやってみてくれ」
「そんなことして、死んだらどうする」
「それは承知の上だ。さあ、早く」
赤ん坊はヤギの乳を飲むと、静かになって眠った。
こんな状況を見て、老ニーロは赤ん坊を可愛いとさえ思った。
「そんなにみっともなくはないよ、な?」
「あんた、そう思うの」とブラウリア。
老ニーロは心の中に何かが湧き出してくるのを経験した。しばらくして言った。
「明日まで赤ん坊みてやってくれないか。泣いたら、ヤギの乳をやってくれ」
ベルナルダは老ニーロが小屋に入ってくると訴えた。
「ずーっと赤ん坊が泣いてるように私に聞こえるんだけど」
「ペチャパイの連れている雌猫が啼(な)いているのさ。見つけ次第、棒で叩きのめしてやる」
ベルナルダは納得しなかった。
「ペチャパイの雌猫、今頃サカリがついてるわけないわ」。しばらくして、ぽつりと言った。「まだ、その時期じゃない」と。
老ニーロは言った。
「もう、寝よう。あしたはあした」
しかし、老ニーロはとても眠れないのを知っていた。
ベルナルダもワラ布団の上で、不安な気持ちで寝返りを繰り返していた。
「どんな具合なの、言ってちょうだい」
「何のことだい」
「子供よ」
「あたりまえの子供だったよ。ただ、死んでいた」
「ねえ」
「なんだね」
「お墓にはニーロって子何人いたっけ」
「五人だよ。こんどのを入れないで」
「なによ、なぜ、こんどの子を数に入れないの」
ベルナルダはすっくと立ち上がった。
「ねえ、聞いて。あれはペチャパイの雌猫ではないわ。絶対そうではないわ」
「おれには何も聞こえない」
「今泣き止んだわ。でも、あれは赤ん坊よ」
急に跳び上がった。
「あんたたち、まさか、赤ん坊を生き埋めにしたんじゃないでしょうね」
「まさか」。老ニーロは言った。「一晩中かかって、たいへんだったんだよ」
「ねえ」
「なんだ」
「お墓の敷地を、わたしたちニーロで独り占めするのは正当なことか、って村長さん言うわよ。他の人たちは文句言わないのかしら」
「言いたい人には言わせておくさ」
「よくいうわ。税金上げられるんじゃないの」
「上げたらいい」
「どうやって払うの」
「上げろってんだ」
「あんた、クルミの木六本じゃ、パン一かけらにもならないってこと、誰よりもよく知ってるくせに」
「そりゃそうだが」
「ねえ、ニーロ。私の言うことわかる?」
「何だ」
「ペチャパイの雌猫はサカリがついてるはずないわ。まだその時期ではないよ」
「黙らないか」
「私のこと、だましてるんじゃないの。そうでしょう」
翌朝、医者は驚きを隠さなかった。ペチャパイは言った。
「この子ったら、ますますしっかりと呼吸するようになったわ」
それから、老ニーロを振り向いて、「どこか赤ちゃん欲しい人のところにあげるっていうのはどうかしら。もう、わたし、世話できないから」と言った。老ニーロはじっと医者を窺い、医者の決定を待った。医者は赤ん坊に聴診器を当てると、「確かに、心臓の鼓動が力強くなっているようだな」と言った。
村では老ニーロに可哀そうな子が生まれたことが知れ渡り、みんながこぞってブラウリアのところへやってきた。
「どれどれ、拝見」
「みんなに見られて、顔擦り切れて、しまいに名前まで擦り切れちまうぞ」
「ひぇー、手何本ある」
「片方に八本ずつだとでも言うの、ばかばかしい」
「まるで自分の赤ちゃんみたいに」
赤ん坊と初めていっしょに寝た夜、ブラウリアの中に、一途でじわっとした母性感情が芽生えた。つまり、ブラウリアが赤ん坊にあげたヤギの乳は、まさしく母乳であった。ブラウリアは哀れで不恰好な老ニーロを見ていた。ズボンの後ろの破れ目からお尻が見えていた。ブラウリアは老ニーロに言った。
「あんた。ベルナルダのところに行っておやり。そして、本当のことを話してあげなさいよ。もし明日になって本当のことが分かると、あんたは赦してもらえないよ」
老ニーロは躊躇った。
「勇気がないな」
「勇気がない?」
「ない」
「それじゃ、わたしが行くわ」とブラウリアが言った。
ベルナルダの家から戻ってきたブラウリアは、まるで死人のようだった。
「死んでたわ」。ぽかんとして言った。そして急に笑い、泣き、歯を食いしばると、ベルナルダはベッドで固くなっていたわ、と大声で言った。
老ニーロは若ニーロを育てるために、なけなしの土地を売らねばならなかった。手元に残ったのはクルミの木と、ミツバチの巣だけとなった。ベルナルダは夭折した五人の息子たちといっしょに、すでに墓の下で眠っていた。老ニーロの心の中に、細やかな思い遣りがひろがった。毎日、六本のクルミの木を仰ぎ見た。それから、希望に輝いた目で息子の方を見た。「息子にはちゃんとした生活をして、クルミの木を面倒みてもらわなくちゃならない」と独り言を言った。
当時、老ニーロは村一番の「クルミ叩き」になっていた。大地主たちは老ニーロに連絡してきて、クルミを叩き落として、収穫してもらった。彼の競争相手たちはクルミの実も枝も、ごちゃまぜに叩き落した。老ニーロはこの仕事に対する、生まれつきの能力、つまり、素晴らしい脚力と手際のよい指先の能力を発揮した。
彼は考えた。「脚は腕と同じくらい大切だ。腕は脚ほど物に耐える力はない。これは誰も知らない秘密だ」と。これは自分だけの秘密にして、誰にも言うまい、と思った。いつの日か、この秘密を若ニーロに教えてやることにしよう。小屋の片隅には、クルミ叩き用の、太さの異なった棒切れのセットが置いてあった。この地方一番の「クルミ叩き」になる武器は、刃は欠けてもよいが、丸型刃のナイフと奇跡的な手があれば十分だった。遠出の時は子供を連れて行った。若ニーロを大きな背負い篭に乗せて歩き、昼と夕暮れ時には、ヤギの乳を水で薄めて少しずつ飲ませた。背負い篭の赤ん坊を木の根元にそっと置くと、赤ん坊はぐっすり寝入った。
子供が物心付いてきた時、父親は子供に言い聞かせた。
「ニーロよ。おれの仕事をよく見ておけよ。仕事を覚えなくちゃいけない。お前の生活はこれだよ」
しかし、老ニーロが木のてっぺんから、さて、息子はどうか、と見下ろすと、息子は仕事ぶりを見てくれるどころか、ぐっすり眠りこけているのが茂みの間から見えた。三歳になっても若ニーロは歩かなかった。這い這いして移動した。言葉も出なかった。無理して話させようとすると、「バーバー」と言うのが関の山だった。「クルミ叩き」ってのは、人間とは関わりがないからなー、クルミを叩き、収穫し、食べて、寝るには、言葉は要らないからなー、と息子に言い訳した。しかし、子供は頭が良かった。時間がたつにつれて、みんなにそれが分かるようになる。若ニーロはミツクチの上に、食べることと眠ることしかしないので、村人たちは彼を薄弱児だと思い込んでいた。
七歳になり、若ニーロはようやく「パン」という言葉を発した。十歳になった時、足のカユイカユイ病が始まった。その頃、ハチクイドリが老ニーロのミツバチの巣に穴を開け、ハチミツとミツバチを食い荒らしてしまった。若ニーロが「クルミ叩き」にまったく興味を示さないので、父はまだ時期尚早と考え、そのかわりに、松林の丘にあるミツバチの巣の見張りをさせた。夕方、子供を迎えに行くと、案の定、松の落ち葉の上で眠りこけていた。
ある晩、窓から入る月明かりを浴び、ワラの上に寝転がって、老ニーロは息子に話しかけた。
「クルミ叩きってのは素敵な仕事だぞ、ニーロ。木の上の高いところから下を見るとな、神様が下界を見下ろすのといっしょの気分になれるぞ」
薄明かりの中、子供は空ろで訴えるような、斜視の小さな目で父親を見ていた。時々言った。「父ザン、あまりボグのことワルグ言わないでよ」。しかし、たいがいは沈黙を守った。老ニーロは続ける。
「昔、父さんは金持ちだった。分かるか。本式の家を持っていた。金色に塗った鉄製のベッドもあったし、クルミの木とミツバチの巣以外に、二オブラーダ〔一オブラーダ=五四〇〇平方メートル〕の畑を持っていた。ところが、三年続けて夏場に雹(ひょう)にやられ、畑を売りに出さなくちゃならなくなった。父さん、自分に言い聞かせたね。『おれ、木登りできる脚がある限り、クルミをもぐ両手がある限り、十分やっていける』と。おれはその通りやってきた。そうして、おれはクルミの木の下にこの小屋を建てて生活するようになった。初め、屋根をアシで葺(ふ)いた。しかし、雨が降り、日が照って、腐って水が漏れるようになった。おれは、よし、それなら、と自分に言って聞かせたね。『雨水を通さないワラを見付けてやるぞ』とね。そしてトトラ〔がま、カヤツリグサ科の多年草〕を見付けた。村ではその頃、屋根葺くのにトトラなんか使う人はいなかった。こうして、おれの脚が頑張れる間は、おれとお前はなんとかやりくりできるが、おれの脚がどうかなる前に、お前、力はあるんだから、仕事を覚えてもらわんといかん。クルミ叩きってのは誰でもやれることじゃねえのだ」
両手の指を首の下で組み、少しの間沈黙し、月の上に浮かんだクルミの木のシルエットを眺めていた。急に、体の下のワラががさごそと動くのを感じた。
「お前、また足を掻いてるのか」
「かゆいんだよ、父ザン」
「かゆいのをがまんしろ。掻くな。でないと、明日の朝まで掻いてないといかんようになるぞ」
老ニーロはしつこく言った。息子とクルミは相容れない二つの世界かもしれない。老ニーロはそんな予感がしたが、それは認めたくなかった。老ニーロが息子を刺激しようと試みると、息子は眠り込んでしまうのだ。若ニーロは学校へ行くようになると知恵がついて、こんなことを言い出すようになった。
「先生が言っデダゾ。神ザマの作ったものはドデもヨグできている、って」。老ニーロは、やれやれ、とばかりに、他人の所有権を尊重する心を失うことはどんなことか、とか、労働を嫌う危険性について説教しようとしたが、若ニーロは理解したようにはみえなかった。
ある春のこと、小屋には食べ物がすっかりなくなっていた。老ニーロは若ニーロに、働かなくちゃならない、と言った。若ニーロは父親の意見を汲んで、村長の土地の鳥追いをしようと決心した。二日目、村長は、若ニーロが土手の上で横になり、眠りこけているところに出会した。若ニーロの肩の上でカササギが一羽、ゆらゆらと安心しきった様子で揺れ動いていた。その時、老ニーロは確信した。自分の脚が衰えてしまった日に、生活はすべて瓦解し、夏毎に、秩序立てて叩き落している六本のクルミの木は、只の飾り物になってしまう、と。
ある時、老ニーロは、息子が鳥の内臓を塩漬けにしているところに出くわした。ある期待に言葉を呑んだが、やがて言った。
「エビガニ獲りにでも行くのか」
「そうしようと思っデル」
「今年は、くねくね道のあたりでたくさん獲れるそうだぞ」
「そんなこと言っデルね」
若ニーロの頭は大きく、目は斜視、唇はミツクチだった。老ニーロが仕事から帰ってみると、小屋はひどい悪臭を放っていた。鳥の内臓が小屋の隅っこで腐敗していた。エビガニ漁の手網も腐っていた。
「エビガニたくさん獲れたかい」
「行ガなかった。足の裏ガユグなって」
「またかい」
「またじゃない。ズーッドだよ」
老ニーロは七十歳になった時、クルミをもいでくれと、時々頼まれて行く場合を除いて、他所の家のクルミ叩きを止めにした。
年をとっても、老ニーロの手は相変わらず確かで、素早かった。みるみるうちに、小さな頭蓋骨のようなクルミの核果が彼の右側に、殆ど無傷の果肉の皮が左側に山と積み上げられていった。果皮はキャベツとアスパラガスの肥料にされた。十月下旬になっても、老ニーロは自分の畑の六本のクルミにせっせと登り続けた。そして、秩序立てて丹念にクルミを叩き、無傷のまま中から果肉を剥き出した。もし、実を隠している枝があれば、彼はその意図を尊重した。老ニーロは常に、木は感情を持っている、と信じていた。木の感情にひしひしと愛情を感じていた。畑から、コロハ〔ハーブの一種〕の家庭的な香りが立ち昇っていた。年老いた彼の胸は和み、膨らんだ。しかし、役立たずの息子のことを考えると、気が滅入った。日が暮れると、実をもいだ。夜明けには実をていねいに日向に干した。二時間おきに裏返しにした。殻がごく柔らかいクルミだったので、市場ではトリツツキクルミと呼んで売っていた。果肉を包む薄皮はほとんどない。果肉はカリカリして美味である。しかし、時に、ネズミトリ鳥の旺盛な食欲を見ていると、老ニーロは、ネズミトリ鳥などにやられないような、外殻の硬いクルミの木を持ちたい、と思った。夏になると老ニーロは、息子の怠惰に活を入れ、息子の中に眠る天職を呼び覚まそうと努めた。クルミの木の高いところにいて、大枝に両足を踏ん張って頭上に細枝を仰ぎ見ていた時、老ニーロは予感するものがあった。両手両足がいうことをきかなくなり、ガキ共、リス、クリミガ、ネズミトリ鳥共が、せっかく実った作物を台無しにしていくのを、黙って見過ごさねばならなくなる日が近いのではないか、と。これは強迫観念となり、ぜひとも、今のうちに将来の保証をしておかなくてはならない、と思うようになった。
「これ、ニーロ坊。明日、クルミ叩きを手伝ってくれるかね」
若ニーロは、怠惰で物欲しそうな斜視の目を老ニーロに向けた。
「クルミはもう、穫り入れの時期にギデるよ。父ザン。みんな神様がおヅグりになるんだって、先生が言っデダ」
老ニーロは溜息混じりに答えた。
「神様は、ニーロ様のクルミを、村の子供たちや、リスやネズミトリ鳥に取られることをお望みではないのだよ。わかるかい。クルミは地面に落ちてしまうと、十ファネーガスも収穫できない。これだけは先生様がなんと言おうと、神様はお望みになるはずはないぞ。ハチの巣はなくなった。あとはクルミの木六本でなんとかやっていかなくちゃなんねえぞ」
時々老ニーロはベルナルダを、切なく、やるせなく思い出した。「この子に会おうともせず、逝ってしまって」と独り言を言った。そして、自分の足が段々こわばっていくのを思うと、気が気でなかった。
若ニーロは、父が汚いズボンを捲(まく)り上げては、いよいよ形が崩れていく膝の関節を、しげしげと眺めているところに度々出くわした。
可哀そうに、というように、若ニーロは訊いた。
「父ザン、ガユイの」
消え入りそうだった老ニーロの目が、瞬間、希望を取り戻した。
「かゆーい。かゆーい。とっても、かゆーいぞ」と言った。
若ニーロは斜視の小さな目を、葉の茂ったクルミの木のてっぺんの方に逸らしていた。
「じゃあ、売らなくちゃなんないね、父ザン」と、ぽつりと言った。
老ニーロが木に登っている所に出くわすたびに、医者は説教した。
「おい、じいさんよ。もうそんな仕事する年ではないのがわかんねえのか」
「おれがやらなきゃ、だれがやるんかい」。素直に応じた。
「息子さんさ。何のためにお前、息子可愛がって育ててんのかい」
木のてっぺんから、息苦しそうな溜息が漏れてきた。老ニーロは、形のくずれた膝が胸のいちばん出っ張ったところに、がくん、とめり込むような感じがして言った。
「子供は役立たずですよ、先生。ヤツの足にはどこの悪霊が憑いているのか、しょうもなく、かゆい、かゆい、と言うようになっちまって」
「試しに、クツはかせてみなさい」
クルミの木のてっぺんから、心地よい枝葉の間を抜けて、また息苦しそうな溜息が降りてきた。
「こちら、食うや食わずの生活ですからね。お医者さん。お分かり下さいませよ」
医者は離れ際に言った。
「いいか、じいさん。今日は、わし、検死を二つやんなくちゃならなかったぞ」
老ニーロは今でもはっきり思い出す。キンティンは足が動けなくなったある日のこと、自殺に追い込まれたのだ。優れた「クルミ叩き」になるには、自分の手の指のように脚が強くて、柔軟で、素直でないといけなかった。キンティンは動作が鈍かった。自分でも、そう信じているくらいの鈍さだった。カミさんに恵まれなかったチューチョが遭遇した事件は、誰のせいでもない。老ニーロは口を酸っぱくしてチューチョに言っていた。「クルミ叩きやってると、十月にはワインがたらふく呑めるぞ、お前」。チューチョは、ほいきた、とばかり、唄うようにして酔っ払って木に登り、不器用な手つきでめちゃくちゃにクルミの木を叩き続けていたが、ある日、クルミの木はまるで、聞かん坊の子馬が後ろ足で立ち上がったようにチューチョを跳ね上げ、ひっくり返してしまった。チューチョの死体を発見したのは、旅館屋の雌イヌのネリーだった。厳しい冬のオオカミのように遠吠えしていた。老ニーロが現場に駆けつけた時、折れた細枝の先からは、樹液が滲み出したばかりだった。古木の高い枝は無残にも擦り切れていた。
老ニーロは夏になると、チューチョの転落死を思い出した。特に、月の光が小屋の窓から差し込むような晩、チューチョの事件を思い出して、老ニーロは眠りを妨げられた。若ニーロは老ニーロのそばで、口を開けていびきを掻いていた。ある晩、老ニーロはマッチを擦って、炎を息子の口元に近づけた。ミツクチの唇の先は、まるで生まれ立ての小鳥の羽のように赤く、呼吸のたびに振動した。老ニーロは振動するミツクチの唇の先を、一時間近くも夢中で眺めていた。マッチがなくなった時、老ニーロはワラの上に横になって、独り言を言った。若ニーロのやつ、なぜ、底なしにものを食べるのか、なぜ、切れ長の目がいつも飢えているように見えるのか分かったぞ、と。
七十九歳になった時、老ニーロは脚に不安を感じた。それでも夏が終わると、クルミの木に登って木を叩いた。しかし、こむら返りが二回起こり、一本の木を叩き終わった後、小屋まで歩いて帰る力が残ってなかったので、木の根元で横になった。木の高いところにいると、時々居眠りしては、若ニーロが高い木の上で、疲れ知らずでクルミの木を叩いている夢を見た。夢の中の若ニーロは、大天使〔天使の長、黙示録では地獄軍と戦う天使の軍の長。二枚の翼、槍を持っている〕のように力強く勇ましかった。これこそ、老ニーロが若ニーロに求めた理想像だった。清々しい朝まだき、刈り取りの済んだ畑で、ハトがくうくうと優しく鳴いて、老ニーロは目を覚ました。老ニーロは腿、ふくらはぎ、脇の下が痛くてたまらなかったが、また、木に登った。木のてっぺんまでくると、しばらく動きを止め、小鳥たちの、その日の初めての飛翔をじっと眺めていた。老ニーロの脚は、クルミの木の太い枝に危なげに固定されていたが、日が登るにつれて次第に緩んでいった。しかし、老ニーロはこのことにまだ気付いていなかった。しかし、老ニーロは虫の知らせで、自分の命の終わりを予感していた。この前、本格的な冬となり、風邪を患って治った時、これは生涯最後の風邪だ、と悟った。それから二日後、老ニーロは足に力が入らないので小屋まで歩いていくことができず、いよいよ、最期の時が来たことに気付いた。息子にはその時何も告げなかった。告げたのはずっと後になってからだった。
その年、クルミは八月の初めに実り始めた。毎朝、老ニーロは小屋の入り口に立って、クルミの実を食べるネズミトリ鳥の群を追い払っていた。この鳥は小さいが、形に似合わず、クルミをどんどん食べ尽くしてしまう強欲な鳥だ。老ニーロは当初、この鳥を大したことあるまい、と思っていたが、憎むようになってしまった。クルミ叩きの季節が到来していたが、老ニーロの足はすっかり動かなくなっていた。若ニーロは、老ニーロがズボンの裾を膝まで捲り上げて、脛(すね)を太陽に当てているところに出くわした。この時、老ニーロは、太陽だけが奇跡を起こせる、と信じていた。それを見た若ニーロは、老ニーロに言った。
「ガユイのか、父ザン」
「かゆい、かゆい」と老ニーロは言った。
若ニーロは老ニーロの上に身を屈め、さも愛おしそうに擦っていたが、擦りながら、そのまま眠ってしまうのだった。夢うつつ、若ニーロは、クルミの木の高いところで、クルミの実がぷちっと音を立てて枝から離れ、下草の上に落ちる柔らかい音を感じていた。夢の中、神様のお作りになった作物を間近で見る喜びを感じていた。しかし、毎朝老ニーロが収穫するクルミは減り、せいぜい二ダース位になった。しかも、半分は中身をクリミガとネズミトリ鳥に食い荒らされていた。
ある朝、老ニーロは、村のガキ共四人がかりでクルミの木を揺さぶっているのに出くわした。老ニーロは小屋のドアのところに出て、木の小枝を振りかざして威嚇した。子供たちは逃げて行った。
息子はワラの上で眠っていた。老ニーロは息子を起こした。
「登んなくちゃなんねえ。それしかねえ」と言った。
「登るのガイ」
「そうだ、クルミの木にだ」
「クルミのギにだって」
「ああ、そうだ」
「先生言っデダ。神ザマのヅグったもの、みんな素晴らしいんだっデ。父ザン。神ザマが、せっかくヅグったもの、壊すのはヅミだから、ボクしたくない」
「おい、聞け」。老ニーロは言った。「神様はな、汝盗むな、と教えている。あの四人のガキ共はクルミの木を揺さぶっていた。もし、今日のうち、お前が木登りして取ってくれなきゃ、収穫は十ファネガも上げられないぞ」
若ニーロは切れ長の哀れな目で、老ニーロの鼻先をじっと見ていた。
「うん。ボク登るよ。でも、その前に、司祭ザマにこのこと、言ってこなくちゃ」
十五分たって戻ってくると、無言で小枝と毛布を手にして小屋の出口のところにやってきた。父は足を引きずりながら、後ろに従った。出口の所で立ち止まった。
「ただ叩いたってだめだぞ。クルミの木にはな、叩いているのは棒切れか、愛情そのものか気付かせないように叩かないといけない」
「めちゃ叩きしていたチューチョのこと思い出してくれ」
「うん、父ザン」
「どうしても届かない枝があったら、それは残して放っておきな。時々、クルミの木は実を庇おうという気を起こすのだ。無理して取ろうとすると、クルミの木に仕返しされる。このこと忘れるな。赤ん坊猫を守る母猫と同じよ」
「ワガった、父ザン」
息子への忠告の言葉が、矢継ぎ早に老ニーロの口をついて出てきた。若ニーロはうるさそうに木の方へと遠ざかって行った。老ニーロは声を上げた。
「ニーロ!」父は呼んだ。
その声に、若ニーロは振り向いた。叩き棒のセットを右肩の上に、ばらばらに乗せていた。
「父ザン、なんだい」
「いいか、よく聞いとけ。クルミ叩くのには足が肝心だぞ、腕よりもな。これはヒミツだ。分かるか。腕力ってのは、脚力が支える以上は支えることはできない。分かるか。これ、お前だけに話しておく。他の誰にも言ったことはない」
「ワガった、父ザン」
伝えるべきことは伝えた、と満足の笑みを浮かべて、数分後、どれ、様子を見てこようと、老ニーロは足を引きずって、クルミの木の方に歩いて行った。すると、一番手前のクルミの木の下で横になり、うとうとと、うたた寝している若ニーロを見つけた。何も言わなかったが、息子の頭の下から叩き棒のセットを引っ張り出すにつれて、口元から微笑は消え、むっと顰(しか)め面になって凍りついてしまった。そよ風がコロハの香りをあたりに振り撒き、クルミの木のてっぺんまで満遍なく優しく包んだ。
老ニーロが木に登り始めた時、若ニーロは、誰かといっしょにいる、という感じがぼんやりとしていた。どうしようもない横着さで、クルミの実が下草に落ちて立てる、微かな柔らかい音を繰返し聞きながら、うたた寝どころか、すっかり寝入ってしまっていた。目蓋を持ち上げる力はなかった。クルミの枝が、めりめりと激しく軋んで折れる音と、老ニーロが地面に落ちる鈍い衝撃音をどこかで感じたが、若ニーロは動かなかった。すべての出来事は、若ニーロの世界の秩序の中では辻褄が合っていた。熟した木の実が自然に落ちるように、老ニーロも落ちていったのではないだろうか、ぼんやりとした意識の中で本能的に、そう感じた。若ニーロは右手を前に突き出した。すると、死体に触れた。本能的に一度、もう一度、ブドウの蔓(つる)のように細くなった老ニーロの足を撫でた。目を閉じたまま言った。「ガユイのか、父ザン」。しかし、返事がもらえないので、父は眠ってしまったのだ、と思った。
若ニーロは顔を空の方に向けたまま、間延びしたように微笑んだ。 終
『そよ吹く南風にまどろむ Siestas con viento sur』
ミゲル・デリーベス 著, 喜多 延鷹 訳
定価:2,200円 + 税
2020年5月21日ごろ発売予定
■ミゲル・デリーベスの本■
『赤い紙 La hoja roja』
ミゲル・デリーベス 著, 岩根 圀和 訳
四六判 / 221ページ / 上製
定価:2,136円 + 税
『エル・カミーノ(道) El camino』
ミゲル・デリーベス 著, 喜多 延鷹 訳
四六判 / 233ページ / 上製
定価:2,200円 + 税
『マリオとの五時間 Cinco horas con Mario』
ミゲル・デリーベス 著, 岩根 圀和 訳
四六判 / 261ページ / 上製
定価:2,200円 + 税
『ネズミ Las ratas』
ミゲル・デリーベス 著, 喜多 延鷹 訳
四六判 / 232ページ / 上製
定価:2,200円 + 税
『糸杉の影は長い
La sombra del ciprés es alargada』
ミゲル・デリーベス 著, 岩根 圀和 訳
四六判 / 300ページ / 上製
定価:2,500円 + 税
『落ちた王子さま
El príncipe destronado』
ミゲル・デリーベス 著, 岩根 圀和 訳
四六判 / 205ページ / 上製
定価:1,900円 + 税
■関連書籍■
『新訳 ドン・キホーテ 【前編】
Don Quixote』
セルバンテス 著, 岩根 圀和 訳
A5判 / 495ページ / 上製
定価:4,500円 + 税
『新訳 ドン・キホーテ【後編】
Don Quixote』
セルバンテス 著, 岩根 圀和 訳
A5判 / 517ページ / 上製
定価:4,500円 + 税
『アマディス・デ・ガウラ(上)
Amadís de Gaula Ⅰ』
ガルシ・ロドリゲス・デ・モンタルボ 著,
岩根 圀和 訳
A5判 / 604ページ / 上製
定価:6,500円 + 税
『アマディス・デ・ガウラ(下)
Amadís de Gaula Ⅱ』
ガルシ・ロドリゲス・デ・モンタルボ 著,
岩根 圀和 訳
A5判 / 603ページ / 上製
定価:6,500円 + 税
『エスプランディアンの武勲 続 アマディス・デ・ガウラ
Las sergas de Esplandián』
ガルシ・ロドリゲス・デ・モンタルボ 著,
岩根 圀和 訳
A5判 / 516ページ / 上製
定価:5,000円 + 税
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?