
ゲームで学び、ゲームを学ぶ(19)-「5対5」のゲーム①
今回からは「5対5」のミニゲームについて取り上げていきます。6対6から1人足りないことによって、ディフェンスにどのような負荷をかけていくのか、いくつかの具体例を挙げて説明していきます。
はじめに
これまで2対2、3対3、4対4のゲームにおいて、ゲームで学べる内容は人数によって変わることを解説してきました。ゲームで学べる内容は5対5と4対4では大きな違いはありません。しかし、6対6から人数を1人減らした状況と捉えると意義がでてきます。今回はディグ・フォーメーションに焦点をあて、解説していきたいと思います。
1.ディグ・フォーメーション(日本バレーボール学会2012)
一般的なディグ・フォーメーション(6対6)を3つ挙げます。図1は基本隊形です。図2はペリミター・フォーメーション(以降、PF)、図3はボックス・フォーメーション(以降、BF)、図4はスライド・フォーメーション(以降、SF)です。それぞれ長所と短所があります。




2.ペリミター・フォーメーションのすゝめ
PFは、トップ・レベルではほとんどのチームが採用していると言われています。リードブロックを前提に、ワン・タッチ・ボールを拾う機会が増えることを想定すると合理的だからです。しかし、トップ・レベルに限らず、どのようなレベルでもチームの選択肢として持つことをお勧めします。なぜなら、レベルを問わずに、フェイント・カバーよりもワン・タッチ・ボールやコートのライン際に落ちる強打に対する対応を優先させたい状況があるからです。PFを選択肢として持つことは、相手との攻防の駆け引きにおいても重要な意義があります。
3.人数を減らすことの意味
図5の通り、基本隊形から6番(後衛センター)を除き、前衛3人が後衛2人の5人とします。この場合、人数を減らすことがディグ・フォーメーションに及ぼす影響を解説します。図6は相手レフト攻撃に対するディグ・フォーメーションです。ここでのポイントは、5人の場合、そもそもフェイント・カバーに人を配置する余裕がなくなることです。そのため、1番および4番はBFやSFのようにフェイント・カバーの位置に動くことなく、PFのようにフェイント・カバーは配置せず、自然とライン際に落ちる強打に対する対応を優先させることに繋がります。つまり、5人にすることで自然とフェイント・カバーの配置を実現できなくなる環境になるのだと考えることができます。


4.状況判断をしてフェイントに対応する重要性
攻防は相手に対処して、いかに優位に立てるかです。例えば、打ち合い勝負になり、強打やワン・タッチ・ボールが繋がらない場合はBFもしくはSFは合理的ではありません。その場合、PFで対応する必要があります。ただし、PFで対応できた場合、相手が更に対応してフェイントしてくる場合があります。この時、その後の展開が2通りに分かれます。PFから状況に応じてフェイントに対応できれば、相手はそれ以上打つ手がなくなり、駆け引きでは先手を取れます。一方、フェイントに対応できなければ、再度BFもしくはSFでの対応を迫られ、駆け引きでは後手に回り、優位に立てません。この勝負の分かれ目は、PFから状況に応じてフェイントが取れるかどうかです。
つまり、ディグ・フォーメーションにおいて、優位に立ちたいのであれば、結果的にはフェイントに対する事前配置的な対応ではなく、状況判断的な対応が求められることを意味します。このことは意図的にトレーニングしないと身に付きません。6人であれば、なおさら意識的にPFからのフェイント対応をトレーニングしないと攻防の選択肢になりえません。
このように5人にすると、6人と比べて人数的な余裕をなくすことで、6人でいるときよりもかえって状況判断的な対応が実現しやすい環境をつくることができます。次回は他の5人の組み合わせからゲームで学べる環境を解説していきたいと思います。
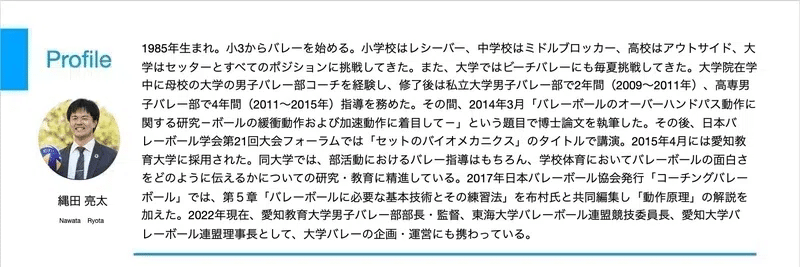
いいなと思ったら応援しよう!

