
【読書録】大好きなほんを探して⑧(2021.8)
日々の読書、ああ今月はあんまり読めなかったなあ、と思ってたら月末になんかめちゃくちゃ加速したりする。
薄い本を読んでたというのもあるけど、なんかうまいこと読書のための時間が一日のなかにすとんと当てはまってけっこういろいろ読める。
毎月そういう感じだといい。
①『情報を正しく選択するための認知バイアス事典』高橋昌一郎監修

「認知バイアス」というものには興味をもってて、やっぱり自分だけでものを考えててもどんどん自分の中の深みにはまっていっているだけでしかないという感覚になるときはあって、そういう時に自分が沈んでいってるのとは違う視点でものを考えられるヒントをくれるのが「認知バイアス」という視点だと思ってた。
大学のテキストとして使われることも想定しているらしく、各トピック4ページで均等にまとまっているかたち。確かに教科書っぽく見える。
「論理学的」「認知科学的」「社会心理学的」アプローチの順に項目がまとまってて、個人的には後ろに行くほど関心が近い。
記述は網羅的というよりは具体例をできるだけ挙げて、可能な範囲で実感を伴ってそれぞれの項目を理解できるように工夫されている感じ。なので広く浅く、というとこなんだろうか。
「システム正当化理論」とかシステム正当化バイアスみたいな話ははじめて聞いた時からおもしろいと思ってたし、やっぱり今回読んでもおもしろい。
「賢馬ハンス効果」とか「フォルス・メモリ」みたいなものは知らなかった。こっちの熱狂的な思い込み。本当はどこにもない記憶。そういう渦の中にいるときはその渦の中にいることしかできない。渦の中から一歩身を引いて、どんな渦が自分を取り巻いているのか、それを見たい時に開きたい。
②地方でクリエイティブな仕事をする 笠原徹
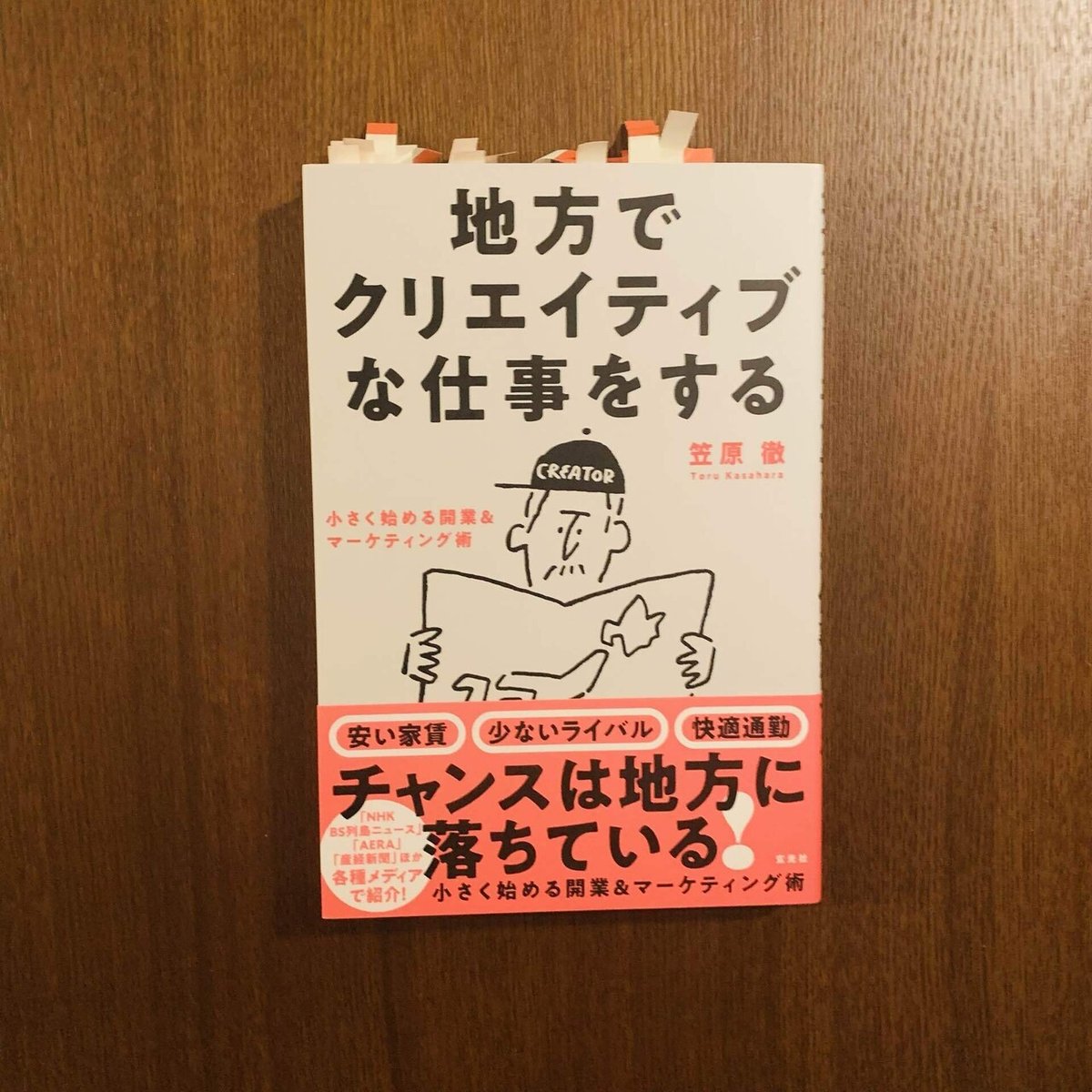
佐賀で写真館を開いた笠原さんという写真家の著書。
東京でしかやれないことって、ほんとうにあるのか、みたいなことに最近関心がある。
東京と地方はどう違うのか、質的にどう異なるのか。
これについて語り出すともう何万字かかるかわからないけど、東京に自分が求めてきたこと、地方でこれまで存在してきたいろいろなクリエイティブなこと、これを整理しないと自分はこれから先に進めないんじゃないか、そういう気持ちがけっこう強くあって、この本をそのときに見つけて、ドンピシャで読んでみたいタイトルだったのでamazonでポチる。
そもそも「地方」と一括りにすることにどのくらい有効性があるのかも疑わざるを得ない気はするけど、同じような気持ちを抱いている人には元気がでるような本だったと思う。
笠原さんという人が佐賀で、写真館を開くまでは決して順調な道を歩いてきた訳ではなくて、色んな道のりを経て、苦労もされて、試行錯誤をしてきて、色んなひとに愛される写真館を開いてきた。
そういう、「求められる」ことをやりながら「クリエイティブ」なことをやる、いわばサスティナブルなクリエイティブ・ワークの実現のための指南書だ。
現実にどういうことを考えて、どんなふうに動けばよいのか、ということが語られているからぐんぐん読める。興味が尽きない。もっと長くてもよかったんじゃないか。
笠原さんという人の苦労を読んで、なんだか勇気が湧く、自分も頑張れるんじゃないか、みたいな気持ちになれる。
表紙の長場雄さんの絵もとてもよくて、それだけで気になるのも本としてよかった。
③鳥がぼくらは祈り、 島口大樹

群像新人文学賞受賞作。
これが載ってる号は持ってるけど、本屋さんで見かけてああ、単行本化したんだと思って、しかも装幀がなんかけっこういい。それで買ってみた。
純粋に面白くて、どんどん読んでしまった。分量のわりに読んでいる体感時間は長い。
各々の理由はどうあれぼくらは住み飽きていい思い出もとくにないこの土地でただのらりくらりしているだけで鬱憤が溜まるというか、ただ日々をやり過ごしていくだけの日々に摩耗してしまって、詰まるところ何かしら欠如したぼくらは、いや誰もが欠如を抱えながら生きているのだろうが、それに後ろ髪を引かれ続けて自分が今立っている場所も未来も正しいかたちで見ることのできないぼくらは、……(後略)(p.19)
独得の文体はうねうねしていて、それだけでなくて荒涼としている。地方都市、東京からはさほど遠くないけれど、その影響は及んでいない、鬱屈とした地方都市で暮らす10代の荒涼としたきもち。それは確かにこんな感じだったと思えなくもない、と思った。いや、むしろこの文体に、自分の10台が引っ張られているのか。
視点がいつのまにかくるくる代わり、行と行とを跨いで感情が切れ切れに移っていく。それが新鮮でおもしろい。
最後の一行、最後のシーンまでぐんぐん読める。おもしろかった!
④カフカ式練習帳 保坂和志

今月のHOSAKA①。
断片が断片につながる、謎(?)の文章。
カフカの日記の断片がおもしろくて、そういうのを書いたものということ。
いっこいっこの連続性に意味を見出そうとしてもあんまりうまくいかない。本全体で共通する人物やキャラクターを見つけようとしてもあまり意味を感じない。それはたぶん、作品の構成要素が基本的に完全に断片で、そのそれぞれの断片のなかでこそ、人物やキャラクターの一回性が生きているからなんじゃないだろうか。
断片ごとに目を落として、連続して読んでいくとおもしろい。そこに意味みたいなものがどう生まれてくるのか、それを追っかけるような感じも持ちつつ、ただただ交錯する断片の流れに身を任せるのが心地いい。
個人的には磯崎憲一郎が保坂和志の解説を書いたらそこに新しい発見があるはずがないというか……もう、それは綾部が又吉の解説を書くようなものじゃん、と思って初めからあまり面白くないような気になってしまう。
楽屋落ちを見せてくれるのはいいんだけど、僕はもっと大貫妙子が「この人の閾」に寄せたような解説が読みたい。そうしないと保坂ワールドが僕の中で意外性をもって広がっていってくれない。
⑤抱擁家族 小島信夫

来たよこれはやばかったよ。欲しい欲しいと思っててどこにも売ってなくて吉祥寺パルコのブックパークで売ってたよ。泣
もうこれはなんか、冒頭からお尻まで完全にやばいじゃん。抱擁家族がなんだったのかわかんないけど、タイトルが「抱擁家族」であることによって絶妙な温度があるじゃん。
明言されて、全体としてこういう話だった、というより、家族の一時期をトリミングしたような感じだったのかと今になって思う。はじめとおわり、その二つの時間軸上の点をもってきっちり区切られるそういうものではなくて、はじめとおわりの前後に広大な時間を続いていることが明らかで、それがリアルだ。
時子に俊介はどうしてあげられたのか。逆はどうだったのか。深刻なストーリーが喜劇的に語り上げられるその「味」にはもうすっかり魅せられる。
「馬」にすっかりやられて以来、小島信夫読みてえ~~モードだったけどここまで読んでませんでした。ほかのもよも。
⑥文体の舵をとれ ル=グウィンの小説教室 アーシュラ・K・ル=グウィン 大久保ゆう訳

ツイッターで話題だった本。厚さの割に本文の組は余裕があって、そんなに苦じゃない。
ル=グウィンが設定した10のテーマが解説されて、そのあとに練習問題や合評会での取り上げ方が説明される。だから一人で黙々と「文体の舵をとる」のもいいけど、作者の意図としてはみんなで合評会やってガンガン活用してもらいたかったんじゃないかな。
冒頭と最後の「自分の文のひびき」「詰め込みと跳躍」みたいに、感覚的なところをしっかりおさえてくれるのが嬉しい。
素直な感想を言えば、文章を上達させるには年始に読んだスティーブン・キングの「書くことについて」のほうが参考になった。こっちはもうちょっとやさしめなイメージ。
章立ては明快だし、なにより装幀が可愛くて、本として「持っていてうれしい」のはこっちなんだけどね。
⑦売文生活 日垣隆

これもツイッターで見かけたもの。古いちくま新書なんて、よっぽどじゃなければ書店になくて、amazonで1円で購入した。1円……。
「原稿料」というのは、個人的にもいろいろ考えているけど、やっぱり相場はまちまちで、支払時期もちょっと遅くて、そう考えると作家やライターは企業である出版社にいる編集者の下請けでしかない、そんな気持ちがよぎるとき僕はうんざりする。だって、本質的には立場はまるっきり逆のはずだからだ。生み出す方が優位であるべきにきまっている。
その「下請け」の作家たちはどんな原稿料・印税生活を送って来たのか。……いや、けっこう儲けてるんかい!!!!
というツッコミを要所要所にはさみたくなる痛快な「売文」物語だ。
日垣隆の文章はところどころでやりすぎていて、確かにちょっと「んん……」となるところがなくはないけれど、別にそれで質が落ちているわけではないと思う。文豪たちや、さいきんの文筆家がどういう経済状況にあったのか、あるのか。文筆業というのはロマンだと僕はやっぱりどうしても思ってしまうし、たぶん世間的にもそうで、だからこそお金の話みたいな、実務的な部分が浮き上がってこないふしがある。それを軽妙な筆致で読み物として伝えているこの本はすごくおもしろい。筒井さんの白熱する執筆の様子も、すごい。
⑧限りなく透明に近いブルー 村上龍

この小説を知ったのはやっぱりLUNA SEAだった。LUNA SEAがすきな小説、というイメージだけをもったまま何年も経って、あるとき実家の本棚にこれがあるのを見つけて、そのうち読もうと思って東京に勝手に持ってきてからもう4年ぐらい経っている。
さいしょの1ページだけをチラ見して,やっぱり読むのをやめる、というのをたぶん4、5回はやったんじゃないか。それで東京にきてからもずっと本棚に入ったままだった。誰かが言ってたけど、積まないで本棚にしまった本は「本棚」になってしまうから読まない,というのは本当にその通りだと思った。読みたい本は本棚にいれずに詰んでおく必要がある。
それで、でも村上龍、そろそろ一冊読みたいな、と思った時に家にはこれがあって読んだ。
そしたらすごい。
もうむちゃくちゃだ。起きてることがむちゃくちゃだ。なのにそこにある心象風景がありありとわかる。
ドラッグとセックスの小説とだけ言えばなんだかもはやあり体な印象も受けるんだけど、ドライな文体がかえって抒情的でいい。トマト畑に突っ込むところが好きだ。
しかも1976年初版で、僕が知っている1976年というのは、GSが流行って、ヒッピーがいて、浅間山荘みたいなきな臭い事件が起きる、そういう時期が終わって、それからピンクレディーみたいなのが出てくるまでの時期で、テレビで見るその頃を振り返る映像がほんのすこし綺麗になるような、はざまの時期だ。
その時期のイメージを、新たに僕に根付かせるような話だった。けっして一般的なできごとが語られているわけではないけど。なんかよくわかんないけど、いまの若者が1970年代を想像するときのイメージからは違和感がない。
どことなく都会の話のような気がするけど、これは福生の話だ。福生は田舎だと思う。そこにだけリアリティを得られなくて、おかしかった。
⑨銃 中村文則

「限りなく透明に近いブルー」を読んだらなんだか「銃」を読みたくなった。
どっちも新人賞受賞作というくらいしか共通項ない気がするけどなんか読みたくなった。この人は本棚に突っ込まないでその辺の棚に積んでおいたので、やっぱり本棚に入れとかない方がいい。わたしの本棚では「ナウシカ」の漫画とかが眠り続けています。
最初に目を通したのはたぶん半年くらい前で、ぱらぱらめくって、なんと言っても冒頭の書き出しがいいんだけど、その後の展開がなんだかぎこちないなあと思って数ページでやめてた。
今回、あらためて全編読み通して、ふつうに「掏摸」につながるし、なんならほとんど空気感がいっしょだ、と思った。ちょこちょこ、あんまり好みじゃない気がする言い回しはあったけど、それは、そういう中村文則文体への反応は、掏摸のときもそうだったし、嫌いではないのでたぶんほかの作品読んでくうちにすぐ好きになる。
150ページくらいかけてハラハラしていって、最後にいきなり散る感じ、そのあっけなさと最後数ページのなさけなさが、意外や意外で、それまでの丁寧で、どちらかといえば重厚な語り口をまったく裏切る。
え!これだけ?! こうなるだけ?! みたいな。
そのあっけなさが、これはすごい!いい! って感じだった。
当時の選考委員の、警官の描き方とかに問題はある、というのには同感で、そこは読後も気になったけど、でもこれ、全体を楽しく読むには充分すぎる感じを受けた。
わたし、「掏摸」より「銃」派です。装丁、新潮文庫の方がいい気もする。
9月はすでに保坂「アウトブリード」などを読んだ。保坂本をアマゾンで中古でポチるのが好きだ。なんかテンションあがる。
ちなみに「売文生活」はワクチン2回目打ったあとで寝てる時に読んだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
