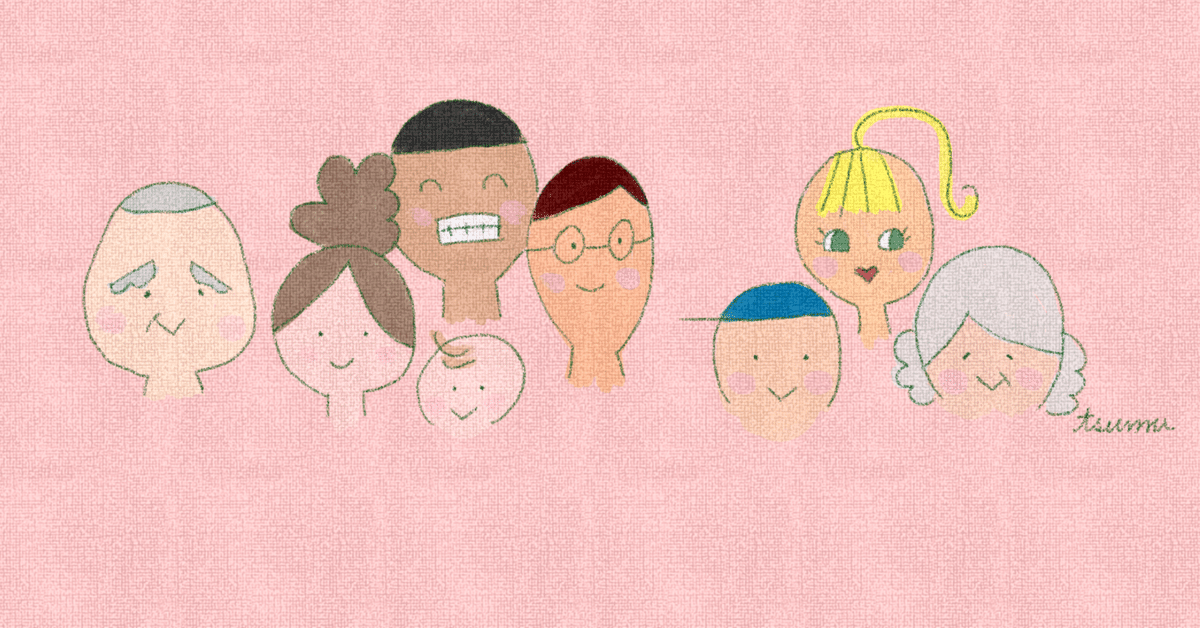
【小説】恋の幻想
私たちは本当の意味では、家族を知らなかったのかも知れない、私はそう思って裕子さんを見つめた。
裕子さんの家族は彼女に興味を示さないと聞いた、良平の家族は早くに亡くなっている。
その意味では、3人とも同じような立場なのかも知れない、私達だけでは無い、人間全てが親とは離れて居たり、いつか疎遠になるのかも知れない。
きっと死ぬまで親や親族と仲良く暮らしました、なんておとぎ話はごく少数なのだろう。
家族って生まれた所が如何とか、親子として認めて貰っているからでは無いんだ、共有する気持ちが有ればいいんだ。
「忍ちゃんはね、妹だったり娘だったり友達だったり、全てを与えてくれたんだよね。」裕子さんの中の家族に成っていたのだろう。
「俺もね、忍を最初に見た時には、妹だったり娘だったりしたよ、直ぐにそうじゃ無くなったけどな。」良平にもあった時から家族だったんだ。
「今でもその感覚だったら変態じゃん、そんなの嫌だわ。」嬉しそうに裕子さんが答える。
何時から恋人になったのかな?ちらと思いながらも、恋人よりも家族に成りたかった自分が居る。
「私、妹だったり、娘だったりしたの?あの時にはちゃんと大人だったんだけど。」少し拗ねた気持ちになって言う事にする。
「拗ねないで、私に中では今でも感覚は変わってないよ、だから良平と結婚するのは大賛成だったんだから。」裕子さんが続ける。
「良平もね、家族って感覚だから、つい来てしまうんだよね、お兄さんていうか、お父さんて言うか。」裕子さんの気持が分かる、恋人では無いけどずっと居たい人なんだよね、良平は。
「俺って父親役なの?年一緒なんだけどな、そこまで老けてないんじゃないか。」今度は良平が拗ねる番だ。
「雰囲気がね、お父さんだったりするんじゃ無いの、ほら落ち着きすぎているから。」私が答える。
そこでフフフ、と3人で笑いながら、言葉を紡いでゆく、細い糸だった言葉が編みこまれて、一つの作品に成るまで時間を掛け乍ら。
親が何か命令してきたり、人生に問題は有るけど、そんな問題は乗り越えてしまえ。
親とは疎遠になっても、良平と裕子さんは家族だった、最初に会った時から、ここに連れてきてもらった時から、3人が家族なんだ。
私も親族とは離れても、家族に成ってくれる人が居るんだ、若しかしたら偶々親子になってしまった親族よりも、自分で紡ぐこの糸の方が強いのかも知れない。
私たちは喧嘩しながらも、家族であり続けるんだろうな、そう考えながら私は新しい生活に向かっている。
いいなと思ったら応援しよう!

