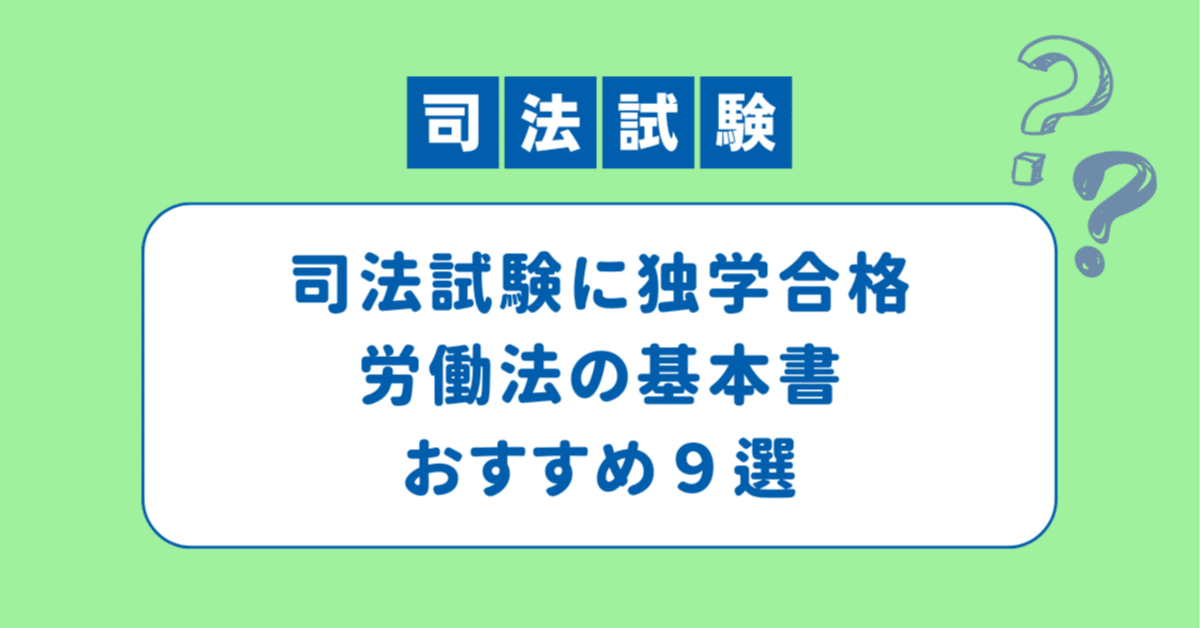
【司法試験】労働法のおすすめ基本書9選
この記事では、司法試験に一発合格した弁護士である筆者が、おすすめ労働法のテキスト・基本書について解説していきます。
労働法は選択科目のひとつであるため、受験生の学習時間が圧倒的に少ないという特徴があります。その割に重要な判例が多く、「この判例知らない」が致命傷になりかねない科目なのです。
上記3行まで読んで、「やっぱ労働法選択やめようかな・・・」と思った方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、そんなあなたに声を大にしてお伝えしたいのは、・・・
「あなたも労働者になる可能性が高い!」
ということです。
労働法というのは、社会に出て働くために必須の知識です。
・上司に残業代は出ないと言われた
・残った仕事は自宅に持ち帰ってやれと指示されている
・給料の減額に応じない場合には退職してもらうと言われた
・育休から戻ったらきつい業務の部署に飛ばされた 等々。
これらの問題を解決するためには、労働法の知識が絶対に必要となります。
社会人として組織に所属して勤務する場合、長い目で見れば身に着けた労働法の知識は、あなたを守る「鋼鉄の鎧(よろい)」となるかもしれません。
以下目次で一覧がわかるようにしておりますので、気になるものがある場合には、ぜひチェックしてみてください。
参考までに、Amazonの広告リンクを掲載しておりますので、チェックしてみてください。
1.労働法の勉強方法について
労働法の学習は、判例の学習と言っても過言ではありません。
そのため、できるだけ早くテキストを通読して、または並行して判例の学習に時間を割かなければなりません。
そのため、
・配置転換といえば?→「東亜ペイント事件」!
・賃金請求権の放棄とくれば?→「シンガー・ソーイング・メシーン事件」
という風に、瞬時に判例規範が出てくるのが理想です(あくまで理想です)。
試験問題のモデルになった判例とその判例規範が頭に浮かべば、勝利は目前です。
そのためにも、やはり、判例の規範をまとめたり要約したりして、自分のものにする訓練を少ない時間の中で効率的に行う必要があるでしょう。
私個人としては、比較的短期間で読める基本書(後掲「リーガルクエスト」等)で全体像を把握して、「重要判例200」の各判例の規範を付箋にメモしてまとめていくという作業を行っていました。
最終的には、試験直前はその付箋のメモを復習しながら、判例規範を自力で再現できるように練習していました。
2.おすすめの労働法のテキストについて
最初にお伝えしておきますが、以下の①~③のテキストについては、どれか1冊を手元に置いておけばよいと思います。
①『労働法 第13版』:菅野和夫 → 発売日2024/4/11
②『労働法〔第10版〕』:水町勇一郎 →発売日2024/3/25
③『労働法〔第5版〕』:荒木尚志 →発売日2022/12/25
いずれも学部やロースクールで教科書として指定される定番の基本書で、どれも最近、改訂されているため、お好きな1冊について、読み進めていくことが大切です。
①~③の基本書は、ぜひ書店でお手に取ってみてください。その分厚さに圧倒されると思います。そのため、短期間の通読には向かないかもしれませんが、労働法の体系的な学習のためには必携だと思います。
①『労働法 第13版』:菅野和夫
労働法の定番のテキストといえば、菅野先生の「労働法 第13版」でしょう。
労働事件を積極的に受任している弁護士の本棚には、本書が待機している印象で、実務家であれば持っておきたい1冊です。
ただ、そうはいっても初学者の方が、読みやすいというものではありません。
他のテキストと比較しても圧倒的な情報量です。
しかし、他のテキストを通読してわからなかった場合には、まずは本書を確認することで解決することも少なくないはずです。
2024年4月11日に改訂版が出ているため、多数の法改正・新法、重要判例等もフォローされています。
②『労働法〔第10版〕』:水町勇一郎
続いて、こちらも定番の基本書、水町先生の「労働法[第10版]」です。
本書の特徴は、具体的な事例・ケーススタディーがあることです。
事例を通じて重要判例の理解を深めることができるため、実務や問題演習には非常に有益でしょう。
また、菅野先生のテキスト①と同様2024年に改訂版が出版されており、さら①の半分程度の値段であるため、比較的購入しやすいのではないかと思います。
③『労働法〔第5版〕』:荒木尚志
荒木先生の「労働法[第5版]」は、水町先生のテキスト②より情報量が多く、菅野先生のテキスト①よりは少ないといった印象です。
本書も2022年に改訂されているため、育児介護休業法や職業安定法などの改正や、有期雇用者に関する判例についてフォローされています。
④労働法 第4版 (リーガルクエスト):両角道代,森戸英幸,小西康之,梶川敦子,水町勇一郎
私個人としては、これから労働法を勉強し始めるという初学者の方は、リーガルクエストの「労働法 第4版」が良いのではないかと思います。
リーガルクエストシリーズは、コンパクトながら要点を抑えた丁寧な解説で、通読のしやすさに定評があります。なにより学者や実務家向けというよりは、学部やロースクールで労働法を勉強する学生向けに書かれている点がおすすめポイントです。
実際、リーガルクエストと判例集を丁寧に学習をすれば、司法試験レベルの労働法の問題は解けるのではないかとすら思います。
とりわけ、短時間で労働法の全体像を把握したい・判例解釈論を抑えたいという方は、リーガルクエストでも十分その目的は達せられるのではないかと思います。
⑤ベーシック労働法〔第9版〕 (有斐閣アルマ):浜村彰、唐津博、青野覚、奥田香子
⑥労働法 第6版 (有斐閣アルマ):浅倉むつ子、島田陽一、盛誠吾
初学者の方が、労働法の全体像を短期間でとらえたいという場合には、有斐閣のアルマシリーズ⑤⑥も良いと思います。
「労働法 第6版」は、改訂が2020年と他のテキストよりは古くなりつつありますが、コンパクトかつ要点がまとまっているという点は、リーガルクエストに引けを取らないと思います。
さらに、アルマシリーズのサイズは四六版(シロクバン)といって、他のテキストよりも一回り小ぶりである点も、持ち運びに非常に便利です。
⑦『プレップ労働法 第7版 (プレップシリーズ)』:森戸英幸
また、プレップシリーズの「プレップ労働法 第7版」を愛用している受験生の同期もいました。
プレップ労働法は、これから労働法を学び始める学生や社会人に向けて、手っ取り早く知識が必要な方向けの1冊であると紹介されています。
確かに、全体の記述としては、薄くなっているところもありますが、第7版は、2023年に改訂されています。高齢者雇用安定法や育児介護休業法、パワハラ防止法などの近年の重要な改正についてもフォローされてるため、最初に読破する1冊としては最適でしょう。
3.判例集、その他副読本
⑧最新重要判例200労働法[労働法] 第8版:大内伸哉
「最新重要判例200」の特徴は、掲載されている判例の量が多いということと、1つの事件の概要・判旨・解説が「見開きの半分」に収まっているため、学習しやすい(規範をまとめやすい)という点です。
そして、本書は非常に頻繁に改訂されているため(第8版は2024年に改訂されています)、最新の判例を学習し損なうリスクを回避することができます。
まだ、労働法の判例集を持っていないという方は、この200選をおすすめします。
労働法の司法試験においては、出題されている問題の「モデルとなっている判例が頭に浮かべば勝ち」です。本書で判例の事案と判示をさらに、コンパクトにまとめた論証を付箋等にまとめて暗記しておけば、現場でスムーズに答案を組み立てることができます。
⑨労働判例百選〔第10版〕別冊ジュリスト第257:村中孝史, 荒木尚志
判例百選を利用している方は多いと思いますので、こちらもおすすめしておきます。
大前提として、判例百選で紹介されている判例については、どれが出題されても文句は言えないと考えておきましょう(解説に出てくる裁判例も含む)。
2022年に改訂されているため、比較的近年の重要判例についてもフォローされているため、すでに百選を持っているという方は、これをベースに学習を進めていくと良いと思います。
まとめ
今回は、司法試験の労働法の学習に必要な、おすすめテキスト9選をご紹介しました。あくまで、「これから学習を始めようと思っている」方向けの記事でした。
現在の日本で強く生き抜くためには、労働法の正しい知識が大切になるかもしれません。長い人生で「勉強したことが無駄になる」などということはありませんので、頑張っていきましょう。
労働法などの選択科目は、「まとめてやる」よりも、「ちょこちょこやる」方が良いと思います。私自身も、一度忘れてまた思い出す作業を何度も繰り返していました。
それでは、皆様の健闘をお祈りしております。
最後まで、読んでくれてありがとうございました。それではまた。
