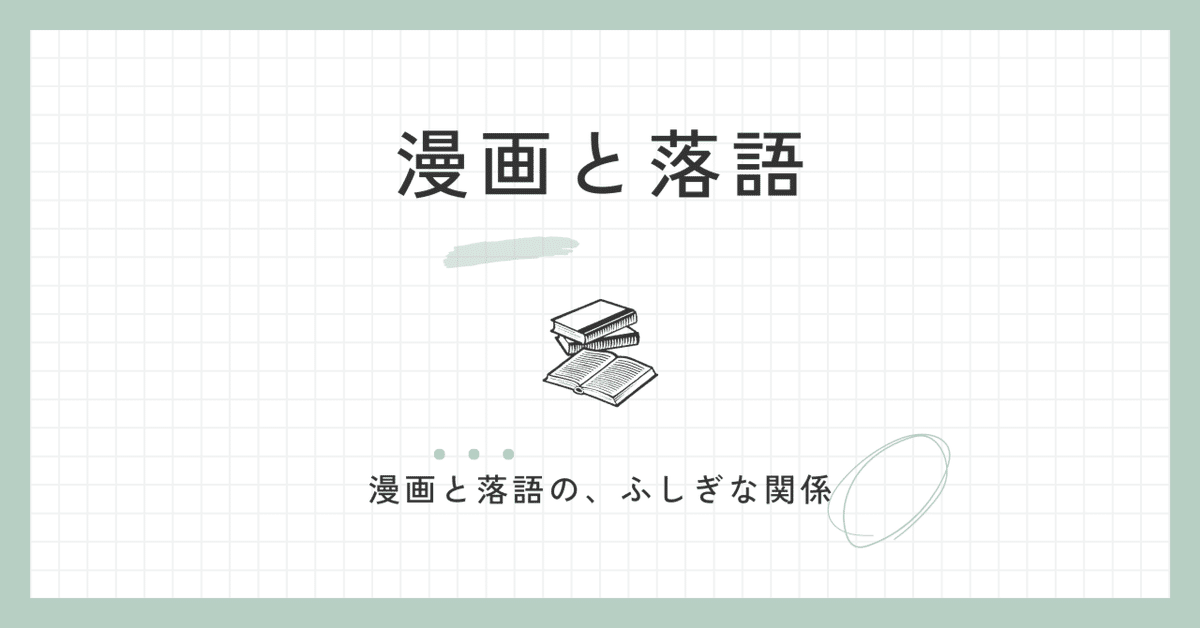
漫画と落語:田河水泡『のらくろ』 5
「落語作家」を生んだ明治深川の大衆演芸事情
1905(明治38)年、仲太郎は小学校へあがり、伯父の知り合いが校長を務める私立の金生堂小学校(現在の永代二丁目あたり)へ通うようになる。金生堂はもとは寺子屋だったが、明治維新後に新政府が学制を整えた際に、校舎数の不足を補うために小学校へと改められたものである。
仲太郎が入学した年に百年祭を迎えたので、創立は文化年間、11代将軍・徳川家斉の治世下ということになる。ところが、この金生堂小学校は百年祭ののちに不審火で全焼してしまい、仲太郎は新設されたばかりの深川区立臨海尋常小学校(現在の江東区臨海小学校)へ転入することになった。
この当時、臨海小学校の表門には仲町の大通りがあり、入口には「桜館」という講談の寄席があった。六代目三遊亭圓生は「桜館」について次のように記憶していた。
ただいまでは、永代二丁目となりましたが、以前は黒江町といった、その市電の停留場のすぐそば、こっちから行って右がわの表どおりにあった席で、はじめは浪花節の席だった。それがのちに色物席になったわけですが、場所がらもいいんでしょうか、大変お客が来まして、まず深川では、この桜館というのが、いちばんお客さまが来たように思います。

同書は1977(昭和52)年に刊行された圓生の語り下ろしで、関東大震災(1923)や戦時中の空襲(1944〜1945)で焼失する前の東京の寄席事情を記録している。
同書では、1921(大正10)年の雑誌「寄席」の東京寄席案内から引用し、当時の東京15区には約90軒、郡部には約40軒、あわせて130軒あまりの寄席があったと記している。現在の都内には、落語の定席の寄席は4軒(上野鈴本演芸場、新宿末廣亭、浅草演芸ホール、池袋演芸場)しかないことを考えると、現在とはかなり事情が異なる。関東大震災後の大正末期には180軒を超えていたという。
仲太郎の育った深川界隈は、日常の風景に大衆演芸が溶け込んでいた。仲太郎は学校からの帰り道、「桜館」から講釈師の叩く張り扇の音が聞こえていたと記憶している。「桜館」の隣には「深川座」、中洲に「真砂座」とあり、仲太郎は吉富町(現在の永代一丁目)の「吉富座」に足繁く通った。というのも、客寄せのために人力車で太鼓を叩きながらビラを撒く際に、タダ券や半額券の札を一緒に配っていたので、下町の子供にとって寄席は格好の遊び場だったのである。
家に帰ればご隠居のような伯父がいて、町には寄席がある。仲太郎の育った環境は、まさしく落語の世界そのものであった。
小僧時代と立川文庫
藤助伯父の家には、10歳年上の従兄弟の高見澤遠治がよく出入りしていた。油絵の勉強をしていた遠治は、かすりの着物に絵具箱やキャンバスを携え、伯父に油絵を見せによく訪れていたという。
この高見澤遠治こそ、のちに仲太郎に大きな影響を及ぼす人物なのだが、それについては後述するとして、仲太郎はこの遠治の姿を羨望の眼差しで眺めていた。「俺も絵描きになりたい」という将来への夢が、幼い仲太郎の胸に生まれる。
1911(明治44)年、仲太郎が尋常小学校を卒業する2年前に藤助伯父は亡くなっており、尋常小学校を卒業した仲太郎は、旧制中学へ進学することなく、親戚の経営する薬屋へと奉公に出された。住み込みで商店の使い走りをする年少の使用人、いわゆる「小僧」(関西では「丁稚」)となったのである。とはいえ、奉公先は伯母の家の隣なので、さほど環境的な変化はなかったようだ。
もとより学業の道に進む気のなかった仲太郎は、伯母が取り寄せてくれた中学講義録や「日本少年」(実業之日本社)を店番しながら読んでいた。仲太郎は、笑話をつくって「日本少年」に投稿し、それが採用されたことがあり、会う人ごとにそれを見せびらかして喜んだという。この小さな成功体験が、のちに落語作家となる素地のひとつとなったのかもしれない。
薬屋での奉公は3年ほど続くが、この時期に世間で大流行したのが立川文庫だ。立川文庫とは、大阪の立川文明堂が発行した少年向けの娯楽読み物シリーズである。
立川文庫は『水戸黄門』や『真田幸村』といった講談の筋を題材として扱ったが、立川文庫がエポックだったのは、文体にある。それまで講談を題材にした読み物は速記本が主流であったが、立川文庫では「書き講談」という、口述に似せた文体を用いた。
落語は会話の連続が主であるのに対し、講談は地の文(ト書き)が多いので、活字にするのに向いていたのだろう。この立川文庫のブームもあって、講談の読み物のメインストリームは速記本から「書き講談」へとシフトしていく。なかでも人気があったのは真田十勇士が活躍するもので、1914(大正3)年に出版された『猿飛佐助』は、立川文庫の名を一躍メジャーに押し上げるほどのヒット作となった。
また、立川文庫は販売方法に独自のシステムを採用していた。価格は二十五~三十銭程度だったが、読み古した本を書店に持っていくと、その古本に三銭追加するだけで新刊と交換できたのである。文庫サイズは着物の懐に忍ばせるのに最適であり、なおかつ安価ということもあって、立川文庫は小僧や丁稚の娯楽として愛好された。
仲太郎もご多分に漏れず立川文庫に手を出し、道を歩きながら読むほど熱中したが、彼はもっぱら貸本屋を利用したようだ。この当時の貸本の代金は1冊二銭で、本を返すときに一銭返金された。最初の二銭のうち一銭は保証金のようなものだ。PASMOやSuicaなどの交通系ICカードはカード返還時に500円の保証金が戻ってくるが、そうしたデポジット制度が貸本屋にもあったわけである。
落語と言文一致運動
仲太郎は立川文庫と同様に、落語集もよく読んだ。まだ小学校を出たばかりだったが、 心中ものや廓噺などの大人向けの噺もこの時期に知る。
ここで落語集の歴史について触れておきたい。大正に入った頃には、すでに数多くの落語集が発行されるようになっていた。
その嚆矢となったのが、1884(明治17)年7月から12月にかけて東京稗史出版社から出版された『怪談牡丹灯籠』である。これは初代三遊亭圓朝の創作した落語「牡丹灯籠」の口演を書き取った速記本だ。三遊亭圓朝は、幕末から明治にかけて活躍し、「落語中興の祖」と評される大名人である。「真景累ヶ淵」や「牡丹灯籠」といった現在まで伝わる大根多は、圓朝の手によって創作されたと伝えられている。
速記を手がけた若林玵蔵は、のち1890(明治23)年に帝国議会が開設されると議会速記を担うようになる、日本における速記のパイオニアだ。はじめて若林の速記を読んだ圓朝は「これは声の写真か」と驚いたという。
翌1885(明治18)年2月、合本された再販版の『怪談牡丹灯籠』が刊行された。これには序文が付け加えられており、「春のやおぼろ しるす」と記名されている。「春のやおぼろ」とは「春廼舎朧」のことであり、坪内逍遙の雅号である。
このとき逍遥は、圓朝とは面識はなかったらしい。
圓朝の速記本は日本の近代文学にも寄与した、とされている。それというのも、明治期の文壇にとって喫緊の問題は、文体の確立であった。口語と文語が大きく乖離していた状態を是正するため、より話し言葉に近い文体(口語体)を生成する必要に迫られていた。いわゆる「言文一致運動」だ。
言文一致運動の端緒は、二葉亭四迷の長編小説『浮雲』とされる。『浮雲』が刊行されたのは1887(明治20)年のことで、のち1906(明治39)年に書いた『余が言文一致の由來』のなかでは、以下のように述べている。
坪内先生の許へ行つて、何うしたらよからうかと話して見ると、君は圓朝の落語を知つてゐよう、あの圓朝の落語通りに書いて見たら何うかといふ。
坪内逍遥から「圓朝の落語通りに書いてみたら」とアドバイスされたとあり、言文一致の文体は圓朝の速記本を参考にしたと考えられているようだ。
しかし、それに先立つ1897(明治30)年のインタビュー(『唾玉集』に収録)では、「一体『浮雲』の文章は殆ど人真似なので、先ず第一回は三馬と饗庭さん(竹の舎)のと、八文字屋のものを真似てかいたのですよ」と話している。
三馬というのは江戸時代後期に活躍した戯作者の式亭三馬のことで、『浮世床』や『浮世風呂』などの滑稽本の作者として知られる。
三馬の名前は『余が言文一致の由來』にも出てきており、「僅かに参考にしたものは、式亭三馬の作中にある所謂深川言葉といふ奴だ」と記している。
こうした事例をあわせると、実際に落語の速記本が言文一致にどの程度の影響を及ぼしたかは定かではないが、現在では「江戸弁」と称される下町言葉を「深川言葉」と称しているところは興味深い。
速記本の利点は、イメージの喚起力にある。演者独自の言い回しや口癖までも活字で再現されると、その演者の高座に足を運んだ経験がある読者であれば、その高座をまざまざと頭のなかに思い浮かべることが可能だ。
速記本の誕生によって、寄席でしか楽しめなかった話芸の落語は、「読む」楽しみ方を獲得した。それまで一部の都市圏のみの娯楽だった落語が、全国的に普及していく可能性を手に入れた瞬間であった。
娯楽スタイルの変遷
ここで時代の流れを整理しておく。
落語の速記本が誕生し、言文一致運動が進み、「話芸を活字で読む」という娯楽スタイルは講談にも飛び火し、弁論雑誌を出版していた大日本雄辯会は、1911(明治44)年、講談速記を中心とする文芸雑誌「講談倶楽部」を創刊した。この大日本雄辯会は、のちに「大日本雄辯会講談社」と改称し、これが現在の「講談社」となる。
落語や講談は、速記本の影響で、「演者を知らずに読み物として筋を読む読者」という、新しい顧客層とニーズを生んだ。
そして、口語をそのまま活かした速記本の形式から、書き言葉として洗練された「書き講談」が生まれ、立川文庫のブームへとつながった。
こうした出版が大衆化する流れを肌で感じながら、仲太郎は大衆演芸の古典をその身の内に蓄積していった。いわば「作家・田河水泡」の揺籃期であった。
いいなと思ったら応援しよう!

