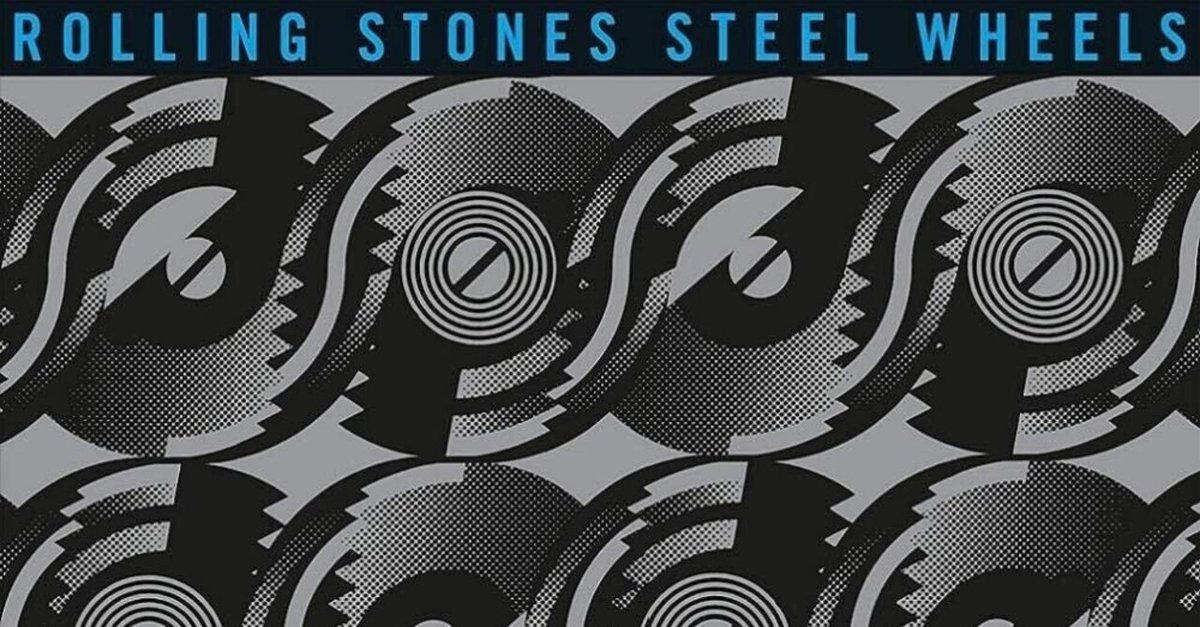
ザ・ローリング・ストーンズ スティール・ホイールズ① アルバムレビュー
「スティッキー・フィンガーズ」について書いて、次に、どうしようかなと思っている中で、ひらめいたのが、このアルバムでした。
今のところ、ストーンズのアルバムについては「転換期と言っていいかな」と思われるものを選んで書いてます。
スティール・ホイールズに関しては、キースの言う「第三次世界大戦」終了後(大げさな表現だなキース、、、)のアルバムということで、現在の路線に続く形で始めた初のアルバムと言えるかなと思います。
「外側から見て」とか、「外部からの評価として」ということは別としても、ストーンズというバンドの内側からみても、このアルバムはかなりの「転換期」だったと言えるかもしれません。
転換点と思える事柄まとめ
・イワン・スチュワートが参加していない初アルバム。
・サポートメンバーを固定してやりはじめた初アルバム。
→ミック、キースそれぞれのソロの関係者が多かった
・チャック・リーヴェル初参加アルバム
・ビル・ワイマン最後のアルバム(結果的に)
後は、転換期と言っても、少し意味が違っていますが、我々日本人にとっては、やはりなんといっても、「初来日」かなとは思います。
CDとLPの両方を初めて出したのは、「アンダーカバー・オブ・ザ・ナイト」からかと思いますが、CDをメインフォーマットとしてだしたのはこれが初だったかと思います。
プロデューサーは、クリス・キムゼイで、89年作です。
音楽的には、90年代以降のストーンズのひな型になった部分がいろいろあるかなと思いますね。
ここでかじ取りを間違っていたら、ストーンズは生き残ってなかったかもしれませんね(ここで言う「生き残る」の意味は、「時代遅れにならずに、第一線でやり続ける路線を選んだ」という趣旨です)。
アダルトなストーンズ、ブラコン的な要素(しかし、これもダンス音楽絡みなことに注目)も吸収してますし、「大人な音」になった部分。アルバムとしての完成度が高く、表面的には粗削りな部分をあまり前に出していない部分が強いかなと感じます。
要するに、パッと聞いた感じでは、サウンドにまとまりがある方向で仕上げている感じで、『ダーティー・ワーク』とは、真逆な音作り、方向性と言ってもよいかなと思います。個人的には『ダーティー・ワーク』もだいぶ好きなんですけどね(笑)。
ミックスの視点からみても、とにかく創り込みがしっかりしているので、ストーンズのラフさがほぼ前に出ていない(出ていないように聞こえる)という面はあるかもしれません。ストーンズの場合、それをもって完成度が高いというべきかまではわかりませんが、とにかく、創り込みが、いつも以上にしっかりしてますね。
リバーブも結構深めですしね。時代の音ではありますね。
ただ、大体の曲で、左Channelに定位されているキースのリズムギターは、ほんの少しだけ、音量を上げて絶妙なバランスになってると思います。
おそらく、他のギターより2-3dbくらいですかね。
いずれにせよ、80年代の終盤において、自分達の個性を生かしつつも、サウンドを時代になじませてる点が前面に打ち出されていて、ソロをやったことで持ち帰ったものの大きさはかなりあるかなと感じますね。
そういうこともあってか、結構、ミックがギターを弾いてる曲が多いですし(#1、#2、#4-7、#11)、ロニーがベースを弾いてる曲も多いですね。
後は、コーラス隊と、マット・クリフォードのキーボードが、隠し味としてかなり効いてますね。
ほんとは、このアルバムをより深堀するには、各自のソロを掘り下げないといけない面もあると思うんですが、それは、また別の機会にして、まずは、普通のレビューから書いてみようかなと。
一曲ずつレビューをしていたら、長くなってしまったので、これ以降については、読みたい方だけ、読んでもらえればと思います(笑)。
Side One
1."Sad Sad Sad" 3:35
2."Mixed Emotions" 4:38
3."Terrifying" 4:53
4."Hold On to Your Hat" 3:32
5."Hearts for Sale" 4:40
6."Blinded by Love" 4:37
Total length: 25:55
Side two
7."Rock and a Hard Place" 5:25
8. "Can't Be Seen" 4:09
9."Almost Hear You Sigh" 4:37
10."Continental Drift" 5:14
11."Break the Spell" 3:06
12."Slipping Away"
Total length: 27:00
1."Sad Sad Sad" 3:35
これまでになかったヘヴィー気味なサウンドでアルバムの幕が開けます。
時代はメタル全盛期でもあったので、かなり意識しているのかなと感じます。とはいっても、あくまで色付けがそうなだけで、中身自体は、まったくのストーンズ流ですけど(笑)。
ソロでは、キースがガンガンにソロを弾いていますが、それ以外のところは、オーダーダビングの嵐ですね。左は確実にキースのリズムギターだとわかりますが、後のオーバーダビングのところは、一部はキースと判別できますが、その他のところは、キースが弾いてるのかミックなのかまでは識別できませんね。それにしても、部分部分であるにせよ「ギター、何本重ねているんだ?」と言いたくなります。
ベースはロニーで、クレジットによると、ロニーは弾いてないようですね。
チャーリーのドラムは4うち系。しかし、やはりチャーリーのビートは心地いい。ストーンズファンにとってはなのかもしれませんが。
しかも、この曲、フィルがほぼない!スタジオ版のジャンピングフラッシュほどではないにせよ、基本ビートのみでフィル(おかず)がない。
余談ながら、このアルバムは、こういう歪み系が多いこともあってか、エレキ主体の曲では、アコギの併用があまりないのも、特徴かもしれません(60年代後半、70年代初期のミックテイラー期のストーンズでは、アコギを併用する曲が多かったことを思えば、尚のことかなと思います)
それと、ストレートなロックンロール曲が入ってないという点でも、珍しいかもしれませんね。だいたい、チャック・ベリー系譜のスリーコードのストレートなロックン・ロールが一曲位は入っているんですけどね。
では、次、行きます。
2."Mixed Emotions" 4:38
この曲は、MVも含めて、個人的にはだいぶ好きでしたね。よくできた曲だし歌詞も好きですね。
再始動時の記者会見(アルバムとツアー両方を兼ねて)の際に、会場でこの曲を流していたような記憶があります(ラジカセだった記憶があります)
以下、少々細かく、楽器のところも書いていきますが、「木を見て森を見ず」ということもありますし、識別することに意味はありませんが、逆に「細部に神は宿る」という言い方もしますし、両面から聞いて楽しめばいいのかなと思います。まぁ、ストーンズの音楽に神が宿っているとは思いませんが(笑)
ギタリスト目線で分析したことを書いてみますが、、、、
左がキースですね。これは間違いないです。右のリズムギターはキースが自分でオーバーダビングしたのか、それともロニーかミックかこれも識別は難しいですねただ、ところどころ右チャンネルで入って来るおいしいリードフレーズは、間違いなくロニーですね。
エンディングのところくらいになると、ギターの数が、聞こえるだけで4本くらいになってます。これもオーバーダビングの嵐ですね(この手の手法自体は、60年代後半からやってますし、ストーンズでは珍しいわけではないんですが、その処理の持っていき方がこの時代に適応してますね)。
後は、ミックのボーカルと分厚いコーラスワークも好きですね。
それと、後ろに薄く、色んなキーボード類が入っているので、空間的には広く、背景は埋められていて、音の厚みを薄く作っているあたりは時代のサウンドをうまくとりいれてますね。
エンディングのフェードアウトのところなんかを聞くと、「無情の世界?」と、笑ってしまいそうになるくらい、ストーンズにしては過剰な演出が「こっそり」しこまれています。
まぁ、それはともかく、よくできた曲だと思います。
ただ、作りこまれすぎているのが祟って、ライブでは若干パッとしなかったですね。そこが惜しい(そこはワン・ヒットやハーレム・シャッフルも少し同じようなところがありましたが)。
ミック自身もこの曲はライブでは難しいと発言しています。
その反省もあってか、ヴードゥーラウンジ以降の、シングル的な曲は、ライブで再現できる範囲の創りこみ方、あるいは仕上げているのかと思いますね。
しかし、このMV、ファンとしてはうれしかったですね。
キースもミックもうれしそうだし、ミックはギター弾いてるバンド映像と、これまたスタートミーアップ風の怪しげ衣装で「らしい動き」を連発。
特にキースはうれしそうですよね。張り切ってますし。
ビルも珍しく多めに映るし、チャーリーはロン毛。
ロニーはいつも通りのキャラで振舞ってますね。
コーラスシーンもいい感じだし、うまくまとめてますね。
和解宣言を曲とビデオで前面に打ち出してますね。これを観て、ほっとしたファンも多かったかと思いますが、そこはわかってやってますよね、これ。
3."Terrifying" 4:53
イントロのチャーリーのドラムが良い音してます。
これは、ブラコン(ブラック・コンテンポラリー)を意識した創りですね。
3曲目にもってきて、更に12inchも作っているあたり、当時としては自信作だったのかなと感じます。たしかに、言いたいことはわかります。
軸になっているギターは、カッティング、リフ系でありつつも、ファンクとは違っていますし、ロックという感じでもなく、という感じですが、個人的には、なかなか秀逸な曲だなと思います。リズムとその変化が主体であるところが、とことんストーンズらしくて、私は、好きですね。
シンプルなんですが、深いところでは実に深く「単純で特徴のあるヴァースをうまくまとめて、飽きさせない」の典型的なパターンでかなと思います。
マニアックに聞くとしたら、ギターの絡みが凄く面白いですね。
そのギターの流れの上に、ミックのボーカルや、ペットなんかも入っていて、この時点での「新しいストーンズ」を表現してるなと思います。
リフ自体は、ファンクとかでやりそうな感じではありますが、リズムの置き所は、全く別物ですね。
個人的には、キースのギターのリズムの変化だけ聞いても一曲聞けてしまいます。
左がキース(これは確定ですね)、多分、右はロニーだと思いますが、もしかしたら、右もキースがオーバーダビングで弾いてるのかもです。
なんにせよ、この基本のリフ、カッティングがずっと微妙に、休符のタイミングや、アクセントを変えて、でてくるところは「らしいな」と感じてしまいますね。これを軸に、上物として、それとは別に、ソロフレーズでロニー(センター)がはいっています。
ということで、多分3本は確実に入っています(部分的に、4本になってるように聞こえる個所もあります。この辺りは、かなりオーバーダビングを繰り返して、録音していそうなので、正直判別が難しいです)。
ただ、ソロのフレーズはロニーですね。フレーズ自体は、シンプルではあるんですが、印象的な実においしいリードフレーズを入れてますね。
チャーリーのドラム、Mixed Emotions、もでしたが、録音の仕方と音の分離の良さもあってか、例の2拍4拍のハイハットを叩かない省エネ奏法が、結構、明確にわかりますね。これもほぼフィルなし。Reverbがスネアだけではなく、シンバルにも、結構、深めにかかっているところも、時代の音だと感じますね。
上物でパーカッション的なのが入ってますが、パーカッションのクレジットがないので、マット・クリフォードがキーボードでいれてるのかもしれませんね。
その他では、ペットのソロとか入っていたりと、この辺りは冒頭部ハードロック風から、急展開していきなりジャジーに「大人なサウンド」に振ってますし、余裕を感じますね。
この曲を深堀している記事はあまり読んだことがないので、ちょっと詳しく書いてみました。
4."Hold On to Your Hat" 3:32
これもHR/HM時代を意識していますね。
ギターはリードがキースでミックがリフ的なリズムを担当してますね。
ロニーはベースでギターは弾いてません。
キースがリードギタリストとしてガンガン弾いてますね。
ピッキングハーモニクスを使いまくっているところが笑えますね。
いえ、馬鹿にしているんではないですよ(笑)。
これは、シルエットですかね。
個人的には、このロニーのベースは好きですね。面白い!
これも四つ打ち風でありつつ、同時に、若干、シャッフル気味のリズムに感じます。
5."Hearts for Sale" 4:40
こちらは、HR/HRを意識しつつも、同時にアダルトなサウンドを意識しつつ仕上げてる印象ですかね。おまけにブルースハープを持ち込むことで、まったくの独自サウンドを展開していますね。面白いです。
リフがミックでキースとロニーは自由に隙間を埋めてる感じでしょうかね。
歪んだリフがミック、左がキース、右がロニーで間違いないと思います。
ソロは、ロニーですね。ロニーのソロは、ニュアンスが絶妙で好きです。
ところどころではいるAcoustic Guitarぽいのは、これはマット・クリフォードがキーボードでいれてるのかもしれませんね。
ビルのベースがいい味出してますね。
チャーリーのドラムは、これも、私の耳には、ちょっとだけシャッフル気味にしているようにも聞こえます。ハイハットがそういう感じにしてるからですかね。微妙なさじ加減のリズムですね。ハイハットの「バシッ」は入れてますが、フィルは、手癖フレーズを封印して、この感じにしたのかなという印象を受けます。この曲のチャーリーのドラムは、ニュアンスにこだわっている感じがして、そこが好きですね。
ここからの数曲はミック、キース、ロニーのギター三本体制です。
6."Blinded by Love" 4:37
明らかにミックのソロからのフィードバックもありありの曲だなと感じますよね。
装いとしては、カントリー的な要素が強い曲ですが、いわゆるカントリーではない面白いサウンドだなと。
これはミックもギターを弾いてるようですね。
これは、外部ミュージシャンによる、フィドルやマンドリンなど、色んな楽器が入っていて、創り込みがしっかりしています。
7."Rock and a Hard Place" 5:25
LPもまだだしていた時代ですので、LPでは、ここからB面です。
これを初めて聞いたときに思ったのは、「ガンズとか意識してますよね?」
ってことでしたね。ただ、ストーンズらしく、かなりダンサブルだし、ファンク要素も入っているという。面白い曲ですよね。結構、独自路線だなと。
ミックのボーカルが気合が入っていますし、ニュアンスも工夫してますし、こういう歌い方は、ミックの演劇的なボーカルの成熟度を感じますね。
後、このアルバム以降特徴になったコーラスワークも効いてますね。
この辺りは、ミックの意見として強く打ち出された結果でもあるのかもしれませんね。
で、ギターですが、、、。
これも結構、ギターの本数が多いですね。3-4本は入ってますね。
左のカッティングギターはキースで、右のコンピングぽい合いの手はロニーだと思います。右寄りのキースと同じようなリズムギターはミックかと思います。サビは3本になってますが、その部分では、目立ちませんが、ロニーのギターは、和音の構成を変えて厚みをつけてますね。こういうところ、ロニーはほんとに曲者です。「あんたらがそれでいくなら、自分は、これでいっとくわ」と、うまいことを居場所を創ってしまう感じと言えばいいんでしょうかねw
チャーリーのドラムは、これもメインリズムが四つ打ち系ですね。
色々変化をつけて終盤にはあおりも加わってますね。
それと、ロニーのソロと後半にかけてのリードギターがかなりいい感じだなと思います。「やろうと思えば、やれるロニー」の典型ですね。
他、例えば「アンダーカバー・オブ・ザ・ナイト」のギターとかもですが。
具体的に言えば、これのロニーのソロはBベンダーを使ってますね。
このBベンダー搭載のギターについては、その②で、別途書きます。
これのビルのベースがなかなかにダンサブルなのもいいですね。
ホーンセクションも自然に入っていて、更に、決まってますしね。
ただ、これクレジットを見る限りホーンセクションはないので、マット・クリフォードがキーボードでやってるのかな?。ライブは違ってましたが。
後半にかけて、あげていく感じがらしくて好きですね。特にエンディングのあの感じは、ベテランバンドの味わいというか、特にロニーのフレーズとチャーリーのドラムであおる感じがやばいですよね。
こういうのをやらせたらストーンズはバンドとして、ほんとにうまいし、狙いが明確で自己プロデュースに長けていると思います。
余談ながら、MVミックの衣装がマイケル的な何かを狙ってて笑えます。
この映像はシングルのと同じかな。ロニーのソロが削られていたような(「そこ削るなよ」と思った記憶がw)こちらは、2バージョンありましたかね?。
それはともかく、この曲のMVは、「Mixed Emotions」の和やかモードと真逆で、ライブも意識した熱いストーンズ、映像にしあげていますね。
「和解した後は、これしかないでしょ?」という、意志を感じます。
まぁ、アルバムを出して、早速ツアーに出たからこそ、作れたMVと言えますしね。
8. "Can't Be Seen" 4:09
こちらはキースのボーカル曲ですね。
冒頭オルガンから入るイントロがいいですね。これはミックは参加なし。
この曲もギターの角度から掘り下げてみたいと思います。
要するに、二本ギターの絡みについてですが、、、。
これは、左がキース(二本)で右がロニー(一本)ですね。
この曲はわかりやすいので、明確に判別できます。
なんですが、この曲、基本キースがソロ弾いてますが、裏で、細かく、隙間を埋めるように、支えるフレーズを弾いているロニーが流石なんですよね。ヘッドホンで聞くとよくわかります。歪んで派手なおいしいところはキースがもっていってますが、その後ろで、キースを支えつつ、自分の色を出すロニーは流石だと思いますし、私は、ロニーのこういうギターが好きなんですよね。音楽的にミック・テイラーの評価が高いことに対して、全く異論はありませんが、ギタリストとしては、ロニーのこういうギターでの貢献は見逃せないと思いますね。
しかも、カッティング、リフ、ソロフレーズを崩したような弾き方とか、もはやなんでもありで、アイディアの宝庫ですね。
しかも、「これ、キースのソロボーカル曲だし、こんな感じで弾いてもいいかなと」いうロニーのアピールに彼の曲者度を感じます。
これができるから、彼は長続きしてるんだろうと推定します。
同時に、これをこの音量感で、「聞きたい人は聞いてね」というバランスにしたのも素晴らしいですね。これはバランスを間違えると、崩壊しかねないので(うるさくなりすぎるので)。
これを識別にする聞き方モードになると、歌よりギターを聞いてしまうんですよね。「すまん、キース」と、言っておきます(笑)
ただ、キースとロニーは二人して、このギターの絡みを聞いて、にやにやしてるんだろうなと思いますので、まぁ、いいでしょう。
ビルは「らしい」ベースを弾いてます。
これもチャーリーは四つ打ちベースで、結構、ダンサブルですね。
9."Almost Hear You Sigh" 4:37
これも大人な感じですね。
ミックのソロとキースのソロが融合されたような印象があります。データによると、キースのソロ、「トーク・イズ・チープ」の際に作った曲のようですね。後半のコーラスの繰り返しとかはキースのソロの手法ですし。
これのミックのボーカルは、ソロを通ったことによる変化が強く出てると思います。これは、これ以前にはなかった歌い方ですしね。
Guitarや楽器面でみると、実際のところは、60年代、アズ・ティアーズとかレディ・ジェーンでやっていた手法の延長線で、それを90年代を迎えようとしていた80年代後半に、その時代の音で、蘇らせたと言えなくもないと思うこともあります。
しかし、リバーブとディレイが長い。この時代の音ですね。
中盤のアコギのソロはキース。後半のロニー ギターソロがいい
10."Continental Drift" 5:14
これはこの時点での彼らにとっての原点回帰の意味合いもありつつ、違ったことをしてみたかった部分かなと。ブライアンのことが関連している点から見ればそうでもあるし、サウンドとしては、過去なかった位、振り切っていると言うか(サウンドはアフリカンですが、この頃、黒人音楽としてはアフリカ音楽が流行っていたんですよね。パパ・ウェンバとかユッスー・ンドゥール とか)。その意味では、原点回帰しつつも、時代性には応えているという、、。
キースは自転車の何かをつかってリズム楽器でも参加していて、ご本人は、楽しくそれを語ってましたね。右チャンネルでチリリン、チリリンと入ってるのがそれだと思います。
クレジットによると、ベースは、ロニーによるアコースティックベースだそうです。
まぁ、これを聞くと、あのライブの冒頭と思いだすという人も多いかなと思います。
曲名は、「大陸移動説」のことなんでしょうが、歌詞には直接関係あるのかよくわかりません。
11."Break the Spell" 3:06
これも不思議な感じがするブルースぽい曲ですよね。
このアルバム唯一のブルース臭がする曲だなと。
このアルバムには、直接的なブルース・ナンバーは入っていませんが、そちらは後述するアウト・トラックとして2曲を出してます(その②でとりあげます)。それらをメインのアルバムに入れなかったところにも、この時点での狙いや意思決定があったのかと思います。
しかし、ミックの歌い方が、何とも言えない味を出してますね。
キースのギターは左ですかね。こちらは、ショートディレイが効いてますね。
これはミックもギターを弾いてるようですね。左のリフがミックですかね。
時折入るドブロによるスライドがロニー。
ギタリスト目線でいえば、ロニーの彼らしいスライドが面白いですね。
ベースもロニー。この辺りは、Jeff Beck Group時代のベースを感じます。
この発想は、ベーシストではなくギタリストがベースを弾いたときの発想ですしね。優越ではなく、まぁ、そういうベースです。それにしても変なベースですね。多弁なベースとしては面白いです。ここにロニーの基本にあるファンキーさを感じますね。
それと、これのチャーリーのドラムは、キックがかなり巧妙で曲者だなと思いますね。一聴するとツービードですが、バスドラはなかなかよく考えられてますね。
12."Slipping Away"
これはもう、ストーンズでキースが歌うの最高のバラードの一つかなと。R&Bではなく、ソウルなサウンドですよね。
もはや、イントロのギターとドラムの入りだけで、「来ましたか」状態になってしまいます。
ギターはキースが左。右がロニー、センターも、少しギターが入ってますが、これは識別できないですね。途中で入るアコギのアルペジオはキースですね。
なにげにビルのベースもいい味出してますしね。
後は、ホーンセクションが渋い!
この曲は、25×5というVHSの秀逸なビデオがありましたが、あれのエンディングでもつかってましたね。
ということで、各曲をレビューしてみました。
アウトトラックやその他は、その②でまとめまーす。
