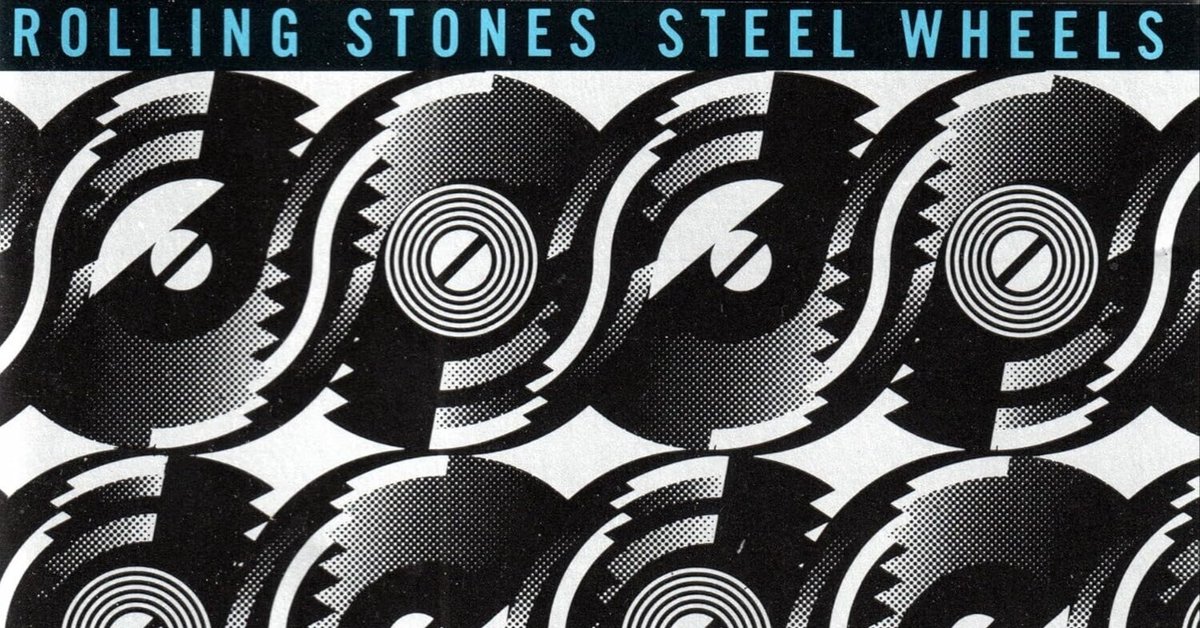
ザ・ローリング・ストーンズ スティール・ホイールズ② アウトトラック/各自のソロ、その他
ということで、このアルバム自体については①を読んで頂くととして、そこで書き切れなかったことなどを、色々書いておきます。
こちらは、ランダムな内容を取り上げてますので、文章としてはまとまりはありません(笑)。
では、前の記事の続きとして、まずは、アウトトラック関係から。アウトトラックは、ブルース系と、リミックス系の2種類が軸になってましたね。
では、聞いてみましょう。
<アウトトラック>
FancyMan Blues
まずは、オリジナルのブルース曲です。先にも触れましたが、こういうストレートなブルースは、アルバムには入れずに、ここにもってきていますが、それは正解でしょうね。こうして発売して、自分達としても収益をあげつつ、「ブルースを忘れたわけではないよ」ということで、ファンにもアピールするという「したたかさ」が、いい意味での商売人だなと思いますね。
とはいっても、時代に合わせてブルースも大人なサウンドにまとめてますね。
サウンド的には歪みも強めですし、サウンドは自己流なんですが、スタイルは、いわゆるブルースロック的なサウンドではなく、やはりシカゴ系のバンドアンサンブル系のブルースですね(いわゆるアーバンブルースではないんですが、サウンド的にはアーバンという感じですね)。
私の勝手な思い込みかもしれませんがこの後のツアーの名前が「アーバン・ジャングルツアー」なのは、このアルバムの伏線としてもつながっているのかなと思ったりすることもあります。
それはさておき、この曲は、チャック・リーヴェールのピアノが効いてます。これを初めて聞いたとき「うぉー、オールマンのあの音がストーンズに!!」と、興奮しましたね。今では、そんな風には思いませんが、当時は、新鮮でしたね。
Cook Cook Blues
こちらもブルース。タイプは違いますが、これも上と同じ系ですね。
"Wish I'd Never Met You"
これは、このアルバム時の録音なのかわかりませんが。一応、この時代のなんですかね。最終的にはRaritiesにも入れてましたが、初出は89だったとおもうので、この時期の録音なんだとは思いますので、一応、ここに入れておきました。
<12㌅系>
クリス・キムジーによる12㌅。これとは別でシングル用のもあったと思いますが、そちらは曲の長さが少し短かったような。
"Rock and a Hard Place"
こういうダンスミックス系は、普通の「ロックバンド」ではやらないところかと思いますが、ストーンズはやってますね。初出は「ミス・ユー」あたりだったかと思いますが、以来、必ずだしてきましたよね。
こういう12inchのリミックスは、ストーンズファンの間では、評価は分かれているかと思いますが、これはこれで「はまる人」もいるようですしね。
こうして、ファン層を広げるのは、ミックらしいと思いますね。
余談ながら、個人的にはミス・ユーの12inchは面白かったですね。あれは、この手リミックスのとは違っていて、どっちかというとロングバージョン的な感じでしたからね。
"Rock and a Hard Place"
これはその別バージョン
"Terrifying"12㌅remix
これも同じく12inch。これは、基本素材は同じですが、ミックスでバランスとかは変えてますね。
これは同曲のライブ
アウトトラックは、こんなところでしょうかね。
<CD/アナログ/>
このアルバムのアナログはうちには2枚ありました。
CDはCBS/ソニー時代のと、ヴァージョン、2009年のリマスター。DSDマスターからCD(UICY-40162)
アナログはリズムセクションがいい感じで鳴りますね。まぁ、うちの再生環境の要因が強いのかもしれませんが。
うちにあるアナログ2枚のマトリックスの印字は以下でした
(よっしーさんへ)。
AL 45333 Dmm 2A G4 STERING A1 BL 45333 Dmm 1A G1 STERING A10
AL 45333 Dmm 2A G2 STERING A8 BL 45333 Dmm 2A G2 STERING
CBS/ソニー 25DP 5566
流石に、CD前提になっているからか、音が悪い印象はないですね。
ボーカルが結構前に出て聞こえ、まとまりがある印象ですかね。
VJCP-25121
今回聞き比べてでテストしてないので、後日、加筆予定です。
UICY-91489
2009リマスター 現行のでもあるわけですが、このリマスターはどうも好きになれません。このアルバムは、まだましですが。
音圧が高いので、リバーブは前目にてきますね。
CD(UICY-40162)
DSDマスターシリーズのSACDシングルレイヤーで、唯一発売がなかったのがこのアルバムでしたが、なぜか、後で、CD版を出した際に、これも入っていました。これは音が良いですね。このDSD(SHMターコイズブルー)→CDのシリーズは2009リマスターとちがって、普通のCDPで聞けるやつの中では、音が素直な音で、リマスターとしては良い印象です。
※このDSDシリーズはデッカ時代のは、ほぼ、出ていません。
※マジェスティック以降(ゲットヤーを除く)ダーティー・ワークまでの全アルバムがSACDシングルレイヤーで出ていた。これは音が良いです。
※上記に加え、このCDシリーズは「スティールホィールズ」と「フラッシュポイント」が含まれていた。
<各自のソロ活動>
このアルバムの流れに繋がる、各自のソロに少しだけ触れておきます。
前作「ダーティー・ワーク」からで見ると3年間、ストーンズは活動してませんでしたが、そうはいっても、各自、自分の活動は精力的にやっていたわけで、改めて働き者だなと思います(笑)
ここでは、そのあたりのことをさらっと書いておきます。
まずは、ソロを分類するとしたら
1.ミック・ジャガーのソロ 「プリミティブ・クール」1987年
2.キース・リチャーズのソロ 「トーク・イズ・チープ」1988年
及び、ストーンズ外での活動 アレサ、チャックベリーなどと
3.チャーリー・ワッツのソロ 「Live at Fulham Town Hall」1986年
4.ロニーはボ・ディドリーとの活動
尚、ビルはこのアルバムの前後にソロだしてるわけではないので、触れないこととしました。
ミックのソロは、スティール・ホィールズに関係するところでいえば「プリミティブ・クール」1987年になりますね。個人的には、好きな曲もありましたし、Jeff Beckのギターもさえてて好きでしたね。
とりあえず、この二つを貼っておきました。MV自体は、他にもありましたが。
これはライブ感があって、Jeff Beckも映像にまで参加していて好きでしたね。
時代の空気も取り入れている感じはしますし、曲的には、リズムとかも好きでしたね。
キースの方は、元々ソロアルバムなんて、出す気はなかったんでしょうけど、ミックのソロを横目に見ていて、やろうと決めたようなことは言っていましたね。これが1988年。初アルバム「トーク・イズ・チープ」は、なかなかの名盤でしたね。これは改めて、別で記事にしたいアルバムですね。
この曲は、ほんとに渋くて好きです。
キースの方は、自身のソロだけではなく、ひとつは、チャック・ベリーの映画、ヘイル・ヘイル・ロックンロール(1986年)は避けては通れないかなと思います。この流れから、上のソロに繋がったという意味でもですが、個人的には大好きな映画でしたね。今でもたまに見ます。
こちらは映画ですし、どれとは選び難いので、貼りませんでした。
これ、今は絶版扱いだったような。惜しいですね。
後は、単発であるものの、アレサとやったジャンピン・ジャック・フラッシュ1986年がありますね。
ロニーも参加してますしね。
個人的意見ですが、ストーンズの曲は、ロックバンドがカバーしたものより、黒人ミュージシャンがカバーしたものの方が、好みのものが多いです。
これとか、その典型です。
その他で言えば、この頃キースはネヴィル・ブラザーズのアルバム(Uptown/1987年)にも、一曲、参加してましたね。このアルバム(アップタウン)は、ネヴィルにとっては闇歴史扱いされているようですが(笑)。
下に貼っておきますが、キースのギターはなんともいえず「らしい」ですね。隙間埋める系のギターが、何とも言えず、しぶいなと思ったのを覚えています。※余談ながら、初めて聞いたとき、ソロの部分で、いきなり雰囲気が変わったので、「何これ、Keithがひいてるのか?」と、焦りましたが、当たり前ですが、ギターソロは、キースではないです(ネヴィルにアーミングプレイ!かよ、、、。)
それ以外では、もはや、忘れ去られている感がありますが、キースとロニー数曲ずつ、ダーティー・ストレンジャーズ(1987年)に参加してましたね(なんと、キース6曲、ロニー3曲も参加してるんですよね)。
というわけで、自身のソロを出す前にも、色々、活発にやってますね。
キース曰く、「二十数年、ずっとバンドの殻にこもっていたが、外に出てみたら、別の景色が見えた」「フロントマンとしての責任の重さも理解できした」というような趣旨のことを話していましたし、キースにとっても、ミックにとっても、ストーンズにとっても、各自のソロ活動はは大きな転換点になったのかなと思います。
バンドが復活した要因にはロニーの貢献もあったんだろうと思いますし、授賞式のこともあったりとか、会わざるを得ない状況となって、それをうまく生かして、戻れたと言うことでしょうね。
ただ、こうした各自がソロなどでやっていた色んな部分をバンドに持ち帰っている部分が反映されているのは間違ないと思います。
まぁ、特に、ミックとキースがというべきでしょうけど、それはあると思います。
初来日については、取り上げると長くなるので、これはやめておきます。
ただ、ミックのソロでの初来日1988年とロニーも同じ頃に来日していて、この辺りで、もうストーンズが来日できる素地ができてきていたのかなと思いますね。
ということで、このスティールホィールズを出す数年前まで、各自、色々とソロ的な活動を個別でやっていました。
<解散問題に関しての個人的見解>
解散問題ですが、確かに、この時、ストーンズは、事実上は、崩壊はしかかっていましたが、「解散」ということを公言したことは、一度もないわけで、あれだけやりあっても、その言葉を使ってないわけですから、そこは彼ららしいかなと思っています。その部分における一線をまもったところにも、結局、ミックもキースもわかってはいたんだろうなと感じることはあります。要するに、「矛先をどう収めるか」みたいな感じでだったのをうまくいかして再始動した感じなのかなと。
別にミックも、ソロをしたからと言って、解散しようと思っていたかと言えば、それは、良くも悪くも計算高いミックのことですから、そこまでは思ってなかったんじゃないかと思います。もちろん、マイケル・ジャクソンより売れたとか、評価されたとかまでになってしまっていれば、どうだったかわかりませんが。
ですので、個人的には「解散なんてするかな?」と思っていました。
確かに、インタビューとかでやりあってましたし、危険な空気であったことは間違いないですし、確証はなかったのですが、なんとなく、「解散まではしないんじゃないかな」と思っていました。根拠としては、ストーンズの理想形態は、マディーとかのブルースなんだから、「ミック、キースのどっちかが、途中で死なない限り、80歳でやっていても不思議ではないだろう」と思っていました。なので、今のストーンズを見ていても、「やってくれたか」とは思うものの、ある意味、予想の範囲内であったとも言えます。
ただ、それでも予想以上の元気さだとは思っていますがw
<この時代を彩ったストーンズ史上、異色のギター達>
最後に、この時代、使っていたギターが、彼らにしては、オールド、ヴィンテージ系ではない、いわゆるモダン系のギターを使っていたのがなつかしいですね。
例でいえば、
・ミュージックマンのシルエット(主にキースですが、ロニーも使ってましたね)。
ミュージックマン自体は、メーカーとしては、レオ・フェンダーがフェンダーをやめた後に立ち上げたメーカーですが、シルエットは、どっちかといえば、系譜としてはFender系の主流からは外れていたModelでしたからね。
フレットも24とかありましたしね。
私も知人が安くで譲ってくれたので、使っていました(キースを意識したわけではなく、たままた知人が譲ってくれたのが理由でしたが)。
あれ、ソフトケースだと飛行機の機内に持ち込んで、機内の頭上のトランクに収納できるのとかも売りだったんです。面白いギターでしたね。
・ESP(主にロニー)
先に書いた通り、この時代、ロニーはこのEPSのギターも時々使っていましたね。
特に印象的だったのが、ESPのBベンダー(ストリングス・ベンダー)のモデル。スティールホィールズのアルバムで言えば、先に書いたように、ロック・アンド・ハードプレイスのソロで使っています。
これは興味本位では、欲しいギターではあるんですが、出番がないだろうな(笑)。Bベンダーはそれを搭載するだけで、ギター本体をくりぬかないといけないので、それが嫌な人向けにHipshotというかに改造パーツがあるんですが、こちらはストラップではなく、腰をくねくねさせて操作するという、なんとも恥ずかしいのがありました。
これ、私のTelecasterの一時期つけていたんですが、やはり使い辛く、難しいうえに、その音を出すとき、腰をくねくねしないといけなくて、ある意味「恥ずかしい」ので、そのうち取り外しましたね。改造の跡はいまでもうちのテレにも残ってますがw
Bベンダーはもともとは、カントリーギタリストのために開発されたB弦をベンドする機能が搭載されたギターのことです。要するに、2弦だけ、ストラップで下げるとベンド(チョーキングされる)という、特殊改造ギターです日本では2弦をB弦とは言いませんが、2弦はレギュラーチューニングではBなので、海外ではこう呼ばれています。
そのためだけに大掛かりな改造が必要なのもあってか、一般的なギターではないです(表からはわかりにくいのですが、背面から見ると、この機構のために、大きなザグリが施されているので、すぐわかります)。
音的には、カントリーとかのペダルスチールギターのようなサウンドになります。なので、普通は、カントリーで使われています。
ロックでは、ジミー・ペイジとかも使ってますが、ここでのロニーの使い方も、なかなかはまっていて、秀逸だなと思います。
しかし、Fenderではなく、日本のメーカーであるESP製なのが興味深いですね。
興味があれば、こちらも参考にして下さい。
ちなみに、余談ついでに、先に書いたBベンダー、スティール・ホィールズ・ツアーのライブアルバムのフラッシュポイントのスタート・ミー・アップのソロでもつかってましたね。
これです、ソロで、そのサウンドを聞けるところの辺りから、再生されるようにしておきました。ウニウニしているのがそれです。しかし、ロニーは、こういうソロなのか、オブリガードなのか、リズムなのかわからないようなソロがほんとにうまいですね。
<制作過程のレア映像>
最後に"Rock and a Hard Place"と"Mixed Emotions"の制作過程をスタッフが記録で撮影していたものが流出したと思われるビデオがあるので、それを貼っておきます。こういう制作過程は、ファンとしては興味深いですね。ただ、これは、余程のストーンズファンか、時間がある方だけ見てもらえればよいかなと(笑)
この頃から見ても、もう、30年以上は経っているわけで、この長寿さには驚きますよね。
