
「独白」 /短編小説・前編

(良くわからん…)
そう、スーパーの野菜売り場を見て庄一は心の中で呟いた。白菜が298円もする。昔はごく当たり前に小鳥の餌として与えていたものだ。それが今では人間の口に入る物として倍以上の値段で平然と販売されている。たまたまこんな値段なのか?知らない間に世の中はすっかり変わってしまった。
(いや、狂ったのか)
気付けば握り締めていた白菜の包みを静かに元の場所に戻すと、大体この時間から増え始める主婦達が放心したように下げ持つ買い物かごにぶつけられないようにと、庄一は見切り品のワゴンへと足を向けた。
(今日は何が残っているかな…)
ワゴンを覗き溜息を零す。バナナとブロッコリーばかりだった。ついてないなと思い、庄一は仕方無く白菜と薄揚げを一つずつ買い求めて自宅への帰路に着いた。
淡い春の宵、何気なく空を見上げると近頃建てられたばかりのマンションと、古く所帯じみた洗濯物が干しっ放しになっている背の低いアパートとの間に、まだ光を放ち始める前の白い月が浮かんでいた。
(下弦の月、か…)
庄一はしばらくそれを横目に見やりながら線路沿いの道を曲がった。
いつの間にか砂利の上に柔らかに下草が萌え出していた。先月出来たばかりのコインパーキングの数ヶ所からは、いつの間にか菫の青紫の花が僅かに風に揺れている。一瞬良い物を目にした気になったが、花の存在を露とも知らぬ誰かの車に轢かれてしまう姿を想像して目を逸らした。ここがコインパーキングになる前は一体何が建っていたかを考えてみたが、何も思い出す事が出来なかった。

とぼとぼと歩く。スーパーの袋を下げながら。角を曲がったせいで正面に現れた白い月を見るともなしに見上げながら、少し肌寒い風に吹かれてとぼとぼと歩く。
背後から近寄る若い声に振り向いてみると、何がそんなに楽しいのか、数人の男子学生が自転車で道いっぱいに広がりながら大声で笑っていた。道の端に避けたが、すれ違いざまその中の二人にあからさまに邪魔者扱いされたような視線を投げられ、庄一は思わず顔を伏せた。
彼らは初めからそこに人間など居なかったかのように笑い声を上げ、少しずつ遠ざかって行った。
(俺は、いつからこんなに弱気になってしまったのだろうか)
庄一はスーパーの袋を持ち直すと、また自宅に向かってとぼとぼと歩き始めた。

すり減った靴の底が何とも頼りない感覚を足裏に与える。西の空は残照を受け、花曇りに何とも言えないような色彩を帯びて広がっていた。淡い色ばかりを使った絵筆を洗った水を流したような、それはとても淡いものだった。穏やかとも表現出来なくもないが、また同時に儚くもあり、それらは決してスーパーの見切り品のワゴンの中には見付ける事の出来ない、何か淡く静かな存在が開いた羽の内側の綿毛のようであった。
庄一は不意に神聖な何かを盗み見た気になり、つい、と両脇に建ち並ぶ民家の軒先の植木鉢に視線を泳がせた。自分がとても罪な事をしている錯覚に捕らわれ、一つ咳払いをした。
(良くわからん…)
近頃ではすっかり心の中で口癖となった言葉を呟き、庄一は少し足を早めた。
少しだけ早く、とぼとぼと歩く。しかし早々に疲れを感じ、またいつもの歩みで一つ角を曲がる。もう月は見失った。右手に持つ杖が急に疎ましく感じられてその場に打ち捨てたい気分になった。しかしそんな事をすると困るのは自分自身だという事も解っている。
一度歩みを止めて静かに溜息を漏らすと、また歩き始めた。かすかな風が一つ吹き、庄一の間延びした影を揺らしていた。
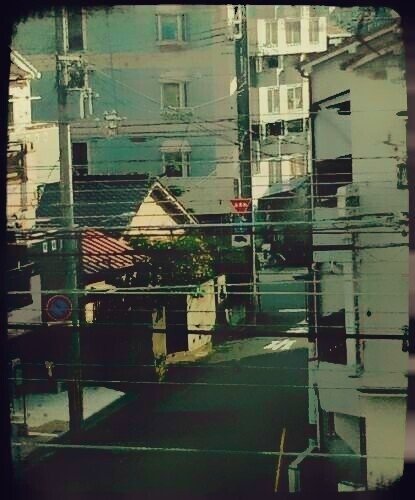
空の色は、端の方から藍玉を水に溶いたように少しずつ青く暮れてゆく。
庄一は自宅の小さな門扉の前に立ち、年季の入った表札をぼんやりと眺めてからその下の呼び鈴の黒いボタンを見た。
(俺が最後にこれを押したのはいつだ?)
そう思い、それをそっと押した。玩具のような音が小さく響いた。
誰も出ない事くらい分かっている。しかし、無人の居間に虚しくその音が流れる場面をその場でしばらく庄一は想像した。
ポストに手を入れるとダイレクトメールが二通入っていた。それらをスーパーの袋に入れて、門を開いたすぐ先のドアに鍵を突っ込む。埃臭い玄関の中に身体を入れて後ろ手にドアを閉めた。金属的な音をたてて鍵を回し、杖を下駄箱に立て掛ける。くたびれた靴を脱いで我家へと上がり壁伝いに居間まで歩き、引いたままになっている椅子に一気に腰掛ける。
(随分疲れた気がする…)
一度座ると足先から波のように脱力感が押し寄せてきた。手にしたままの袋を食卓の上に置く。その上には出涸らしの茶が入ったままの急須と湯呑みがあり、後には端の方に小さな陶器の醤油差しがぽつんとしているだけであった。
どことなく全体が静まり返り、部屋には青に近い灰色、そんな空気が漂っていた。
湯呑みの中に僅かに残った冷えた茶で、庄一は少しばかり喉を潤した。音の無い食卓の上の有田焼の揃いの急須と湯呑みは、その色彩の中に沈んでいた。沈黙に沈み、静寂にうらびれていた。庄一はそっと湯呑みを食卓の上に戻した。それと同じ物が、流しの蛇口の下にもう一つあった。庄一は揃いの湯呑みを交互に使っていた。まるで同じ月日の中でどちらもが同じように歳月を経るように、と。どちらか片方だけが静止した時の中に沈み込んでしまわないように、と。
それは庄一が送る暮らしの中で一際儀式めいたたった一つの事柄であり、逆にその他の食器、例えば揃いの茶碗や小皿などには庄一は何事も求める事もせず、時と共に水屋のガラス戸の向こう側で風化するに任せていた。
なぜ湯呑みだけなのか。
庄一は特に深く考えてそうしていたわけではなかった。ただ近頃は何となく、
(いつでも使うものだから)
ではないかと心のどこかが感じているような気がしていた。無意識にせよ、茶碗や小皿と共に時に任せる気にはならないだけだった。
それは庄一と日常とを繋ぐ、たった一つの要素だったのかも知れない。

庄一はスーパーの袋から先程のダイレクトメールを取り出し目を通した。一通目は来月駅前に開店するらしい眼鏡屋からのもので、優待割引の知らせが添えられてあった。
(まだ、俺に葉書を寄こす者がいるか)
そんな皮肉な気分になり、足元に置いてある屑籠の中に静かに落とし込んだ。もう一通は貴金属高価買取りと印字された葉書で、宛名を見ると木田佐知様となっていた。
(この会社は家内がまだこの世に居ると思っているようだ)
そう先程より皮肉を込めて一瞥し、水屋の引き出しの中に放り込んでそっと引き出しを押し戻した。庄一は亡き妻宛に届けられた郵便物を、そうして引き出しの中に幽閉していた。
ゆらりと立ち上がり、側の棚の上にあるポットから急須の中に湯を足す。色の悪い茶を湯呑に注ぎ温い液体で喉を潤す。決して美味くは無かったが庄一は今の自分にはこれくらいの温度が相応しいような気がし、表情を変えることも無く一人納得した。
思い出したように棚の上の小型ラジオの電源を入れると、急に部屋の空気が揺らいだ気がした。何かの雑誌の特集について男性二人が対談をしているようだったが、古い歌謡曲が急に耳に飛び込んでくるよりかは良かった。

スーパーの袋から、購入した品を取り出し流し台へ持ってゆく。まな板の上に包みから出した白菜を乗せ、根元を落とした後に残りを適当に切り分けてザルにあけて水で洗った。
春先の水道水は思ったよりもヒヤリとした。薄揚げも適当に切り分けそれぞれが入っていた包みを捨てると、庄一は手鍋に水を入れてインスタントの出汁の素を加えて火にかけた。
また椅子に戻り、そこからガスコンロの青い炎を見るともなしにぼんやりと眺めていた。
日々の食事は自分が必要とする分だけを用意すれば良かった。たまに倦怠感に見舞われると惣菜を購ったが、毎日そうしていると予想外に出費が嵩むため、庄一は出来るだけ自炊を心掛けるようにしていた。元より勝手の分からない料理だったから、その分逆に気楽といえば気楽だった。
独りになって以来、食事は作る度に味が変わり、薄かったり濃かったりと失敗ばかりだったが、損をするのは自分一人だけなので自業自得だと単純にそう思えた。
所帯をもつ前は一人暮らしをしていた庄一だったが、炊事場共同の風呂無しの安文化に暮らしていた。その為つい億劫になり近くの食堂で外食ばかりしていたものだ。男子厨房に入らずと己に言い訳をして日々を送っていた。
しかしそれも、蜃気楼のように遠い昔だ。
(それがどうだ。今俺は、煮物を拵えているじゃないか)
庄一は苦笑いと共に胸の内で呟いた。
煮立った鍋の中に先程切った物を入れ、未だ適量の分からない調味料を足した。料理酒など使った事は無いし、砂糖と醤油、油と塩コショウがあれば何とかなった。
別に誰か人様に振舞うわけでも無しに、そう思えば少々悪い出来でも気にせずに食す事が出来た。

手鍋の中身を煮ながら菜箸で突付いていると、足元が少しひんやりとした。
(今年、あと何回使うかなぁ)
そう思い、食卓の側の石油ストーブのスイッチを押した。灯油切れだった。
(参ったな)
庄一はガスコンロの火を一度切り、ストーブから灯油タンクを引き出して玄関から続く廊下の先まで持って行き、ゴミ袋を被せたポリタンクから灯油を補給した。ジーッと電動ノズルが灯油を吸い上げる音をしばらく聞き、半分ほどタンクに注がれると後始末をして居間へと戻った。
ストーブにタンクを戻しスイッチを入れる。ピッと電子音が鳴った後、足元に暖かい空気が流れ込んで来た。流しで手を洗うとやけに家の中が灯油臭い気になり、ポリタンクの後ろにある引き戸を開けに戻った。その先は隣家のブロック塀が控えているだけであったが、塀まで40センチ程の距離があり、そこにまさしく猫の額程の庭土が存在していた。
庄一が引き戸の鍵を外して戸を開くと、急に湿気を含んだ土の香りが廊下に流れ込み、その分押し出されてゆく灯油臭い空気が流れて行く姿が目に映るような気持ちになった。
(あ...)
その僅かな土の上に、いつの間にか花を開いていた沈丁花が誇らし気に香っていた。確か4年ほど前、気紛れで購入した鉢植えをここへ植え替えていたものだった。日当たりが良いとは言えないが風通しは悪くも無く、植え替えた当初よりも株が大きくなっていた。
(確か去年の今頃も、花を見て思い出したんだっけな)
庄一は控え目な花の放つ意外にも力強い春の香りを胸いっぱいに吸い込み、隣家との合間に見える僅かな空を見上げた。そこにはいつしか薄い檸檬のように色付いた月が春宵を穏やかに照らしており、緩く輝いていた。
(春宵、値千金…か)
庄一は花の香りと共にしばらく月を見上げていたが、風の冷たさに我に返り、そっと引き戸を閉めて施錠した。
戻った居間を満たすストーブが吐き出した温気は、なんだか全てを嘘臭く感じさせるような、庄一はそんな風に漠然と感じた。
棚の上の置き時計を見ると、何時の間にか午後7時になろうとしていた。その横でテレビの画面がすっかり埃を被っていた。
手鍋の中身もぐったりとして、すっかり熱を失っていた。

後編
