
あなたの居場所 どこ選ぶ?
ティール組織からみたコミュニケーションの質
組織づくり・チームづくりがシステムより人間中心で行われるために、私たち一人ひとりの「コミュニケーションの質」も進化していかねば。
「コミュニケーションの質」には上や下があるのではなく。上手い下手ではないんです。
だから「コミュニケーションについて私はまず何を勉強すればいいですか?」と聞かれても、その設問自体が間違っています。
私たちが所属する・関わる組織やコミュニティの「あり方」によって、必要とされるコミュニケーションの質そのものが変わってくるからです。
だから「コミュニケーション力を上げる」ことを目指すのではなく、どんな居場所(組織)にあなたがいて、そこではどんなコミュニケーションの質が必要とされているか、をセットで考えることが大切です。
フレデリック・ラルー氏の著書「Reinventing Organizations」(邦訳版:ティール組織)で紹介されている組織の5段階を元に、それぞれに求められるコミュニケーションの質をぼくなりに咀嚼的解釈をしてみたいと思います。
(あくまでざっくりとですが・・・)
(HR Trend Labより) 2014年フレデリック・ラルー氏の著書『Reinventing Organizations』の中で紹介されたのが「ティール組織」です。著者であるフレデリック・ラルー氏は長年組織改革プロジェクトに携わったのち、エグゼクティブ・アドバイザーやファシリテーターとして独立した人物。その彼が世界中の組織を調査し、新しい組織モデルについての考察をまとめたのが『Reinventing Organizations』です。本書は各国語に翻訳され世界中でベストセラーになりました。日本では2018年に『ティール組織』(英治出版 Kindle版 2018/01/23)というタイトルで邦訳版が出版され、それをきっかけに日本のビジネス界で一気に新しい組織モデルとして注目されるようになりました。組織モデルについてのビジネス書は他にも多数存在します。そんな中で、『ティール組織』が注目されるようになった理由は、ティール組織がいままでのマネジメントにおいて常識とされていた考え方や組織構成とはまったく異なる内容を示したものでありながら、ティール組織を構築することで成果をあげた事例が数多く現れたからです。

衝動型・順応型・達成型 組織でのコミュニケーション
衝動型の組織(レッド)
衝動型の組織(レッド)は、カオスな状況での対応力は高い。ただ安定した成果は出ないためずっとカオスな状況を求めていかざるをえない。社会的にブラックな組織はモラルのないカオス環境でしか生きられない。言い換えればカオスな状況で生存するために特化された組織が(レッド)だからだ。
その中で要求されるコミュニケーションとは、「指揮」(命令こそ正義)を意味するものでしかない。「指揮」の中には、言動・態度・肉体的な暴力も含まれる。それらも含めて「指揮」なのだから。
だから組織内には、軽微なものから激しいものまでハラスメントは内にも外にも常態化している。ハラスメントとコミュニケーションが渾然一体となっているのである。
(レッド)から組織段階が発達していくに従って、ハラスメントは無くなるのではなく段々と見えにくくなっていく。いわば関係性の中に「内面化」していくのだ。
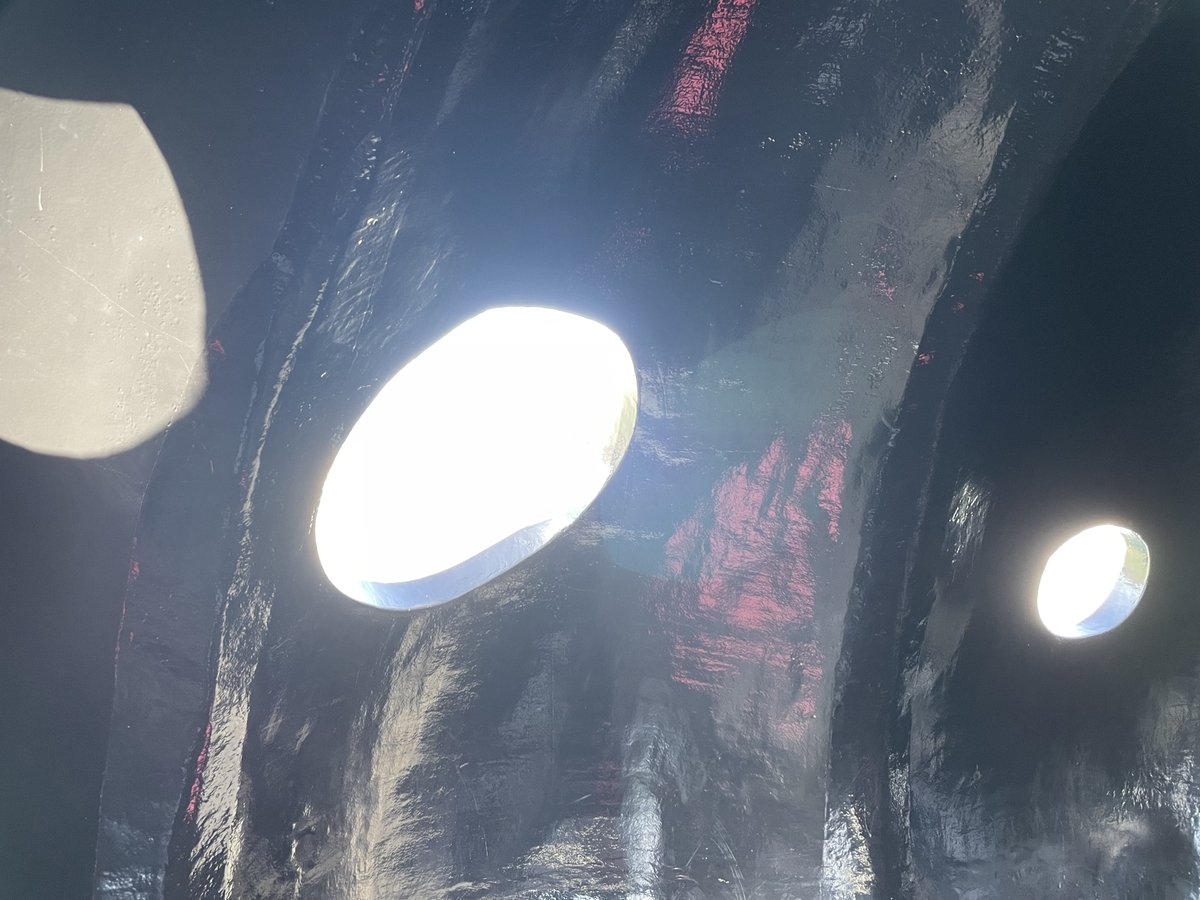
順応型の組織(アンバー)
順応型の組織(アンバー)では、長期的な計画を元に規模拡大した安定した活動ができる。そこでは規律と安定が優先される。
だから求められるコミュニケーションとは規律を確認する規範とセットで行われる。儀式的なものを正確に行なって機能し評価されるが、時間と共に形式的なものへと収斂していくため、「形式」そのものを絶対視する考えに陥りやすい。
そこでは、ハラスメントすら形式化(ルール化)されるため、その暴力性はルールの影に内面化される。つまり外部には見えにくく組織内にいても認識されにくくなってしまうのだ。
達成型の組織(オレンジ)
現代のわたしたちに馴染みの多い達成型の組織(オレンジ)では、倫理より有効性が大切にされる。
その中で要求されるコミュニケーションには、説明(プレゼンテーション・説得)が異様に重要視される。しかしそれは短期的な有効性を求める手法であり、人間的な相互的コミュニケーションの質よりも、コントロールと誘導が是とされる。
ハラスメントは(アンバー)よりも内面化されにくい代わりに「外部化」されていく。つまり、組織の機械の歯車として短期的な有効性を求められるあまり、心身が摩耗すれば、それは「脱落」を意味する。
組織が生み出す暴力的な摩擦力(ストレッサー)は、摩耗した人が組織外へ捨てられていく方に働くのだ。そうすることで組織そのものはなんとかその耐久力を保つことができる(オレンジ)が重視する市場原理において「外部化」はセットなのだ。

多元型・進化型 組織でのコミュニケーション
ここからやっと人間中心へと、組織の形態が複雑化してくる。
まるで、荒地に生えていた草木が年月と共に自然遷移をして、林っぽくなり、動植物の種類が増えていき、だんだんと森に近づいていくように。
多元型の組織(グリーン)
多元型の組織(グリーン)では、価値観をベースに公平さ、調和、協力が重視され始める。多くの権限が移譲されてボトムアップ型の運営へ。
短期的で限られた対象への利益を求めるだけだった(オレンジ)と比べ、より様々な分野で関わる対象へその価値を提供しようとする。
しかしその反動としてボトムアップ・プロセス重視のため運営スピードが落ちてしまい、コミュニケーションコストが大幅に上がる。
ここで初めて「感情を丁寧に取り扱う」コミュニケーションや、相互支援のコーチング的コミュニケーションが必要となってくる。
良い面としては、組織内にハラスメントが「発芽」する前に、その萌芽を外部化することなく、メンバーの相互協力を促進し課題解決するための「養分」として使うことができる。
進化型の組織(ティール)
さらに。
進化型の組織(ティール)では、より複雑な世界に対処するために複雑な方法へと自主経営をおこなっていく。組織そのものもフルクタル(ピラミッド型ではなく部分と全体が相似形であるフラットな形態)へと進化していく。
組織の存在目的そのものが固定化せず進化し続け、個人と組織全体とが
オープンな場を生かして磨きあう。ここでは個々のコミュニケーションのテクニックよりは、「場づくり」こそがその力を発揮する。
ハラスメントの種であるわずかな対立であっても、相互が豊かに変化するチャンスとして効果的に使われていく。そのために、お互いが調和し成長していくために、相互学習していく非暴力コミュニケーションが基本となる。
(ティール)では「感情」も「思考」も大切な資源であり、一人一人が自己理解・他者理解を伴った責任を持てるコミュニケーションが求められる。
▼ Podcast(幸田リョウ 深掘りトーク)

つまり。
わたしやあなたが、今いる居場所・今後 望む居場所ごとに求められるコミュニケーションの質は違うということ。その居場所でこそ活かせるコミュニケーション(活かせないコミュニケーション)があるということだ。
何より大切なのは「あなたの居場所 どこ選ぶ?」なのだ。
そしていつでも。
どこを選ぶかは、あなた次第。なのです。
だれでもコーチ!(コーチングを取り入れて双方向で高め合う関係づくりのヒント)(動画講座)
PARK STARSでは、企業向けコーチングスキルアップ研修を行う傍ら、個人向けでも、オンラインで受講できるコーチング認定講座を(株)未来クリエイションの主催にて行っています。
対話を行いながらコーチングを軸にした人材育成・対人支援が求められている昨今、コーチングの基礎知識と実践プロセスを学べる入門編を、動画講座にしてお届けしています。※動画講座の視聴をご希望の方は、下記の有料部分より視聴いただけます。
<重点レッスン動画>
だれでもコーチ!(コーチングを取り入れて双方向で高め合う関係づくりのヒント)

<主な講座内容> 時間(50:20)
・相手を理解するアセスメント/観察/質問
・社会・職場を5つの組織モデルから理解する
・コーチングを通じて相手の何に貢献できるか?
・認知のクセ(認知バイアス)を知る
・コーチングの流れを組み立てるための基礎知識
・コーチングの組み立て方
・コーチングにおける介入とは
・コーチ養成講座について
<この講座で得られること>
・コーチングの基礎用語や基礎知識を学べる
・コーチング対象の個性・タイプ・認知の癖を理解しやすくなる
・人材育成や対人支援の現場で使えるコーチングの流れ(プロセス)を体系的に理解できる




動画講座の視聴をご希望の方は、下記の有料部分より視聴いただけます。
ここから先は
¥ 1,980
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
