
未来の誰かのために本を読む 【#60】
利他的に言葉を手にしていく感覚
もしかすると「自分は未来の誰かのために本を読んでいるのかもしれない」と思うようになった。 10代の頃は好奇心の赴くまま、知らぬ世界に誘われるよう、あくまでも自分のための読書をしてた。けど、20代後半から現在につれて、読書観が変わった。
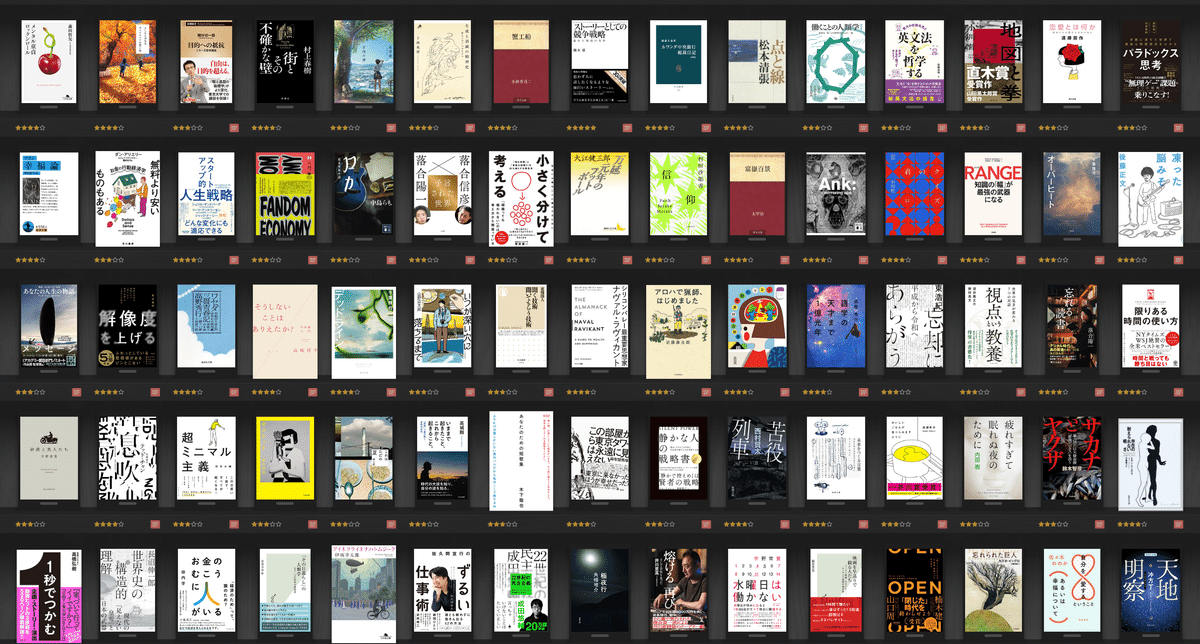
自分は性懲りもなく、今でも本を読み続けている。活字の向こう側に広がる世界に魅了され続けている。昨日より今日、今日より明日、一歩でも自分の思考を前進させるためにページをめくり続けている。だけど、立ち止まるなら、自分はもう十分に本を読んだのかもしれない。
それでもなお読書をやめないのは、その先に他者の姿を見るからなのかもしれない。人生は短く、時間は有限だ。誰も彼もが、わざわざ時間も集中も要す、読書に大量の時間を投下する必要はない。
いつかの誰かに語りかける物語や哲学の考え方を、必要なとき、必要な用法・容量で差し出すため、今日も自分は“誰かのために”本を読んでいるのかもしれない。
前から楽しみにしていた小川哲さんの新刊『君が手にするはずだった黄金について』がちょうど今日発売された。
そのプロローグの中に、読書に関するこんな記述を見つけた。
読書とは本質的に、とても孤独な作業だ。映画や演劇みたいに、誰かと同時に楽しむことはできない。最初から最後まで、たった一人で経験する。それに加えて、本は読者にかなりの能動性を要求する。目の前で何か行われていることを受けとればいい、というわけではない。読者は自分の意志で本に向き合い、自分の力で言葉を手に入れなければいけない。そんな拷問を、場合によっては数時間、十数時間も要求する。僕はときどき、本というものが、わがままな子どもや、面倒臭い恋人のように見える。
「僕だけを見て。私だけにずっと構って」
本が、そう喚いているように感じられるのだ。実に傲慢だと思う。 しかしその傲慢さのおかげで、僕たちは一冊の本と深い部分で接続することができる。誰かによって書かれたテキストと、たった一人の孤独な読者。二人きりの時間をたっぷり過ごしたからこそ、可能になる繫がりだ。
孤独のトンネルの先は必ず景色とつながっているはずだし、その景色は他者と共有したときにだけ感傷を呼び起こすのを知っている。そのことを知ってから行う読書は質感と意味が変わる。本の中身ではなく、読書という鋭意そのものをメタ的に捉え直し、自分の有限な人生に位置づける。「確実に歳を取りつつある」証左とでも呼ぶべき、人間としての成熟なのかもしれない。
知識は本から、視座は人から
読書で知識は手に入っても、視座の高さは誰と一緒に時間を過ごすかに規定される。「やる気」よりも「やれる気」の方が大切みたいな話で、「自分もできるかもしれない」と真に思わせてくれるのは本ではなくて人。だとして、知識と視座がない混ぜになった人間存在をぶつけて、交換し合える関係性が望ましい。

編集協力で入らせてもらっているいくつかの書籍が佳境を迎え、大部分のリソースをある経営者の方の思想を言語化して、バイブルに落とし込む仕事に注ぎ込んでいる。前項で述べた「誰かのための読書」の総決算とでも呼ぶべき、僕の中に詰め込まれた知識や思想の体系が拠り所になる仕事だ。言葉や思想を引っ張り出すための引き出しと同時に、構造を頑健に組み立てていく構成力も求められる。
この仕事の関連で、改めて稲盛和夫さんの『生き方』とレイ・ダリオの『PRINCIPLES 人生と仕事の原則』を読み返した。東洋と西洋、異なる文化圏を生き抜いてきた二人の思想に共通点はほとんどない。その実、二人とも自らの生き方の指針を絶対のものとして勧めることもない。あくまでも一つの人生を生き抜いた上で、事後的に編み出した生き方のヒントを粘り強く言語化した結晶が紹介されている。
思えば自分は10ヶ月しか会社員として働いた経験がない。黙っていても給料が振り込まれるのは楽だし、安心だけど、どこかで違和感が拭えない。独立独歩フリーで働くには真正面からフェアネスに向き合わなければならない。だから自分自身で出せるバリューに値付けして交渉しないといけないのはしんどいけど、楽しい。
モメンタム・バーベキュー

ここから先は
ケニアで無職、ギリギリの生活をしているので、頂いたサポートで本を買わせていただきます。もっとnote書きます。
