
歩行で股関節転子部に痛みが生じる症例
以下に記す症例について、見方、知識の使い方、考え方の流れが参考になれば幸いです。
情報)
20代の方である。
歩行のTStで右転子部に痛みが生じる。

そして、TSwにかけて余韻が残り、外果辺りまで痛む。

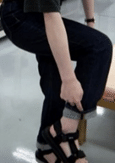
また、長時間の立位で腰が重くなる。
腰はPSISあたりで右>左で重く、今も少し重い。

他に、立位で足を閉じると痛みが強まり、開脚の歩行は痛まない。
評価では
右の大転子が左に比べて出ていた。
右転子部に圧痛があり、右の腸脛靭帯、大腿筋膜張筋緊張、内側ハムストの緊張が確認された。
但し、右外側広筋の緊張や萎縮はなかった。
また、右股関節の外転運動で痛みが出現した。
歩行ではトレンデレンブルグなどの跛行はないが、右立脚終期の骨盤後方回旋が左立脚終期に比べて大きかった。
Q) 原因は?
A) 右転子部に圧痛・腸脛靭帯緊張・股関節の外転運動痛・立位で足を閉じると痛みが強まり、開脚の歩行は痛まないことから、転子部で腸脛靭帯が圧迫されて痛みが出現していることが考えられる。
Q) 歩行のTStで右転子部に痛みが出るのは?
A) TStでは大腿筋膜張筋が骨盤水平保持に働き活動する。

Q) 歩行のTStで右転子部が痛み、TSwにかけて余韻が残り、外果辺りまで痛むのは?
A) 筋連結では腸脛靭帯は腓骨筋とつながる。
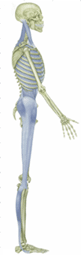
Q) 大元の原因は?
A) 大腿筋膜張筋の緊張による圧迫と転子部の突出である。
ここで、転子部の突出は骨性なので変えられない。
そこで、大腿筋膜張筋の緊張について考える。
Q) 緊張の原因は?
A) 内側ハムストの緊張があることから股関節の安定化が考えられる。
Q) それは?
A) 大腿筋膜張筋の作用は股関節屈曲・外転、内側ハムストは伸展・内転で、お互いに拮抗する。
その合力は骨頭を臼蓋に引き付ける。
また、外側広筋に緊張や萎縮がなかったことからも、膝ではなく股関節であることが伺える。
Q) アプローチは?
A) 骨頭安定化を別で担い、大腿筋膜張筋の緊張を減らす。
骨頭を直接安定させるのは、関節包に付着する筋であり、大腿筋膜張筋と類似作用は小殿筋である。
Q) 方法は?
A) 小殿筋は大転子の前方に付着する。また、中殿筋よりも起始停止間が短い。
そこで、軽度の股関節内旋・屈曲・外転自動運動を休憩を含めて5分間実施した。

Q) 結果は?
A) 転子部の痛みは減少し、腰の重さも減少した。
また、歩行における右立脚終期の骨盤後方回旋も減少した。
Q) 何故、腰の症状が減ったのか?
A) 右立脚期の骨盤後方回旋が減り、仙腸関節への回旋ストレスが減ったからではないかと考える。
Q) 後方回旋が減ったのは?
A) 大腿筋膜張筋の緊張が減り、股関節伸展が以前より行えるようになり、それほど骨盤回旋による歩幅の獲得をする必要がなくなったからである。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
