
車いす自走により肩痛が生じる症例
以下に記す症例について、見方、知識の使い方、考え方の流れが参考になれば幸いです。
情報)
高齢の方である。車いすを自走していると徐々に右の肩から前腕に痛みが出現する。

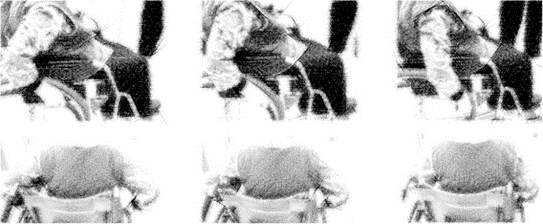
車椅子自走の様子
Q) どのように考えればよいか?
A) 車いす自走の様子を観察しても答えは出にくい。
まずは痛みの部位からメカニカルストレスを特定し、それに照らし合わせて車いす自走の様子を観察する。
Q) 痛みの原因は?
A) 痛みは肩から前腕外側にかけてであり、ある特定の筋に絞れない。
また、それら筋(三角筋中部、上腕二頭筋長頭、上腕三頭筋外側頭、腕橈骨筋)の作用と車いす自走の上肢の動き方からオーバーユースとして一致しない。

Q) では?
A) 関連痛や放散痛が考えられる。
Q) どれか?
A) しびれなどの神経系に由来する痛みの訴えはない。
Q) すると?
A) 痛みの部位について、症例が最初に手をかざしたのは肩関節の部分である。

最初に手を持って行くと言うことは、その部位が最も痛みがあり、そこから遠位に痛みが広がると考えられる。
このことから肩峰下部でのインピンジメントが考えられる。
Q) 症例のインピンジメントは、骨頭がどの方向に偏位するのか?
A) 上方である。
Q) すると、車いす自走のどこで、そうなるのか?
A) 症例はハンドリムを前方に押して、タイヤを回している。
この時、骨頭が上方変位するのは、ハンドリムからの反力が関係する。

Q) いつか?
A) 車椅子自走の様子
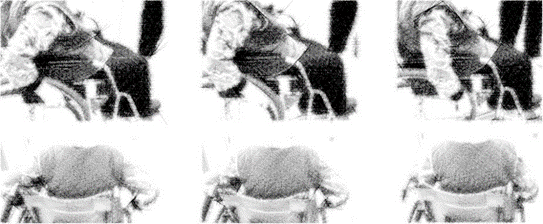
②のハンドリムを押す瞬間が最も力が必要であり、ハンドリムからの反力が骨頭に伝わる時期である。
③では上肢を前下方に持っていくので、この時期は骨頭が肩峰から離れてインピンジメントは起らない。
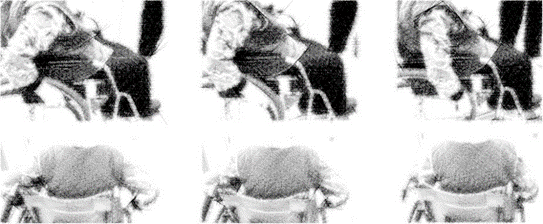
Q) ②の上肢の運動をどう変えればよいか?
A) この時期に上腕を下方に下げる力が働けばよい。
Q) 何筋か?
A) 骨頭を下方に下げる筋は、背部では広背筋、前部では大胸筋胸肋部下部から腹部線維である。
Q) どれか?
A) ②の肩関節の動きの方向は、矢状面では屈曲、前額面では内転である。
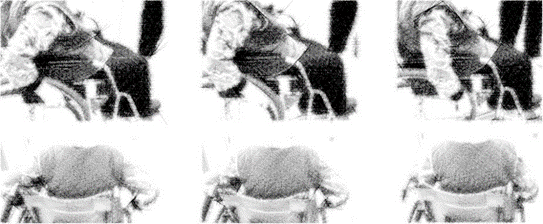
これに当てはまる筋は大胸筋である。
Q) ここで、骨頭を下方に下げる代表的な筋に肩甲下筋や棘下筋があるが、それら筋は考慮しなくてよいか?
A) 腱板筋は肩関節拳上において、三角筋への対抗措置として活動する。
今回の場合はそれとは違い、ハンドリムからの反力なので、反力に対抗する作用筋を軸に考える。
Q) アプローチは?
A) 大胸筋胸肋部下部から腹部線維の収縮力増加なので、万歳の姿勢から症例の両上肢を腹部(肘関節が腹部)に持って行くような引っ張りっこをPTと行った。
Q) 結果は?
A) 1か月ほど経過してからの報告では、痛みは消失したとのことである。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
