
柳原良平主義 ~RyoheIZM~ 02
人物画に宿るオリジナリティ
道は、自分で切り開く
船や港は、柳原良平が一生を通じて向き合ってきたテーマであり、その絵を前にすると誰もが、オリジナリティあふれる、柳原ならではの作風に魅了される。その魅力については今後、手を替え品を替え何度も書くことになろうが、その前にあえて、彼の作品のもうひとつの特徴である、人物画の面白さにスポットを当てておきたい。
柳原が描く人物画はマンガチックなものが多い。一時期、漫画家としても活躍していたから当然と言えば当然だ。そしてその独特な作風ができあがるまでの道のりは、寿屋(現サントリーホールディングス)への入社からスタートした。
柳原のアルバイト先には、尊敬するアートディレクター、山崎隆夫という人物がいた。そんな山崎が寿屋にヘッドハンティングされたことを知った柳原は意を決して「僕も連れていってください」と頼み込む。これが寿屋入社のきっかけだった。
運も実力のうち
挿絵を描くアルバイト青年に過ぎなかった柳原の才能を見込んで、寿屋に頼み込んだ山崎の行動も頼もしいが、その頼みに「かましまへんでェ」のひと言で引き受けた佐治敬三(のちの寿屋社長)の懐も深かった。だがそうした運に恵まれたことも含めて、自分を連れていってほしいと頼み込んだ、つまり自分の道を自分で切り拓いた柳原良平の決断は、天晴れという他ない。運も実力のうちだからだ。
ちなみに「運も実力のうち」とは、実力不足を運が補っている状態を指すのではない。本人が謙遜で言う分にはいいが、他人がそのように使うのは間違っている。そうではなく、運さえ引き寄せてしまうほどの、潜在・顕在を含めた実力があることが前提となっていると考えるほうが、個人的には腑に落ちる。柳原のその後の快進撃ぶりを知ると、なおのことそう思う。
才能の塊が、続々と集結
晴れて寿屋に入社した柳原は、開高健(のちの芥川賞作家)と出会う。優秀なアートディレクター山崎隆夫をヘッドハンティングするだけあって、宣伝に力を入れる寿屋は、開高と柳原をクリエイティブの中心に据え、厳しいながらもある程度の自由を与えた。そしてその結果すぐに巷で大評判になり、鳥井信治郎(寿屋の創業者)の「やってみなはれ」精神が実らせた、会社のイメージを大きく上げる果実となった。
コピーを開高、イラストレーションを柳原がそれぞれ担当し、そこに経験豊富なデザイナーでありプロデューサーでもある坂根進が加わったトリオは最強だった。洒落ており、時代を反映したノリのいい広告は、広告業界に旋風を巻き起こし、各種の広告賞を獲りまくった。
彼らは、一流の職人同士による掛け算パワーが無敵であることを証明し続けた。その後、さらにそこに山口瞳(のちの直木賞、菊池寛賞作家)が加わる。1958年の朝日広告奨励賞やADC賞、1959年のテレビ広告電通賞を受賞するなど高い評価は相変わらずで、こうなるともう「無敵」というより「つまらないものが作れない」くらいのレベルだったのではないかと推測される。
このクリエイティブ集団は、新聞広告だけでは飽き足らず、トリスウイスキーのチェーン店向けに『洋酒天国』というPR誌まで制作。時代を最短で言い当てる気の利いたコピーと、楽し気で都会的なイラストや切り絵、そして洗練されたアートディレクションにより、それらの広告作品は大衆から圧倒的な支持を獲得した。
憧れを増幅した、オシャレな挿絵
新聞広告に登場する人物画は、この時点では8頭身のオシャレな女性(赤玉ポートワインのPR用)や、足の長い若者ビジネスマン(トリスウイスキーのPR用)らが楽しく一杯やっているといったもので、マンガチックではあるものの、ひたすらオシャレでコミカルな雰囲気はない。
『洋酒天国』には、柳原の描いた酒の神バッカスやら、世界中の多様な人種が登場し、文化的に欧米への追従傾向が強かった、戦後復興〜成長期を生きる大衆の憧れを大いに煽った。全体に言えるのは、時代の最先端をいく最高に洗練されたビジュアルだったということ。寿屋の酒も、さぞ売れたことだろう。大きなお世話だが。
アンクルトリスは、機能美の象徴?
そんな時代に満を侍して誕生したのが不滅のキャラクター「アンクルトリス」だった。白黒のテレビが浸透し始めたのに目をつけた寿屋は、テレビCMへの参入を決定。それに合わせて、柳原良平と開高健、柳原の後輩になる美大卒の酒井睦雄の3人は、早速ミーティングを開始。そして驚くなかれ、30分後にはもうアンクルトリスが誕生していた。
超安産の理由。それはなんと言っても、コンセプトが秀逸だったからだ。テレビに登場することを前提に考えられたそのコンセプトは、以下3つに集約された。
(1)表情が出るように
(2)(その表情豊かな)顔が目立つように
(3)頻繁に登場しても、嫌味がないように
表情を出すために、それまで単純な黒点で描いていた人物の目は「丸いまぶたの中に黒目」を描くことで、目にニュアンスを与えた。顔が目立つようにするため、大胆に「2頭身半」のバランスにした。そして、テレビでCMが頻繁に流されても(飲酒シーンを何度も観せられても)嫌味を感じさせぬよう、若者ではなく「初老の紳士」にした。
アンクルトリスが柳原を、漫画家にした?
いわば機能的に作られたキャラクターだったが、この丸まぶた に2〜2頭身半の中高年は、ほどなく他のキャラクターにも転用され、柳原マンガに登場する人物画の標準仕様となる。
朝日新聞の5コマ漫画『ピカロじいさん』(1959年〜)、読売新聞夕刊の『今日も一日』(1963年〜)、公明新聞の『良ちゃん』(1980年〜)などを見れば、それは一目瞭然。童話の『三人のおまわりさん』も同様だった。
しかし、このキャラクターを生み出すのに30分しかかかっていないというのは奇跡としか言いようがない。おそらく、会議室に酒の神バッカスが降臨し微笑んだのだろう。なぜなら3人の脇には、バッカスが潜むのに都合のいい(撮影用)ウイスキーボトルが、鎮座していたであろうから。(以下次号)
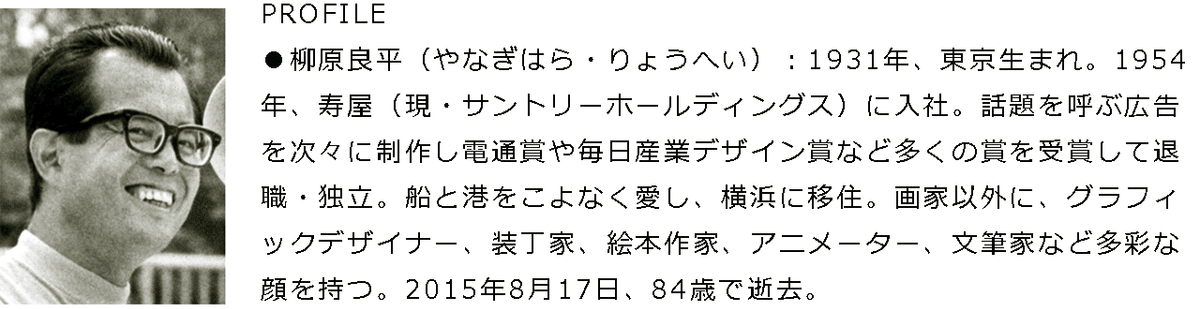
「船キチ」という表現は「尋常ではない船マニア」といったニュアンスを表しています。柳原良平が自著の中で、主に自身に対して頻繁に使用している表現ですが、そこに差別や侮蔑の意図はまったく感じられません。従って本コラムでは、他の言葉に置き換えず、あえて「船キチ」という単語をそのまま使用しています。
★質感までわかる高精細な複製画、かわいいアクリルフォトを展示・販売中!
柳原良平作品展示・販売(バーチャルミュージアム)
参考文献
・『柳原良平のわが人生』(如月出版)
・『船旅絵日記』(徳間文庫)
・『柳原良平 海と船と港のギャラリー』(横浜みなと博物館)

